
- あの医者の視点は、私とは違うところがあるなぁ
- 医師の言うことをそのままやらないといけないの?
- 精神保健福祉士としての考えで支援したい
結論から言いますと、法的には、精神保健福祉士は”主治医”の「指導」を受ける必要があります。
主治医の言う通りにはしなくても良いんですが、意見は聞いておかないといけないってニュアンスです。
ちなみに、”主治医ではない医師”については、指示も指導も受ける立場にありません。当たり前ですけどね。
私は精神科クリニックで働いたこともあるので、現場の実情も含めてお話しします。
法的な根拠
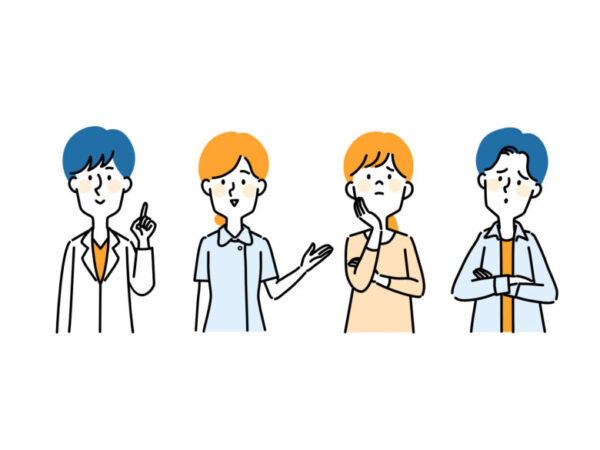
精神保健福祉士は主治医の「指導」を受ける立場です。
これは精神保健福祉士法で決められています。
精神保健福祉士は、その業務を行うに当たって精神障害者に主治の医師があるときは、その指導を受けなければならない。
引用元:精神保健福祉士法 第41条2

指導ってどういうこと?やっぱり言う通りにしないといけないの?
精神保健福祉士と主治医の関係|指導とは?
「指導」と「指示」いう言葉は、どちらも上から教えられている感じがありますが、法律での意味は違います。
法律での「指導」には、法的に強制する力はありません。
専門的な見地をもって、助言・意見・アドバイスすることですね。
必ず従わなくてはいけない決まりはありません。強制ではないんですね。
だから、精神保健福祉士は主治医の意見や助言を聞かなくてはいけませんが、従う必要はないということです。
例えば、作業所で働く精神保健福祉士が、利用者の希望をもとに、一般就労の支援をすすめているとしましょう
精神保健福祉士は利用者さんの主治医の診察に同席し、一般就労をする際の留意点、必要なサポートなどを主治医にたずねました。
主治医からの返答は、
「睡眠リズムが崩れないように、日中だけの仕事にしたほうが良い」
「週3日から始めること。日を増やすのは慣れてからが良い」
という内容でした。
では、精神保健福祉士は、主治医が言った通りに支援しないといけないのか?
答えはNO。
だから、利用者さんが

それでも私は週4日から働きたい。自信があるし大丈夫です。
と意思を示すならば、精神保健福祉士は意見や助言をしつつ、「やはり利用者さんの意向・決定を尊重すべき」と判断し、週4日の方向性で支援する・・・
それで良いのです!
主治医の指導内容には留意しておいて、ね。
ちなみに、この「指導」とよく比べられるのが「指示」です。
精神保健福祉士と医師との関係|指示とは?
法律で「指示」とは、決められた行為に従わなくてはいけないことという意味です。
つまり、強制する力があります。
精神保健福祉士と医師との関係|医師の指示を受けるのは誰?
医師との関係で「指示」を受ける立場になりやすいのが、看護師です。
医事法では、医療行為を自分で判断できるのは医師だけです。
≫参考:厚生労働省HP 第2回 医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会 令和元年11月8日 診療の補助・医師の指示について
医療行為というのは、医師の医学的判断や技術がなければ、人体に危害を及ぼしたり、危害を及ぼす可能性のある行為のことです。
例えば、医師でもない人が高血圧の患者さんに血圧を上げる薬を出したりしたら、危険ですよね。
手術だって、健康な人にやったら傷つけることになります。
こうしたことについては、主治医の指示のもと、医療職が行うことになっています。
でも、精神保健福祉士が行う相談支援は医療行為ではありませんよね。
相談支援が医療行為だったら、誰かの相談を受けたり、支援したりすることは医師にしかできなくなってしまいます。それはおかしいでしょう。
精神保健福祉士と医師との関係|でも実際は・・・
精神保健福祉法では、精神保健福祉士は”主治医”の指導を受ける立場にあります。
しかし実際、例えば同じ病院で働く主治医と精神保健福祉士の関係には、上司と部下の関係も備わっていたり、医師が絶対というルールがあったりして、実際は”指示関係”ということもあるでしょう。
特に、個人でやっている診療所やクリニックで、主治医が経営者だったらなおさらです。
現場や現実というものは、いつもきれいに整理されていません。矛盾があるものです。
こういう現場でどうやって仕事をするかが、精神保健福祉士・PSW(MHSW)としての技術です。私もまだまだ勉強中です。
精神保健福祉士と医師との関係|まとめ
というわけで、精神保健福祉士と医師の関係についてもう一度まとめます。
要は、主治医の意見を参考にしながら、精神保健福祉士としての支援を考え実行すれば良いということです。
公益社団法人日本精神保健福祉士協会のHPでもこのように書かれています。
精神保健福祉士は医療職ではありませんので、医師の指示によって業務を行うものではありません。
ただし、「主治医がいれば、その指導を受けること」も精神保健福祉士の義務として定められています(同法第41条第2項)。
つまり、主治医の意見を聞き、指導を受けますが、精神保健福祉士として独自の専門的な視点に基づく判断と、それによる支援を行う職種となります。
引用元:公益社団法人日本精神保健福祉士協会HP
言い方は悪いかもしれませんが、私たち精神保健福祉士には「主治医をいかに使うか」という視点も必要です。
世間的に、医師には権力があります。「医師が○○と言った」となれば、その影響力は大きいし、印籠のように使えたりもします。
だから、あなたに支援で推し進めたい方向性があるならば、その方向性で医師の意見を使えるかどうか、考えてみると良いと思います。
そのために、例えば受診に同行したり、意見を聞きに行ったりするのです。
あと、「医師」と「主治医」との違いも大事です。
利用者さんや患者さんの主治医ではない医師からは、指導される法的な根拠もないということです。(そりゃそうですよね)
以上、精神保健福祉士と医師との関係は指示?指導?【法的な根拠も解説!】という話題でした!


コメント