
自己覚知って何なの?必要な理由がよくわからない。レポートを書かないといけないから、具体例を知りたいなぁ。
こういった思いの方へ。

私は某自治体で働く社会福祉士・精神保健福祉士です。現場歴はおよそ13年です。
- 自己覚知とは?必要な理由
- 自己覚知の方法3つ解説
- 【具体例】わたしの自己覚知
自己認識は超カンタンにいうと、自分を知って支援に活かすということです。
似た言葉で「自己分析」がありますが、これの意味するところは「自分を知ること」です。
就活の時などに自分の適性を知るためによく使われる言葉ですね。
自己覚知は、支援に活かす意味も含んでいるのが自己分析との違いでしょう。
- 自己覚知くらい知ってるよ!
- 自分のことくらいわかってます
- もう自己覚知はできました。
と思う方は多いかもしれませんが、自分のことは、自分よりも他人の方がわかっているというくらい、自分とは奥が深く、正しく見つめることが難しいものです。
実際、現場でも自己覚知を知っている人は多いけれど、習慣にできている人は少ないと思います。
「知っている」と「やっている」の違いはとても重要です。
自己覚知の習慣がないと、例えば、独りよがりな関わりをしてしまったり、
利用者・患者さんの課題と自分自身の課題を取り間違えたり、
メンタルのコントロールが難しくなったりします・・・。
言ってしまえば、デキない支援者になってしまう。
例え経験年数が長くなっても、「利用者が悪い!」「あの患者さんがおかしい」と、自分視点でしか分析できない支援者になってしまいます。(実際よくおられる)
しかし、自己覚知の必要性を理解し、方法を会得できれば、支援レベルが段違いになるでしょう。
いろんな課題をいろんな視点で、色メガネ無くとらえられるので、しっかりと核心をついた支援ができるようになるわけです。
ちなみに自己覚知は、社会福祉士・精神保健福祉士・福祉の仕事をしている方だけでなく、対人支援・教育の仕事の方なら誰でも活用できることです。
難しそうなイメージがありますが、ポイントをおさえれば自己覚知の方法はカンタンです。この記事では自己覚知が必要な理由とやり方を解説していきます。
ではまいりましょう!
社会福祉士の自己覚知とは?【必要な理由・方法をわかりやすく解説】

自己覚知が必要な理由
自己覚知が必要な理由は、自分を使って支援するからです。
「自分」とは、例えば次のような要素ですね。
- 見た目の特徴
- 声
- 捉え方のクセ
- 考え方のクセ
- キャラクター
- 個性 など
支援とは、こうした自分自身を通して、利用者さん、患者さん、メンバーさん等と関わることです。
なので、自分自身を理解することが大切なのです。
理解するのは、長所にかぎりません。短所など負の一面も含めるのがポイントです。
自己覚知せずに支援するというのは、
例えていうなら、お医者さんが薬の効果も知らずに処方するようなものです。

この薬、よくわからん薬ですけど飲んどいてください。
こんな医者、ヤバいですよね。
実際の医師の方々は、薬の効果を理解して処方しますね。薬には効果がありますが、副作用もあります。メリット・デメリットを理解・説明して処方しますね。
これは社会福祉士をはじめ、福祉現場で働く私たちも同じです。
- 私は人にどのような影響を与える人間?
- どんな長所や短所がある?
- 特性がある?
- どんな人が好きで、どんな人が嫌い?
これらを知ることで、自分の使い方がわかり、利用者さん等への関わり方がわかります。
例えば、「利用者さんにどう関わって良いかわからない・・・」という悩みはよくありますが、この課題の背景には自己覚知の課題もあるんですね。
自己覚知して初めて関わり方がわかるのです。社会福祉士にはそれくらいマストなことです。
自己覚知の方法3つ

自己覚知が大切なのはわかったけど、どうやったらいいの?

3つ解説します!
1人で自己覚知
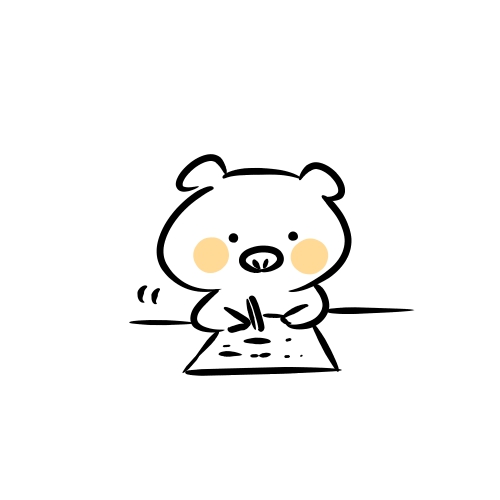
支援の1つ1つについて、その都度内省するように振り返る方法です。
オススメは、紙に書き出すことです。
理由は、紙に書き出すことで、客観的に振り返りやすくなるからです。
ノートやルーズリーフ、手帳、どんな紙でも構いません。
気持ちがリアルなうちに、紙に全てかき出すことがポイントです。

書いてるヒマがない時はどうしたら?
忙しくてメモを書く時間もない時は、例えば頭の中で
- 「どうして私はさっきのような言葉をかけたのだろう?」
- 「俺が〇〇さんを避けたくなる理由は何だろう?」
- 「△△さんと距離が近づきやすいのはどうしてだろう?」
このように、自分の行動や気持ちに質問をするのです。「どうしてだろう?」と。
これで自己覚知をすすめられます。
ただし、自分で振り返る方法にはデメリットもあります。
それは、自分で気づけないポイントは、いつまでも気づけないということです。
誰でも経験があると思いますが、人に言われて初めて気づくことってありますよね?
自己評価と他者評価には違いがあるものですが、いずれが正しいにせよ、どのように人から見えているのかを知ることは重要です。
薬で例えるなら、自らの薬効を理解して活かすことになりますね。
そこで、人と振り返る方法が有効です。
人と振り返って自己覚知
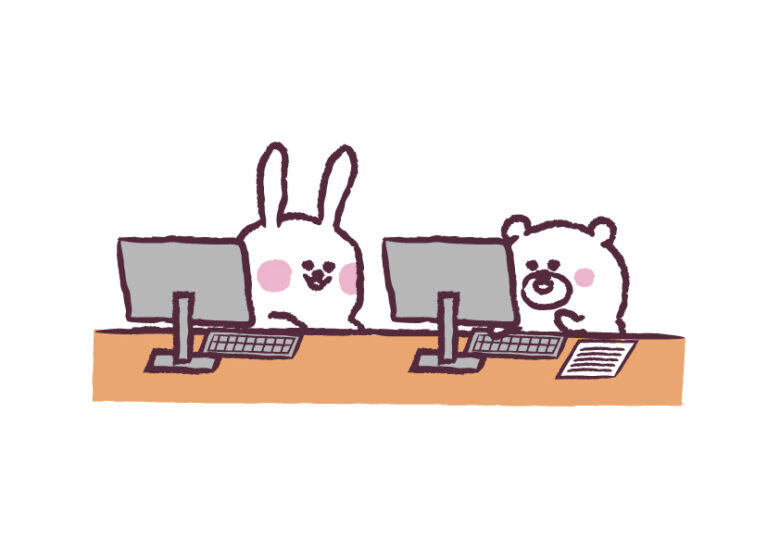
支援を職場で振り返るなかで、あなたの特性や支援のクセを知る方法です。
メリット・デメリットは次のとおり。
- メリット:意見や指摘をもらえるため、自分では気づけないポイントに気づくことができる
- デメリット:傷つくかも(悲)
人から指摘されるのって、怖いですよね。「お手柔らかにお願いします」「俺のLIFEポイントは0ポイントだ!もう勘弁してくれー!」みたいな。
これ、自己覚知のあるあるなんです・・・(泣)
自己覚知は、私たちのありのままを直視することです。
他人にダメ出しされたり、痛いところを突かれたり、すごく恥ずかしい内面をさらけ出すことにもなります。
「こんな自分はダメだ・・・」と思うこともあるはず。私は幾度とありました。
直そうとする努力も時に必要ですが、「これが自分だから許してあげよう」という受け容れる気持ちも大切にしていきましょうね。
自己覚知は心の修行です。普通は楽しくできるものではありません。
でも、自己覚知の修練を続けている人こそが、社会福祉士や精神保健福祉士、福祉職のプロフェッショナルです。
自己覚知をしていない人というのは、自分の課題をおざなりにして、周りの課題ばかりに目を向けてしまいます。
したがって、クライエントや関係機関、他者のせいにばかりしてしまい、見立てを間違ったり、支援を間違ったりします。良い質の支援もできません。それって、とてもカッコ悪いんです…。
でも、あなたはこのような記事をご覧なので、きっとできます。私は信じていますよ!
事例検討

事例検討はご存知でしょうか?
事例検討の苦しみを乗り越えた事例提供者は、レベルアップします。
事例検討にはいろんな形がありますが、
例えば1つのケースについて、事例提供者が成育歴や支援を報告し、困っていることや検討したいことを話します。
これを参加者間で意見交換して、より良い支援を考える、というパターンが多いですね。
この事例検討、経験のある方ならわかると思いますが、事例提供者はけっこうツライです。
理由は次のとおり。
事例検討がツライ理由
- 事例提供者は準備(資料作成など)が大変
- 当日の事例検討が怖い
- 緊張する
- ダメ出しをくらう
- 終わってから落ち込む・・・
といった具合で、辛い課題となりがちです。
事例提供者は、わかっていないこと、自らの支援のクセに直面します。
批判されているわけではなくても、さまざまな質問を受けるので辛くなることがあるでしょう。
なので、多くの人が怖がったり、面倒がったり、避けがちです。
しかし、事例検討のチャンスがあるなら経験しないと、成長機会を失うかもしれません。
事例検討ができる機会はそう多くありません。
ダメ出しもあるので、若手の間でなければ参加し辛いものです。
しかし、覚悟を決めて事例検討に挑めば、自己覚知がすすみ、支援レベルが上がるのです。
【具体例】わたしの自己覚知

自己覚知あるある 「自分はなんて悪い奴なんだ」「こんな一面があったなんて、恥ずかしすぎる・・・」と思う
例えばで、わたしの体験した自己覚知の話をします。
(学校でレポートを書かないといけない人にとって、役立つ話かもしれません)
学生の頃、福祉の仕事を志した動機は「人のためになりたい」でした。
(そう自覚していました)
しかし、どうして私は人のためになりたいのか?理由はよく考えていませんでした。
わたしはそのまま社会人になって、支援を始めました。
深く考えるきっかけになったのは、障害福祉の作業所で、あるクライエントの支援を上司に報告している時でした。
わたしは熱心にやっている支援を得意気に報告したのですが、上司の顔は真剣そのもので温度差がありました。
上司には、わたしが専門職としての根拠や意図なく動いているように見えたようです。
上司から「どうしてあなたはその支援をするの?」と問われ
私は言葉に詰まりながら
「困っているから」
「支援した方が良いから」
など、取ってつけたような理由を言ったように思います。上司からは、
「それは支援が必要な根拠じゃない」
「その人にどういう障がいがあって、どういう支援がいるのか考えないと」
と、指摘を受けました。
厳しい話ですが、意図や根拠なく行っている支援は、自分の感情に任せたものであり、支援と呼べるシロモノではないという話でした。
けっこうガーンときたんですけど、指摘には納得した私。
「このままではいけない」と思って、病気や障害に関する本をたくさん読みました。本の中には、自分自身のしんどさに通じる内容がありました。
それで気づいたのです。わたしは自分のために支援をしていたということに。
わたしは「人のためになりたい」という動機で福祉の仕事を志しましたが、
さらに深めていうと、「人のためになりたい。なぜなら自分の無価値観を埋めたいから」という動機だったのです。
自己覚知をすすめた結果、ピュアで善にあふれた気持ちなどは偽りで、自己利益や自己都合だらけと気づかされました。
自己覚知で嫌な自分に気づいても「だけど、自分はこれで良い」と認めてあげよう
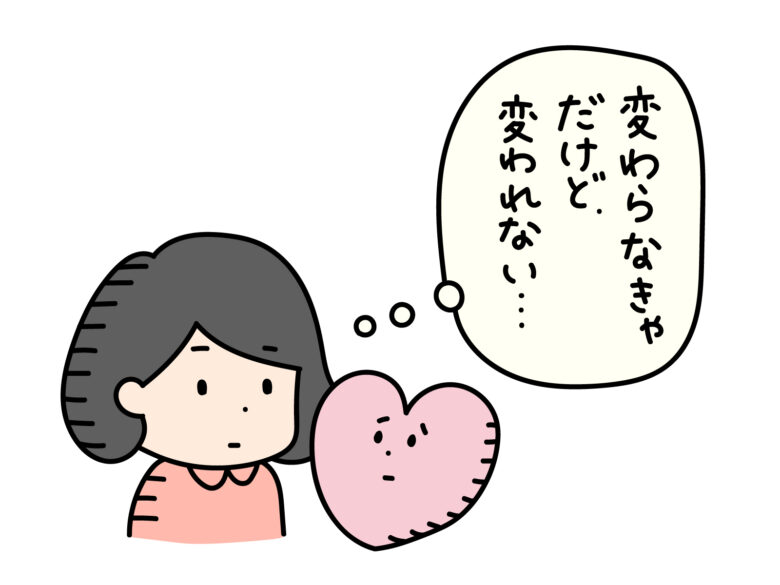
世の中には、「福祉の仕事をする人は素晴らしい」というイメージがあるかもしれません。
しかし支援者たちの心の内を掘り下げてみると、人のためより自分のために働いているのが普通だったりします。
もしかしたらあなたも、自己覚知をすすめる中で、自分自身の嫌な面、認めたくない部分に直面するかもしれません。
だからといって、自分自身を責めることはありません。責めても何も得られませんし、傷つくだけです。
むしろ、「だけど、自分はこれで良いんだ」と声をかけてあげてください。
「自分自身を変える」という考え方は大切ですが、「こんな自分はダメだから変えないといけない」と考えると苦しいです。
自己覚知の目的は、自らを変えることや否定することではありません。
気づいていなかった内面に気づき、自覚し、支援のクセを軌道修正できるようになることです。
例えば私で言うなら、「自分はこのタイプの人をついつい過剰に支援しようとしてしまうから、一呼吸置いたり、周りに意見をもとめるようにしよう。」という具合です。
もしかしたらあなたには、利用者さんを嫌う気持ちが沸き起こることがあるかもしれません。
しかし気持ちを自覚して、対応できれば良いのです。こちらの「【利用者が嫌い・苦手!】でも全く問題ない理由【社会福祉士解説】」でも解説しています。
もし、ご自身の受け容れがたい面に気づいても、優しく包んであげてくださいね。
自己覚知では「家族歴史の棚卸し」がカギになる
自己覚知をすすめるなかで、自らの特性・長所・短所・感じ方などの理由をほりさげていくと、過去にさかのぼっていくことになります。
つまり、あなたの家族史を振り返ることになります。
自分自身がどのような家庭で育ったのか、親、祖父母、兄弟姉妹、ご近所、勉強、スポーツなど、さまざまな経験を振り返ることになります。
自らの幼少期や成育歴を振り返ることで、より深い自己覚知ができるようになります。
「三つ子の魂百まで」といいますが、家族歴史を振り返ると、子どもの頃の環境が今現在につながっていることがわかるはずです。
家族歴史を棚卸しするときには「愛着スタイル」について理解しておくと、自己覚知が進めやすくなります。
愛着スタイルは、私たちの根底で、対人関係や感情、認知や行動を左右しているものです。どのような対人関係を結ぶかのベースとなります。
この愛着スタイルは、主に親との関係によってつくられます。
つまり、私たちが日ごろ人と結ぶ対人関係のモデルは、親との関係にあるのです。
さらに言うと、愛着スタイルは支援関係にも強い影響を与えています。
なので、母親との関係、父親との関係、夫婦の関係、親の不在、いるけど存在感が無い等。
こういったことを振り返ると、さらに自己覚知がすすみ、より良い支援ができるようになるのです。
人によっては辛い作業になると思います。これも、私が自己覚知を心の修行と呼ぶ理由です。
恥ずかしながら、プロフィールでは私の育ちを一部公開しています。あなたの参考になるかもしれません。
より高度な自己覚知を実現したり、愛着を理解してより良い支援をしたい方には、精神科医の岡田尊司氏の下記の本がオススメです。
岡田氏は愛着についての第一人者です。福祉現場で対人支援をする社会福祉士・精神保健福祉士・介護職等の方なら知っておいて損することはない一生ものの知識が得られます。
2011年発刊ですが、こうした知識は色あせるものではありません。
マンガが良い方はこちら。岡田尊司氏の著書なのでエッセンスは同じです。
最後に 自己覚知で辛くなったら

あなたが自己覚知をすすめるなかで、
「こんな私は社会福祉士に向いていないのでは」
「精神保健福祉士に向いていないのでは・・・」
と悩むことがあるかもしれません。
そうした方へ向けて↓の記事も書いています。
私にも経験があるのです。
「向いてない」
「あの人の方が向いている」
何度考えたか・・・。だからそう感じてしまう気持ちに、とても共感します。
正直に告白すると、現場経験10年超となった今でも、「この現場にオレは向いてないなぁ」と思うことはあります。
自己覚知を続ける中で、自らの得意・不得意もわかったし、残念ですが努力しても変えられない自分の特徴もわかってきました。
未だに、苦手な部分で仕事につまずくとこたえます。
でも、もはや克服するとか、否定するとかではなく、「だってこれが俺だもの」と思うようにしています(笑)
10年以上向き合って変わらなければ、さすがに受け容れるしかない、と思うのです。
苦手な部分の克服にとらわれると、辛くなるばかりです。
支援ではストレングス視点といって、利用者さん達の強みや長所に目を向けますよね。
ならば、自身についても、ストレングス視点をもって見てあげたいですね。その方がよほど前向きだし、結果的に成果もついてくると思います。
ぼちぼちで。やっていきましょう!
自己覚知についてもっと知りたい方へ
こちらの記事でも自己覚知の必要性ややり方を書いていますので、よろしければご覧くださいね!









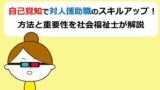
コメント