こんにちは。私は某自治体で働く社会福祉士・精神保健福祉士です。現場経験はおよそ14年で、いちばん長い職歴は児童相談所の児童福祉司です
今回、「プーさんを児童虐待で保護すべきか?-ソーシャルワーカーの想像力と文学性」という本を読んでみました。
この本は、ディズニーのキャラクター「くまのプーさん」が5歳の子どもだったら、児童相談所の職員としてどう対応するかという話から始まります。
最初は冗談かと思いましたが、読んでみるととても面白かったです。
この本をおすすめするのは、以下のような方。
本書をオススメする人
- 児童相談所・児童福祉司の仕事を知りたい人
- 福祉現場で記録を書いている人
- スキルアップしたい福祉職の人
この本は、児童相談所の職員がどんな仕事をしているか、どんな視点や考え方が必要か、どんな課題や難しさがあるかを教えてくれます。
そして、『記録』はソーシャルワーカーの想像力と文学性によって書かれるという、鋭い指摘をしている超マジメな本でもあります。
私が解釈した、本書の要点は次のとおり。
本書の要点
- 記述や説明は『物語』だ。
- 『物語』なので、各ソーシャルワーカーの想像力や文学性によって仕上がりが変わる。
- 『物語』という不確実なものなのに、人の人生を変える権力をもつ。
- このことを自覚して、自らの記述と説明の質を高めることが大切。
- でも、限界はあるから、いつまでも反省的でいよう。
とても面白かったので、シェアしますね。
【書評】プーさんを児童虐待で保護すべきか?|児相経験者おすすめ!
プーさんについて
プーさんをよくご存知でない方もいると思います。でも大丈夫。
この本は、「くまのプーさん」のストーリーを知らなくても読めます。失礼ですが、私も「はちみつをなめてるクマ」くらいしか知りませんでしたが、楽しく読めました。
『プーさんを児童虐待で保護すべきか?-ソーシャルワーカーの想像力と文学性』の内容
プーさんの調査とアセスメント
この本は、住民(?)からの通告をもとに、調査がすすめられます。
- プーさんの年齢
- 健康
- 検診情報
- 食事
- 精神状態
- 保護者の存在 など
多角的に深く分析されていきます。リアルですねぇ。児童相談所の業務をよくわかっておられると感じました。
例えば、プーさんの状態と見立てについて、次のように書かれています。
プーさんは普段から完全に下半身を露出しています。ボディラインがはっきりとわかるピチピチの赤いTシャツを着ているだけです。そして何より、プーさんはそのことに羞恥心を抱いていません。性に関する観念にも歪みがあると考えられます。
引用元:プーさんを児童虐待で保護すべきか?-ソーシャルワーカーの想像力と文学性 篠原拓也ゼミ「プーさん会議」著(2021)
扱うのがやはりプーさんなので、滑稽だったり、非現実的だったりしますが(笑)
プーさんは下半身を露出していることに気づいていないし、はちみつばかり食べているし、友だちとトラブルになったりすることもあります。
これらのことは、プーさんに何か虐待などの問題があるのか、それともプーさんの個性なのか?
そして、プーさんを一時保護する必要があるのか、それとも自分たちが関与するべきではないのか?
この判断をする材料は、『ソーシャルワーカーが記述・説明する物語だ』という話につながります。
ソーシャルワーカーが記述・説明するのは権力的な『物語』
記述や説明は主観的なものです。
例えば、児童福祉司がケース記録で事実だけを書こうとしても、何を書くか否かを選別するのが人である時点で、100%客観的であることはできません。
記述・説明のいかんによって、ケースという物語はいくつも成り立ちます。
しかも、そうして出来上がった物語によって、児童相談所では『一時保護すべきか否か』の判断をすることになります。
一時保護は保護者から子どもを強制的に引き離す行政処分です。強い権力性が備わっています。
だから、記述や説明は権力的だと言うのです。
私たちの記述・説明の能力は、いつだって限られた認識枠組と語彙の中でなされる不十分で権力的なものです。
引用元:プーさんを児童虐待で保護すべきか?-ソーシャルワーカーの想像力と文学性 篠原拓也ゼミ「プーさん会議」著(2021)
このことは、児童相談所や児童福祉司だけじゃなくて、福祉の現場で記録を書く福祉関係者すべてにあてはまります。
記述・説明する人がかわれば、その記述や説明も変わり、ケースという物語もかわる。
児童福祉司に限らず、ソーシャルワーカーの活動は、『ソーシャルワーカーの想像力と文学的能力に依るところが大きい』と言うのですね。
最後に
「プーさんを児童虐待で保護すべきか?-ソーシャルワーカーの想像力と文学性」は実にユニークな切り口で、しかし真面目に、児童福祉や児童虐待を扱っています。
現場で記録を書いたりケースの説明をする身として、気の引き締まる思いがしました。
ソーシャルワーカーをめざす学生だけじゃなく、すべての福祉関係者の方におすすめできます。

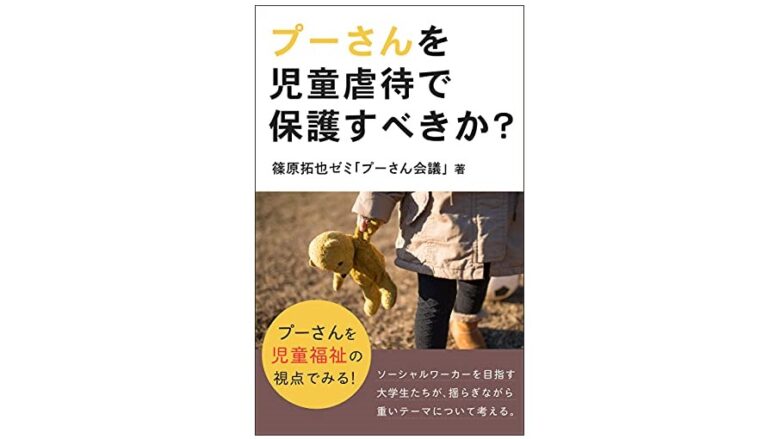
![プーさんを児童虐待で保護すべきか?[新版]](https://m.media-amazon.com/images/I/51SCdE9QVoL._SL160_.jpg)

コメント