
児童相談所って、どんな仕事してるのかな?児童福祉司ってどんな役割?「走れ!児童相談所」っていいの?
こういった思いの方へ。
この記事の内容
- 児童相談所ってどんなところ?【報道と実際】
- 『走れ!児童相談所』の著者と内容
- 私が『走れ!児童相談所』を読んだきっかけ
- 児童福祉司を経験してから再読して思ったこと
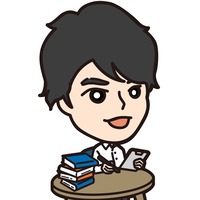
私は某自治体で働く社会福祉士・精神保健福祉士です。児童相談所での児童福祉司経験があります。
児童相談所は、テレビや新聞では「子どもを救えなかった」という見出しで、書かれることが多いですね。
しかし、そうした報道だけが児童相談所や児童福祉司の全てなのでしょうか?
答えは、もちろん違います。
この記事では、私の経験をもとに児童相談所や児童福祉司のリアルを話し、
児童相談所のリアルを知れる著書『走れ! 児童相談所 発達障害、児童虐待、非行と向き合う、新人職員の成長物語』をご紹介します。
【経験者書評】『走れ!児童相談所』は児童福祉司が小説でわかる本!
児童相談所ってどんなところ?【報道と実際】

児童相談所は、子どもの権利や幸せを守るために、さまざまな相談を受けたり、支援するところです。
でも、テレビや新聞では、児童相談所の悪い話ばかり聞きませんか?
- 児童相談所は子どもを助けられなかった
- 親から子どもを無理やり引き離した
- 事実がないのに虐待してると決めつけた
しかし、多くの報道は児童相談所のリアルな姿を明らかにしていないし、視聴率を稼ぎたくて視聴者の感情をあおっているようにしか見えません。
なぜなら、ネガティブなニュースばかりを垂れ流しているから。
児童相談所のリアルを報道したいのであれば、児童相談所が子どもを救ったことも報道すべきです。
実際には、相当の数の子どもたちの命を守り、保護者さん達を支援しています。
しかし、そうした良いニュースは報道されませんよね?
なぜでしょうか?
私は、児相のポジティブな話をニュースにしても『視聴率』が取れないからだと考えています。
人の関心をひくのは、ポジティブなニュースより、ネガティブなニュースです。
「児相が子どもを救った!良かったですね!」というニュースを流しても、視聴率は取れませんね。
それよりも、

無実の子どもが、ひどい親に虐待されていて、助けを求めていたのに助けてもらえなくて、児童相談所は知っていたのに助けられなかった。皆さんどう思いますか?
という報道の方が、人の関心を惹きつけられます。
人には『ネガティブ本能』があります。
カンタンに言えば、ネガティブな情報を重要だと思ってしまうし、耳が傾いてしまう。こちらの著書で紹介されてもいます。
だから、児童相談所など、誰かしらを悪者に仕立てた報道をバンバン流せば、視聴率が取れる、お金がもうかるわけです。
しかし、こうした報道ばかりでは、子どもや子育てに困っている保護者さんのためになりません。
メディアでイメージが刷り込まれてしまった保護者さんは、児童相談所に相談しにくいし、関わりたくないと思うでしょう。
そして、相談できない保護者さんは孤立が深まり、児童虐待が起きる温床となってしまうのです。
不利益をこうむるのは、子どもです。
実際、保護者さんとしては『児童相談所が関わってくる=虐待している親だと思われている』というイメージが強くなっていて、児童相談所を警戒する人が多いです。
しかし、本来、児童相談所は子どもの味方です。
子どもを安心して育てられるように、保護者さんにアドバイスしたり、必要なサービスを紹介したり、一緒に解決策を考えたりします。
確かに、子どもよりも自分の利益を優先している保護者さんとは、対立することがあります。
時には、危険な状況から子どもを守るために、一時保護など、強い権限を使うこともあります。
しかし、これは最後の手段です。
子どもの利益を第一に考えている保護者さんとは、協力関係になれます。
児童相談所の仕事は大変ですが、やりがいもあります。
例えば、虐待対応の第一線では、保護者さんからは煙たがられたり、対立したり、緊張感のある関係として始まっても、
粘り強いかかわりや、一時保護などを経て、時に子どもや保護者さんの笑顔を見ることがあります。
『報道されることが児童相談所の全て』と思う人が増えるのは問題です。
今回、わたしが紹介する『走れ! 児童相談所 発達障害、児童虐待、非行と向き合う、新人職員の成長物語』も、そうした問題意識から書かれた本です。
『走れ!児童相談所』は児童相談所や児童福祉司が小説でわかる本

児童相談所や児童福祉司に興味がある人におすすめの本、それが『走れ! 児童相談所 発達障害、児童虐待、非行と向き合う、新人職員の成長物語』です。
この本は小説ですが、著者は本当に児童福祉司だった人です。5年間の経験をもとに書かれています。
著者は、児童相談所の本当の姿を伝えたかったそうですね。
少し引用させていただきます。
最近では福祉を志す若者でも児童相談所は敬遠する傾向にあることや、児童相談所の本当の姿が世の中にはまったく知られていないため、子育てに悩んでいる人がいても、気軽に相談に来ないのではないかといったことが話題に上りました。
その時、児童相談所を正しく描いた小説でもあれば、随分違うんだろうなっていう意見が出たんです。
引用元:(株)アイエス・エヌHP [インタビュー] 著者・安道理氏
本書の主人公は、福祉に関係のなかった部署から児童相談所に異動してきて、ケースワーカー(児童福祉司)として働くようになります。
この本を読むと、児童相談所がどんな仕事をしているのかや、どんな困難、喜びがあるのかがざっくりわかります。
実際にあった事例がベースになっているので、リアルです。
例えば、1巻では下記の内容がわかります。
- 児童相談所職員の仕事と心構え
- 福祉専門機関として必要な技術、ノウハウ
- 非行相談への支援
- ネグレクト家庭のエンパワメント
- 発達障害児と保護者の苦悩
- 立入調査の現実と里親制度による被虐待児への支援 など
引用元:『走れ!児童相談所』帯紙
主人公は、最初はわからないことだらけで戸惑いますが、先輩や同僚から教えてもらったり、自分で勉強したりしながら成長していきます。
主人公が色々な仕事を経験することで、読者にも幅広く知ってもらえるように工夫されています。
あくまでストーリー主体なので、よくある学習マンガのような勉強くささは感じません。
私が『走れ!児童相談所』を読んだきっかけ

私がこの本を読んだのは、児童福祉施設で働いていた頃でした。
職場では、職員同士で「児童相談所が〇〇してくれないと〇〇できない」といった不満話をよくしていました。
まるで、児童相談所がなまけているみたいに。
でも私は、「ほんとうに児童相談所ってそんなにひどいのか?」とギモンにも思いました。「相手の立場にたてば、違った景色が見えるんじゃないか?」と思ったんですね。
加えて、施設に入所してくる子どもは、必ず児童相談所を経由していました。
それで、「児童相談所ってどんな所なんだ?どんな仕事をしてるんだ?」と気になって読んでみたのが、この本でした。
※私が読んだのは旧版
私はこの本を読んで、児童相談所のリアルを知って、児童相談所の立場を共感的にくみとりやすくなりました。
児童相談所には児童相談所の正義がある。努力と苦労があるとわかる。
そうした現実がわかると、児童相談所だけをこき落とすような言い方はできなくなります。
児童福祉司になってから、改めて読んで思ったこと

私はこの本を読んだのちに、縁あって児童福祉司となりました。
それからこの本を改めて読み返してみたんですが、本書の紹介事例は幅広いですね。
きっと、著者は児童相談所のリアルを伝えるべく、全体像がわかるよう工夫したのでしょう。
例えば事例には、次のシーンがあります。
- 児童心理司の発達相談場面
- 非行少年の面接
- 継続指導中と思われる家庭への訪問
- 一時保護 など
幅広いです。
補足させてもらうと、近年の児童相談所では、業務分担されていることが多いです。例えば次のように。
- 介入班(虐待係)
- 支援班(相談係)
- 心理判定係 など
なので、実際の児童福祉司の職務は、本書の児童福祉司よりも限定的だと思います。
立入調査も紹介されていますが、全国で年間100件前後です。児童相談所によっては年間1件もないことがありますので、けっこう特殊なシーンです。
≫参考:厚生労働省 児童虐待防止対策の状況について
どうしても小説やマンガで絵になるのは、立入調査や臨検・捜索のような、行政処分をする時なのでしょう。
これは致し方ないですね。「新・ちいさいひと 青葉児童相談所物語」にもそうした傾向はあります。
それでも、『走れ! 児童相談所 発達障害、児童虐待、非行と向き合う、新人職員の成長物語』は脚色しすぎることなく、児童相談所・児童福祉司のリアルが書いています。
児童相談所・児童福祉司のリアルを知るなら、「ちいさいひと」シリーズよりも、こちらの方がおすすめです。
児童福祉司に興味のある方なら読んでおいて損はないと思います。
【旧版はこちら】
児童福祉司の仕事は大変ですし、福祉職のなかでは異色です。しかし、子どもの利益につながる大切な仕事です。
児童福祉司になる方法はこちらの記事でわかります。

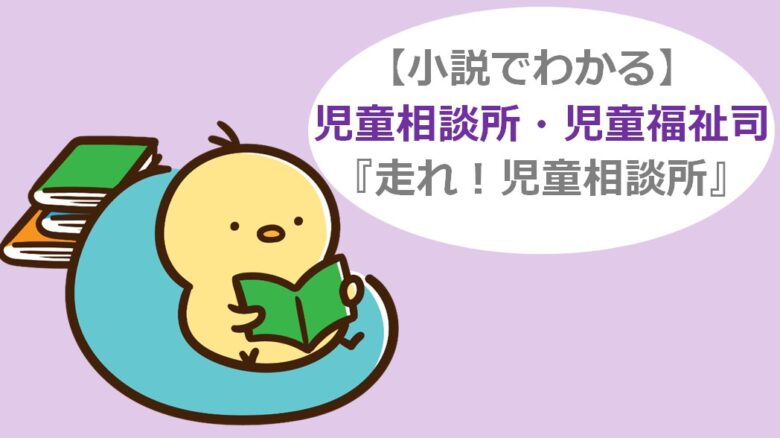



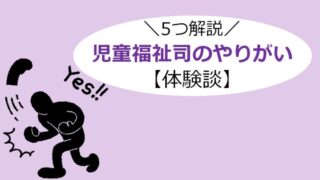








コメント