
社会福祉士とか精神保健福祉士に向いている人ってどんな人?

継続してみて初めて分かると思う。
やる前からはわからないだろうな。
どうも!社会福祉士・精神保健福祉士のぱーぱすです。現場経験は約10年です。
「社会福祉士や精神保健福祉士に向いているのはどんな人?」ときかれれば、
- 優しい人
- いつもニコニコできる人
- コミュニケーションの得意な人
- 人と関わるのが好きな人
といった答えがあると思います。
でも、こういった意見をうのみにして社会福祉士や精神保健福祉士をめざしても、現場に出てから苦労することが必ずあるでしょう。
「私は向いてるんじゃなかったの!?」
と、壁につきあたるかもしれません。
そもそも、向いているかどうかが気になる根底には「幸せになりたい」「不幸になりたくない」という思いがあるものです。
向いた仕事を選ぶことで幸せになれると誰もが思うでしょう。
かく言う私も、社会福祉士や精神保健福祉士に向いているのかどうかと思い悩んだ時期がありました。
でも今は、そうやって「向いてるかどうか」と悩むこと自体、あまり意味がなかったように思っています。
向いている人をあえて答えるなら、「社会福祉士や精神保健福祉士の仕事を続けられた人」と私は言います。
「続けられた」と過去形な理由は、仕事選びの段階では、向いているか向いていないかは判断できないと思っているからです。
このあたりを詳しく話していきます。ではまいりましょう!
社会福祉士や精神保健福祉士に向いている人とは?
「コミュニケーションが得意な人は向いている」は本当か?

社会福祉士や精神保健福祉士に向いている人として、よくある意見は「コミュニケーションの得意な人」「コミュニケーションの好きな人」でしょう。
でも、コミュニケーションの得意・不得意は関係ないと私は思います。むしろ、コミュニケーションの苦手な人のほうが、伸びしろがあって可能性を秘めていると思います。
確かに、もともとの素質が良ければスタートダッシュがきめられます。コミュニケーションが得意な人のほうが適性あるように見えます。
コミュニケーション能力は確かに必要だが・・・
コミュニケーション能力は大切なのは確かなことです。
例えば、利用者・患者さんは、自らの気持ちを100%わかっていて、100%誤解なく言葉で伝えてくれるでしょうか?
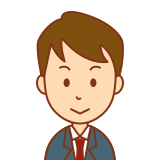
わたしの主訴は〇〇でして、解決したいことは〇〇なので、あなたに〇〇を助けてほしいと思って相談にきました。
こんな風にキレイに言う方はいません!
なので、質問を重ねて、理解をすりあわせて、事実を積み上げていくことになります。なので、コミュニケーション力が大切なのは確かです。
でも、社会福祉士や精神保健福祉士として「よーいドン!」と出発した時からコミュニケーションが得意じゃないといけないでしょうか?
コミュニケーションの苦手な人は、努力を重ねるプロセスで「どうすればコミュニケーションをうまくできるか」を知識的に理解していきます。
なので、コミュニケーションが苦手な人は「コミュニケーションをうまくする方法」を人に教える力を秘めています。
逆にいうと、はじめからコミュニケーションが得意な人は、感覚的に上手い場合が多いので、教えるのは苦手かもしれません。
つまり、初めからコミュニケーションがうまくなる必要はないのです。継続すれば問題なしということです。
こちらでも解説しています。キャリアガーデンさんへ寄稿した記事です。
向いていると思って社会福祉士や精神保健福祉士の仕事を選ぶのはリスク
「向いている」と思って社会福祉士や精神保健福祉士の仕事を選ぶのはキケンだと思います。。
なぜなら、失敗や挫折に直面したときに
「やっぱり向いていないのかな・・・」
「本当は適性が無いのかも・・・」
という気持ちのブレや自信喪失につながってしまうからです。
例えば、「感謝される仕事がしたい」と思っていたのに、全く感謝されない。むしろ、苦情を言われてクレーム対応することがあります。
「利用者のための仕事がしたい」と思っていたのに、会社や組織のエゴのために仕事せざるをえないこともあります。
「向いている」と思って社会福祉士や精神保健福祉士になってしまうと、嫌なことに出くわした時のギャップが大きくなります。
「やっぱり私にはやっぱり向いていない・・・?」と疑念を感じることもあるでしょう。
継続するうち天職になる【好きも情熱も後でついてくる】

私自身、福祉の仕事をはじめてからは苦労や挫折をさんざん経験して、「俺は向いてないんじゃないか?」と心底思ったものでした。
同僚や先輩の成長にくらべて「ぜんぜんできていない」と自信を失くしていました。
それでもこの仕事を続けてきた結果、私はいま、この仕事がライフワークだと思っています。
プライベート時間も仕事に関するブログを楽しんで書いているのです。たぶん、天職と感じているのでしょう。
これは、福祉の仕事を始めた頃には想像もつかなかったことですし、10年以上続けてきたからこそ至れた境地です。
ちなみに、続けているうちに好きになるのは私だけの話かと思っていたら、実はそうではなかったようです。
「やっているうちに好きになる」
「情熱が後からついてくる」
というのは研究にもとづく適職選びの専門書でも証明されています。
真の天職は「なんとなくやってたら楽しくなってきた」から見つかる
『科学的な適職 4021の研究データが導き出す、最高の職業の選び方』出版: クロスメディア・パブリッシング(インプレス) 著者:鈴木祐
「やってみたい」と思えたなら飛び込んでみよう
福祉現場を体験してみて「やってみたい」と思えたなら、めざす価値があると思います。
向いている、向いていないは気にしなくて良いと思います。考えても答えは出ないと思います。
熱意をもてるかどうかも気にしなくて良いと思います。熱意は、努力や時間をかけた結果、後でついてくるからです。
迷っている方は、福祉関係のアルバイトやボランティアを体験してみるのが良いです。やってみないと分からないからですね。
ボランティアを探すには、全国各地のボランティアセンターが活用できます。
アルバイトを探すならタウンワークが安心で便利だと思います。

最後まで読んでいただいてありがとうございます!それではまたね!

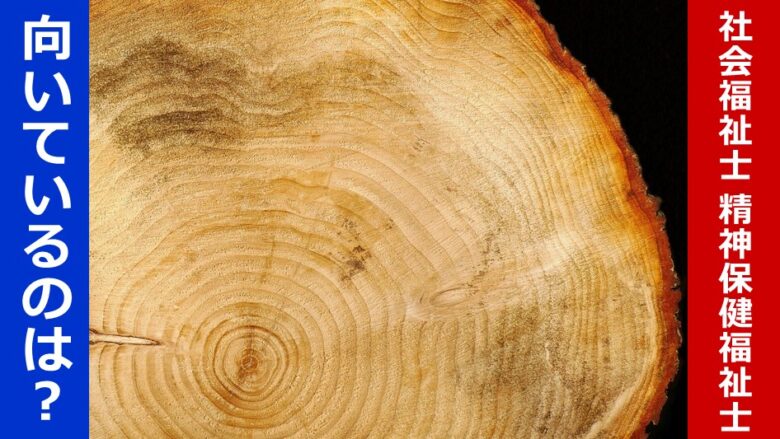
コメント