
こういった思いの方へ。
児童福祉司1年目の読者さんのご質問にお答えします

私は某自治体で働く社会福祉士・精神保健福祉士です。現場経験はおよそ13年で、いちばん長い職歴は児童福祉司です。
児童福祉司は、保護者が望まなくても、必要となれば介入しないといけません。
お互いの合意で支援するというより、保護者が望んでいない「支援」ってやつを、あの手この手で届けようとするんですね。
民間であれば交わすサービスの利用契約書などは、児童相談所と保護者の間にはありません。
むしろ保護者へ渡すのは、一時保護決定通知書や「児童福祉司指導措置をとりますよ」という通知書だったり。
望まれていなくとも、説明して渡すシロモノです。
ではこのように強制的に介入すれば、児童虐待は無くなるのか?
そんなことはありません。現実は厳しい。指導の論理で児童虐待が無くなるならば、警察からの注意で事足ります。
「虐待したらダメ!」と言うだけでは改善しないので、やっぱり支援がいる。しかし児童福祉司が支援しないといけないケースは複雑困難です。
例えば、子どもの利益と保護者の希望が対立することもあります。児童相談所が優先すべきは子どもの利益ですが、セオリー通りにはいかないんですね。
今回、そのような現場で奮闘する児童福祉司1年目の読者さんから、ご質問をいただきました。
児童福祉司1年目です|自分で支援を組み立てられない・・・対処法は?
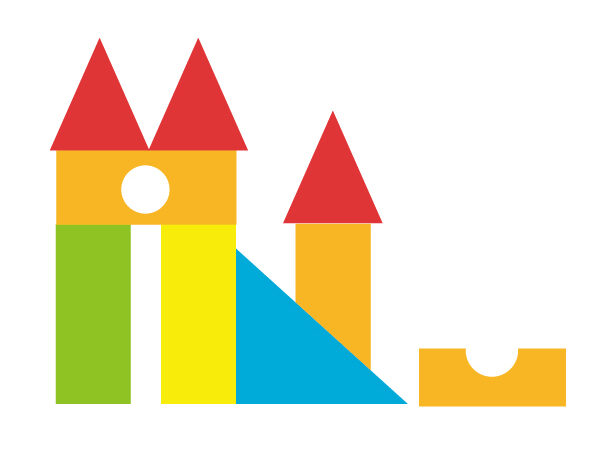
読者さんからのご質問(抜粋)
業務に関して。私の現状は、自分でケースの組み立て方がわからず、先輩にアドバイスしていただいたものをそのまま実行しているような感じです。
ケースに対して、自分はどうしたいか、どういう選択肢があってどういう方向性で進めたいかがなかなか思いつかず苦労しています。
先輩に助言されて、「あ、なるほど」となるのです。
もちろん経験を積み重ねていくしかないと思っているのですが、今すぐ現状を打破したくてモヤモヤしております。
私のお返事
お悩み、よくわかります。
児童福祉司をしていると、先輩や上司から「君はこのケースをどうしたいの?」とよく聞かれたりします。ちょっと意地悪な人もいたりして。答えに困ってしまうんですよね。
どうしたいも何も・・・どう考えて良いのか、どういう選択肢があるのかわからないわけで。
これは児童福祉司に限らず、対人支援で多くの人がつまずくことかもしれません。
しかしお気づきのとおりで、私の結論も「特効薬は無い」ということです。
福祉現場でのこれまでを振り返ると、わたしも『特効薬』のようなものを探し求めていた頃があります。一気にレベルアップみたいな方法はないものかと。色々試しました。
しかし、そうした方法は無かった。マンガや小説のようにはいかないですね・・・。
ではどうしたら良いかというと、知識(経験)を増やすことと思います。
なぜなら、支援の選択肢・方向性などは、思い付きやセンス、発明するようなものではないからです。
職場で先輩たちが、アドバイスなどをしてくれたとしても、それは全くのオリジナルではなく、今までのやり方から言っていることが大半でありましょう。
例えば、くまもんをデザインした水野学氏の著書に『センスは知識からはじまる』という本があります。
この本の要点は、センスというのは才能やひらめきが必要と思われがちですが、実は、既存のものの応用や、既存のもの同士のかけ合わせである、という話です。
つまり、知識があればセンスはつくりだせる、ということです。才能では無い、と。
わたしたちの職務も同様です。
支援の選択肢や方向性、どうするかという話は、考えれば思いつくというよりも、まずはたくさんの知識(経験)が必要なんですね。
年月とともに経験は増やせます。ひたすら耐えながら続けているだけでも、いずれは慣れてラクにはなれるはずです。
これにかかる年月を早めるには、先人の人生の集積である「本」から知識を得るのが有効です。
(こちらの『児童福祉司に向いていない?続けられるか不安・・・私はどうしたか?』で紹介している手引きやガイドラインも方法の1つです)
それと使い古された言葉ですが、修行では『守・破・離』が大切といわれますね。
はじめは先輩たちのやり方を、その通り真似ること。
読者さまは今は「守」のステージにおられると思いますので、それで良いのではないかと思います。今のままでも順調ということですね。
いずれ、「破」にうつっていくはずです。
応援しております!




コメント