
ボクは児童福祉司に向いていない?この先も続けられるか不安・・・どうしたら良いんやろ・・・
こういった思いの方へ。
児童福祉司1年目の読者さんからのご質問にお答えします。

私は某自治体で働く社会福祉士・精神保健福祉士です。現場経験はおよそ13年で、いちばん長い職歴は児童福祉司です。
児童相談所の児童福祉司(ケースワーカー)はほんとうに激務です。
連日報道される、子どもの虐待。重大事件になることもあり、対策として児童福祉司の増員がすすめられています。
しかし各自治体では、児童福祉司の募集に定員割れが起きるほどの事態で、目論まれたようには集まっていません。
児童相談所は不人気職場なんですね。理由は過酷すぎるからでしょう。
しかし中には、使命感をもって児童福祉司になる方がいます。
今回、児童福祉司1年目の読者さんからご質問いただきました。
児童福祉司に向いていない?続けられるか不安・・・私はどうしたか?
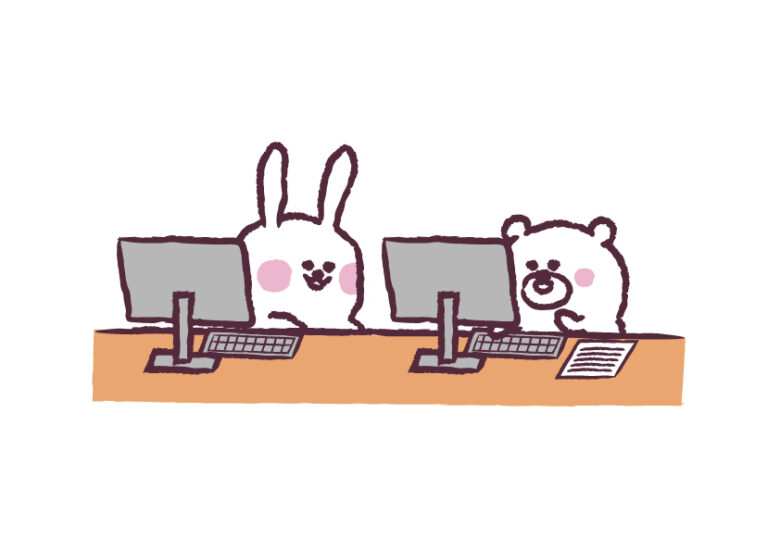
読者さまからのご質問(抜粋)
とても興味深くブログ拝見しております。
3年前に社会福祉士資格を取得し、兼ねてから目標だった児童相談所の児童福祉司として従事するようになりました。
今はまだ学ぶことも多く、周りについていくのがやっとな状況ですが、日々奮闘しております。
しかし目標であった児童福祉司にやっとなれたにも関わらず、
自分には児童福祉司の仕事は向いていないのではないか?
長くこの仕事を続けていくことは難しいのではないか?
いつかバーンアウトしてしまうのではないか?
と、不安に思う気持ちがとても強いです。
ぱーぱすさんは、日々の多忙な業務の中でどのような心持ちで働いていましたか?
福祉業界で長く働く上で、大事にされてることは何でしょうか?
私のお返事

状況や心中、お察しいたします。ほんとうに、ほんとうにお疲れ様です。
わたしも「いつか自分が病むのでは?」と思いながら、児童福祉司をしていました。
児童福祉司の職務は、福祉現場の中ではとても特殊と感じます。
特に最近の児相は福祉警察化していて、虐待の取り締まりを期待されるし、保護者さんや子ども、関係機関からもそういう目で見られていますね。
配属当時は「オレは福祉の仕事をしたくてこの仕事を選んだんだけど?」と、釈然としない思いをしていました。
自己決定をもとに「その人の希望によりそって」など、ケースワーク上の原則がまるで忘却の彼方という感じでした。
- 自分には福祉司の仕事は向いていないのではないか?
- 長くこの仕事を続けていくことは難しいのではないか?
- いつかバーンアウトしてしまうのではないか?
と不安に思う気持ちがとても強いです。
わたしも同じ気持ちでした。周りで休職・退職する人も出てきますよね。
いったい、児童福祉司の何がやりがいなのか?何をめざしているのか?誰のためになっているのか?
よくわからなくなることもありました。
メンタルをいかに保つか
私のメンタルは強くありませんが、休職するようなことはなくやり遂げられた理由は何だったか考えてみますと
まずは次の習慣に救われていました。
- 運動の習慣
- 睡眠の死守
- プライベートで仕事を忘れるくらい没頭できる趣味(ブログや読書など)
これらは心身の回復力につながっていました。人一倍、気をつけていたことです。
次に、仕事上のモチベーションというか心持ちですが、次の記事にまとめたことがあります。
しかし正直に申し上げて、これでも苦しみは強かったです。
周りに聞かないとわからない状況の頃は、面白みなどありませんでした。
自分の担当圏域が、まるで児童虐待だらけの地域にみえたり。
ところが丸2年ほど経った頃からは慣れて、おさえどころがわかるようになってきて、
保護者さんの苦しみに共感できることや、ケースを関係機関へつなぐことができたりして、「案外良いものだな」と感じることが増えていました。
いつの間にか「周りについていくのがやっと」から、「このケースはこう進めたい」と思って、いくらか自分の裁量で進められるようになっていました。
こうなった頃には、バーンアウトの懸念からは脱して、やりがいを得られるようになっていきました。
ノウハウの拠り所は何か?
私のノウハウ上で拠り所になっていたのは、次の資料です。
- 子ども虐待対応の手引き
- 児童相談所における性的虐待対応ガイドライン
- 児童福祉司のコンピテンシーモデル
- 法律知識
- (おすすめの研修)
子ども虐待対応の手引き
≫子ども虐待対応の手引き(平成 25 年8月 改正版)
厚生労働省のものですが、かなり実務的です。
しっかり活用するだけで、「何に気をつけて対応したら良いか」はかなり解消できます。
PDFでダウンロードして開き、文字検索( ctrl + F )して気になる情報にすぐアクセスできます。

PDFを開いて「ctrl 」と「F」を同時に押せば、検索窓が出てくる。
例えばネグレクトケースの対応で困ったら、PDF上で「ネグレクト」と検索すれば、対応で気をつけるべき内容が複数HITします。
こうした内容を頭にしっかり落とし込めている人は、現場でも少ないです。
周りに相談できずに困った時や、どのようにケースの支援をすすめるか迷ったときは、まずいちど調べてみると良いでしょう。
児童相談所における性的虐待対応ガイドライン
≫児童相談所における性的虐待対応ガイドライン(2011年版)
性虐待は、困難ケースとして児童相談所の児童福祉司が直接対応にあたることが多いですね。
私はこちらを読んでおいて、性虐待の通告がはいったときも参考にしました。「困難」と言われますが、基本はシンプルとわかるようになるはずです。
児童福祉司のコンピテンシーモデル
≫児童福祉司のコンピテンシーモデル(前編)_PDF
≫児童福祉司のコンピテンシーモデル(後編)_PDF
コンピテンシーモデルには「どういう心持ちで職務に当たるべきか」が具体的に書かれています。
「いったい何をめざしてこの仕事をしているのだろう・・・」とやりがいを感じられなかった時期、ネットで見つけた資料ですが、私を救ってくれました。
ちょっと古い資料ですが、今にも通じる内容です。
こちらの記事でも紹介してあります。
法律知識
児童福祉司ほど、法的知識が必要と思った現場はありません。
例えば児童福祉法、児童虐待防止法、民法など。
すべて覚えるなんて無茶なので、「困った時に調べる」くらいでもやってみると徐々にラクになると思います。
おすすめの研修
オススメの研修は『全国児童相談研究会新任児童福祉司ワークショップ』です。
これは全国の児童福祉司が年に1回あつまるのですが、全国の児童福祉司が同じように苦しんでいることがよくわかる研修です。
「自分だけが苦しんでいるのでは?」という孤立感を和らげてくれるはず。
2023年は8月予定です。人気なので募集があれば、すかさず申し込んでみてくださいね。
福祉業界で働いてこられた理由7つ
わたしが福祉の仕事で大事にしていることというか、やってこれた理由としては、キャリアガーデンへ寄稿したこちらの記事にまとめてあります。
理由だけをまとめると次のとおりです。
- 給料・年収が安定している
- 福祉以外にしたい仕事・業界が無くなった
- 人とのつながり
- 自分で決めた業界だから
- 気合と根性
- ブログで記事にできたから
- 心から共感できる人を支援する喜び
詳しくは記事を読んでいただくとありがたいです。
それと、『福祉の仕事をやってて良かったなあ』と思ったことは、自分が変化できたことです。こちらの記事にまとめてあります。
≫【体験談】社会福祉士・精神保健福祉士の魅力【自分が変わる】
読者様も、これまでのお仕事での1年目は大変だったかもしれません。しかし3年目の頃には違ってきていたのでは、と推察いたします。
同じように児童福祉司も・・・とまではいきませんが、続けていると違いは必ず出てきます。
しかしどうしても続けられない時は、休んだり転職するのは全然アリと考えます。
組織は自分の人生の責任はとってくれませんし、最後は冷たいもの・・・
それに、私は2回転職していますが、転職したあとも人生はつづきます。その先で開く花もあります。これは私の人生経験から言えることです。
長くなってすみません。何かお役にたつものがあればと思います。
応援しております!



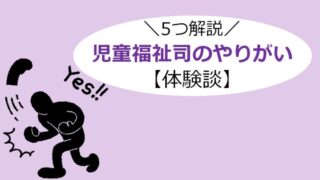
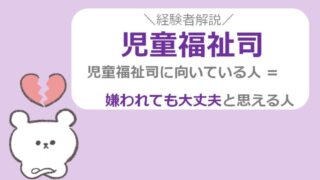
コメント