こんにちは、ぱーぱすです。
現在は自治体で働く精神保健福祉士・社会福祉士です。
児童相談所などで働いて15年程になりますが、これまで何度も「自分は向いていない」と思うことがありました。
2年目の頃の私は、支援の本質をまだまだわかっていませんでした。
今回は、そんな私が精神保健福祉士2年目に味わった“挫折”と“気づき”をお話しします。
「人は変えられない」と骨身で知った日
初めての職場は、精神科クリニックのデイケアでした。
デイケアは、日中の居場所として生活リズムを整え、社会とのつながりを保つ場。
学生を終えたばかりの私は、「支援すれば人は良くなる」と信じていた時期でした。
当時の私は、いま思い返すと恥ずかしいくらいの“万能感”のかたまり。
理屈っぽくて、でも正義感は強く、「私が関われば何とかできる」と思い込んでいました。
しかし現場に出ると、そんな理屈はあっけなく吹き飛びました。
書道を続ける男性との出会い

担当になったのは、毎日デイケアに通う白髪まじりの男性。
いつも笑顔で、「やあぱーぱすさん」と声をかけてくれる方でした。
診断は統合失調症。
長年、デイケアでひたすら書道を続けている方でした。
「主治医に言われたから」と淡々と筆をとる姿が印象的で、
副作用のためか、手は小刻みに震え、筆先が波打って文字がゆれる。
それでも真剣に半紙を見つめていた姿を、今でも思い出します。
話しかけると、軽口で返してくれるユーモラスな人。
私はその人の人柄に救われていた部分もありました。
支援しているつもりで、実は支えられていたんです。
「もうデイケアをやめたい」と言われた朝
ある朝、いつものように声をかけたら、彼がぽつりとつぶやきました。
「毎日毎日、書道をしてつらい。もうデイケアをやめたい。」
その瞬間、空気が少し冷たく感じました。
私はうまく返せず、ただ「どうしたんですか」と繰り返すことしかできませんでした。
主治医に報告すると、「通うよう説得しなさい」と言われました。
あの頃の私は、「私が話せばきっとできる」と本気で思っていました。
支援と押しつけの境界で迷う
私は説得を試みました。
「デイケアに来る意味」「主治医の考え」
……いろんな言葉を尽くしました。
でも彼の表情はだんだん硬くなっていくばかり。
最後には、「もう行きたくない」と静かに言われました。
そのあと、彼はデイケアを休みがちになりました。
数日後に顔を見せたときには別人のように明るく、大声で話し、見るからに落ち着かない雰囲気を漂わせていました。
声をかけても、話が通じないのです。
あの時の違和感は、今でも鮮明です。
「もしかして、薬を飲めていない?」
胸の奥で冷たいものが流れた瞬間でした。
支援にのめりこむほど、空回りしていく
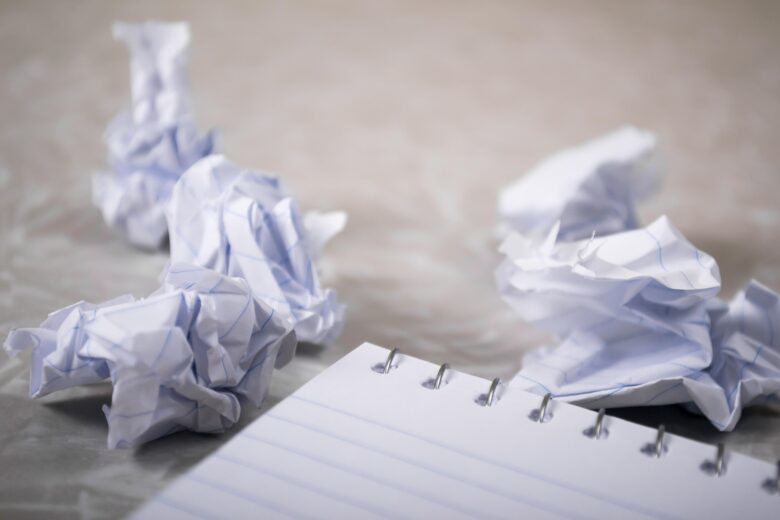
私は焦りました。
デイケア後に家庭訪問。
夜遅くに薬カレンダーを一緒に作り、服薬チェックも続けました。
家にあがると、インスタントラーメンの残り香と、タバコの脂と皮脂の香り、散らかった新聞紙。
蛍光灯の白い光の下で、彼は「もう病気は治ったから薬は飲まない」とすら言います。
「こんなにやってるのに、なんでうまくいかない?」
努力の量と成果が比例しない
――その現実が、心を削っていきました。
「まるで憲兵だな」と言われた瞬間
ある日、主治医から「入院が必要」との判断。
私は彼を病院に連れて行くよう強く指示されました。
一人で訪問し、玄関のチャイムを押しました。
ドアが開くと、彼は明るく笑いながら「行かないよ」「病気は治ったから」と言いました。
何度も説明しても、言葉が届かない。
私は焦り、声を荒げてしまいました。
「行きましょう! 行かないといけません!」
その瞬間、彼の顔から笑みが消えました。
「まるで憲兵だな!」
その言葉を受けてもなお、
私は、ひるみませんでした。
彼は病院へついてきてくれ、
そのまま精神科病院へ入院することになりました。
――しかし、その対応を終えたあとも、
彼から投げかけられた言葉と、
私が取った一連の行動は、
繰り返し、私自身に問いを突きつけてきました。
自分の“正しさ”に依存していた
あの仕事の帰り道、
そして家に帰ってからも、
また次の日からも、
私は、ずっと考えていました。
反省と自責。
「支援」って、何なんだろう。
「正しいこと」って、何なんだろう。
自分が「正しい」と思い込んで、
相手の痛みを、見失っていたんじゃないか。
他人のことなのに、自分なら変えられるなんて、
とても傲慢だった。
もっと、謙虚にやらなきゃいけない。
自分には、まだまだ知らないこと、
できていないことが、たくさんある。
その気づきが、
私のスタンスを、少しずつ変えていきました。
「変えられるのは自分だけ」だと悟って、ようやく楽になれた

この経験を通して、
私は、心から理解したことがあります。
それは――
人は、自分の力では変えられない。
変えられるのは、自分だけだ。
言葉で聞けば、当たり前のことです。
でも、現場で「骨身でわかる」には、
どうしても時間がかかりました。
それ以降、私は、
他人を変えようとするよりも、
「自分の関わり方を変える」ことに、
力を注ぐようになりました。
正しいと信じていた、自分なりの支援。
その前提そのものに、
疑問を持つようになったのです。
この挫折体験を経て、
ようやく私は、
ソーシャルワーカーとしての
スタートラインに立てたのかもしれません。
※本記事は、筆者の過去の経験をもとに一部内容を再構成したものです。登場する人物等はすべて仮名・創作を含み、実在の個人・組織とは関係ありません。
同じ悩みを抱えている方へ
背景には、現場特有の“きつさ”があります。だから、「向いていない」と感じるのは自然なことだとお伝えしたい。
「向いていない」と感じるあなたへ、本気で伝えたいことを記事にしました。

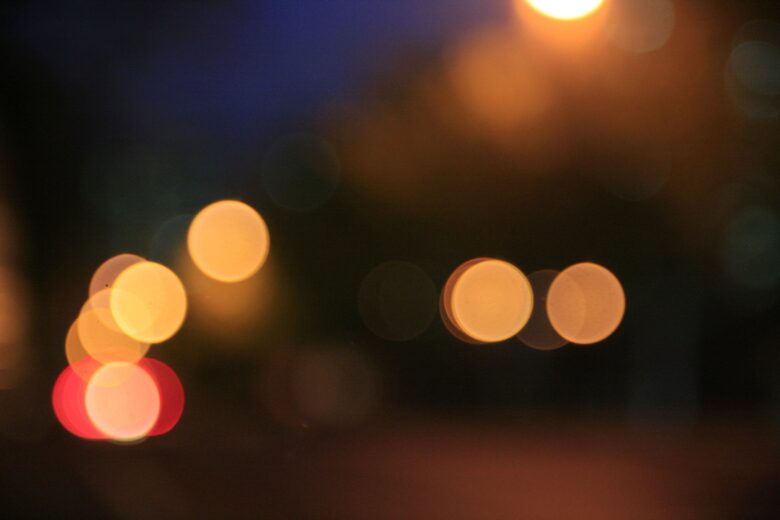


コメント