
ボクは仕事がぜんぜんできてないし、周りの人の方がもっとできてる。迷惑かけてるし、福祉職に向いてないと思う。そもそも福祉職をやりたいのかわからなくなってきた・・・。
こうした思いのあなたへ。
この記事の内容
- 『福祉職に向いてない』と悩んでいるあなたへ【本気のアドバイス5つ】
(1)「周りに迷惑をかけている」は「役に立っている」
(2)たいていの悩みは『運動・没頭・睡眠』で解消できる
(3)「昔の自分」と「今の自分」を細分化して比べる
(4)あなた自身を研究しよう 『育ち・愛着関係』と『発達特性』
(5)仕事を細分化して適性を考える

私は某自治体で働く社会福祉士・精神保健福祉士です。現場経験はおよそ13年です。「向いていない」と繰り返し悩んできました
私自身が困ったり、失敗したり、同僚よりもできていないと感じるたび、
まるで持病のように「向いていない」という悩みに駆られてきました。
最近、新人の後輩が「私は福祉職に向いていないんです・・・」と悩んでいたので、私のそうした話をしたら驚かれました。
「10年以上も続けてきた人が、まさか自分と同じように悩むのか?」と、信じられなかったようです。
そこで私は、「今まさに悩んでいる人に何がしかアドバイスできるかもしれない」と思い、この記事を書くことにしました。
『福祉職に向いてない』と悩んでいるあなたへ【本気のアドバイス5つ】
「周りに迷惑をかけている」は「役に立っている」

- 失敗ばかりして、先輩たちに迷惑をかけてしまう・・・
- 何をやってもうまくできない
- 周りに迷惑ばかりかけてしまう。自分は出勤しないほうが良いのでは?
このように悩んだりしませんか?
まずですね、迷惑をかけていると思ってしまうでしょうけれど、実はあなたは周りの役に立っているんです。
こんなことを言ったら、
「いやいや、そんなはずはない」
「お世辞ですよね?」
そう思われたかもしれません。
でも、嘘じゃないですよ。
なぜなら、人をサポートすると、自己効力感につながるし、幸福感につながるから。
周りの人がね。
周りの人があなたをサポートすることで、その人たちは実は「役に立てている」と感じているのです。
特に福祉の現場は、誰かを助けたい、支援したい、役に立ちたい、といった人の集まりです(笑)
だから、サポートしている職員は

あの子はサポートが必要。私がみてあげないと。
と感じて、自己効力感や優越感を抱けるのです。自分の役割を意識するのです。
人間の心理とはそうしたものです。
あなたが悩んでいたら、周りの人も同じように悩んだり、難しい顔をされているかもしれません。
なのに、あなたは同じようなミスをしてしまって、迷惑をかけていると感じているかもしれません。
でも実は、あなたは周りの人の自己効力感を上げるのに役立っている。
「迷惑」とは、周りは感じていないと思います。
いずれ、あなたが『できている』『迷惑をかけていない』状態に成長できたとき、
周りの人は嬉しいかもしれないです。でも一方で、あなたを助ける役割を失って、寂しさも感じたりするでしょう。
まるで、独り立ちした子どもを手放すような感覚です。
だから、迷惑ってかけていいんです。
たいていの悩みは『運動・没頭・睡眠』で解消できる

たいていの悩みは、運動・没頭・睡眠でかなり解消できます。
なぜなら、行動を変えたり、体を整えることで、心がつられて変わる・整うからです。
「根本的な解決になっていないのでは?」と思われたでしょうか?
確かにそうです。
「向いていない」と悩んでいるのに、運動したり、何かに没頭したり、果てにはよく眠ってくださいという話なので・・・。
でも、いくらあなただって、24時間365日「向いていない」と悩んでいるわけじゃないと思います。
例えば、スポーツなどの激しい運動をしているとき、何かに没頭しているとき、眠っている間などは、悩めない。
人間はそのようにできています。
確かに、我に返ったときは「向いていない」「迷惑をかけている」「やめたほうがいいんじゃないか」と悩み始めてしまうかもしれません。
でも、ずっと悩み続けることは、できないのです。
「向いていない」という悩みは、あなたのメンタルによって、大きくなったり小さくなったりしている。それがリアルです。
大丈夫、私こそがそのような人間ですから。
運動・没頭・睡眠の具体的な話をしていきましょう。
運動
激しく運動すれば、脳の血流が良くなるし、悩んでいたことが軽くなったり、消えていったりします。
それはやせるためとか、キレイな体になるためとか、モテるためではなく、
この仕事のしんどい時期を乗り越えるための必須科目だと思ってください。
どうしても面倒くさいものは、面倒くさいと思います。運動が嫌いな人が、好きになるのは難しいでしょう。
でも、運動習慣は社会福祉士や精神保健福祉士などの福祉職の必須科目なので、諦めてください(笑)
極論をいえば、運動するか、折れるか、です。
運動はとても大切です。私のようなタイプの人は、運動しないと病みます(笑)
こうした話を口酸っぱく伝えても、「へえ、そうなんだ」「また今度からしよう」「運動できる体調じゃないし」と感じていませんか?
実際に運動をする人は10%もいない。知ってますよっ!
でもね、どの仕事、どの人生だって、何かを変えた人は、必ず行動をしています。行動量が違うのです。
ここからは、あなたが運動をするか、しないかです。それが運命の分かれ道です。
なお、私が毎日のようにしている運動は、こちら紹介しているHIITです。
別にHIITのような激しい運動じゃなくても良いです。
大切なのは、あなたが少しでも楽しんで続けられる運動です。それは、人から教えてもらうことはできませんね。
見つけられるのは、外ならぬあなただけ。思い出してみる、体験してみる、とにかくやってみるしかない。
ぜひ、見つけてくださいね!
没頭
没頭することで、「向いていない」という悩みは薄れます。
なぜなら、没頭している間は、悩みから解き放たれるから。
没頭しながら「向いていない」と悩むことは、不可能だからです。それは、右を見ながら左を見るようなものです。
「向いていない」と悩んでいる時間が減ると、実際に「向いていない」という悩みが小さくなっていくのです。
人は、暇になると考えなくても良いことを悩んでしまいます。
考えても意味がないと分かっていても、繰り返し考えて悩むのはメンタルに悪いです。(これを反芻思考と言います)
例えば、
- オレはできない
- 私は何をやってもダメ
- 失望されたんじゃないか
- 迷惑をかけている・・・
などと、自分を繰り返し痛めつけているんですね。
傷ついた実際の場面は1回だったのに、そのあとで自分が自分を10回、100回、1000回と繰り返し罵倒し続けている・・・
そうした状態です。
なんでそんな拷問みたいなことを、する必要がありましょうか?
あなたがあまりに可哀そうではありませんか。
でも、癖や習慣のようなもので、時間や暇ができたら自分を責めてくる自分がいる。
だから、考えがちでしんどくなってしまう方は、考えなくても良いようにすることが大切です。
でも、人は何かしら考えを巡らせてしまうので、別のことに集中する必要があります。
「忘れよう」を決心したり、「考えないようにしよう」と意識しても、あまり効果は無いでしょう。
頭をフリーな状態にすると、自動的に思考し始めますし、勝手に傷口をほじくり返してしまうものです。
だから、没頭することが大切です。何かに没頭している間は、悩めませんよね。
だから、没頭できる趣味や活動を意識的にやると、ラクになれます。
仕事が終わってからも、仕事の失敗を繰り返し思い出して、落ち込んだりブルーになる人には、特に効果的です。(それは私です)

没頭できる趣味?活動?何をしたらいいのかな?
私であれば、登山、ブログ、読書、YouTubeやAmazonプライムだったりします。
妻と会話するのも、気をそらせられるので効果的です。
方法は人によって違いますから、あなたオリジナルで良いです。
そうした時間を、1日で1分、10分、1時間でも良いのでつくること。
「向いていない」と悩んでいなかった時間に気づけたら、勝ちです。
悩んでいなかった時間にしていたことが、ヒントになります。
没頭できる趣味や活動があれば、結果的にメンタルをタフにできます。
「没頭できるようなことが無い」という方は、忙しくするのも効果的です。
スケジュールに何か予定をいつも入れるイメージですね。
忙しくすることは、家族や親しい人の死の乗り越え方としても、効果があると言われています。
悩んでもどうしようもないときは、別のことに集中したり、没頭したりするのが効果的なんですね。
睡眠
- なかなか寝付けない
- 途中で目が覚める
- 早く目が覚める
- 一回覚めると再び寝られない
こうした心当たりのある方は、気を付けてください。
全ての精神疾患は睡眠障害から始まると言われるほど、睡眠はシグナルです。
あなたの不調のサインとなります。
睡眠の質を上げる方法としては、
- 朝に太陽を浴びる
- 日中に運動をする
- 入浴して体を温める
- 寝室は真っ暗にする
- 眠る前はブルーライト(スマホ、パソコン)を避ける
- 毎日(休日含む)、同じ時間に寝起きする など
たくさんのやり方があります。
あと、まずは現状を知ることが大切ですから、
ウェアラブル端末を使って睡眠時間や質を計測するのが効果的です。
価格は高いですが、applewatchやGarminなどのスマートウォッチを私は愛用してきました。
探せば、もっと安いスマートウォッチはあると思います。
体は資本。健康は失ったらお金でも買えなくなるので、私はあまり惜しまないようにしています。
メンタル面の対策については、こちらの記事にもまとめています。ご参考にしてくださいね。
「昔の自分」と「今の自分」を細分化して比べよう

ここからの話は「向いていない」悩みにダイレクトに向き合っていく方法です。
効果的ですが、その分、かかる労力もあるでしょう。
「そこまでやるのはしんどい」という方は、サラッと知ってもらうくらいで構いません。
「昔の自分」と「今の自分」を細分化して比べようには、2つのポイントがあります。
- 他者と自分を比べると不幸になる。今の自分と昔の自分を比べるのが幸せへの道。
- 大雑把に比べても成長には気づけない。細かくみることで、成長に気づける。
まず大切なのは、今の自分と過去の自分を比べること。
他人と自分を比べると、劣等感を感じます。そして、不幸になるんです。
なぜなら、他人の長所と自分の短所を比べてしまうからです。
福祉職のあるあるですけど、
私たちって、支援対象の利用者さんや患者さんには、とても優しくなれますよね?
失敗にも寛容じゃないでしょうか。
例えば、利用者さんや患者さんは、仕事のできない状態にある人が多かったりすると思います。
だからと言って、「ぜんぜんできてない」と評価したりしませんよね?
でも、いざ自分のことになるとどうでしょう?
「ぜんぜんできてない」「何もできていない」と感じてしまいませんか?
毎日仕事をして、苦しみながらも頑張っているはずなのに・・・。
確かに、あなたは、あなたが思う目標には到達できていないのかもしれません。
先輩や上司、デキる同僚のようにはできないのでしょう。
でも、すごい先輩や尊敬する人と同じにはなれません。
その人とあなたは根本的に違うので、あなたはあなたの持ち味を磨いた方がいいのです。
だから、目標となる人をもつのは良いですけど、その人と同じようになることを目指していると、いつまでも「できていない」と感じてしんどいです。
ではどうしたら良いかというと、昔の自分と今の自分を比べることです。
今の仕事に就いた頃を振り返ってみましょう。
ここで次に大切なのが、細分化して振り返ることです。
なぜなら、大雑把に振り返っても、「全然できていない」「成長できていないから、向いていないんだ」と考えやすくなるから。
仕事を細分化する。1つ1つ、細かく振り返ることで、成長に気づけます。
0か100といった判断をやめ、柔軟に自分を見つめられる。これは幸せに近づくことです。
あなたが今の仕事についたのは、4月だったでしょうか?
はじめは、職員や利用者さん患者さんの名前を知らなかったのではないでしょうか。今はどうですか?
電話が鳴っても、ガチガチになって電話を取れなかったことはありませんか。今はどうでしょうか?
相談の記録の書き方は、知っていたでしょうか?
面談で何を話して良いかわからず、パニックになっていませんでしたか?
基本的な業務すら、できなかったのではないでしょうか?
「そんなのできていて当たり前」と思われたかもしれません。でも、できるようになったことは確実にありますよね。
きっと、あなたが今、できないと悩んでいるのは、プラスアルファの部分ではないでしょうか?
先輩や上司ができているのとレベルでできていないから、自分は福祉職に向いていない。そのように考えていないでしょうか・・・。
本当はできていることはあるのに、「これぐらいはできて当然」と思って、全く評価していないかもしれません。
でももし、あなたの友人や利用者さんが、あなたのような悩みを抱えていたら、どんな言葉をかけるでしょうか?

ぜんぜんできてないじゃないか!もっと頑張れよ!向いてないなあ。
こんなこと、言わないですよね。
あなたは優しい言葉をかけるのではないでしょうか?
- よく頑張ってるなぁ
- 向いてないなんて、そんなことないんじゃない?
- できてることたくさんあるよ!前より成長したじゃない。
自分のことになると、客観的に評価できない。主観的に評価してしまう。
「全然できていない」というように、0か100か、白か黒か、で捉えてしまいがちです。
でも、そうじゃなくて。
あなたの仕事を細かく分けて、それぞれについて成長したかどうか分析してあげましょう。
- あいさつ
- ルーティン業務の慣れ
- 電話対応
- 面接
- それぞれの時の心境 など
「できて当然」と思わず、振り返ってみましょう。
すると必ず、成長したポイントが見つかるはずです。
あなたの進歩があるはずです。そのペースを周りと比べるのはナンセンスです。
「全然できていない」「向いていない」と悩んだら、少し立ち止まって昔の自分と、今の自分を比べてみてください。
このとき、必ず紙に書くか、スマホのメモに書く等してください。視覚化することが大切です。
なぜなら、書きだして、目に見えるようにすることで、自分を客観的に振り返りやすくなるからです。
頭のなかで考えるだけでは、効果はいまひとつです。ぜひ試してくださいね。
あなた自身を研究しよう 『育ち・愛着関係』と『発達特性』

私は福祉職に就く前も、就いてからも「向いていない」と繰り返し悩んできました。
そして長年、この仕事をしていて気づいたこともあります。
それは、福祉職の多くの人が、私のように「向いていない」と悩んでいるということ。
もしかしたら、半数以上の人がそうした経験をもっているかも?
しかも、私と共通点のある人が「向いていない」と悩みがちなことにも気づきました。
その共通点は何か?
それが『育ち・愛着関係』と『発達特性』です。
福祉職として「向いていない」と感じるだけじゃなく、そもそも生きづらさがあるとか、人間関係が苦手といった人の背景には、
何かしら『愛着の傷つき』や『発達特性』の影響があると思います。
誰を隠そう、私自身がそうなので、プロフィールでもお話しています。
それが良いとか悪いとかではありません。
私が言いたいのは、『育ち・愛着関係』と『発達特性』があなたの苦しみや悩みのルーツになっている可能性があるので、よく理解するとラクになれる、ということです。
- 自分に自信を持てない
- いつも何だかしんどい
- 自分は陰キャだ 陽キャの人とは住む世界が違う
- 人からどう見られているかが気になる
- 人と同じようにできない 浮いてしまう
といった悩みがある人は、必ず知っておいて通っておいた方が良いテーマです。
私が『育ち・愛着関係』や『発達特性』について勉強したきっかけは、支援のためでした。
「支援に必要な知識だ」と思って、本を読んだ。
そうしたら、読んで学んでいくうちに、まるで「自分のことを言われているような気がした」のです。
これって、自分のことじゃないか、と。
それで、愛着障害や発達特性・発達障害に関する本を読み漁るようになりました。
自分のことが知りたくて。なぜ、自分が苦しいのか知りたかった。親のことが知りたかった。どうしたら楽になれるのか、知りたかった。
変われる部分、変われない部分があるとわかりました。
残念だけど、受け容れるしかないこともありました。
しかし受け容れられると、対策できるようになります。
それでラクになれたり、長所をもっと活用できたりします。
結果的に自己覚知となって、支援に活きるようになったのです。
出発点は、まずは自分を知ること、研究すること。
おすすめ本4冊
私が自分を知って、分析できたきっかけになった本は、精神科医の岡田尊司氏の本です。
愛着関係は、私たちが幼少期に養育者との間で築かれる、人間関係のキホンとなるものです。
後の人生に大きく影響し、性格や人格の形成につながります。
私たちが感じる「不安」の正体は、愛着関係、母子(親子)関係にあると言われます。
愛着関係の形成が大きくこじれると、大人になってから、いわゆる人格障害(パーソナリティ障害)と呼ばれることにつながったりします。
それと、発達特性や発達障害についても、岡田尊司氏の著書でよくわかります。
私は岡田尊司氏をリスペクトしているので、他の著書もたくさんもっていますが、上記は特におすすめです。
それともう1冊。
人生で一度でも「消えたい」と思ったことがある人や、子どもの頃に両親がよくケンカしていたとか、きょうだい差別があったとか、虐待を受けていた経験があるという人には、高橋和巳氏の本を読むと発見があるはず。
私はこの本で、自分が虐待による影響を受けていたと気づきました。
同じように感じた人には、こちらの本もおすすめします。
虐待を受けてきた著者が、その苦しみからどう脱却し、幸せになったのかがわかります。
こうした知識を得ていくと、あなた自身を深く知れて、対策したり生きやすくなるはずです。
支援力もアップします。
なぜなら、私たちが支援する多くの人は、何かしら愛着や発達、虐待などの影響を受けているから。
だから、『育ち・愛着関係』と『発達特性』というテーマを良く知ることは、あなたのアセスメント力や支援力を上げることになります。
なにゆえあなたは「福祉職に向いていない」と悩んでしまうのかの答えだけじゃなく、一生モノの知識、教養を得られるでしょう。
仕事を細分化して適性を考えよう
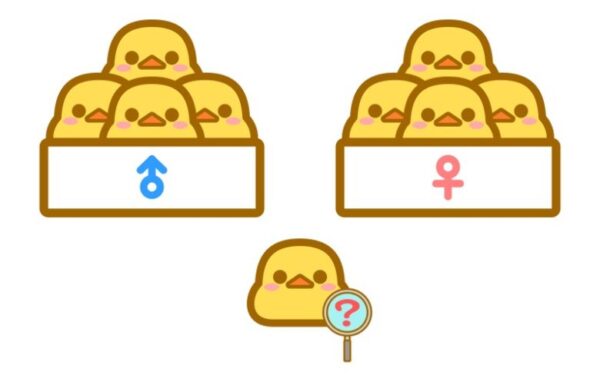
もしあなたが、ここまで私がお伝えした話を実践してもなお、福祉職に「向いていない」と感じたとしても、
「福祉職に向いていない」とは考えなくて良いです。
仕事への適性は、業務を細分化して考える必要があります。
もし、あなたが今の福祉現場に向いていないと思っても、
「今の現場に向いていない=福祉職に向いていない」
「今の現場に向いていない=社会福祉士に向いていない」
「今の現場に向いていない=精神保健福祉士に向いていない」
「今の現場に向いていない=介護福祉士に向いていない」
・・・ではありません。
例えば同じ福祉職でも、
児童相談所で児童福祉司として働く場合
地域の法人で相談支援事業所で働く場合
病院でMSWとして働く場合
それぞれで仕事内容は違いますよね?
例えば児童相談所なら、嫌われても大丈夫なくらいのメンタリティの人が向いています。でも、これは福祉職全般に言えることではありません。
福祉職は、基本的には信頼関係を基に支援をしていきます。
嫌われていては仕事にならないのです。同じ福祉職の現場でも、このように人間関係のとり方から変わってきます。
児童指導員の現場であれば、体力やメンタル面のタフさを求められるでしょう。
デスクワークというよりも、直接的に子どもと関わる仕事が多いです。
また、行政機関であれば文書を書ける・読み解ける力を重視されやすいですが、(近年はコミュニケーション能力も重要視されていますが)
民間の福祉職だとコミュニケーションや人柄の方が重視されるように思います。
つまり、あなたが今の福祉現場に向いていないと感じたとしても、
そして、もし本当に向いていなかったのだとしても、
だからといって、「=社会福祉士に向いていない」「=福祉に向いていない」と考えなくても良いのです!
そんな、一面的な話ではないんです。
だから、仮に転職をするとしても、福祉の仕事から離れる必要があるとは言えません。
そうじゃなくて、仕事への適性をもっと細分化して考えるのです。
例えば、子どもと関わりたい、子どもを支援したいと思っている人が児童相談所の児童福祉司として働くと、あまりやりがいを得られないです。
なぜなら、実際の仕事でよく関わるのは、関係機関や保護者だからです。
子どもと関わりたい、子どもを直接支援したいと思うのであれば、児童養護施設や放課後等デイサービスで働いた方が、やりがいを得やすいと思います。
また、自分の裁量で支援をすすめていきたいと思っている人が、MSWになったり、精神科病院で働くと、医師の意見伺いが多すぎて不全感を抱きやすいかもしれません。
また、同じ福祉職でも、パソコン業務のウェイトは現場によって違います。人と接している時間量も違いますね。
直接支援が良いのか、間接支援が良いのかという、好みもあります。
介護を直接している方がやりがいを得られる人もいるでしょうし、ケアマネジャーのように支援計画や調整業務をしている方が性に合っている人もいるでしょう。
つまり、これは福祉職の特徴ですが、どの職場・どの職種・どの配置になるかで、私たちの向き・不向きや適性はカンタンに変わるのです。
それくらい、福祉職の現場はバラエティにあふれています。
だから、もしあなたが私がここまでお伝えした話を実践してもなお、「向いていない」と感じたなら、
今の仕事の好きな部分・嫌いな部分・向いている部分・向いていない部分を、細かく分析しましょう。
全て嫌い、全て向いていないということは無いはずです。もしそうなら、あなたは今まで仕事を続けられなかったでしょう。
ご安心ください。「仕事の全てがあなたの適性に合っていない」は間違いだし
「仕事の100%が自分の適性に合っている」も間違いです。
向いている部分も向いていない部分もある。人によって違うのは、その割合、バランスです。
きっとあなたは、今の業務で「向いていない」と感じるウェイトが大きいのでしょう。
そうだとしても。今の福祉現場で向いていないと感じていても、「=福祉職に向いていない」と考えなくても良いです。
異動できる職場なら、異動を希望しましょう。
転職するのも1つの道です。転職は自分の生き方や働き方を考えての決意・行動の結果だと思います。私は転職を2回していて、後悔は全くありません。
今は『1つの職場で定年まで働く』という時代ではありません。
会社の寿命は、人間の寿命よりもたいてい短いです。
変化の激しい時代です。同じであり続けるよりも、変化へ適応していく力の方が求められるようになりました。
もし転職するなら、あなたの好き・嫌い、適・不適、情熱をかけられるかどうかといった点で、細かく分析してください。
転職を考えたり、「福祉職から別の業界にうつろうかな・・・、でも何をやりたいのかわからない」「何が適職なんだろう?」といった悩みのある人には、こちらの本がヒントになります。
「好きを仕事にすれば良い」という考えではなく、論理的に仕事の満足感や適性をはかれるようになります。
なお、この本の知見をつかって、児童相談所の児童福祉司の仕事を分析してみたのがこちらの記事です。何かご参考になれば。
最後に
『福祉職に向いてない』と悩んでいる人へ、本気のアドバイスをしました。
この記事の内容
- 『福祉職に向いてない』と悩んでいるあなたへ【本気のアドバイス5つ】
(1)「周りに迷惑をかけている」は「役に立っている」
(2)たいていの悩みは『運動・没頭・睡眠』で解消できる
(3)「昔の自分」と「今の自分」を細分化して比べる
(4)あなた自身を研究しよう 『育ち・愛着関係』と『発達特性』
(5)仕事を細分化して適性を考える
お役に立つことが1つでもあれば嬉しいです。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました!

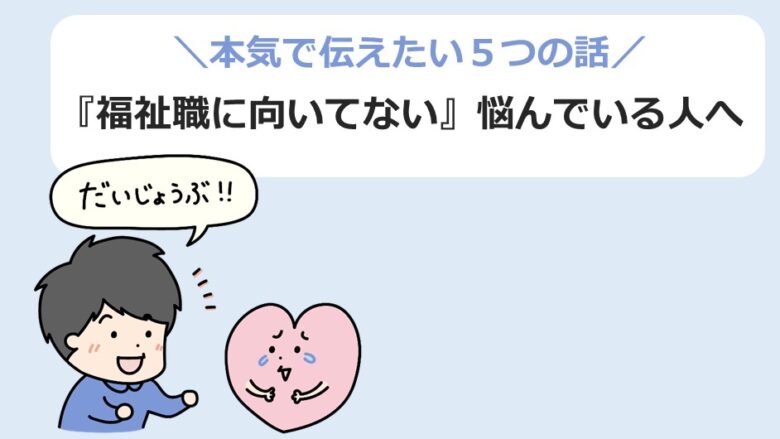

























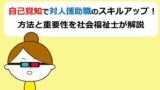








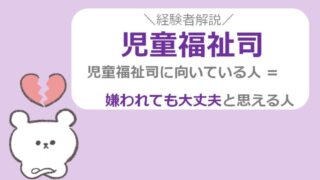

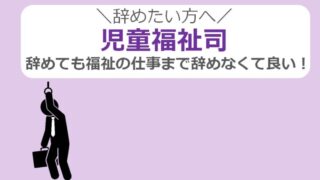



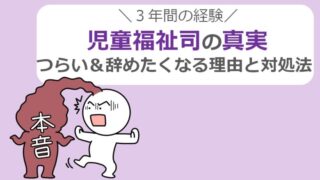
コメント