最近よく本を読んでいます。時間のマネジメントを扱った本もあり、その中で強く思ったのは「時間は財産だ」ということ。
だからこそ、私は朝早く起きることもあります。
けれど、この時間という財産は、世の中があの手この手で奪いに来る。
テレビ、スマホ、YouTube、アマプラ、AbemaTV…。
私たちの関心を引きつけ、時間を使わせようとしてくる。ぶっちゃけ、私のブログだってそのひとつかもしれません。
相談支援で「時間がかかる」場面
福祉の仕事に立ち戻ってみると、やっぱり時間の奪い合いだなと思います。
話が長い人(発達特性が関わることも)、まとまりのない人、事実が見えにくい話をする人(パーソナリティ傾向の方に多いと感じる)…。
電話をとる前から「これは長くなるぞ」と覚悟することも少なくありません。
でも、効率よく進めたいのは私の都合。
「早く終わってほしい」と思っていると、なぜか余計に長引いてしまう。相手に伝わるんでしょうね、「聞いてもらえてない」と。
福祉職はどうしても「相手の都合に合わせてなんぼ」です。
ACT-Kの高木Drは、私たちはまずは”御用聞きになることが大切”と表現していました。まさにその通りです。
対面の強みとオンラインの限界
面接、家庭訪問、電話、メール、LINE…。
いろんなツールがありますが、やはり「顔の見える関係」が一番。誤解も少なく、話も整理しやすい。
その代わり、時間はとてもかかります。面接室を準備したり、家庭訪問に出かけたり。移動時間も含めると、半日があっという間に過ぎていく。
Zoomなどのオンラインも便利ですが、通信環境の差や雰囲気の違いで「完全な代替」とまではいきません。
特に児童相談所のアポなし訪問なんて、オンラインでは成り立たない。
ソーシャルワークはどうしても他律的

ソーシャルワークは他律的です。
”他律的な仕事”というのは、自分の意志による裁量がすくない仕事です。
他者や組織の都合、外部の規範やルールに合わせないといけない。
――まさにソーシャルワークの性質です。
例えば、入所施設ならシフトがあっても、突発的なトラブルは日常茶飯事。
児童相談所なら夕方に「子どもが家に帰りたくない」と連絡があれば、即座に動かざるを得ない。
こうなると「緊急対応」と呼ぶのも空しくなるほどです。日常的すぎて。
だから私は、「ソーシャルワークは自分の思い通りにはいかない」と受けいれるようにしています。
守れるところは守る、全身全霊で向き合う
それでも全部を流されるわけにはいきません。
面接や家庭訪問は1時間を目安に。初めに伝えておけば失礼にもならないし、お互いに負担が減ります。電話だって、次の予定を理由に区切ることがあります。
そして、対応しているその時間は全身全霊で相手に向き合う。これが私のスタイルです。
時間も「見える化」してみる
仕事中の時間をコントロールするにも限界があります。
結局、コントロールできるのはプライベートの時間です。(家族との関係などで自由のない場合はあるだろうけど)
趣味の時間、友人・家族との時間は確保したい。誰かの奴隷ではなく、自分も人間なのだから。
お金を守るには家計簿アプリで「見える化」するのが第一歩だと言われます。時間も同じじゃないでしょうか。
まずは、自分の時間がどう奪われ、どう使われているのか。把握することから始めたいと思っています。
私たち福祉職は、どうしても相手に合わせて時間を使います。奪われることもあるし、守りきれないこともある。
それでも「時間は財産だ」と思う気持ちは手放したくありません。あなたの「時間の財産」は、いまどんな状況でしょうか?

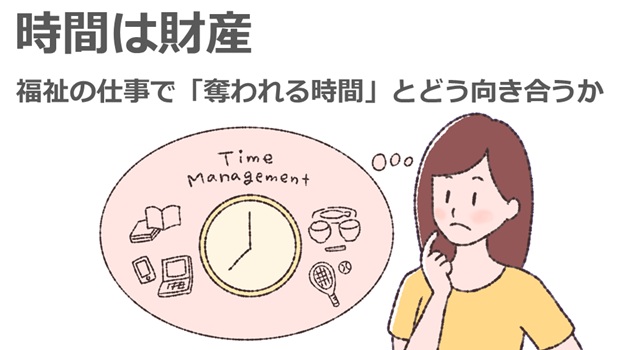


コメント