
相談って、どうやってするのが正しいのかな・・・?
- 話を聞いてあげるだけでは、問題が解決しない
- 相談がうまくできているかどうかわからない
- 家に帰っても、相談のことばかり考えてしまう
こんなふうに思っている方におすすめの本です。

私は社会福祉士さんと精神保健福祉士さんとして働いています。今までに10年以上の経験があります。
あなたは、自分の相談の仕方について、不安はありませんか?もっと上手になりたいと思いませんか?
相談の仕方がわからないと、相談してくれる人を助けられないだけでなく、「何もできない」「役に立たない」と自分を責めてしまうこともあります。私もそうでした。
でも、ちゃんとした理論で説明された相談の仕方を学べば、自分を責めることもなくなります。
この本「相談力入門」では、相談で大切な話し方が36個紹介されています。
「相談力入門」は「入門」という名前ですが、実際に使えることがたくさん書かれています。
正直言って、この本の内容が入門レベルだとしたら、現場で人と話す仕事をしている人のほとんどは入門レベルにも達していないと思います。
それでいて、難しく言うのではなく、読みやすいというのが良いんですね。
おすすめ本『相談力入門』 レビュー【結果を出す社会福祉士になる】
「相談力入門」はどんな本?
この本は社会福祉士でも行政書士でもある鈴木雅人さんが書いた本です。
「相談」を36個のスキルに分けて説明してくれていますね。
「相談なんて、誰でもできることだよ。」
「話を聞いて『そうですね』とか『うん』とか言って同意してあげれば、それで十分だよ。」
「先生や上司が相談の仕方を教えてくれることはないよ。だって、相談の仕方は人それぞれだから・・・。」
この本の作者の鈴木雅人さんは、そんな相談現場の現実に対して、「そもそも相談とは何なのか」ということから考え直してくれます。
例えば、この本から一部を引用しますと
現状のままでは問題が解決できないから、相談者は相談に来ます。私たち相談対応者は、その現状を変えていく必要があるのです。
それでは、相談者に変化をもたらすために、効果的なコミュニケーション手法は何なのでしょうか。それは、「質問」と「アドバイス」です。
引用元:鈴木雅人(2013)『「相談力」入門 対人援助職のためのコミュニケーションスキル36』中央法規出版 P152
このあと、質問がどうして効果的なのか。アドバイスをするときに気をつけることは何か。いつ話すのがいいのかなどが詳しく説明されていきます。
ページ数や読みやすさは?
約220ページで、読みやすいです。表紙がとてもシンプルなので、中身で勝負している本だと思います。
欠点があるとしたら?
この本は相談スキルの本なので、
「社会福祉士や精神保健福祉士は、どんなことを大切にしなければいけないのか」
「どういう考え方や倫理観が必要なのか」
ということは別に勉強する必要があります。
相談力は使う人によって、良いことにも悪いことにも使えてしまいます。どんな目的で技術を使うかが大切なのです。
例えば、「包丁」はおいしい料理を作るために使えるけれども、人を傷つけるために使えてしまうこともありますよね。
相談スキルにも同じことが言えます。相談してくる人を助けるためにも、だましてお金を取るためにも使えてしまうのです。
だから、相談の目的を忘れないように気をつけなければいけません。
どんな人に役立つか?
この本が役立つのは、「相談」を仕事にしている人みんなだと思います。
社会福祉士や精神保健福祉士、介護福祉士などの福祉の仕事をしている人はもちろん、
「何となく支援してるけど、これでいいのかな?」
「自己流でやってるけど限界・・・」
という人にも特におすすめです。
社会福祉士や精神保健福祉士は「役に立たない」とか「必要ない」と言われたり、思われたり、自分で思ってしまったりすることもあるかもしれません。
でも、相談の仕方が上手になれば、そんなことは言わせないですね。
「優しい人」「親切な人」だけではなく、ちゃんとした結果を出せる人になれるはずです。

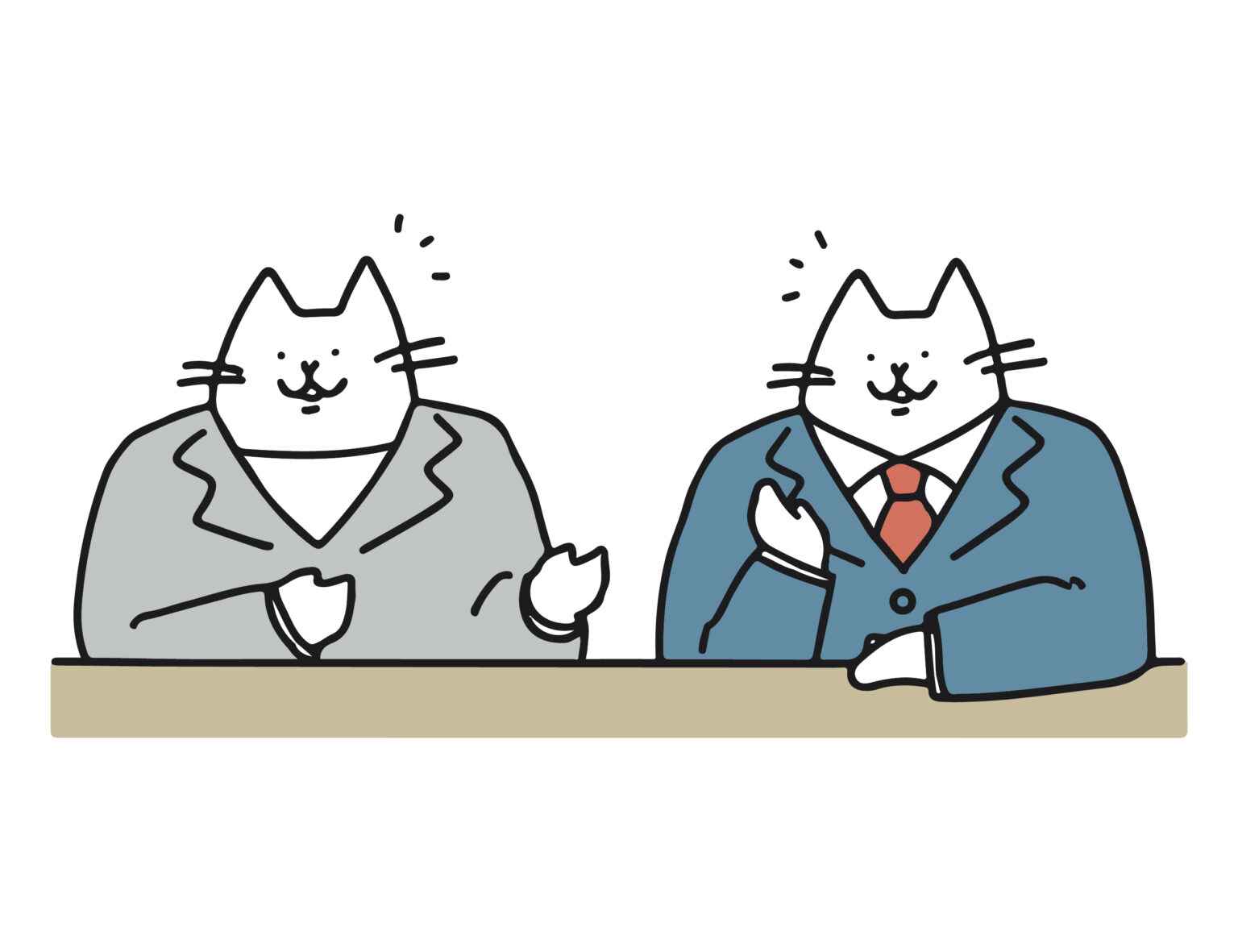




コメント