
社会福祉士の仕事をカンタンに教えてほしいなあ
社会福祉士の仕事を調べても「いまいちよくわからないな・・・」とギモンが残っていませんか?
「社会福祉士及び介護福祉士法」の定義をもとに、社会福祉士の仕事を簡単にいうと
身体・精神・環境等の理由で生活しづらい方の相談を受けて、専門的知識・技術をもって関係者と連携・調整して支援する仕事

んー、ピンとこないなぁ~・・・
「よくわからない」と思うのが普通です。
実は、社会福祉士自身も、どう伝えて良いのか困るのです。お恥ずかしい・・・。
社会福祉士を見かけたら、「社会福祉士ってどんな仕事をするんですか?」って聞いてみるとわかります。
きっと難しい顔をするはず。
そして説明しだしたかと思えば、クドクドと長くて「結局は何なの?」と思うかもしれません(苦笑)
意地の悪い社会福祉士なら、逆に質問し返してくるでしょう。「君はどう思う?」と。(そして、答えない!)
どうしてでしょうか?
実は、社会福祉士の仕事内容はカンタンに言っても伝わらないし、詳細に説明するのも難しいのです。
この理由3つを解説します。ではまいりましょう!
社会福祉士の働く職場が多いし、独自カラーもあるから

社会福祉士の仕事は、職場によって違いがあります。
例えば、こういった職場があります。
- 社会福祉協議会
- 児童養護施設
- 乳児院
- 母子生活支援施設
- 障害児通所施設
- 障害児入所施設
- 地域包括支援センター
- 特別養護老人ホーム
- 介護老人保健施設
- 有料老人ホーム
- 福祉事務所
- 生活保護課
- 児童相談所
- 保健所(健康福祉事務所)
- 病院
- 診療所・クリニック(MSWとして)
- 介護療養型医療施設
- 普通学校
- 特別支援学級
- 特別支援学校 等
社会福祉士が活躍する職場はじつに多いです。職場が違えば仕事もかわってきます。
全ての職場で共通するのは「生活を支援する」という点です。
でも、広すぎてわかりにくい。具体例を教えてもらってもあくまで一例でしかない。
それゆえ、社会福祉士の仕事はカンタンに言われてもわかりにくいのです。
そのうえ、福祉の仕事は「A機関はここまで」「B機関はここまで」と明確になっていないことが多い。
機関同士で重なり合ったり、ケースごとに変わったりと、業務範囲もケースバイケースなことが多い。
いつもあいまいな部分、余白が残っているのが社会福祉士の仕事です。
白黒がはっきりしなくて、グレーゾーンが多いんですね。
それゆえ機関同士で

この支援はあなたのところの仕事でしょ?

いえ、こちらでできることではありません。
と押し付け合ったり、「どうして動いてくれないんですか?」と不満・緊張関係に発展して困ってしまうこともあります・・・。一番困っているのは支援をうける方なんですけどね。
しかし、グレーゾーンがあるからこそ、各機関に裁量があり、自由度が高い、紋切り型にならない血の通った支援ができるとも言えます。
ゆえに、「この現場、この機関だから、社会福祉士の支援はこんなことをしているよ」とはならず、
例えば、「あの社会福祉協議会の社会福祉士は○○という支援を(持ち出して)してくれるけど、そっちの社会福祉協議会の社会福祉士はしてくれない」ということが起きます。
良し悪しありますが、これが実態です。
なので、社会福祉士の現場は多様だし、各機関(の社会福祉士)の独自カラーもあって、さらに多様です。
ゆえに、社会福祉士の仕事はわかりにくいし、画一的な説明はしにくいのです。
社会福祉士が支援する「生活」は「衣・食・住すべて」であり、広すぎるから

社会福祉士は、生活のしづらさを支援する仕事です。
でも、生活の意味が広すぎて、ピンとこないのです。具体的には、生活は次のような活動を意味しますが・・・
- 食べる
- 顔を洗う
- 服を着替える
- 仕事にいく
- 学校にいく
- 運動する
- 電車にのる
- 車に乗る
- 役所手続きをする
- 子育てをする
- 料理する
- お金をつかう
- お金をためる
- 風呂に入る
- 掃除する
- 寝る ・・・etc
ヘルパーが支援するものを具体例としてみました。(あげだしたらキリがありません)
これらを継続して行う日々の営みが、生活です。
つまり、衣・食・住すべてが対象です。ということは、生活は人生そのものです。
例えば、”吉野家”の店員さんの仕事は、もっと簡単に説明できるはずです。彼らの仕事は大まかにいえば「食事の提供」です。
生活のなかから、食に限定してサービスを行うのです。
しかし、社会福祉士が支援するのは生活。衣食住すべてが対象です。範囲が広すぎて、具体的に説明しにくいのです。
数値化しにくいから
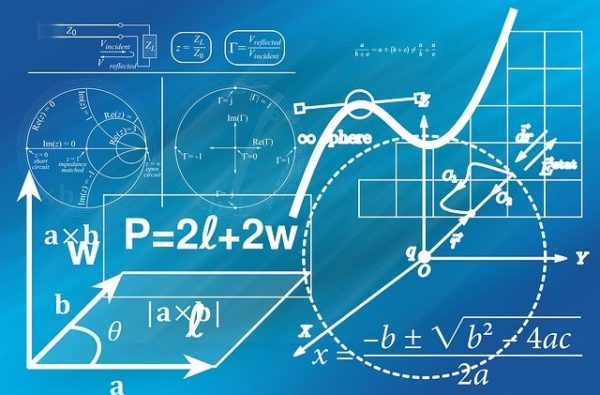
社会福祉士の仕事は数で表しにくいです。社会福祉士は人の生活を支援しますが、生活状況って数で表せないですよね。
例えば、人の生活状況を見立てる場合、
- クライエントが生活で困っていることは何なのか?
- クライエントは、どんな人生を送りたいと思っているのか?
答えは、言葉や文字で表すことになります。
YES・NOで答えにくい問いを扱っているのが、社会福祉士です。
例えば、クライエントの気持ちがそうです。「憎いと思うけれど、好きでもある」「仕事したいけれど、したくない気持ちもある」というように、相反する気持ちが両立しているのが普通です。
しかも、気持ちはゆれ動きます。
「朝はだるかったけど、今は元気」と、1日で変動することもあれば
「あの頃は辛かったけど、今思うと笑える」というように、年月を経て変わることもあります。
支援の効果を測りたくても
- 支援をする前の生活はどうだったのか?
- 支援をした結果、どれほど生活は改善できたか?
こうした答えは、数ではなく、言葉や文字で表されます。
スケーリングと言って、クライエントに数値化して答えてもらうこともしますが、答えてもらった数値はその人の主観表現ですし、正確かは不明です。
このように、数値化しにくいことを取り扱っているのが社会福祉士ですので、周囲からみても社会福祉士は何をしていてどんな成果をあげているのか、ハッキリとわかりにくいことになりがちです。
最後に
ここまで読んでくださった方は、社会福祉士の仕事について真剣に考えている方に間違いないはず。
だからこそ言わせてください。社会福祉士はどんな仕事をする専門職なのか、答えを考え続けましょう。私もそうしています。
私の考える社会福祉士の仕事は、決められた仕事だけでなく、必要なものを創り出すことを含みます。
与えられた仕事をルーティン的にするだけでなく、自らも考えるということです。
時代、地域、機関、各個人に合わせて、何を支援して、何を支援しないのか?答えを模索し続けるのです。
まるで哲学のようですが、そういう一面もあるのが社会福祉士という仕事です。
精神保健福祉士も、PSWからMHSWへと名称を変更しました。これには時代の変化、もとめられる役割、現場実態の変化が影響していました。
人の人生に正解が無いように、支援にも正解はありません。
なんだか嫌ですが、不正解はあります(笑)
でもね、「妥当な支援」の幅はとても広いのです。正解は複数ある、という感じです。
言い換えると、支援者による支援の違いが許されている仕事といえます。「あなたはそう支援したのね」と。それでよいのです。
仕事に自分の裁量をもちこめるわけで、この要素は仕事のやりがいにつながります。
けっこう魅力的な仕事ではないでしょうか?私はそう思います。
このサイトでは社会福祉士について現場経験をもとにさまざまな記事を書いています。いろいろチェックしてみてくださいね!それではまた。

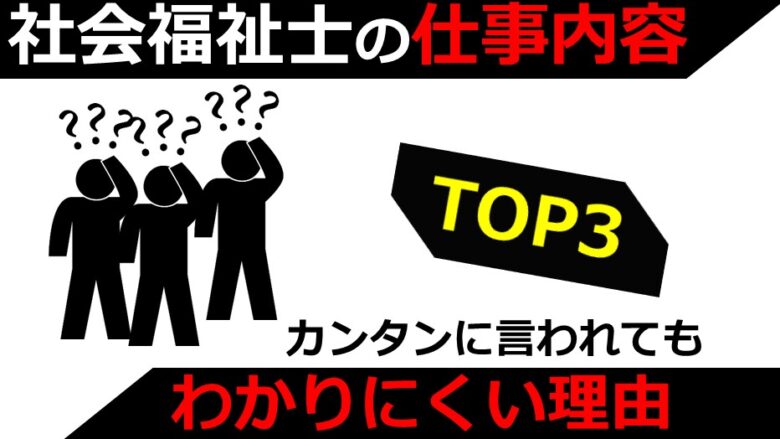


コメント