社会福祉士や精神保健福祉士に法律の知識って必要なのかな?
社会福祉士や精神保健福祉士、児童福祉司にとって支援力の中心は「相談技術」だと思われがちですが、現場で本当に力になるのは、相談技術だけではありません。
民法や福祉関連法をはじめとした法律の知識、そして日常生活で積み重ねてきた生活経験が、支援の現実的な力になります。
本記事では、社会福祉士・精神保健福祉士・児童福祉司にとって欠かせない法律知識の例と、生活経験がどのように現場で役立つのかを、実体験を交えながら解説していきます。
書いた人:ぱーぱす(社会福祉士・精神保健福祉士)
自治体で働くソーシャルワーカー。児童相談所などでの実務経験をもとに発信。
社会福祉士に法律の知識は必要か?
社会福祉士にとって、法律の知識は武器になります。
もちろん、最小限の法律知識でも現場で「戦えなくはない」かもしれません。 しかし、その武器が貧弱だと、いざというときに守り切れず、不利になりやすいのも事実です。
これは精神保健福祉士や児童福祉司にも共通します。
国家試験の勉強では、児童福祉法や生活保護法など幅広く学びますが、実際のところ「ピンとこない」と感じた方も多いのではないでしょうか。私自身もそうでした。
ところが、現場に出ると分野ごとにさらに深い法律知識が求められることを実感します。例えば次のように。
他にも役立つ法律は数多くありますが、現場ごとに特に使う法律はある程度限られているのが実感です。
法律の知識がクライエントを守る
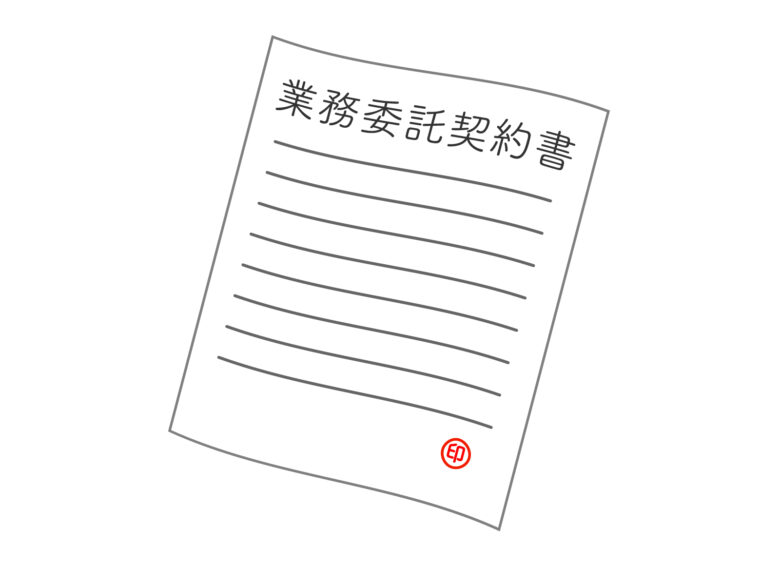
あるとき、担当していた子どもが「キャッチセールスのようなアルバイト」をしていました。
しかし実際には、アルバイトではありませんでした。「雇用契約ではなく業務委託契約」で働いていたのです。
私たちがイメージするような、コンビニや飲食店でのアルバイトは、ふつうは雇用契約です。
雇用契約では、労働基準法が適用されるので、最低賃金・残業代・労災保険・社会保険など、労働者を守る仕組みがあります。
一方、業務委託契約は労働者ではなく「個人事業主」として契約する扱いになります。残業代や社会保険がなく、突然の打ち切りも許されやすいなど、リスクの高い働き方です。
実際にその子の契約書には「賠償責任は本人がすべて負う」と明記されていました。未成年者に賠償を全て求めるなんて、ゾッとしますよね。
しかし民法では、未成年者が法定代理人(親権者)の同意なく結んだ契約は取り消せると定められています。
(未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
引用元:民法第五条
親権者の同意を得ていなかったので、取り消しの手続きをとることができました。こうした知識があったことで、子どもを搾取から守ることができたと思います。
知らなければ、経済的・性的な被害に巻き込まれる危険を見過ごしてしまうかもしれません。
ぜんぶ覚えるのは大変そうに思えるかもしれません。法律家でない限り、最初からすべて頭に入っている人はいません。
さらに言うと、実際に弁護士の方々も「こういう条文があったな」と探しながら確認することが多いそうです。
だからこそ私たちも、「何かおかしい」と感じたときに、法律ではどう定められているかを調べる姿勢が大事なのです。
丸暗記しなくていいのです。
私たちは、「何かおかしいな」と感じたり、対応に困ったときに
「法律ではどう決まっているか?」と考え、調べられたらOKです。
日常生活でも役立つ法律知識 ~私の体験談~
法律の知識は仕事だけでなく、私たち自身の生活を守る武器にもなります。
私の経験では、住んでいた賃貸住宅で「浄化槽清掃の費用は誰が負担するのか」というトラブルがありました。
調べると、
浄化槽法では年1回以上の清掃が義務とされ、さらに民法上、
基本的にメンテナンスは家主の義務とされていました。
(賃貸人による修繕等)
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
引用元:
民法第六百六条
その根拠を示して交渉した結果、費用は大家さんが負担してくれることになりました。もし法律を知らなければ、自分が数万円を負担することになっていたでしょう。
法律の知識が生活を守る実感を得た経験でした。
生活者としてのあらゆる経験が支援に生きる
社会福祉士・精神保健福祉士・児童福祉司にとって武器になるのは、法律の知識だけではありません。
生活者としての経験や知恵も、支援力を高める大切な要素です。
例えば、次のような経験は支援に活かせる機会があります。
- 恋愛、結婚、離婚
- 子育て、不登校、障害のある子との暮らし
- 介護、看取り、家事・介護と仕事の両立
こうした経験があることで、クライエントに寄り添う言葉に重みと熱量が生まれます。
知識だけでは届かない部分に、経験からくる説得力がそなわるのです。
熱量は偽造しにくいもの。「本気で伝えたい」と思っている熱量は、言語としても、非言語としても伝わります。
それが相手の行動を変え、支援を前進させることもあるのです。
法律の知識と生活経験の相乗効果
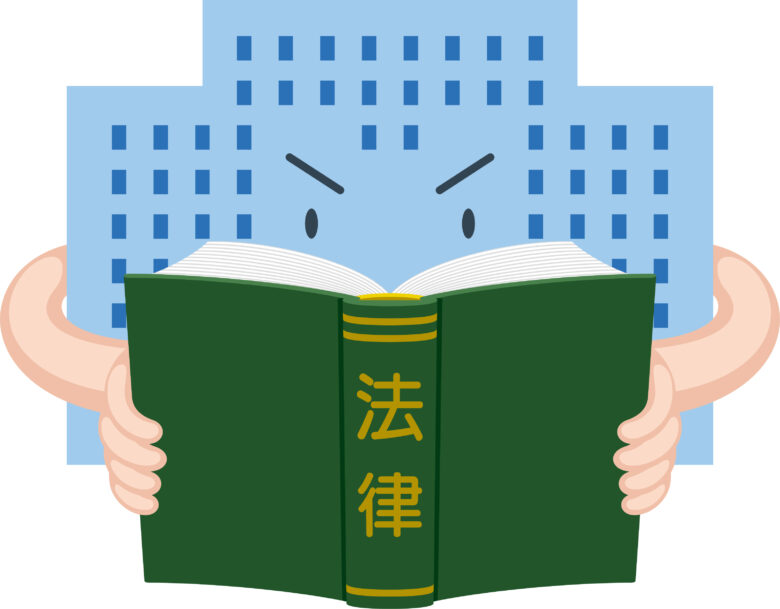
法律の条文は難しく見えますが、私たちやクライエントを守る仕組みがたくさん詰まっています。また、契約書などには、不利益をもたらす条項が小さい文字で書かれていることもあります。
一方、私たち自身の生活経験は、クライエントの気持ちを動かす大きな力になります。生活で得た知識が、支援にそのまま役立つこともあります。
法律の知識で守り、生活経験で支える。
法律の知識と生活経験の両輪が合わさることで、支援の実効性はぐっと高まります。
もちろん、支援には相談援助の技術や心理学的な知識、アセスメント力などなども欠かせません。
しかし、社会福祉士や精神保健福祉士、児童福祉司の支援力は、それだけでは成り立ちませんね。
法律の知識や生活経験といった、あなたの「生きた知恵」が加わることで、支援はより実践的で、クライエントにとって意味のあるものになるはずです。
学生・社会人・ソーシャルワーカーの方へメッセージ
お伝えしたいのは次のことです。
(偉そうにすみません。)
- 学生の方へ:恋愛、アルバイトや日常生活でのトラブルも、将来必ず支援に活きます。ぜひ、経験を積み重ねてください。
- 福祉以外で働く社会人の方へ:どんな経験もソーシャルワーカーの仕事に活かせます。他分野から入職される方は多いです。
- ソーシャルワーカーの方へ:今の職場で必要な法律をまず調べ、興味のある部分だけでも知ると、支援の力を確実に高めるはずです。
まとめ
社会福祉士にとって、法律の知識と生活経験はどちらも大切な武器です。
法律はクライエントを守り、経験は言葉に熱量を与える。この二つが重なったとき、支援はより強固で実践的なものになります。
知識を深め、経験を大切にしながら、共に支援力を磨いていきましょう!それではまた。

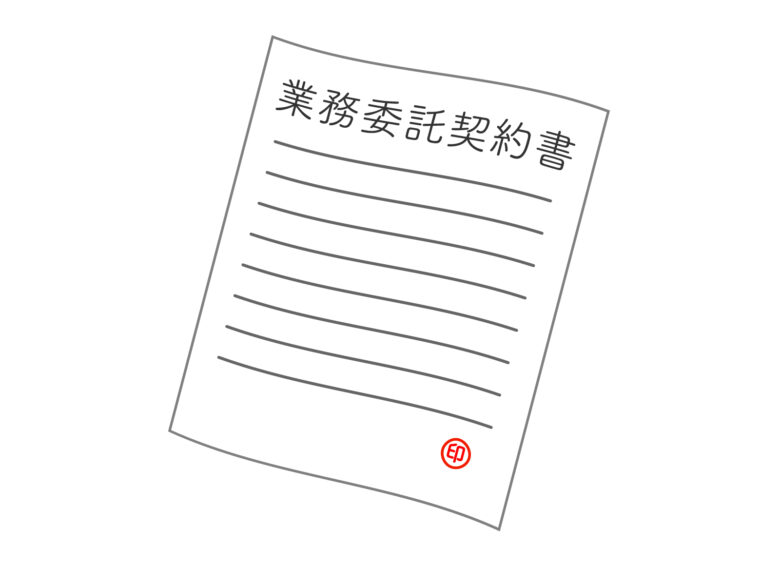

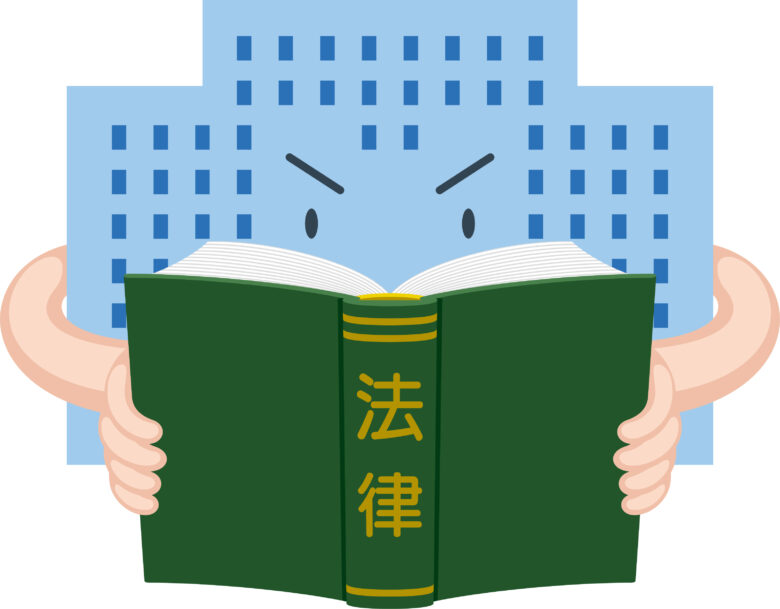

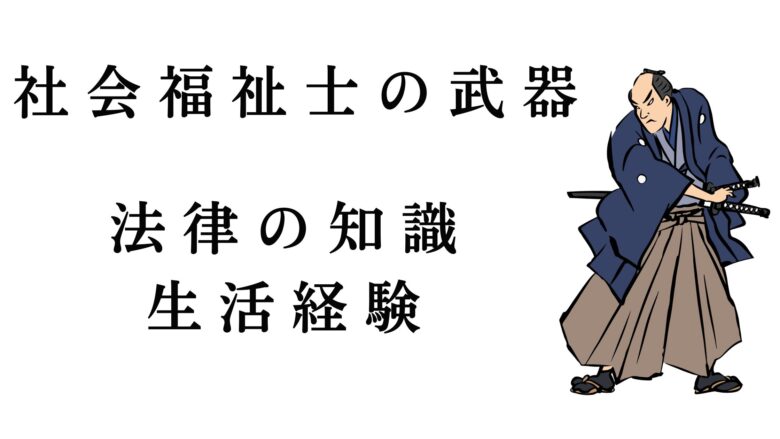
コメント