
発達障害と愛着障害が併発してる子どもって、どう支援したら良いの?うまくいかない・・・。
発達障害だけでも大変なのに、愛着障害もあるとなると、もっと難しいです。
愛着障害がある子どもは、暴力や嘘や盗みなどの課題行動を起こすことが多いです。
そうした子どもに対して、「褒める」だけでは効果がないこともあります。でも、「叱る」だけでは、子どもはさらに反抗的になってしまいがちです・・・。
では、どうしたらいいのでしょうか?
そんな悩みを解決してくれる本があります。それがこちらです。

私は児童指導員の経験があります。現場歴はおよそ13年。これまでの経験をもとに、本書について説明していきますね。
発達障害と愛着障害の併発児童への支援方法がわかる本|経験者が推薦
『「愛情の器」モデルに基づく愛着修復プログラム』は、発達障害と愛着障害の専門家である米澤好史さんが書いたものです。
この本では、発達障害と愛着障害がある子どもへの支援方法がわかりやすく説明されています。
例えばこんなことがわかります。
- 発達障害と愛着障害の違いや見分け方
- 愛着障害は治せる!そのために必要な「愛情の器」モデル
- 「褒める」「叱る」の意味やコツ
特に、「愛情の器」モデルというのは、注目すべき内容です。
これは、子どもの感情や行動に対して、大人が正しく反応することで、子どもが安心感や信頼感を持てるようにする方法です。
「愛情の器」モデルを使えば、子どもは自分の感情をコントロールしやすくなりますし、問題行動も減っていくとされます。
本書では、その具体的なやり方や実際の事例が紹介されています。
私も子どもの支援に携わっている者として、この本はとても役に立ちました。子どもたちとの関係が良くなったり、職場の雰囲気も変わったりしました。
本の中で特に印象的だったのは、「愛着障害は取り返しがつかない」というのは間違いだということです。
これまでの常識では、親との関係ができる期間は1歳半までで、それ以降はどれだけ愛情を注いでも無駄だと言われていました。
でも、そうではなくて、愛着障害は治せるということです。
そのためには、時間と努力が必要ですが、子どもに合った支援をすることが大切です。
また、「褒める」「叱る」についても分かりやすく解説されています。
発達障害と愛着障害がある子どもに対しては、「褒める」だけではなく、「叱る」も必要な場合があります。
でも、「叱る」の意味や方法を間違えると、子どもはさらに傷ついてしまいます。
そこで、本書では「叱る」の目的や効果、注意点などが詳しく説明されています。
例えば、こんな話があります。
「叱る」は、こどもの行動が生じてから大人が対応するという意味において、明らかに「後手を踏む」支援である。そして、脱抑制タイプの愛着障害では、それでも構ってもらったと対象児童は感じて、その行動は叱った大人の意図に反して増えてしまう。
引用元:米澤好史(2015)『「愛情の器」モデルに基づく愛着修復プログラム』福村出版 P203-204
あなたにも経験がありませんか?支援経験のある人なら、「そうそう!」と思った方も多いでしょう。
この本は約250ページありますが、読みやすく分かりやすい文章で書かれています。
発達障害と愛着障害がある子どもを支援する先生や保護者の方におすすめです。発達障害と愛着障害がある子どもへの支援方法がわかる本ですね。
本書のポイントを覚えて支援を続けていくと、「子どもが変わっていく」と感じられるようになるはずです。

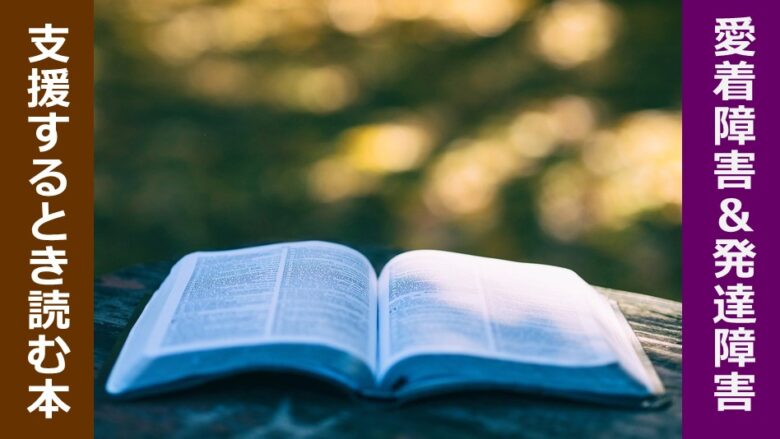


コメント