
児童養護施設って何が厳しいの?

体、メンタル、生活だよ!
- 児童養護施設の仕事って厳しい?きつい?
- 働いていて辛いことって何?
- 残業はあるの?
- 児童養護施設の職員っておかしいんじゃない?
こういった思いのある方へ。
私は某自治体で働く社会福祉士・精神保健福祉士です。現場経験はおよそ13年。児童指導員の経験があります。
児童養護施設の仕事ってどうなのか?
私の結論は、体・メンタル・生活が厳しいということ。
この三重苦に耐えられる人だけが、児童指導員として残れます!障害児入所施設なども同しですね。
ラクして稼ぎたい人にはオススメできません。
児童養護施設は、やりがい重視の人向けの職場です。
では、児童養護施設の仕事は何が厳しいのか?具体的な12の理由を解説していきます!
児童養護施設の仕事が厳しい12の理由【元児童指導員の本音爆発!】
体が厳しい!

体が厳しい理由は、次のとおり。
体が厳しい理由
- 宿直や夜勤で寝不足になる
- 宿直明けに8時間勤務はザラ
- 残業がある
- 交代制勤務(シフト制)で6連勤、7連勤がある
- 人手不足で有給休暇をとりにくい
- 子どもとの食事は「休憩扱い」で本来の休憩時間がない
すべて私の経験です!
知り合いの児童指導員から話をきいても、事情は大体おなじですね。
宿直や夜勤で寝不足になる
宿直と夜勤の違いをカンタンに言うと・・・
| 宿直と夜勤の違いとは? | |
| 宿直 | 眠ってOK。ただし何か起きたら対応してね! |
| 夜勤 | 眠るのはNG。徹夜で仕事しましょう。気合だ! |
私が長く経験したのは宿直。
宿直時間は、子どもの各部屋を1時間ごとに巡回していました。
宿直中の見回り時間には、限度がありました。だいたい23時ごろまでの見回りでしたね。
最後の見回りが終わってからすぐに布団に入っても、睡眠時間は6~7時間が限界でした。
私はギリギリでした。短い睡眠でも大丈夫な人はモンダイないんですけど、私はけっこう長く眠りたいタイプでしたので・・・。

まいにち8時間眠りたい・・・!
私のように「7~8時間は眠りたい」という人は、体が厳しく感じるはず。
家でリラックスして眠るのとは、ワケが違います。
「何か起きたら対応しないといけない!」という状況で眠るので、自然と眠りは浅くなります。
パソコンに例えると、スタンバイモードですね。
体が緊張し続けているためか、遠くで扉を開け閉めする音がするだけで目覚めたりしました。
ちなみに、宿直の間、子どもたちが部屋で静かに眠ってくれていたらいいんですけど、騒いでいたりすると注意しないといけませんでした。
「この先生は優しいから自由にしても怒られないだろう」と思われていると、施設内が無法地帯に様変わりしていたりします。
そして、トラブルや事故がおきる・・・。
一方で、怖かったり厳しさのある先生が宿直の日は、子どもたちは静まり返っていました(苦笑)
子どもは職員に「今日の宿直は誰?」とよく確認していました。
「誰が宿直か?」もっと言えば、「今日の勤務の職員は誰か?」によって、子どもたちの動きは変わります。
同僚の児童指導員は「子どもが眠ってくれるかどうかは運次第・・・」と苦笑いしていました。
ちなみに、夜に子どもが無断で外出した時は大騒ぎです。夜中に捜索することもありました。
それでも朝に寝坊はできません。定刻には起きて、朝食の用意をして、子どもを起こす役割がありました。
「4~5時間睡眠でもバリバリ働ける!」という人には厳しくないでしょうけど、生粋のショートスリーパーは数%くらいしかいないと言われています。
なので、9割以上の人にとって、宿直勤務は睡眠不足になりやすいきつい仕事と言えそうです。
宿直明けに8時間勤務はザラ

宿直明けは、すぐに帰って良いよね!おつかれさまでした~!

いやいや、今から8時間勤務ですよ!!

!!?
「宿直明けは眠いし、帰って良いはず!」
そう思っていたことが私にはありました。
しかし残念ながら、そんなことは無かった・・・。
宿直明けからもう一度、8時間勤務がスタートするのです。
例えば次のように。
拘束時間が長い!まさに一泊二日。
翌日の8時間勤務(残業含む)が終わった時は、合宿から解放されたかのような気持ちでしたね。
ちなみに、慣れないうちは翌日の勤務が眠くてたまりませんでした。
ようやく慣れたと思ったら、たくさん仕事を任されて残業中に二晩目を迎えたり。(いつ帰れるの~)
先輩からは

頑張るね。今晩も泊まってく?
なんて、冗談が飛んできたりしました。笑えない冗談です・・・。
残業がある
「宿直明けでも残業がある」ということは、普段も残業があるわけで。
少ない人員で回す施設現場では、交代職員が出勤するまでの時間を残業でつなぎます。
あるいは、残業時間になってようやく自分の事務仕事ができたり。
つまり、残業ありきの体制なんですね。
イメージとしては、学校の先生の働き方と似ています。
学校の先生って、クラスにいる間はほとんど事務仕事できていませんよね?
子どもたちと関わっている間は、授業の準備などもできません。
施設の職員も同じで、子どもたちと関わっている間は、記録を書いたり、関係機関や保護者との電話はしにくいです。
そのため、次の交代職員が出勤してから、ようやく自分の事務仕事をスタートさせられるのです。
交代制勤務(シフト制)で6連勤、7連勤がある
ここまで話した宿直・残業の日々が、6~7日続く場合があります。
それはどんな時かと言うと、各職員の出張や休日の都合などで、他の職員にしわ寄せが行った場合です。
例えば大きな工場のように、たくさんの人でシフトを回しているなら、一人や二人ぬけても大丈夫でしょう。
でも、小規模な児童養護施設は、代わりの人が限られます。
誰かが体を張って解決するしかないのです。
私は勤務シフトを組んでいた時がありましたが、苦行でした。シフト作成は難解なパズルゲームです。
例えば、次のようなことを考えます。
- 叱れる職員がいないと無法地帯になって事故が起きるから、1人は叱れる職員を配置したい
- 子どもの通院同行に職員が行くから、その間はもう1人出勤させないと回らない
- A職員とB職員は仲が悪いので、一緒のシフトにしてはいけない・・・
- 風呂介助があるので、男女のバランスを考えないといけない
こうした条件はごく一部。
実際は10以上の条件を総合的に考えるのですが、
「あちらを立てればこちらが立たず」で、正解の無いこともあります。
そうした結果、誰かが6~7連勤になってしまいます。
「申し訳ない・・・」と勤務調整担当は頭を抱えます・・・。
皆さん、勤務調整する人には優しくしてあげてくださいね!(笑)
人手不足で有給休暇をとりにくい
6~7連勤が発生するほど人手不足の現場です。有給休暇を取るどころではありません。
有給休暇(特別休暇)をとれる時は、次のパターンくらいでした。
- 体調をくずしたとき
- メンタル疾患になったとき
- 家族(主に子ども)の体調不良
- 冠婚葬祭
- (寝坊)
つまり、「Aさんが有給休暇を取る = Bさんが残業する」です。
助け合いと言えば聞こえは良いですが、誰かに迷惑をかけないと、有給休暇はとれないのです。
これって、労働環境として問題です。
「誰かに残業してもらってでも俺は休む!」というのは、はばかられます。堂々とそんなことしていたら、リンチにあうかもしれません(苦笑)
そのため私は、毎年、使いきれなかった有給休暇が消えていきました。
いったい何日分が消えたんだろう・・・?

休みを取れないなら有休を買い取ってほしい!
子どもとの食事は「休憩扱い」で本来の休憩時間が無い
児童養護施設って、休憩時間が無い!です。
これは児童養護施設だけの問題ではありません。福祉現場のあるあるでもあります・・・。
こちらの福祉・介護現場は休憩なし!?【あるある事例まとめ】で、もう少し詳しく話していますが、
子どもと食事を食べている時間は、休憩時間として扱われる。
「子どもとの食事時間は楽しいものでしょう?」という無言の圧力があります。
でもね、食事中ってトラブルがよくあるんです。
例えば、
- 食べ物の取り合い
- 食べずにすぐ捨てる
- 食べ物を皿ごと投げ飛ばす
など、目が離せないんですね。リラックスはできないし、ゆっくり食べてもいられません。
私は平然とした顔を装いながら、ご飯を口にかき込みつつ、全体に目を配っていました。
(児童養護施設で働いてから、食事のペースが上がってしまいました。急いで食べる習慣がついたのでしょう。)
ある日、私は先輩の50代女性に「休憩とって良いですか?」と言ったら、

え!?ぱーぱすさんが休憩とりたいってー!皆とりたいのに。いいよいいよ。行ってらっしゃい。
と、後ろ髪引かれるような言い方で許可されました。
意地悪な人に聞いてしまった私も不器用でしたが、そもそも休憩が取りにくい職員体制に課題があります。
チームワークの名のもとで、「利用児・者さんとの食事時間は休憩扱い」という実態は、課題と目されずに放置されやすいのが児童養護施設でしょう。
メンタルが厳しい!

メンタルが厳しい理由は、次のとおり。
メンタルが厳しい理由
- 支援がうまくいかない
- 暴言・暴力を受ける
- 職員関係で気を遣う
- 休日に職場から連絡が入る
支援がうまくいかない
児童養護施設って、私たちがどれだけ頑張っても、支援に成果が出るとは限りません。
愛情や関心に飢えている子どもに「愛情を伝えたい!」と思う気持ちは、とても素敵です。
「親に捨てられた」と思っている子どもや、
「誰も信頼できない」と思っている子どもに、
「何とか手を差しのべたい」と思う人は心の温かな方でしょう。
しかしハートだけではうまくいかないのが、支援の奥深さです。
特に、深刻な課題ほど思うようにいきません。例えば、
- 繰り返し手首を傷つける子
- 激昂したら大切な物を踏みつぶす子
- 何度注意しても、喧嘩になったら手が出てしまう子
情熱的に関われば関わるほど、うまくいかなかった時は私たちもダメージを負います。
親身に関わったつもりが、返って来るのは感謝ではなく暴言で、ひどければ暴力を受けます。
支援につまずくたび、私たちは自信を失い、無力感に打ちひしがれます。
メンタルが徐々に辛くなっていくんですね。
心にジャブをくらい続けるうち、知らない間にノックアウトしてしまう。
対策には、自己覚知が大切です。
自己覚知をシンプルに言うと、自分自身を深く知って支援に活かすことです。
例えば、下記の質問に答えられるでしょうか?
- どんな子どもが好き?その理由は何だろう?
- どんな子どもが苦手?その理由は何だろう?
- どんなときが辛い?その理由は何だろう?
- 子どもに関わりすぎてしまうのは、どんな時?
- 子どもとの関わりを避けたくなるのは、どんな時?
こうした質問に真剣に答えようとすると、おのずと自分自身と向き合うことになります。
答えを掘り下げていくと、自分自身の育ってきた環境や、親との関係にまで、立ち返ることになります。
こうした自己覚知のプロセスでは、きっと嫌な思いをするでしょう。
自己覚知は、痛みを伴う外科的治療に近いです。
放っておくと病巣は広がり、手が付けられなくなります。手を施すのは早い方が良いです。
しかし自己覚知に熟練すると、気持ちをコントロールしやすくなります。
身勝手な関わりとオサラバ。意図的な支援をしやすくなります。
自己覚知は、専門的支援の基盤となります。しかも、自らのメンタルを守る盾の役割も果たします。
児童養護施設の厳しい仕事をタフにこなしていくなら、自己覚知は習慣化しておきたいですね。具体的なやり方は、こちらで知ってもらえます。
暴言・暴力を受ける
児童養護施設で仕事をしていると、子どもから暴言や暴力を受けることがあります。
全く不思議なことではありません。
私はたくさんの言葉を浴びてきました・・・。
- 黙れ!
- 帰れ!
- 話しかけてくるな!
- 何も知らないくせに!
- やっぱり大人は信用できん!
- くそジジイ!
例え20代でも男性職員はジジイ、女性職員はババアになります。ご覚悟ください(苦笑)

そんなこと言われたら落ち込むわ・・・腹もたつし!
対処法を少しだけお伝えしますね。
まず、あなたは暴言を真に受けないことです。言葉通りにとらえて言い返すのはキケンです。
腹が立っても、その言葉のウラにある気持ちに焦点をあてましょう。
その子が暴言を言ってしまう気持ちに、応えれば良いのです。
ただし、暴力についてはそうもいきません。
もし、あなたが手や足を出されたら「いいよ~気にしないで」とはいきませんね。「暴力しても許してもらえるんだ」という学習をさせてしまいます。
施設内での暴力を許すということは、DVを許すようなものです。そんなことをしていたら、あなたのつらい仕事は何のだったのか?と思ってしまいかねません。
児童養護施設の仕事は、共感的に関わるだけではダメで、社会的に許されないことは毅然と指摘しないといけません。
バランスを求められる現場です。
しかし、「叱れない」という悩みを抱える職員もいます。
慣れないうちは先輩職員を頼っておきましょう。助けてもらえば良いのです。
暴力はメンタルにもダメージを負います。その痛みは、その子が過去にうけた痛みの再現かもしれません。
彼らのこれまでの育ちの過酷さに思いをはせましょう。
しかし、暴力については許さないことです。
特に、中学生や高校生は体が育ってきています。力が強いので痛いし、実際にケガもしてしまうかもしれません。
ご自身をしっかりいたわってあげましょうね。
職員関係がツラい
児童養護施設の仕事は1人ではできません。個人プレーよりも集団プレーの現場です。
言いかえると、一緒に働く職員の立ち回りから影響を受けます。逆もしかり。
例えばバレーボールでは、選手同士が声をかけ合ってトスをしたりスパイクを決めますよね?
児童養護施設の仕事も同じで、職員同士が声をかけ合い、食事・遊び・外出・入浴などの日課を支援します。
相性の良い人と組んでいる時は、スムーズな支援ができます。
そうした雰囲気は子どもに自然と伝わり、和やかな雰囲気に包まれます。
しかし、次のようにモンダイのある職員と組まざるを得ないこともあります・・・。
- 言い方のキツイ職員
- 妙なコダワリのある職員
- 自分の思い通りにしたい職員
- 不機嫌をまき散らす職員
- ばかでかい声で虐待まがいの関わりをする職員
すべて私の体験談です・・・。
こうした職員がいると、子どもから

〇〇さん(職員)にこんなこと言われたんだけど・・・
と、たびたび相談されたりします。
しかも子どもの主張の方が、よほど筋が通っている・・・。
このような職員が1人でもいると、たいていは職員同士の人間関係に亀裂が入り、子どもにも伝わってしまいます。
人間関係が悪い現場は、支援のクオリティも低くなります。
職員に気を配りながら子どもにも気を配らないといけないので、神経がすりへって疲れます・・・。
なお、児童養護施設の現場は女性が多いです。そのため、男性陣はこちらの福祉現場で女性陣との人間関係にお悩みの男性へ【社会福祉士の体験談】が役立つかもしれません。

人間関係がフクザツそうだなぁ
休日に職場から連絡が入る
児童養護施設は24時間365日稼働しています。
誰かの休みは誰かの仕事日です。
交代交代で回していくので、情報共有は大切ですが漏れは起きがちです。
「Aさんに聞かないとわからない」
「上司に相談しないと判断できない」
となれば、休日でも割とお構いなく電話したりLINEを送ります。
休日に仕事の連絡が入ると、「仕事のスイッチ」が入ってしまいます。
いったん入ったスイッチは、連絡が終わってもすぐOFFには戻れないんですよね。
スイッチの切り替わりスピードには、個人差があります。
私は「カンベンしてくれー!」と思うタイプでした。
忘れていた仕事の悩みを思い出して、気が沈んでしまったり・・・。

自分が病んでしまいそう・・・

しっかり対策していけば大丈夫!
メンタル対策は、私が厳選した方法を下記の記事で知ってもらえます。児童養護施設の仕事でも対策は同じです。
生活が厳しい!

生活が厳しい理由
- 給料が割に合わないかも
- 土日祝の休みが少なく、人と会いにくい
給料が割に合わないかも
児童養護施設職員の給与・年収についての調査は乏しいのですが、
平均年収は約374万~404万円です。
このことは【発表】児童指導員の年収・給料は低い?【職場別の年収ランキング】で解説しています。
また「乳児院・児童養護施設・母子生活支援施設で働く社会福祉士の平均年収」としては437万円でした。
こちらは社会福祉士の給料・年収高い職場ランキングTOP42【最新公式調査より】でご紹介しています。
児童養護施設の職員は、保育士や社会福祉士が多いです。
児童指導員の任用資格だからですね。
それぞれの平均年収をまとめると下記のようになります。
| 保育士 | 児童指導員 | 児童養護施設 | |
| 平均年収 | 326.8万 | 404万 | 437万 |
参考:保育士の平均賃金 – 厚生労働省(出典:平成28年賃金構造基本統計調査)、社会福祉士就労状況調査結果報告書(令和2年度)、厚生労働省 職業情報提供サイト(日本版O-NET)
このように比べると、「児童養護施設で働く職員の平均年収は高めかも?」と思えます。
ただし職場ごとの差は大きいでしょうし、給与規定をよく確認しておきましょうね。
後はあなたの感じ方次第です。
つまり、宿直・夜勤・残業・土日祝日勤務あり、暴言あり、暴力あり(?)という厳しさと
対価(給料・やりがい等)が、割に合っていると感じられるかどうかでしょう。
「やりがいさえあれば頑張れる!」という方なら、長く働いていけるはず。実際、そうした方はおられます。
土日祝の休みが少なく、人と会いにくい
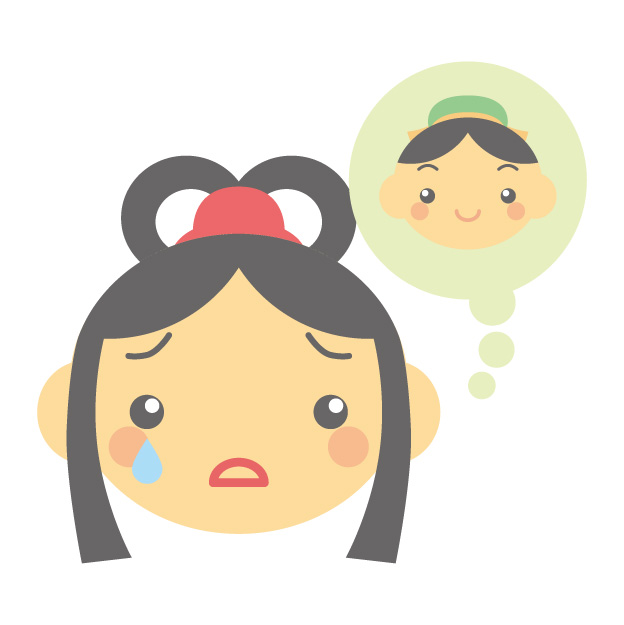
児童養護施設の職員さんは、彼氏・彼女、友だち、家族と会おうとしても、休みを合わせづらいです。
なぜなら、シフト制で土日祝も仕事があるから。
「いつの間にか疎遠に・・・」なんてことのないよう、努力がいります。
休日希望があれば、勤務調整の担当者に、早いうちに、やさし~く、伝えておきましょう!
また、児童養護施設の仕事は他律的です。つまり、周りの都合であなたの予定が決まる仕事です。
したがって、仕事後の予定は組みにくいです。
例えば、勤務終了間際に子ども同士がトラブルを起こすと、人手が必要になって対応に駆り出されます。
なかなか出られず、予定に遅刻したり、最悪の場合はキャンセルに・・・。
そうならぬよう、私は人と会う予定を休日だけに入れるようにしていました。
飲み会もデートの約束を、仕事後に入れるのは避けた方がいいです。
最後に 「きつい」「辞めたい」という方へ
「児童指導員だけどもう辞めたい・・・」という方は、これまでのノウハウを活かしての転職も1つの道です。
同じ児童養護施設でも、職場が変われば事情も違うことがあります。
もう少しホワイトな現場を探してみるということですね。
また、児童指導員は放課後等デイサービスでも働けます。最近はたくさんの求人が出ていて引く手あまたです。
児童養護施設のような宿直・夜勤から解放されるので、つらい方は検討してみる価値があるでしょう。

体の厳しさからは解放されるんだね!
「職員がおかしいから辞めたいけど、担当の子が心配で・・・」という方もいると思います。
ですがそこは割り切りがあって良いのです。案外、気丈に成長していったりするものですから。
それに支援の究極目標は、「自分がいなくてもやっていけるようにする」ということです。
自分がいなくてはダメな状態にしておくのは、むしろ良くない支援です。
今は終身雇用の時代ではなくなりました。欧米では転職してステップアップしていくのがスタンダードです。アメリカの生涯の平均転職回数は11回という調査結果があります。
わたし自身、2回転職しました。福祉業界内での転職なのでこれまでの経験を活かせてスムーズでしたし、年収は100万円以上UPしました。
児童指導員の転職については、こちらの記事でおすすめ転職サイトやエージェントを知ってもらえます。
児童指導員向けのサイトってほとんど無いので、おすすめできるのは限られました。
タイトルからはわかり辛いですけど、まずは公務員をオススメしている記事です。
あなた自身が幸せでなければ、人への支援も影を帯びたものになりやすいです。
人生に2度目はありません。後悔のないように選択していきましょう!

自分も周りもハッピーな児童指導員になろう!

頑張ってください!あなたの健闘を祈ります!









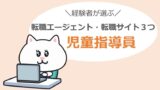
コメント