
パターナリズムってダメな考え方とかやり方じゃないの!?
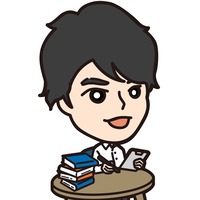
そうでもない。パターナリズムは使い分ければ価値があるんだ。
こんにちは!私は某自治体で働く社会福祉士・精神保健福祉士です。現場経験はおよそ13年です。
この記事は福祉現場で『悪』とされがちなパターナリズムについて、その価値をよく考えてみようという趣旨です。
特に、子どもと直接かかわる立場(児童指導員や児童福祉司)の方に、役に立つと思います。
では、まいりましょう!
福祉現場のパターナリズムの価値を再考しよう|現役社会福祉士の自論

インフォームド・コンセントとパターナリズム
インフォームド・コンセントとは?
最近の福祉現場では、インフォームド・コンセントが大切とされていますよね?
『社会福祉士』や『精神保健福祉士』の勉強では、インフォームド・コンセントの大切さを学びます。
インフォームド・コンセントは「説明にもとづく同意」という意味で、
具体的には「医師が患者さんに病気の説明を十分したうえで、了解を得ながら、治療法などを決めること」です。
これにならって、福祉職たる私たちもインフォームド・コンセントで支援した方が、
- 利用者・患者さんとの信頼関係ができやすい
- 決定後の参加姿勢も積極的になる
こういった効果があると見込まれ、大切されています。
パターナリズムとは?
さて、このインフォームドコンセントと対義的なのがパターナリズムです。
パターナリズムとは何かというと
このような意味合いですね。例えば
- それはあなたのためにならないから、止めるべきです
- もっと〇〇しましょう
- あなたの病気はまだよくなっていないので、退院できません
という、指示的な関わりです。
パターナリズムが起きやすい関係は、次のような間柄です。
- 医者と患者
- 支援者と被支援者(利用者さん等)
- 大人と子ども
上下関係を伴うイメージですね。支持する者、指示される者という関係性です。
福祉現場では、パターナリズムは過去の悪しき考え方・関わり方のように思われていたりします。
『パターナリズム=悪』は行き過ぎだと思う
私は、パターナリズムを絶対悪のように扱うのは行き過ぎでは?と考えています。
※すべてのパターナリズムを肯定するつもりはありません
- 「インフォームド・コンセントは善い」
- 「パターナリズムは悪い」
こういう〇×思考でとらえるのではなくて、それぞれのメリット・デメリットを使い分ける必要があると思うんですね。
福祉現場で長く働いていると、インフォームド・コンセントの考えだけにのっとっても、うまく支援できないことがあるのです。
親子関係でのインフォームド・コンセントとパターナリズム

親子関係には、パターナリズムがよくあります。
例えば、親は、自分の子ども(小学生)がタバコを吸っているのを見たら、どうするでしょうか?
- タバコを取りあげる
- 吸わないように見張る
- お金を渡さないする など
何かしら、制限をかける親が多いのではないでしょうか?
これは、子どもの希望と関わりなく、です。
「お前のためにはならないから、やめておきなさい」と干渉するのです。
では、この場面でインフォームド・コンセント的な関わり方をするとどうなるでしょうか?
【中学生の息子がタバコを吸っているのを見て、父はタバコの危険性を説明した例】
父親:タバコを吸うと病気のリスクが上がる。やめられなくなる。百害あって一利なしだ。やめておいた方が良い。
息子:そんなことは知っとるわ。それでもオレはタバコを吸う。生き方は自由だろ?放っておいてくれ。あんたに迷惑はかけてない。
父親:体に悪いことはわかっているんだな?じゃあ仕方ないな・・・。
(厳密にはインフォームド・コンセントの意味することとは違うと思いますが・・・)
これだと、まるで弱腰の父親ですが・・・
母親から「お父さん、もっとしっかり言い聞かせてくださいよ!」と喝が入るかもしれません。
パターナリズムが必要と思う場面3つ
私が思う、パターナリズムが福祉現場で必要と思うケースは次のとおりです。
- 年齢的に未熟で、自らの決定に対する責任をとれない子ども
- 認知症や知的障がいなどで、判断に支援が必要なとき
- 精神症状等が急性期で、自傷他害のおそれのあるとき
極端な話ですが、1歳の幼児にインフォームド・コンセントだの自己決定だのとは言ってられませんね。
それと、どれだけ説明を尽くしても、うまく理解できない知的水準の方はおられます。
また、精神的な症状の悪化によって、一時的にやり取りできない状態の方もおられます。
ただし、始めから指示的に関わるのではなく、その人の意志を確認できないとか、決定の妥当性に明らかな問題があるときに、パターナリズムを発動するイメージです。
福祉現場はパターナリズムに欠けがちではないか?
「福祉の”福”は服従の服」という皮肉があります。これを言っていたのは、向谷地生良さんだったと思います。
私たちは、利用者・患者さんのためと考えて、彼らの言うことに従ってばかりになっていないでしょうか・・・?
今の福祉現場では、インフォームド・コンセントが大切にされています。社会福祉士のカリキュラムでもそのようになっています。
確かに、原則はインフォームド・コンセントであることに異論はないです。
インフォームド・コンセントを悪者にしたいのではありません。
しかし申し上げたいのは、パターナリズムも時に必要ではということです。
例えば、児童福祉の分野のように、子どもが危ない行動や社会ルールを破る行動をとった時などは、毅然と許さない関わりが必要でしょう。
わたし児童指導員として、虐待にあった子どもの支援にかかわってきました。
その子たちが求めているのは共感・受容でありつつも、それだけではないように見えました。
彼らは、暴力や破壊といった形で、社会ルールを逸脱しがちでした。彼らの多くは、家庭でまっとうな親をみていなかったのです。
暴力で支配された家庭、アルコールやギャンブルで秩序のない家庭、父親はいるけれどとても影が薄いetc・・・
もちろん、傷ついた心をうけとめてくれる優しさは必要です。
しかし、優しさだけでは育ちとして不十分だと思います。
不健全な家庭で育った子たちが実は求めているのは、規範やルールを逸脱してしまった行為を許さず、守るべき規範やルールを明確に示す関わりに思えてなりません。
まとめ
私の主張は、原則はインフォームド・コンセントだが、時にパターナリズムも必要ではないかというものです。
インフォームド・コンセントの方が良いとか、パターナリズムの方が良いとか、そういった〇×の話ではありません。
社会福祉士のテキストなどでは、パターナリズムは否定されているわけではありませんが、インフォームド・コンセントの大切さが繰り返し伝えられています。
これから福祉現場で働く方、働こうとする方には、「パターナリズムにも価値があるかも」という話を覚えておいていただきたい。
私はこれからも実践を繰り返し、必要性や効果を考えていきたいです。
あなたがもっと専門的な見地からパターナリズムを考えたい人には、こちらの論文がおすすめです。
≫山梨県立大学 畑本裕介 正しいパターナリズムと不正なパターナリズム ― ワークフェアをどう正当化するか ―
(前略)現代社会ではパターナリズムのある側面は批判の対象ではなく、むしろ積極的に評価される時代に入りつつあると主張したい。
よって、ここで述べる現代社会において必要とされるパターナリズムを正しいパターナリズムと呼ぼう。
引用元:山梨県立大学 畑本裕介 正しいパターナリズムと不正なパターナリズム ― ワークフェアをどう正当化するか ―


コメント
[…] 10代の利用者様の金銭管理のサポートは、締め付けすぎるとパターナリズムになってしまいますし、任せすぎるとネグレクトになりかねません。 […]