
自閉症スペクトラムの子がパニックになったらどうしたらいいの?落ち着かせるには?
こうした疑問のある方へ。
この記事の内容
- 第一対策:予防 パニックを起こさないようにすること
- 第二対策:対処 パニックが起きたときにすること
- 補足:自閉症と愛着障害がある子にはどうする?
- コツ3つ:人・場所・話題を変える方法
私は社会福祉士・精神保健福祉士で、自閉症や知的障害のある子の支援をしてきました。
今も現場で働きながらブログを書いています。現場経験はおよそ13年です。
自閉症スペクトラムの子は、パニックになると自分や周りの人や物を傷つけてしまうことがあります。
パニックになってしまったら、どうしたら良いかわからない人も多いと思います。
自閉症スペクトラムの子のご家族や学校の先生、施設の先生たちは、パニックになる子を見ていると大変だと思います。私もそうでした。
自閉症スペクトラムにあわせた理論とわたしの現場経験をもとに、対処法などを解説していきますね。
自閉症スペクトラムのパニック|落ち着かせる方法は?【専門家解説】
第一対策:予防 パニックを起こさないようにすること

転ばぬ先の杖
自閉症の子のパニックは、起こさないようにするのが一番です。つまり、予防が第一です。
パニックになりそうなことがわかったら、避けるようにしましょう。
パニックには理由があります。どんなときにパニックになったか、メモしておくと良いです。そうすると、予防しやすくなります。
自閉症の子は、パニックになった理由を言えないことが多いです。それは、自分の気持ちがわからなかったり、言葉で伝えられなかったりするからです。
だから、周りの大人が気づいてあげることが大切です。
「失敗するのも大切」という意見はわかります。しかし、自閉症スペクトラムのある子たちにとって、失敗によるダメージはとても大きいです。
例えば、初めて乗った電車で嫌な体験があったら、二度と電車に乗ろうとしなくなる、という具合です。
だから、特に、初めてやることは良い体験になるようにしたほうが良いのです。無計画に飛びこむと、辛い思い出だけが残ってしまいます。

でも・・・予防してもパニックになってしまうこともあるよね。どうしたら良いの?
確かに、予防してもパニックは起きてしまうことがあります。想定通りにはいかないですからね。
では、予防できなかったパニックにどう対応すれば良いか?次の話に移りましょう。
第二対策:対処 パニックが起きたときにすること

パニックが起きたら何とかするのは諦めてください。落ち着くまで待ってあげましょう。時間がたつのを待つことです。
パニックとは、目や耳で入ってくる情報がわからなくなってしまうことです。だから、例えばこんなことをしてもダメです。
- パニックになった理由を聞く
- 人や物を傷つけたから怒る
パニックのときに話しかけても、効果がありません。怒っても意味がありません。逆に、刺激になって悪くなります。
「どうしたの!?」「言葉で言わないとわからないでしょ!」「やめなさい!」
すべて逆効果です。パニックがもっとひどくなって、火に油を注ぐようなことになります。
良い対応は、落ち着くまで見守ることです。でも、安全には気をつけてください。
例えば、頭を壁にぶつけてしまうなら、壁との間にクッションを入れてあげてください。
周りの物を投げたり蹴ったりしてしまう、人を叩いてしまうようなら、物をどかしたり、安全な場所に移動してもらいましょう。
周りの人にも危険が及ぶことがあるので、離れてもらうようにしましょう。
自閉症スペクトラムと愛着障害がある子はどうする?

上記で教えた対応でも落ち着かない子もいます。よくあるのが、愛着障害(愛情を受け取れなかった)もある子です。
大声を出したり、物を投げたり、人を攻撃してしまいますが、感情の爆発する力が自閉症だけの子より強いです。
特に、中学生や高校生の年代になるにつれて、暴れる力が強くなって危険です。周りは見守っていられません。
私が働いていたときは、窓ガラスが割れることもありました。だから、施設では窓ガラスではなくアクリル板にしていますね。
落ち着かせようと色々してあげると、子どもは「やった!暴れたら優しくしてもらえる!」「構ってもらえる!」と間違った学習をしてしまいます。
その場は落ち着いたとしても、長期的には手に負えないことになっていきがちです。
「こんなに暴れても構ってくれない・・・。もっと暴れよう!」とエスカレートするのです。
こうなると学校の先生や施設の先生も手に負えず、困ってしまいます。
どうしたら良いのでしょうか?
人や場所や話題を変える方法
自閉症と愛着障害(愛情を受け取れなかった)の両方がある子への対応で効果的なのは、人や場所や話題を変える方法です。
併発している子どものパニック対応
- 人を変える
- 場所を変える
- 話題を変える
例えば、対応する人が交代すると、急に気持ちが変わって落ち着くことがあります。
また、パニックになっていた場所から移動したり、外に出たりすると、すぐに落ち着くこともあります。
また、関係のない話題を出してみるのも効果的です。好きなゲームやおもちゃの話などが良いです。ごまかすみたいですが、効果があります。
自閉症スペクトラムと愛着障害が併発している子への対応は、自閉症スペクトラムの子と同じ対応をしてもうまくいきません。それは、愛着障害が絡んでいるからです。
対応方法ををもっと知りたい人にむけて、こちらの記事でおすすめ本を紹介しています。
まとめ
パニックは辛いですし、少しでも楽にしてあげたいですよね。
でも、対応する大人だって大変です。何度もパニックが起きると、自信を失くしてしまうし、疲れてしまいます。
でも、正しい対応方法がわかればあなたも子どもも楽になれます。この記事が少しでも役立てば嬉しいです!

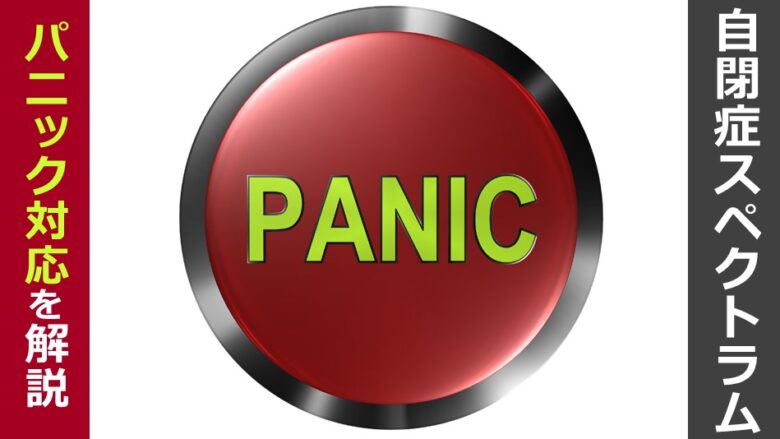

コメント