
利用者さんとどう関わったらいいかわからない・・・。支援関係ってどうすればいいの?
こうした悩みのある方へ。
この記事の結論
- 利用者さんとの関わり方のヒントは、支援計画や支援目標、所属機関の役割にある
- 支援計画や支援目標がある場合は、それらを実現するための関わり方をする
- 支援計画や支援目標がない場合は、所属機関の役割に沿った関わり方をする
- 支援目標と関係ないことは支援しないくらい割り切って関わる

こんにちは。社会福祉士兼精神保健福祉士ブロガーのぱーぱすです。現場経験は10年以上になります。
今回の記事は、私の主張・見解をまとめたものです。
これが正解というわけではありません。でも、利用者さんとの関わり方に悩む方は、1つの解答を知ることができるでしょう。
この内容をもとに、「ここは私の考えとは違うな」「ここはもっとこうした方が良いと思う」とブラッシュアップしてみてくださいね!
利用者さんとの関わり方について悩んだら読む記事【コツ4つを解説】
利用者さんとの関わり方のヒントは、支援計画や支援目標、所属機関の役割にある

利用者さんとの関わり方のヒントは、支援計画や支援目標、所属機関の役割にあります。
- 支援計画
- 支援目標
- 所属機関の役割
利用者さんとの関わり方を考えるときは、私たちが何を目的として、何ができるかを明確にする必要があります。
そのためには、支援計画や支援目標という具体的な目標や、所属機関の役割という枠組みが必要です。
例えば、障害福祉サービスの事業所では、利用者さんと一緒にサービス等利用計画や個別支援計画を作ります。
この計画には、利用者さんのニーズや目標が書かれています。この計画に沿って、利用者さんが目標を達成できるような関わり方をすることが大切です。
また、自分の事業所がどんなサービスを提供できるかも把握しておくことが必要です。
例えば、就労支援や生活訓練などです。これらのサービス以外のことは、自分の事業所では対応できないかもしれません。
その場合は、他の支援機関やサービスなどの情報を伝えることになります。
利用者さんとの関わり方のヒントは、支援計画や支援目標、所属機関の役割にあります。
支援計画や支援目標がある場合は、それらを実現するための関わり方をする
支援計画や支援目標は、利用者さんと一緒に作ったもので、利用者さんの希望や意思を反映したものです。それらを実現することが、利用者さんの利益につながることです。
そのためには、利用者さんの状況や進捗を把握しながら、必要な言葉かけやプログラムを提供したり、サポートしたりすることが大切です。
例えば、精神科病院に入院している方の支援では、退院支援計画を作ることがあります。この計画には、退院後の住まいや生活、就労などの目標が書かれています。この計画に沿って、退院できるような関わり方をすることが大切です。
例えば、退院後の住まいを探すために、情報提供や見学の同行をしたり、生活訓練や社会参加のプログラムに参加したりすることがあります。
支援計画や支援目標がある場合は、それらを実現するための関わり方をします。
支援計画や支援目標がない場合は、所属機関の役割に沿った関わり方をする
支援計画や支援目標がない場合は、所属機関の役割に沿った関わり方をすることです。
支援計画や支援目標がない場合は、私たちが何を目的として何ができるかが不明確になりやすいです。関わり方もわからなくなりがちです。
その場合は、自分の所属機関の役割やできることを基準にして関わり方を考えることが必要です。
自分の所属機関がどんなニーズに応えられるか、どんな相談や手続きに対応できるかを把握しておくことが大切です。
例えば、相談支援事業所では、電話相談や手続きだけの支援もあります。この場合は、利用者さんからの相談内容や手続き依頼が、私たちの事業所で対応できるものかどうかを判断することが必要です。
例えば、障害福祉サービスの利用方法や申請方法などは対応できますが、個人的な悩みや相談などは対応できないかもしれません。その場合は、他の専門的な相談機関やサービスへの紹介や情報提供を行います。
また、利用者さんが自分の事業所に過度に依存したり、不満を持ったりすることを防ぐためにも、電話相談や手続きの時間や回数を決めしたり、必要な情報だけを伝えたりすることも大切です。
支援計画や支援目標がないと枠組みのない『何でもできる』という関係になり、利用者さんの期待が高まりすぎることがあります。それに私たちが応えられない時に、苦情や不満につながりやすいです。
支援計画や支援目標がない場合は、所属機関の役割に沿った関わり方をしましょう。
『支援目標と関係ないことは支援しない』くらい割り切って関わる
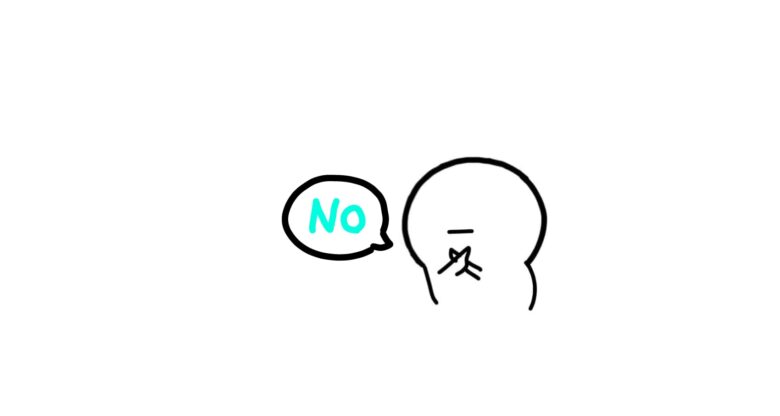
支援目標と関係ないことについても関わろうとすると、私たちの役割や範囲を超えてしまう可能性があります。
それは利用者さんにとっても良くないことです。利用者さんを依存させたり、期待外れにさせたりすることになりかねません。
また、私たち自身も負担や苦労が増えてしまうことにもなりかねません。バーンアウトにつながりやすいのも、こうした対応が重なる時です。
例えば、利用者さんが自分のプライベートな話をしてきたり、恋愛相談をしてきたりすることがあるかもしれません。
このような場合は、支援目標と関係ないことなので、深入りしないするのも1つの方法です。
例えば、相手の話を聞いて共感はするけど、質問やアドバイスはしないことですね。それ以上、話が広がるのを防ぎます。また、必要であれば他の相談機関やサービスへの紹介や情報提供をします。
それと、私たちのプライベートな話を過度にしないようにしましょう。これは、利用者さんとの距離感を適切に保つためにも必要です。
支援目標と関係していて、私たちのプライベートな話が役立ちそうなら、できる範囲でプライベートの話をもちだすのが良いでしょう。
ドライに聞こえるかもしれませんが、『支援目標と関係ないことは支援しない』くらい割り切って関わることが大切です。それくらい、支援目標を一緒につくることや支援目標を意識して関わることが大切ということです。
まとめ
利用者さんとどう関わったらいいかという悩みに答えるために、この記事では、以下のようなポイントを説明しました。
- 利用者さんとの関わり方のヒントは、支援計画や支援目標、所属機関の役割にある
- 支援計画や支援目標がある場合は、それらを実現するための関わり方をする
- 支援計画や支援目標がない場合は、所属機関の役割に沿った関わり方をする
- 支援目標と関係ないことは支援しないくらい割り切って関わりをする
これらのポイントを意識して、利用者さんとの関わり方を考えてみてくださいね。質問などありましたら、ぜひコメントください!それではまた!
関連記事
利用者さんとの関わり方を考えるなら、自己覚知が必須です。必要な理由ややり方はこちらの記事で説明しています。



コメント