
あだ名で呼んじゃダメ?

はっきり言って、あかんですね。
- 「呼び方」でカンタンに関係操作できる
- 大人の利用者・患者の呼び方【5パターン】
- 自立のためにも「呼び方」は重要

私は社会福祉士・精神保健福祉士として働いています。現場経験は約10年です。
呼び方はどれが良いでしょうか?
- 名字+さん
- 下の名前+さん
- ニックネーム・あだ名
- 〇〇くん、〇〇ちゃん
- 呼び捨て
結論から言うと「名字+さん」です。
例えば明石家さんまさんなら、「明石家さん」です。
「それは知ってるよ!」と思うかもしれませんが、なぜ「名字+さん」が良いのか説明できますか?
あるいは「あだ名でもいいんじゃない?」という意見もあるかもしれません。
この記事では色んな呼び方について私の考えを書きながら、「名字+さん」が良い理由を説明していきます。
呼び方ひとつにこだわってこそ、福祉の仕事のプロです。それでは始めましょう!
【福祉の仕事】利用者・患者の呼び方、どうしてますか?【5パターン】
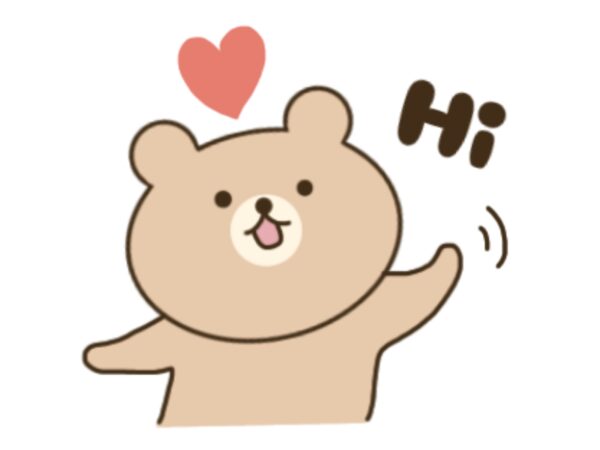
利用者や患者さんの名前は、どう呼んでいますか?あるいは、どう呼ぶのがいいと思いますか?
社会福祉士や精神保健福祉士、福祉の仕事をする人も、いち個人です。
友だちや恋人、夫婦との関係で、呼び方は色々ありますよね。
〇〇さん、〇〇ちゃん、〇〇くん、ニックネームやあだ名もありますね。
名前の呼び方・呼ばれ方は、その人との仲を表しています。
プライベートでは、お互いが気持ちよく呼べる呼び方なら自由です。
では、福祉の仕事ではどう呼ぶのが良いでしょうか?
「呼び方」で関係はコントロールしやすい

人は呼ばれ方に合わせて行動しやすいです。
人は環境に合わせて変わります。呼び方もその一つです。
たとえば、「〇〇さん」と呼ばれたら「〇〇さん」と呼ばれるような行動をしようとします。
「〇〇くん」「〇〇ちゃん」と言われる場合も同じです。そういう距離感・関係になります。
「〇〇さん」よりは近くなりますし、仕事やビジネスよりも友達っぽくなります。
「〇〇先生」と呼ばれれば先生らしくなっていきます。
先生らしい行動をしたり、「自分は偉いんだ!」と思ったりすることもあります。これは良くないことですが…。
「呼ばれ方なんて気にしない人もいるよ!」という場合もあるでしょう。例外はあります。
でも、多くの人は、呼ばれ方に合わせて行動しやすいです。
だから、こういう原理を使って、関係をコントロールできます。相手とどんな関係になりたいかに合った呼び方をすれば良いのです。
もしかしたら「コントロール」とか「操作」と言うと、上から目線で悪く感じるかもしれません。
でも、利用者との関係は、私たち専門職が作る必要があります。
利用者に任せてしまうと「振り回されてしまう」ことになりやすいです。
大人の利用者・患者の呼び方【5パターン】
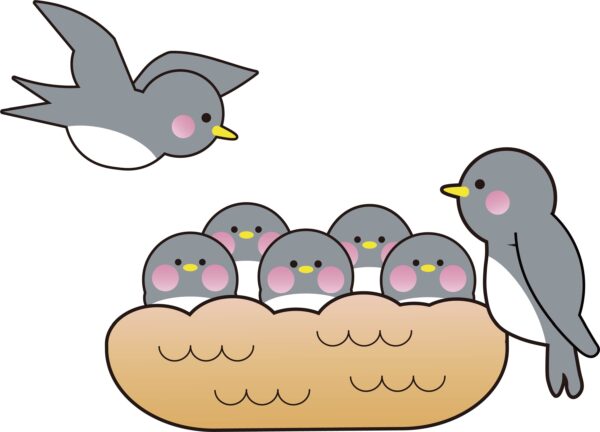
名字+さん
どこで働くかによって、人の呼び方は違うかもしれません。でも、一番良いのは
「名字 + さん」
これなら、相手と同じ目線で話せますし、相手の尊厳を大切にできるし、自立を邪魔しません。
「明石家さんま」なら「明石家さん」です。
日本では、大人同士はそういうふうに呼ぶのが普通ですよね。
福祉の仕事でも、「名字+さん」が一番良いと思います。私もそうしています。
名前+さん
「名前+さん」で呼ぶと仲良くなれるように見えるかもしれません。「名字+さん」よりも友だちっぽくて、近くに感じるかもしれません。
「明石家さんま」が「さんまさん」と呼ばれるとします。「明石家さん」よりも近くに感じますよね?
でも、「名字+さん」で呼ぶのが基本です。
同じ名字の人がたくさんいるときは、「名前+さん」で呼ぶこともありますが。
ニックネーム & あだ名


ボクは先輩だから『ネコさん』ってよんでっ
ニックネームは「名前+さん」よりも、もっと仲良いように感じますね。
でも人によっては、ニックネームで呼ばれるのが嫌かもしれません。「失礼だ」とか「ずうずうしい」とか思うかもしれません。
例えば、入所施設で働く職員が、Aさんのことはニックネームで呼ぶけど、Bさんのことは名字で呼んでいるとします。
すると、「あの職員さんはAさんがお気に入りなんだ」と思われやすくなります。
これは、みんなと同じように扱っていないのでダメです。
それに、人間関係にも悪いことが起きます。
名字で呼ばれているBさんが、「あの職員さんはAさんのことを『Aちゃん』って呼ぶけど、私のことは名字で呼ぶ・・・。私のことは嫌いなんだろうか?」と不安になってしまうとか。
呼び方は、職場内で同じにした方が良いです。
〇〇くん、〇〇ちゃん
大人が「〇〇くん」などと呼ばれると、「子ども扱いされた」と感じるでしょう。
ただしお互いがどう呼んでいるかも大事です。
例えば、利用者さんは職員を「名字+さん」で呼んでいるのに、
職員は利用者さんを「〇〇くん」「〇〇ちゃん」と呼んでいるなら、上下関係ができてしまいます。
職員が上で、利用者さんが下みたいな感じ。これはダメですね。
呼び捨て
呼び捨ては、どこでもダメだと思います。
子ども同士は、呼び捨てでも大丈夫かもしれません。
でも、大人同士で呼び捨てするのは、すごく仲が良い人や、上下関係がある人や、怒っている人(感情的な時)くらいではないでしょうか?
呼び捨てで利用者・患者さんのことを呼んでいる職場があったら、不平等な関係があるのでしょうから、虐待などがないか心配です・・・。
自立のためにも「呼び方」は大切
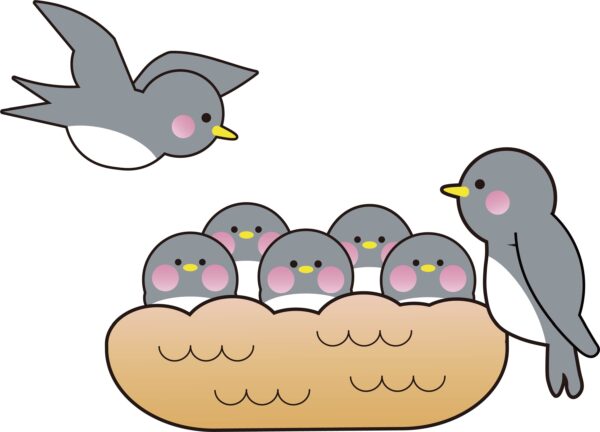
「自分でできることは自分でやってもらう」くらいの距離を保つのが良いです。
自分でできるようになるためですね。
この距離があると、相手が自分でできるようになりますし、相手のことに振り回されなくなります。友だちや親子とは違って、少し離れた感じですね。
ダメなのは、相手が自分でできることも職員がやってしまうことです。
こうすると、相手が職員に頼りすぎたり、職員がやってあげられないときに文句を言われたりすることが多くなります。
そこで、距離を保つのに簡単にできることが「呼び方を変えること」です。
だから「名字+さん」が一番良いのです。

「名字+さん」じゃないとダメ?ニックネームで呼んだ方が嬉しそうだし、話しやすそうだよ?
確かに、ニックネームなどで呼べば、嬉しがる人はいます。
周りからは仲が良いように見えて、上手に支援できている風に見えるかもしれません。
でも、
- 嬉しく感じてもらう方法は、呼び方以外にないか。
- 話しやすくする方法は、呼び方以外にないか。
- その先にどんな目標・ゴールがあるか。
こういったことは考えておいた方が良いです。
私自身の経験から言うと、ニックネームや○○ちゃん等と呼んでいると「その時が楽しければOK」という支援になりがちです。
仲が良すぎたり、相手が働く人に頼りすぎたり。職員自身の気持ちもコントロールしにくくなる危険もあります。だから、あまりよくないと思います。
社会福祉士も精神保健福祉士も、先のことを考えた支援をします。
究極的には「わたし達が支援しなくても生活できる」というのがゴールです。
そのためには、「自分でできることは自分でしてもらう」ということが必要です。
「名字+さん」だと、お互いに距離を保ちやすいです。甘えすぎたり、気持ちが乱されたりすることが少なくなります。「自分でできるようになろう」という関係にしやすいです。
特に、毎日顔を合わせる場所(作業所・デイケア・病棟など)では、どうしても距離が近くなりすぎます。
会う回数が多いと仲良くなりやすいのは、心理学でわかっています。「名字+さん」と呼んでも、距離が近くなりすぎることがあります。
だからこそ、ニックネームやあだ名、「名前+さん」で呼ぶことはハイリスクです。
【福祉の仕事】利用者・患者の呼び方 まとめ
大人の利用者・患者の方の呼び方は「名字+さん」が一番よいです。理由は
「名字+さん」が一番よい理由
- 尊厳や経緯を忘れない
- 節度ある関係にしやすい
- 自立を促せる関係にしやすい
という感じです。
他にも考え方はあるかもしれませんが、私が思うのはこんな感じです。参考にしてくださいね。

呼び方ひとつでも、しっかり意味があるんやな!

わたしたちは『関係性』に敏感になったほうが良い仕事です。気をつけてやっていきましょうね!
関連記事コーナー
利用者・患者さんとの関係をうまくつくるには、自分の気持ちや考え方をよく知ることが大切です。詳しくは次の記事でわかります。



コメント