
自立支援協議会って何?どんなことやってるの?市町村と県の違いは?
こういった疑問のある方へ。

私は某自治体で働く社会福祉士・精神保健福祉士です。現場経験はおよそ13年です。
自立支援協議会って何なのか? どんなことをしているのか? 市町村と都道府県では違うのか?
このような疑問を持っている方に向けて、わかりやすく説明しますね!
【簡単】市町村・都道府県の自立支援協議会とは?【社会福祉士解説】

対象は?
自立支援協議会の対象は、障害者の方等です。
根拠法は?
昔は『障害者自立支援法』という法律がありました。この法律に基づいて、自立支援協議会という名前がついたのです。
今は『障害者総合支援法』という法律に変わりましたが、自立支援協議会は続けられています。
≫参考:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)
『障害者総合支援法』には、自立支援協議会を作るように頑張ってくださいと書いてあります。
国は、「都道府県さん、市町村さん、自立支援協議会を作るように頑張ってくださいね!」と言っているのです。
でも、必ず作らなければいけないということではありません。
「作ろうとしたけど、無理でした」と言えば、「仕方ないね」と許してもらえるのです。
これを、努力義務と言うんですね。
何のためにあるの?目的は?
自立支援協議会の目的は、次の2つです。
自立支援協議会の目的
- 障害のある方の困りごとを聞いて、地域で共通の問題を見つけること
- 地域で障害のある方に必要な支援体制を作ること
地域によって、障害のある方に必要な支援は違います。
例えば、島や田舎では、福祉サービスやお店などが少なくて、困っている人が多いかもしれません。
移動するためのサービス(『移動支援』など)は市町村が決められることですが、厳しく決められてしまって、
サービスを使えなかったり、施設を利用できなかったりする人もいます。
こういうことは、1つの事業所だけではなく、その地域の事業所や利用者さんなども同じように困っています。その地域ごとに問題が似ているんですね。
だから、1つの事業所だけで声をあげるのではなく、地域ごとに集まって、問題を話し合って、「その地域に合った体制を作っていこう!」というのが自立支援協議会の目的です。
構成メンバーは?
決まった人はいません。地域によって参加する人は違います。
例として、平成24年の厚生労働省通知「自立支援協議会の設置運営について」では以下のような人が参加しています。
- 相談支援事業者
- 障害福祉サービス事業者
- 保健所
- 保健・医療関係者
- 教育・雇用関係機関
- 企業
- 不動産関係事業者
- 障害者関係団体
- 当事者
- 学識経験者
- 民生委員
- 地域住民 など
とてもたくさんの人が参加していますね。
自立支援協議会は、福祉だけではなく、住まいや仕事や教育など、障害者の方の生活に関わることを話し合う会です。
例えば、住まいを探そうにも、さまざまな偏見・差別ゆえ入居を断られる場合があります。
そうした場合、不動産関係の方が入っていると解決の糸口が見えたりしますね。
だから、福祉関係者だけではなく、他の分野の人も参加しているのです。
どんな機能があるの?(都道府県と市町村の違い)
市町村の自立支援協議会は、市町村ごとで話し合う会です。
都道府県の自立支援協議会は、都道府県全体で話し合う会です。市町村よりも、広域な課題に対応しますね。市町村にアドバイスすることもあります。
違いは次のとおりです。
| 市町村自立支援協議会の機能 | 都道府県自立支援協議会の機能 |
| 地域の関係機関等によるネットワーク構築等に向けた協議と課題の情報共有 | 都道府県全域における関係機関等によるネットワーク構築等に向けた協議と課題の情報共有 |
| 個別事例への支援のあり方に関する協議、調整 | – |
| 地域の障害者等の支援体制に係る課題整理と社会資源の開発、改善に向けた協議 | 都道府県全域における障害者等の支援体制に係る課題整理と社会資源の開発、改善に向けた協議 |
| 中立・公平性を確保する観点から基幹相談支援センター、委託相談支援事業者、指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の運営評価を実施 | 都道府県内の市町村自立支援協議会単位ごとの相談支援体制の状況を把握、評価し、整備方策を助言 |
| 基幹相談支援センター等機能強化事業及び都道府県相談支援体制整備事業の活用や地域の相談支援従事者の質の向上を図るための研修の実施等、相談支援の体制整備に関する協議 | 基幹相談支援センター等機能強化事業及び都道府県相談支援体制整備事業等による市町村の相談支援体制支援に関する協議 |
| – | 相談支援従事者の人材確保・養成(研修のあり方を含む)を協議 |
| – | 専門的分野のおける支援方策について情報や知見を共有、普及 |
| 権利擁護等の専門部会等の設置、運営 等 | その他(権利擁護の普及に関すること 等) |
最後に
自立支援協議会についてもっと詳しく知りたい方は、下記のリンクも役立つと思います。
- 自立支援協議会のあり方を探る(2010) 発行:財団法人 日本障害者リハビリテーション協会
- ~なまらわかりやすい~協議会(自立支援協議会) 北海道
- 自立支援協議会について 神奈川県立保健福祉大学 行實志都子氏
自立支援協議会は各地域ごとに違うので、1つ1つが特色があるんですね。
例えばですが、下記リンク先からは、東京都の自立支援協議会が行っている活動について紹介されています。
子ども支援部会、進路部会など、いろんな部会が活動していますね。
部会の数や名称は各自立支援協議会ごとに違います。この違いこそが、その地域の個性となっているわけです。
自立支援協議会は、障害のある方にとっても、関係する人たちにとっても、ひいては誰もが暮らしやすい社会にするために大切な会です。
ぜひ、あなたの地域でどんなことをしているか調べてみてくださいね。
以上、【簡単】市町村・都道府県の自立支援協議会とは?【社会福祉士解説】という話題でした!


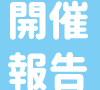
コメント