
精神保健福祉士をめざすなら読んでおいた方が良い本って何?おすすめは?
精神保健福祉士の仕事に興味がある方におすすめの本を紹介します。
精神保健福祉士とは、精神障がいのある方やメンタルヘルスの課題を抱える方に対して、相談や支援を行う国家資格の専門職です。
一言でいうと、「精神障がいのある方の生活のしづらさを支援する仕事」なのですが、具体的には、どんなことをするのでしょうか?

ピンとこないんだよねぇ・・・
解決方法の1つが、実際に現場で働く精神保健福祉士の物語を読むこと。
それは『かかわりの途上で こころの伴走者、PSWが綴る19のショートストーリー』という文庫本です。
私が精神保健福祉士をめざすか迷っていた学生時代に読んだ本でもあります。
2009年出版の本なので、「今さら読んでも意味ないんじゃない?」「実際と違うんじゃない?」と思われるかもしれませんが、色あせていません。
この記事では、この本の魅力をすこしお話しますね。

私は某自治体で働く精神保健福祉士・社会福祉士です。現場経験はおよそ14年です。
【現役おすすめ】精神保健福祉士(PSW・MHSW)の仕事が物語でわかる本
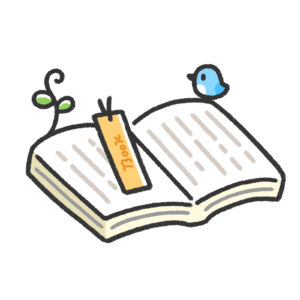
『かかわりの途上で こころの伴走者、PSWが綴る19のショートストーリー』の概要
『かかわりの途上で こころの伴走者、PSWが綴る19のショートストーリー』は、精神保健福祉士(PSW)の仕事を19のショートストーリーで紹介しています。
作業所やデイケア、病院や地域など、さまざまな現場で働く精神保健福祉士が、利用者さんや患者さんとどんな関わりを築いているのか、どんな悩みや喜びを感じているのか、リアルに描かれています。
著者は、精神保健福祉士の資格制度ができた1997年以前から実践してきたベテランの3人です。
現在は大学教授や理事として活躍するかたわら、本を多数出版していますね。
『かかわりの途上で こころの伴走者、PSWが綴る19のショートストーリー』はkindleには対応していないので、文庫本で読むしかありません。
幸い、270ページほどの文庫本なので持ち歩きやすいです。
2009年に発行された本ですが、精神保健福祉士(PSW・MHSW)の仕事でめざすものや、考え方はそうそう変わるものではないので、今でも通用します。
古典といわれる本が読み継がれるように、良書に流行りすたりは無いです。
19のショートストーリーは、1話が10~20ページ程度で完結します。
忙しい日々でも1日1ストーリーという読み方でも十分楽しめます。
物語なので読みやすく、本に慣れていない方でも大丈夫でしょう。
『かかわりの途上で こころの伴走者、PSWが綴る19のショートストーリー』の魅力
著書から一部引用させていただきます。
何度目かの訪問で、竹山さんの許可を得て開けた洋服箪笥には、ロールケーキがずらりと並んでいた。ここで「なんでタンスにパンを入れてるの!?」と驚いたり、「腐っちゃうから冷蔵庫にしまおう」などと言って、やたら手を出したりしてはいけない。
引用元:相川章子 田村綾子 廣江仁(2009)『かかわりの途上で こころの伴走者、PSWが綴る19のショートストーリー』へるす出版 P33
このくだり、「とても精神保健福祉士らしいなぁ」と感じました。
人のテリトリーに土足では決して上がらない。
こういう精神保健福祉士の細かな思考プロセスや所作、一挙一動を知れるのは本書ならではです。
私の印象では、子ども分野とかの現場だと「何してるのー!腐るから冷蔵庫に入れないと」と言って手を入れる人が多いです。
そうした方が同じ要領でメンタル面に不調を抱えた思春期児童に関わって、反感や反発をくらってしまうことがよくあります。
『かかわりの途上で こころの伴走者、PSWが綴る19のショートストーリー』の口コミ
『かかわりの途上で』(相川章子ほか/へるす出版)読了。
教科書の事例とは違い、うまくいったエピソードも悔いの残るものもずっしりと重い。いま読めてよかったと思う。— まえかく (@imuzeam) May 10, 2020
「かかわりの途上で」読了。PSWの仕事って?をエピソードで語っている。表面に見えていることだけではなく、抱えている問題は二面的であり多面的。その多面性にいかに気付けるか、がPSWとしての資質な気がする。その人の望む暮らしを実現すること、それこそがPSWの仕事なのだね。
— ひめ (@mikadukihime) May 18, 2012
備忘録
3年ゼミ前期の課題図書
前半 自分の薬をつくる(坂口恭平)
後半 援助関係論入門(稲沢公一)
かかわりの途上で
(相川章子、田 村綾子、広江仁) pic.twitter.com/eAEtusI8pk— あがのこ (@aganoko08301975) June 25, 2021
最後に
『かかわりの途上で こころの伴走者、PSWが綴る19のショートストーリー』を読むと、精神保健福祉士がどんな仕事をしているかが具体例としてわかります。
また、精神保健福祉士として必要な考え方や姿勢も学べます。
現場で働く精神保健福祉士が読んでみても「そうそう。PSWってそうだよな。」と共感する面白さがあるでしょう。
精神保健福祉士に興味がある方、めざしている方、迷っている方は、いちど手に取ってみてくださいね。
「PSW」は「MHSW」へと名称変更されました
『かかわりの途上で こころの伴走者、PSWが綴る19のショートストーリー』が出版された当時は精神保健福祉士の略称は「PSW」でした。
しかし現在は、「MHSW」が正式な略称になっています。詳しくはこちらの記事で紹介しています。
精神科入院患者の60%を占める「統合失調症」は、精神保健福祉士のマスト知識
精神保健福祉士が支援する方の中で多いのは、『統合失調症』という病気の方です。
精神疾患全体としては、統合失調症の方はそう多いわけではありません。
しかし、入院を要するほどの方の中では、統合失調症の方が6割ほどにものぼるのです。
しかし,統合失調症においては,有病率 1%と一般的な疾患であるにも関わらず,長期入院を特徴とし,平成 26(2014)年現在で約 16. 6 万 人の入院患者が推定され,その割合は,精神科入院患者の約62%と半数以上を占めている
引用元:長期入院統合失調症患者の退院意向と個人因子 渡部誠一 杉原素子(2019)
それだけ、統合失調症は生活に大きな支障をきたしやすい疾患なのです。
統合失調症の特徴は、現実と区別がつかなくなるような幻聴や妄想などの症状があることです。この病気のありようがピンとこない方におすすめの映画が、『ビューティフル・マインド』。
『ビューティフル・マインド』は、実在した天才数学者ジョン・ナッシュの物語です。
彼は統合失調症を発症しましたが、その苦しみと闘いながらノーベル賞を受賞しました。彼の人生を感動的に描いた映画ですね。
『ビューティフル・マインド』を見ると、統合失調症の方がどんなことを感じているかや、周りの人がどう対応しているかがわかります。
精神保健福祉士になりたい方や、統合失調症に関心がある方はいちど観てみてください。娯楽感覚で学べるので一石二鳥です。
詳しくはこちらの記事でも紹介しています。

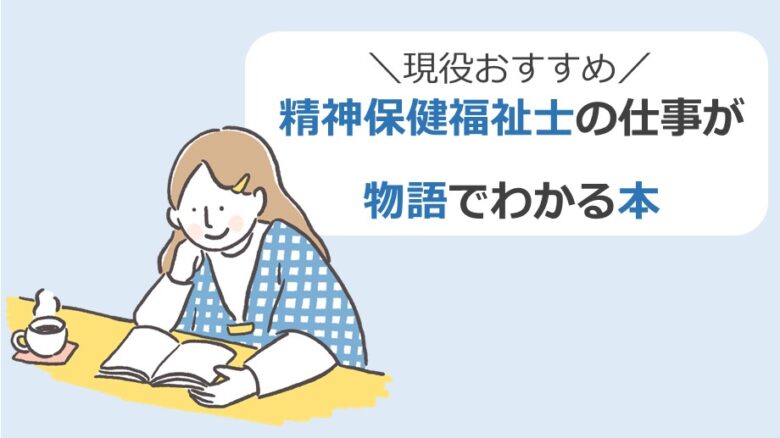



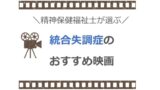
コメント