
地域活動支援センターとデイケアって何が違うの?
こうしたギモンのある方へ。
地域活動支援センターと精神科デイケアは、次の5つが違います。
5つの違い
- 利用人数
- 誰が利用を決めるか
- 利用料
- 職員配置
- 利用時間
ただし地域活動支援センターと精神科デイケアには共通点も多いです。
では、シンプルに解説していきます!

この記事を書いた私は、某自治体で働く精神保健福祉士・社会福祉士です。現場経験はおよそ13年です。
地域活動支援センターと精神科デイケアの違い5つ|精神保健福祉士解説

地域活動支援センターにも精神科デイケアにも個性あり
まず大前提ですが、各地域活動支援センターにも各精神科デイケアにも、それぞれ独自色があります。
いわば、個性があるわけです。同じものはないんですね。
例えば、セブンイレブンのように、
- 全国ほとんど同じ商品
- 同じコンセプト
- 同じ制服
とはいきません。
実際には、

A地域活動支援センターとB地域活動支援センターは全然違うな・・・
というのがよくあることです。
さらに深掘りすると、地域活動支援センターには、Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型という3つの型があります。
しかも同じ型のなかでも、それぞれの地域活動支援センターでの独自カラーがあるのです。
一方で、精神科デイケアについても、利用時間に応じてショート・ケア、デイ・ケア、ナイト・ケア、デイナイト・ケアがあり、小規模と大規模に分かれます。
- ショート・ケア
- デイ・ケア
- ナイト・ケア
- デイナイト・ケア
そして、それぞれの精神科デイケアで独自カラーもあります。
≫参考:厚生労働省 精神科デイ・ケア等の区分と診療報酬について
それゆえ地域活動支援センターと精神科デイケアは、より一層ちがいがわかりにくくなっています。
地域活動支援センターと精神科デイケアの共通点とは?
では、上記のような個性・型などの違いを、ひとまず横に置いておいて・・・。
共通点をリストアップします。
| 地域活動支援センターと精神科デイケアの共通点 | ||
| 通所施設? | YES(入所ではない) | |
| 日中に行く所? | 利用の仕方や各機関によって違う(夜があることも) | |
| 土日祝は? | 各機関によって違う(地域活動支援センターの土日祝開所率は6~7割) | |
| お金は稼げる? | ケースバイケース(作業・内職があったり無かったり) | |
| 集団で交流ある? | ある | |
| レクとかプログラムは? | それぞれが独自設定 | |
| 食事は? | 多分ある(食事代は実費負担が多い) | |
| 食事作りは? | 活動の一環になっているかも(買い物含む) | |
| 職員に相談できる? | できる | |
| 居場所になる? | なる(そういう機能期待がある) | |
こんなに共通点があります。
だから、地域活動支援センターと精神科デイケアって、同じような感じがしちゃうんですよね。
地域活動支援センターと精神科デイケアの違い5つ

では、精神科デイケアと地域活動支援センターの違いは何でしょうか?
大きな点を5つ絞ってお伝えします。
5つの違い
- 利用人数
- 誰が利用を決めるか
- 利用料
- 職員配置
- 利用時間
違い① 利用人数
- 10~20人以上
(類型による)
- 20~70人
(利用時間・規模による)
利用人数については、地域活動支援センターは下限設定があり、精神科デイケアは上限設定があるんですね。
このように見ると精神科デイケアの方が多人数に見えてきますが、実際には見学などをしてみないとわかりません。
なぜなら、数名(20名以下)しか利用していない精神科デイケアがよくある一方で、
多人数でにぎわっている地域活動支援センターもあるからです。
違い② 誰が利用を決めるか?
- 利用者と地域活動支援センターが契約、自治体が認可
- 主治医
結論としては、地域活動支援センターは、利用者と地域活動支援センターが利用契約を結んで始めることになります。
それを自治体(市区町村)が受け付けて、利用許可がおりる、という流れですね。
なんとなく、対等な感じが伝わるかと思います。
地域活動支援センターは、利用目的を双方で話し合いながら整理していくことが多いんです。
一方、精神科デイケアは精神科専門療法の1つであり治療の一環です。したがって、利用するには主治医の指示箋が必要です。
医療では『医学モデル』で患者さんや障害をみることが多いでしょう。『いかに患者さんの課題・問題を解決するか』という視点なんですね。
≫参考:医学モデルと社会モデル
医学モデルでは、病気(課題)の治療(解決)というのが基本原理です。
なので、デイケアの利用目的は医師や職員側が『体調や病状の安定』に設定する傾向があるでしょう。
下記の統計は、精神科デイケアの実態を知るのにとても参考になります。
≫参考:厚生労働省 精神科デイ・ケア等について
違い③ 利用料
- 原則無料(食費等はかかる傾向)
- 原則、保険適用なら3割負担
- 自立支援医療(精神通院医療)の適用で自己負担は1割or負担上限額
利用料は、地域活動支援センターの方が安い場合が多いでしょう。
ただし各自治体によって違いはあるでしょうから、「概ねこのようだ」でご理解くださいね。
≫参考:厚生労働省 自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み
違い④ 職員配置
- 地域生活支援事業等の実施について(通知)で決まっている
- 無資格者がいる場合あり
- 特掲診療料通知で決まっている
- 精神科医が必ずいる
- 原則、職員は何らかの有資格者
地域活動支援センターは類型によって職員配置が決まっています。
≫【比較解説】地域活動支援センターの類型【Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型】の違い
精神科デイケアの職員配置は、こちらの図でイメージしやすいですね。
精神科医は必ず配置。
そのほか、利用者数に応じて下記の職種が配置されることになります。
- Ns(看護師)
- 准看護師
- PSW(精神保健福祉士)
- 公認心理士
- 栄養士
- OT(作業療法士) など
≫参考:特掲診療料通知(令和2年3月5日発)
精神科デイケアで特筆すべきは、精神科医が必ずいるということ。
したがって精神科デイケアは、地域活動支援センターよりも医療的なケアに強いわけです。
対して、地域活動支援センターでは職種の指定はゆるく、雇用形態(常勤)の指定があるくらいです。
専門職員(精神保健福祉士など)の配置が決まっているのは、Ⅰ型(1日平均20名以上が利用)の地域活動支援センターだけです。
≫参考:地域生活支援事業等の実施について 改正通知 令和4年3月30日
結論を繰り返すと、次のようになります。
- 精神科デイケア → 有資格者を配置している
- 地域活動支援センター → 色んな職員(無資格含む)が配置されている
地域活動支援センターの職員配置には、脆弱さという課題があります。
違い⑤ 利用時間
- わりと自由
- 融通がききにくい
どうしてこのような違いがあるのか?理由はいくつか考えられますが、例えば次のことが影響しているでしょう。
- 利用料が決まるしくみ
- 心身の状態を改善することの優先順位
地域活動支援センターの利用時間
地域活動支援センターはわりと自由に出入りしやすい傾向です。
地域活動支援センターの実施主体は、自治体(市区町村など)です。ただし業務については民間法人などへ委託(お任せ)されていることが多いです。
地域活動支援センターは、『利用者が来所すれば利用扱い』です
。短時間利用でも長時間利用でも、地域活動支援センターの事業収入に変わりはないです。
したがって利用者さんが、ちょっとだけ通所して雑談だけして帰るとか、仕事後等に立ち寄るといった利用をしても、事業者としては経営上の影響をほとんど受けません。
ただし、利用の仕方は利用者さんと支援者で相談して決めるので、個別の違いはあります。
例えば、就職に向けた目標で通うなら、決まった時間通りに通うことを目指したりしますね。
精神科デイケアの利用時間
精神科デイケアは、利用時間(始まりと最後)がしっかり決まっていることが多いです。
いいかえると、融通はききにくい傾向です。
背景は診療報酬体系のあり方。精神科デイケアは、長時間利用してもらった方が収益になるしくみです。
≫参考:診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示) 令和2年 厚生労働省告示第57号 第8部 精神科専門療法
地域活動支援センターと違って、利用時間に応じて収入が変わってしまうんですね。
ただし治療的な意味合いもあります。
利用時間がハッキリ決まっていることで、規則的な生活につながり、病状の安定を促す効果があるんですね。
最後に
地域活動支援センターと精神科デイケアには、共通点が多いです。
どちらの利用が向いているかはケースバイケースですし、医療機関や支援者と相談してすすめていくことになるでしょう。
利用目的を整理したうえで、併用している方もいます。
進化の歴史上、人は一人では生きていけないし、本能的に人との関わりを求める生き物です。
孤立はさまざまなリスクにつながります。利用目的をよくよく考えることも大切ですが、通う場所があること自体が救いになると思うんですね。
この情報があなたのお役に立てたなら幸いです。
関連記事
地域活動支援センターと、地域”生活”支援センターの違い。わかりますか?
地域活動支援センターには3つの型があります。ここまで知っていたら、プロな感じですね。
地域活動支援センターと地域”包括”支援センターの違いはわかりますか?たった2文字違うだけで、対象者から全然ちがうんです。



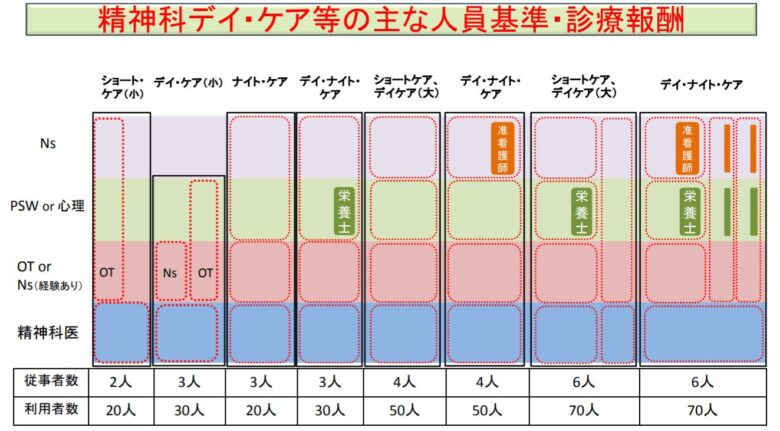
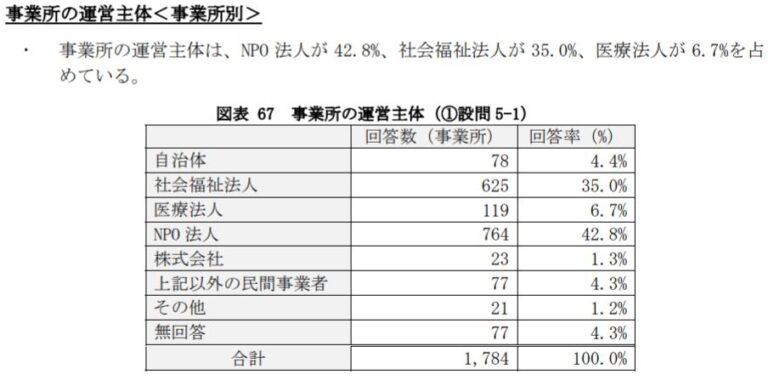
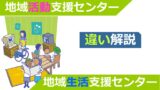

コメント