こんにちは!社会福祉士・精神保健福祉士のぱーぱすです。
相談支援の展開過程は、とても大切なプロセスです。
しかし、実はこの展開過程が「悪い戦略」になっていることが多いんですよね。
「悪い戦略」とは、目標が多すぎたり、専門用語でごまかしたり、目標と戦略を取り違えたりするものです。
これは、「戦略の大家」であるリチャード・P・ルメルトが著書『良い戦略、悪い戦略』 で指摘したものです。
相談支援の専門書ではないので、私たちの仕事に直結はしません。でも、適用できるところはあります。
この記事では、『良い戦略、悪い戦略』をもとに、相談支援の展開過程を「良い戦略」にする方法を考えてみました。
そして、答えのない支援において決断するのに必要な判断力を鍛える1つの方法をお示しします。
「良い戦略」「悪い戦略」とは?「良い戦略」のチェックポイント
「良い戦略」とは、診断・基本方針・行動の3つからなる筋の通った、達成可能で、具体的で、現実的な戦略です。

診断?お医者さんがすること?
「診断・基本方針・行動」といきなり言われても、私たちには聞きなれない言葉ですよね。「診断」と聞いたら、病気のことをイメージしてしまいます。
『良い戦略、悪い戦略』では次のように説明されています。
- 診断 状況を分析し、取り組むべき課題を見極めること
- 基本方針 診断でみきわめた課題に、どのように取り組むのか大まかな方向性を示すもの
- 行動 基本方針を実行するための具体的に行うこと
この3つの筋が通っていることが、「良い戦略」の原則だというんですね。
勘の良い方は、「診断・基本方針・行動」は相談援助の展開過程のアセスメント・プランニング・インターベンションと似ていると気づかれたのではないでしょうか?
- 診断 ⇒ アセスメント
- 基本方針 ⇒ プランニング
- 行動 ⇒ インターベンション
このように考えると、『良い戦略、悪い戦略』の理論は、私たちの相談支援の展開過程に応用できそうです。(それが本記事を書こうと思ったワケです)
「良い戦略」のチェックポイント
「良い戦略」のチェックポイントは、次のように示されています。
良い戦略のチェックポイント
- アセスメント、状況分析は正しいか?
- 取り組むべき課題は合っているか?
- 長期目標・短期目標・具体的な支援課題は、筋が通っているか?
- 具体的か?
- 達成可能か?
- 重大な問題をムシしていないか?
- 目標と方法をとり違えていないか?
- 目標は多すぎないか?
- 非現実的な目標になっていないか?
- 当人の最大の強みを活用できているか?
どうでしょうか?
残念ながら、福祉関係の法人や現場にはこのような「良い戦略」のチェックポイントからズレた「悪い戦略」がよくあると思います…。
例えば、
- 「共生社会をつくる」
- 「活力にあふれた職場をつくる」
- 「心を満たす福祉の実現」
- 「保健医療・福祉の増進」
などは、良い戦略になりえるでしょうか?
もちろん、ビジョンや理念は大切なことですが、これだけでは戦略にならないということです。
『良い戦略、悪い戦略』の知見をもとに捉えると、「悪い戦略」と評されるでしょう。
「悪い戦略」とは、目標が多すぎたり、専門用語でごまかしたり、目標と戦略を取り違えたりするものです。
福祉の現場では、
- 非現実的な目標
- 達成できない目標
- どうなれば達成できたと言えるか不明な目標
- 専門用語が使われていて意味がよくわからない目標 etc…
こうした目標を立ててしまう(立てられてしまう)ことがよくありませんか?
すると私たち自身、「どうせ言ってるだけ。」とやる気を失くしたり、
具体的な行動への移し方がわからず、ストップしてしまったり(結果、目標を達成できなくて自信を失う)
目標を立てたことすら忘れてしまったり・・・
悪循環に陥ってしまいます。
だから、相談支援の展開過程で「良い戦略」を立てられれば、悪循環を断ち切れるかもしれません。
判断力を高める1つの方法 「判断した理由を記録する」
「良い戦略」を立てる視点を磨くことは、支援計画を実行性のあるものにつなげ、より良い支援ができることにつながるはず。
では、「良い戦略」を立てるために必要な力は何か?
『良い戦略、悪い戦略』の著者は、判断力と言います。
そして、判断力を高める1つの方法とされるのが、自分の判断を記録するということです。
判断理由を記録することで、次のことができるようになるんですね。
- 判断の正誤を検証できる
- 他者と判断が違ったときに、学習できる
「判断 → 反省・検証」の繰り返しで、判断力を高めることができるということです。
これは日常生活でもできそうですね。
例えば私が、”余裕をもって出勤したいので「朝6時に起きる」を目標にした場合”で考えてみます。(レベルが低いかもしれませんが・・・)
私は、朝6時に起きるには「22時45分には布団に入ること」を実行することが必要と判断しました。
なぜなら、私は1日7時間は眠らないと、朝6時に目が覚めても二度寝してしまうと思うから。
これが判断理由となりますね。とても単純化したものですが。
判断理由を記録しておくと、やっぱり私が二度寝してしまったときには、判断理由を検証したり、反省して他の方法を選択することができるわけですね。次こそは二度寝しないぞ、と。
実際の支援でも、面接前や家庭訪問前に、いろんな想定をする、その判断理由を書いてから臨むことですね。そして、終わってから記録を見返してみる。
ちょっとした手間ですが、判断の理由を記録に残すことで、判断力は鍛えられていくんですね。
やってみると意外なほどに効果を感じられると思います。
最後に
今回は、著書『良い戦略、悪い戦略』をもとに、相談支援の展開過程を「悪い戦略」にしない方法を考えたり、判断力を高める方法を解説しました。
『良い戦略、悪い戦略』は相談支援についての専門書ではないので、理論をそのまま適用はできません。
でも、こうした名著には、福祉の専門書ばかり読んでいても得られない着想があるし、共通点など意外な発見ができたりします。
福祉関係の専門書を読んでばかりで疲れてしまった方や、タイトルに興味をもてた方はチェックしてみると面白いと思います。

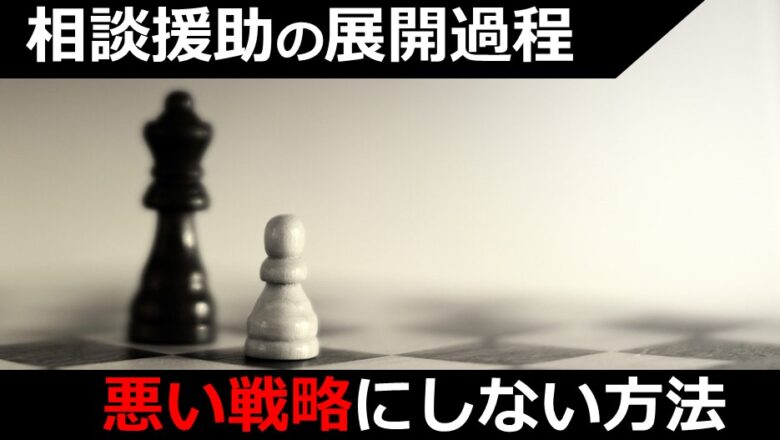

コメント