
職場の人間関係は、支援と関係なくない?
実は、人間関係が良くないと、支援の質も低下してしまうんです・・・。

私は某自治体で働く社会福祉士・精神保健福祉士です。現場経験はおよそ13年です。
あなたの職場では、みんな仲良くやっていますか?
福祉施設で働くと、人間関係が悪くなることもよくあります。こんなことはありませんか?
現場あるある
- 職員同士で悪口や陰口を言う
- 派閥ができる
- いじめが起こる
- あいさつしない
- 会議で責められる
あなたの職場はどうですか?私は色々な経験をしています(今もです!)
人間関係が悪いと、プロだからといっても辛いですよね。
意味がないし、イヤになるし、疲れてしまいます。
仕事を辞める理由としてもトップレベルです。(社会福祉士:2位、精神保健福祉士:1位)
そして、人間関係は支援に大きな影響を与えます。職員の人間関係が悪いと、支援も悪くなってしまいます。
人間関係が悪いとどうして支援に影響するのか?
この理由を知ることは、良い支援をするために必要ですし、人間関係を改善するためのやる気にもなります。
では見ていきましょう!
児童福祉施設|職場の人間関係=支援に影響大!理由3つ経験者が解説
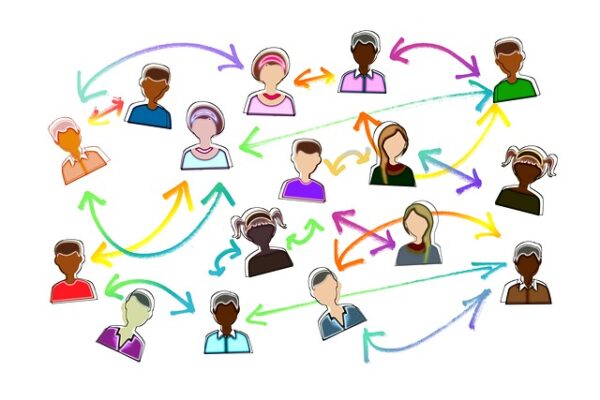
理由1:ストレスが強くて感情を隠せないから
人間関係が悪いと、職場でストレスがたまります。
職員の隠し切れない感情(イライラ・緊張感・怒り等)は、利用者(児)さんに伝わってしまいます。
ストレスがあっても、みんなは気持ちを切り替えられるでしょうか?
実際は難しいですよね。
例えば、職員室で言い合った後でも(そんなの御法度でしょうけど)、利用者(児)さんに優しく支援できるでしょうか?
私は無理です。どんなに頑張っても感情が出てしまいますね・・・。
鈍感な人は気づかないかもしれませんが、注意深くみている人には表情や声のトーン、反応などでバレてしまいますね。
感情は伝染する
悪い人間関係だと、マイナスの感情が伝染します。表情や声色、ちょっとした反応で伝わってしまうのです。
そうすると、利用者(児)さんにもネガティブな感情がうつってしまい、精神状態が悪くなったり、人間関係が壊れたりすることがあります。
結果的に、支援の質を下げてしまうことになるのです。
理由2:報告・連絡・相談が減るから
職場の人間関係が悪いと、「できれば関わりたくない」「できれば話したくない」という気持ちになります。
誰でも嫌な人と関わるのはストレスですよね。
すると、仕事で必要なのに、報告・連絡・相談をしなくなってしまいます。
これがまた、新たなトラブルの原因になってしまいます。
「わざと言わなかったの?」「仲間はずれにしたんだ!」という思い込みや誤解が生まれてしまいます。それが原因でトラブルやミスが起きることもあります
理由3:支援がバラバラになるから
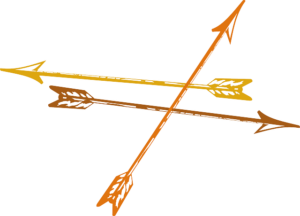
会議での意見交換や協力もできなくなります。
会議で決定しても、従わない人が出てきますね。
派閥があればなおさらです。A派閥の決定にしたがうことは、B派閥の人には許されないこともあるでしょう。表面的にはあわせつつ、裏側でコッソリ別行動・・・なんてこともあるでしょう。
悪い人間関係の職場では、何をしようにもうまくいきません。
支援もバラバラで、足の引っ張りあい。何かミスがおきれば「絶好の攻撃チャンス」として吊るし上げがはじまる。
これで一番困るのは利用者(児)さんです。
職員が職員の顔色ばかり気にして、「私は誰のために仕事しているんだろう?」と感じることもあるでしょう。
まとめ
職場の人間関係が悪いと、どうなるでしょうか?
利用者(児)さんの前では笑顔でがんばっているかもしれませんが、心はツライですよね。
職場の人間関係が悪いと、自分の能力を発揮できなくなります。
会議での意見交換や協力もできなくなります。前向きな話し合いが難しくなるので、足の引っ張り合いになることもあります。
これで一番困るのは利用者(児)さんです。支援がバラバラになってしまうと、利用者(児)さんのニーズに応えられなくなります。
職員の顔色ばかり気にして、「私は誰のために仕事しているんだろう?」と感じることもあるでしょう。
当然、支援力は低下してしまいます。
では、このモンダイをどう解決すれば良いのか?
職場の人間関係の処方箋
- 自分が変えられることに専念する
- あいさつ、声かけ、仕事以外の話もしてみる
- 他人同士の人間関係は放っておく(手を出すとヤケドする)
何より職場の人間関係が悪いと、ストレスで辛くなってしまいます。あなたの体調やメンタルをコントロールすることがいちばん大切です。
関連記事コーナー
職場の人間関係が悪くて大変なのは、児童養護施設や児童指導員のあるある話です。下記の記事では他にも辛いこと、大変なことをまとめています。息抜きにどうぞ!

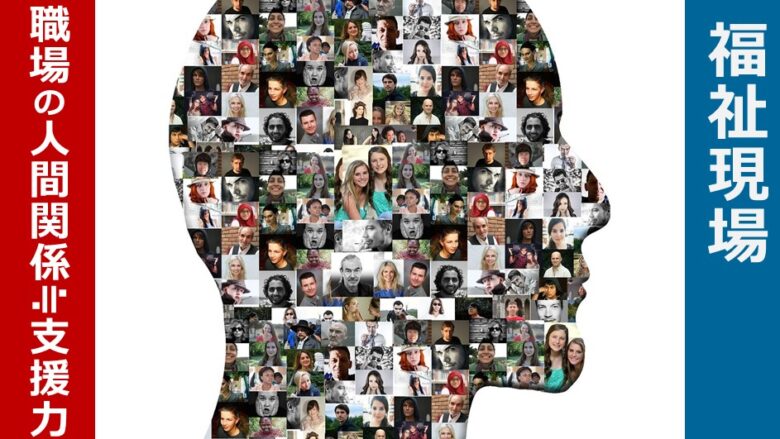





コメント