
社会福祉士や精神保健福祉士はサービス残業が多いの!?
こんなタイトルを見て、びっくりしたかもしれません。本当なのでしょうか?

私は10年以上、社会福祉士・精神保健福祉士として様々な現場で働いてきました。
この記事では、福祉の仕事について、私の体験や考えをシェアしていきたいと思います。
サービス残業とは、働いた時間に対して給料が支払われない残業のことです。
私の経験では、ほとんどの職場でサービス残業がありました。
サービス残業は違法ですが、実際には多くの職場で行われています。特に、福祉の仕事ではサービス残業が当たり前になっているところもあります。
統計データはありませんが、私の知り合いの職場でも、サービス残業があるところが多いです。福祉業界では、サービス残業が当たり前になっているのでしょうか?
この記事は、下記の方に役立つでしょう。
この記事が役立つ方
- 福祉の仕事に興味がある方
- 福祉業界に転職したい方
- 社会福祉士や精神保健福祉士になりたい方
福祉現場の実情を知って、「思っていたのと違う」と後悔しないようにしてくださいね。
それでは始めましょう!
サービス残業が多い?【社会福祉士・精神保健福祉士の現場を解説!】

私はプロフィールに書いてあるように、複数の職場で働いた経験があります。
今回、2つの職場を例にして話をします。
職場1:ある精神科クリニック
サービス残業:月30時間ほど
1つめは『精神科のクリニック』。
わたしは精神保健福祉士として相談員をしていました。サービス残業が月30時間ほどでしたね。
記録やレクリエーションの計画などをするために、毎日2時間くらいサービス残業していました。先輩や同僚も同じようにしていました。
今考えるととてもブラックな職場なんですが、当時の私は「仕事はそういうものだ」と思っていました・・・。
残業しないで帰る人は、「すみません」とペコペコして申し訳なさそうに帰っていくのが風習でしたね。
申請できた残業:月20時間くらいまで
こんな感じでサービス残業が横行していましたが、月20時間までの残業は認められました。
しかし、月20時間以上の残業申請はダメだと言われていました。先輩が上司に確認していたのですが、
先輩)月何時間まで残業申請していいんですか?
上司)・・・20時間までにしてください。(それ以上はサービス残業でやってください)
こんな感じでした。
でも、20時間では仕事が終わりませんでした。管理職の人たちは、みんながサービス残業していることを知っていましたが、何も言いませんでした。
トップである院長がダメと言っていたのですね。
職場2:ある地域の福祉施設
サービス残業:月30時間ほど
2つめは、地域の福祉施設。例えば、就労支援や相談支援などですね。
ここでも、先輩や同僚はよく残業していました。私も「仕事はそういうものだ」と思って、サービス残業していました。
申請できた残業:月0時間
残業の申請用紙は、職場にありませんでした。今考えると、とてもひどいですね。
ある時、同僚が残業申請について聞いたら、法人の代表はこう言ったそうです。
同僚)残業申請したいんですけど、申請用紙はあるんですか?
代表)うちの職場では残業しないようにしましょうと約束してるでしょ?早く帰ってね。(残業申請は受け付けません。サービス残業でやってください)
こんな感じでした。
代表は、みんながサービス残業していることを知っていましたが・・・。
もしかしたらあなたは、「このブログの書き手は、ひどいところばかりに働いたんだな」と思われたかもしれません。
でも、福祉の仕事をするなら、他人ごとではないと思います。福祉業界では、こんなことが普通かもしれないと思います。
なぜなら、私の知り合い(社会福祉士や精神保健福祉士)と話してみると、みんな似たような残業事情だったからです。
社会福祉士や精神保健福祉士は素晴らしい仕事です。しかし職場によっては、残業が多くて大変なことがあるかもしれません。
なぜ社会福祉士や精神保健福祉士はサービス残業が多いのか?
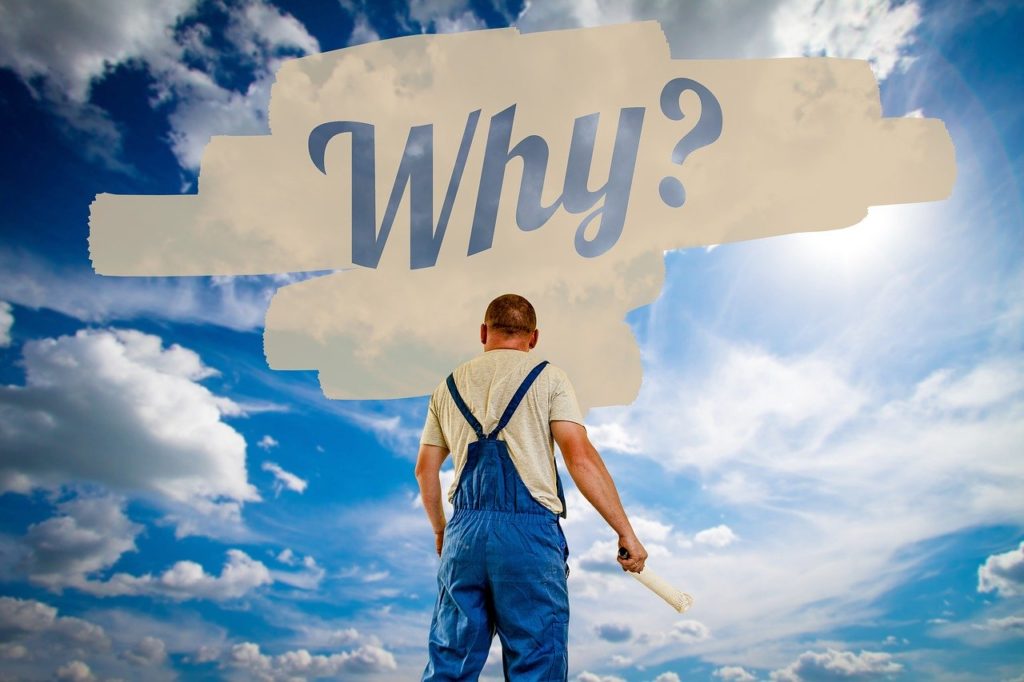
ここからは社会福祉士や精神保健福祉士、福祉現場は残業が多いという前提でのはなしです。
どうして社会福祉士や精神保健福祉士はサービス残業が多くなりがちなのでしょう?
理由1:仕事が終わらないから(効率よりも質を重視しやすい)
まず一つ目の理由は、仕事が終わらないからです。
社会福祉士や精神保健福祉士の仕事は、人と人との関わりが大切です。クライアントの相談に乗ったり、生活を支援をしたりすることが主な仕事です。
しかし、状況やニーズは千差万別です。一人ひとりに合わせて対応することが求められます。
そのため、時間効率よりも質を重視する傾向があります。
例えば、クライアントの生活状況を把握するためには、電話するよりも訪問してみる方が詳しく分かるでしょう。
しかし、訪問するには日程調整や移動時間などが必要です。電話よりも時間がかかります。
また、クライアントから信頼されるためには、じっくり話を聞いたり、気遣いをしたりすることも大切です。しかし、それも時間がかかります。
このようにして、福祉の仕事では時間内に終わらない業務が多くなってしまいます。
それでも良い支援を提供したいと思う人は多いです。その結果、サービス残業をしてしまうことになるのです。
理由2:心の穴を埋めるため
二つ目の理由は、自分自身の心理的な課題からです。
個人的な意見ですが、社会福祉士や精神保健福祉士のような福祉的な仕事をする人は、自分自身に何か足りないと感じている人が多いと思います。
例えば、心に寂しさや虚しさや自信のなさを抱えている人です。
そうした方は、他人に貢献したり支援したりすることで自分の心の穴を埋めようとしていると思います。(私もそういうところがあります・・・)
そのため、サービス残業をしてでもクライアントのためになると思えば、自分の時間やお金を犠牲にしてしまうことがあります。
また、サービス残業をしないと自分の仕事ができないとか、自分は価値がないとか、自己否定的になってしまうこともあります。
サービス残業をすることで、自分の存在意義や価値観を見出そうとするのです。しかし、それは本当に自分の幸せにつながっているかが問題です。いつまでもラクになれません。
こうした悪いループから抜け出すには、自己覚知が役立ちます。具体的なやり方はこちらの記事で紹介しています。
理由3:給料を求めることがタブーになっている
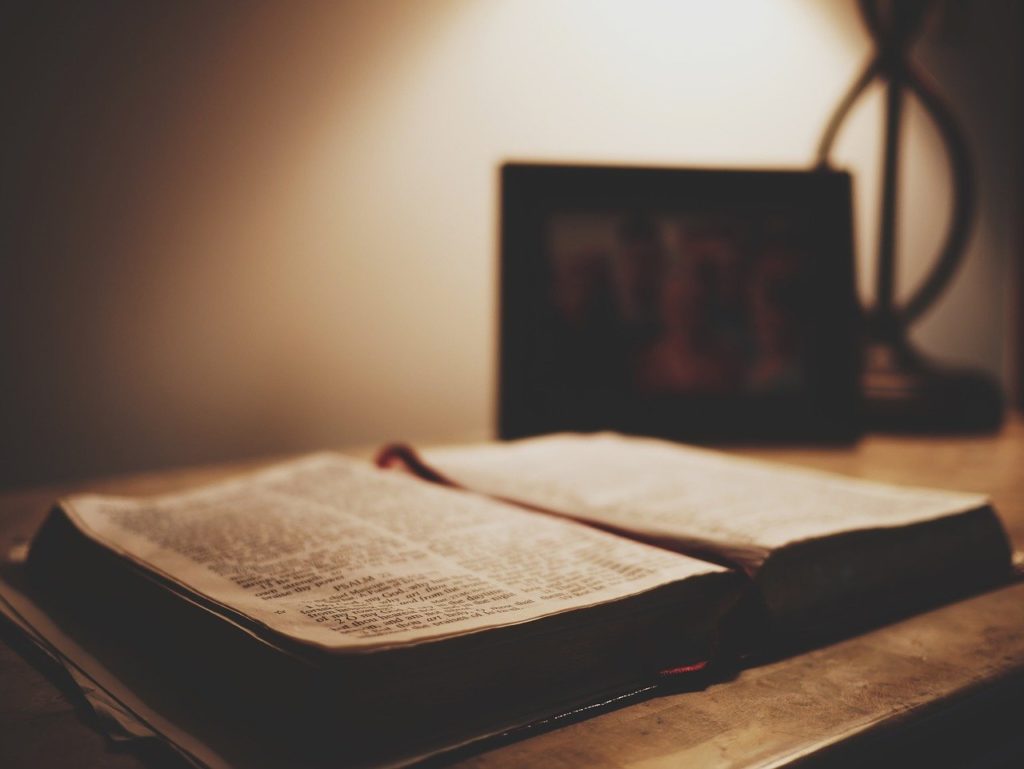
三つ目の理由は、福祉の仕事が聖職だという考え方からです。そうした業界常識みたいのが残っていて、給料を求めることがタブーになりやすい。
聖職とは、神聖な仕事や職業という意味です。昔から、福祉の仕事は聖職と呼ばれてきました。
福祉の仕事は、人間を尊重し、困っている人を支援するという立場を取ります。それは、宗教的な信念に近いものがあるかもしれません。
社会福祉は「すべてかけがえのない存在」として人間を尊重するという立場を採る。おそらくそれに一番近い立場の援助専門職は聖職者であろう。
実際に、福祉の仕事に関わる人の中には、宗教的な背景を持つ人もいます。
しかし、福祉の仕事が聖職だという考え方には、問題点もあります。それは、
- 「働いたらお金をもらう」という当たり前のことができなくなる
- 「クライアントのためになることをする」という名目で自己犠牲的になりすぎる
- 「お金や給料など汚い話はしない」というタブーができてしまう
ということです。
福祉の仕事も、生活のための労働という一面があります。働いたらお金をもらうのは当然です。
クライアントのためになることをするのは大切ですが、自分自身の健康や幸せも大切ですね。
お金や給料などは、汚い話ではありません。福祉業界でも公平で適正な待遇が必要だと思います。
残業は職場の問題
残業は、仕事が多すぎたり、人手が足りなかったりするときに起こります。でも、それは職場の問題です。個人が残業でカバーするのはおすすめしません。
なぜなら、次に来る人にも残業を強いることになるからです。
例えば・・・、
Aさんの事業所はとても業務が多くて、残業しないと仕事が終わりません。しかしAさんは頑張って、サービス残業をしてなんとかやり切っています。
そのAさんの後任に、Bさんがつきました。
業務量が多いので、Bさんもサービス残業をしないと仕事が終わりません。しかしBさんは家に子どもがいるので、早く帰らないといけません。
Bさんが上司に相談すると「Aさんは残業しなくてもできてたよ」と言われました。Bさんの能力不足という評価になってしまったのです。
・・・こんな感じのことが起きてしまいます。AさんもBさんも辛いですね。
そこで、私の考えは次のとおりです。
残業の問題は、組織で解決すべき
- できるだけ仕事時間内に仕事を終わらせて帰ろう
- 残業がひどすぎるときは、労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談しよう
- 個人だけでなく、職場のみんなで問題を解決できるようにしよう(難しいかもしれませんが・・・)
それゆえ、わたしは福祉の職場には労働組合が必要だと思っています。
最後に
社会福祉士や精神保健福祉士は素晴らしい仕事ですが、サービス残業が多くて大変なこと職場もあるでしょう。
もちろん、サービス残業が少なくて働きやすい職場もあると思います。
「定時ですぐに帰りたい!」「プライベートを大切にしたい!」という方は、職場をしっかり選んでいきましょうね。
下記の記事では、社会福祉士や精神保健福祉士が仕事を見つけた方法を、公式調査に基づいてランキング形式で紹介しています。
友人・知人からの紹介が最も多く、ハローワークやインターネットなども利用されています。あなたに合った方法はどれでしょうか?



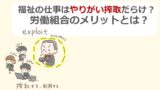


コメント