
双極性感情障害と双極性障害って、どっちが正しいの?

実は、同じ病気のこと。名前が違うだけなんです。
この記事では、こんなことを書いています。
この記事でわかること
- 「双極性感情障害=躁うつ病=双極性障害」ってなぜ?
- ICD-10って何?(歴史や日本での使い方)
- DSM-5って何?(歴史や日本での使い方)
まず結論、「双極性感情障害=躁うつ病=双極性障害」です。
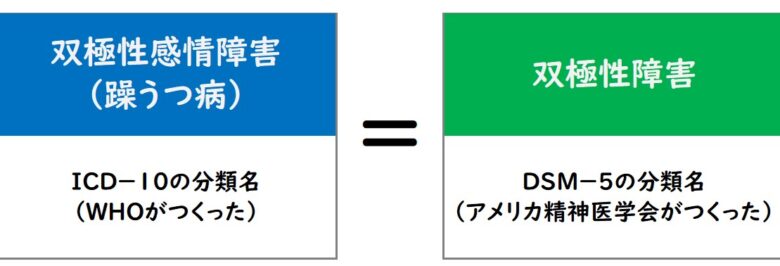
では、どうして名前が違うのか?
それは、病気の分類の仕方が違うからなんです。
病気の分類の仕方には、ICDとDSMという2つの方法があります。
これから、詳しく説明していきますね!

この記事を書いた私は某自治体で働く社会福祉士・精神保健福祉士です。現場経験はおよそ13年です。
双極性感情障害と双極性障害の違いは?ヒントはICDとDSMにある!
これらは全部同じ病気のことです。
名前が違うのは、病気の分類の仕方が違うからです。
ICD-10とDSM-5のどっちを使って病気を分類しているかで、名前が変わるんです。
つまり、こういうことです。↓
次に、ICDとDSMって何かについて見ていきましょう。
ICD-10ってなに?
ICDは世界保健機関(WHO)が作った国際的な病気の分類表です。
正式には「International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems」と言います。頭文字を取ってICDと呼びます。
ICDは、すべての病気について、世界中で同じ分類をするために作られました。

どうしてICDが必要だったの?
国によって病気の分類が違ったら、どんな困ったことが起こるでしょうか?
例えば、私が日本で「双極性感情障害」と診断されたとします。
その後、私はアメリカに引っ越し、病院に行きました。でも「あなたは双極性感情障害ではありません」と言われました。
日本とアメリカでは、双極性感情障害の診断の仕方が違うのです。診察も薬ももらえませんでした。
私は治療を受けられず、病気が悪化してしまいました。
・・・こんな話は、実際にあり得ます。
世界中で同じ病気の分類がなければ、海外に行ったり住んだりするのが怖いですよね。
世界中で協力して、病気を研究するのも難しいですよね。
だから、世界中で同じ病気の分類をするために、WHOがICDを作ったのです。
ICDの歴史

ICDには長い歴史があります。最初のきっかけは1900年の国際会議でした。その会議でICDが作られました。
第1版から第9版までは、10年ごとに新しくなってきました。
つまり、ICDー10の「10」は、10回目のバージョンのことです。
2019年には第11版が出来ました。ICD-11は、日本語に訳したり日本で使えるようにしたりしているところです。

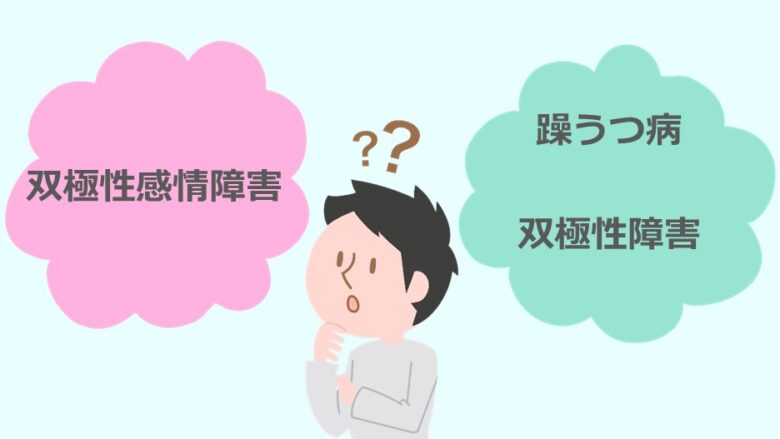















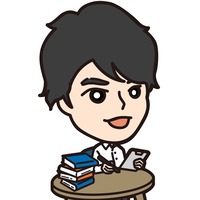
















コメント