
君はまだまだ『福祉の心』が足りんなっ!

ごめんなさい!もっと勉強します!
こんにちは!私は某自治体で働く社会福祉士・精神保健福祉士です。現場経験はおよそ13年。
「福祉の心」という言葉、どんな意味だと思いますか?
自分なりに考えてみても、簡単に言えることではないですよね。(私もそうです)
福祉の仕事では、「福祉の心」以外にも、よく聞くけどよくわからない言葉があります。例えば、
- アドボカシー
- 自己決定
- 共生社会
などです。
これらの言葉は、福祉の仕事で水戸黄門の印籠のごとく、”良いこと”として使われることがあります。
しかし私はこのブログでは、できるだけそういう言葉は使わないようにしています。
読む人によって理解が違うかもしれない言葉ですし、私自身もしっかり説明できるだけの知識がないからです。それに、定義するのが大変だから(汗)
でも、私たち社会福祉士や精神保健福祉士は、話すことが大切な仕事ですし、扱う言葉に敏感になった方が良い。
そこで今回は、篠原拓也さんの本「福祉の心って何だろう」を読んでみたのです。
福祉の心とは?福祉労働者に贈る『福祉の心って何だろう』レビュー
「福祉の心ってやつで、自己犠牲を頼むよ」といったけしからん悪用があるときには、逆にこれを投げ返していく必要がある
引用元:篠原拓也『福祉の心って何だろう』(2020)
福祉の現場では、「福祉の心」という言葉をすごく大切なもの、まるでお守りみたいに使われて、我慢したり、上司に利用されたり、やりがいだけで働かされたりする危険があります。
実は、「福祉の心」という言葉がなくても、福祉の現場というのはお金やボーナスなどの報酬を求めないで無償で尽くすことが大切で、報酬を求めるのは悪いことみたいな雰囲気があると思います。
だから、福祉現場にも労働組合が必要だと私は思っています。
実際に、福祉業界では、残業が当たり前になっていたり、残業申請書がなかったり、休日出勤がタダだったりします・・・。
ボランティア精神みたいなものを求められて、お金をもらうことができない職場もあります。(私の経験でもあります)
そもそも日本の福祉は、昔は宗教家などが善意でやってきた歴史があります。
例えば、『社会福祉の父』と呼ばれる糸賀一雄氏はクリスチャンでしたし、近江学園で働く職員に3つの条件を求めていました。
近江学園の職員に求めたこと
- 四六時中勤務
- 耐乏の生活
- 不断の研究
恐れ多いですが・・・今だと上記のような労働環境はブラック職場ですよね。
でも、そのころは戦後で、知的障害や発達障害もまだわからないことが多かった時代です。
食べていくことすら大変な時代だったので、労働環境なんて言ってられなかったと思います。
そういう意味では、労働環境に不満や文句が言える今は、戦後よりも幸せな面がある社会になっていると思います。
でも、福祉の現場は人数が少なくて回すことが多く、人の目が少なかったり閉じこもったり、「福祉の心」を求められたりするので、パワハラやブラック環境になりやすいです・・・。
社会福祉学者の安藤順一は「福祉の心」という概念が求められる背景に、他者を機械のように所有し支配(コントロール)しようとする人間の欲求への憂慮があると述べています。
引用元:篠原拓也『福祉の心って何だろう』(2020)
「福祉の心」という言葉だけじゃなくて、
私たちは、きれいな言葉で操られて、自分を犠牲にさせられていることはないでしょうか?
長時間労働、サービス残業、休日返上・・・
あなたの職場は大丈夫ですか?気をつけてくださいね。
今回、私は「福祉の心」について悪用の問題を取り上げましたが、この本ではもっと色々な立場からの定義や意見が紹介されています。
どれが正しいとかじゃなくて、特徴がわかりやすくまとめられているので、読みやすくておすすめです。
関連記事
「福祉の心って何だろう」の著者である篠原拓也教授は、『福祉の先生あのね: 対人援助職をめざす学生からの質問・相談・ぼやきにこたえる』というユニークな本の著者でもあります。
この本はけっこう笑えるけど、福祉に関する勉強もできるので、息抜きにちょうど良いです。下記の記事で紹介しています。




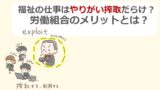
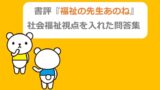
コメント