
社会福祉士の魅力は?精神保健福祉士になって良かったことは?どんな仕事なのかなぁ?
こういった疑問のある方へ。
本記事の内容は、私が働く中で変化した体験談です。
- 自分が変われば周りも変わるとわかった
- 自己管理ができるようになった
- 自分に優しくなれた

私は某自治体で働く社会福祉士・精神保健福祉士です。現場経験はおよそ13年です。。
私は社会福祉士・精神保健福祉士になって変わりました。
今の私があるのはこの仕事に出会ったおかげです。
少々恥ずかしいですが、私の変化をお話しします。
【体験談】社会福祉士・精神保健福祉士の魅力【自分が変わる】
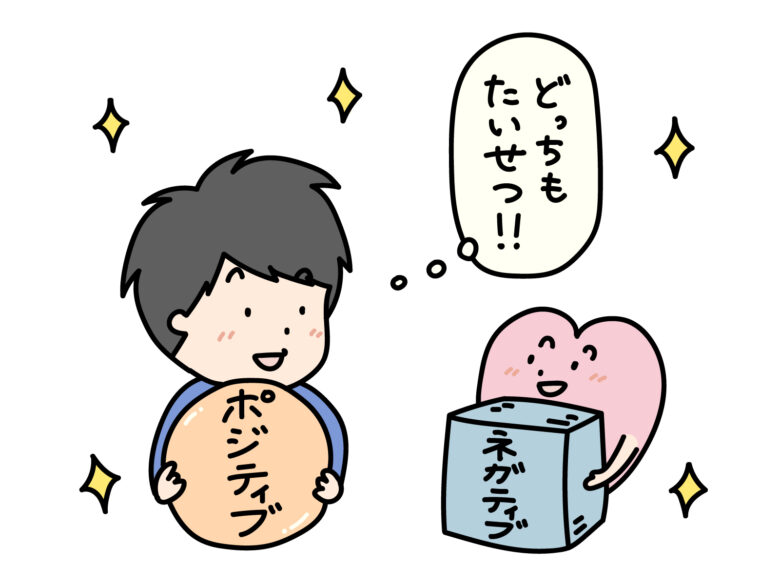
私が変わったことは、こんな感じです。
- 人のせいにばかりする
- 自分の気持ちや体調がわからない
- 自分に厳しい
- 自分が変えられることに集中する
- 自分の気持ちや体調に気づいてケアする
- 自分に優しくする
社会福祉士や精神保健福祉士は、自分が変わることで人生が変わっていくという魅力的な仕事です。
私は昔は、友達からは「福祉の仕事なんて似合わない」と言われていました。
でも今では、「昔のぱーぱすとは別人」と言われます。
私だけではありません。周りの社会福祉士や精神保健福祉士も、「今があるのはこの仕事に出会えたから」と言っています。
では、どうして私は変わったのでしょうか?
変化1:自分が変えられることに集中する

周りのせいにばかりしている人生のつけは、ブーメランとなって返ってくる
この仕事を通して学んだことがあります。
それは、「人のせいにしている人の人生は良くならない」ということです。
しかし元々の私は、人のせいにばかりして生きていました。
- どうして○○してくれないのか?
- 俺が○○するのはあいつが○○だからだ
周りが悪いと思っていたので、周りを変えようとしていました。
でも、変わらないんですよね・・・。だからイライラして、不満や怒りをかかえていました。
しかし私は、支援する相手の人たちを見ていて気づきました。
「自分に問題は無い」「周りが変わるべき」と言っている人たちは、支援が進まないのです。
”困難ケース”となりがちな人たちは、「周りが悪い」「あいつが悪い」「親が悪い」「子どもが悪い」と言ってばかりです。
どれだけ支援で手を尽くそうとも、そういう人たちの人生には、変化が起きませんでした。
逆に、「自分にも問題がある」「自分が変わろうとする」と言っている人たちは、支援が進みました。
「周りを変えようとするのではなく、自分を変えることに努力する」と言う人たちの人生には、少しずつ変化が起きました。
これを見て、私も自分の人生について考えてみました。
そう思って、自分を変えることに努力し始めました。
周りを変えるのではなく、自分が変えられることに集中することが大切とわかったのです。
これはアルコール依存症の人が回復するための原則にも通じますね。
≫関連記事:アルコール依存症家族に贈る「回復の法則」25【社会福祉士の書評】)
また、アメリカの有名な神学者の言葉にも似ています。
神よ
変えることのできるものについて、
それを変えるだけの勇気をわれらに与えたまえ。
変えることのできないものについては、
それを受けいれるだけの冷静さを与えたまえ。
そして、変えることのできるものと、変えることのできないものとを、
識別する知恵を与えたまえ。
自分が変わると、周りもおのずと変わりだす。私の生き方が変わった気づき・体験でした。
変化2:自分の気持ちや体調に気づいてケアする

私は昔は、感情のコントロールが苦手でした。
ちょっとしたことで怒ったり、機嫌が悪くなったり。周りからは気難しい人だと思われていました。
でも、社会福祉士や精神保健福祉士の仕事をすると、感情をおさえないといけない場面が多くありました。
例えば、支援する人にイライラしても、それをそのままぶつけるわけにはいきませんでした。
「この人は嫌いだな」と思っても、全ての人をかけがえのない存在として尊重する専門職なので、冷静に対応しなければなりませんね。
たから、自分の気持ちを見つめて、「専門職としてどうすべきか」を考えて行動するようにしました。
そうした日々のくり返しによって、自分の気持ちに気づきやすくなっていきました。
自分の気持ちに気づくと、感情をコントロールしやすくなります。
自分の気持ちや体調に合ったケアを、早めに・意識的にできるようになるのです。
例えば、「自分は今、怒っている」とわかれば、怒りを抑える方法を考えられます。「この場を離れて落ち着こう」とか「誰かに話してスッキリしよう」とかですね。
こうして私は、昔よりも気持ちのコントロールができるようになっていったのです。
変化3:自分に優しくなれた
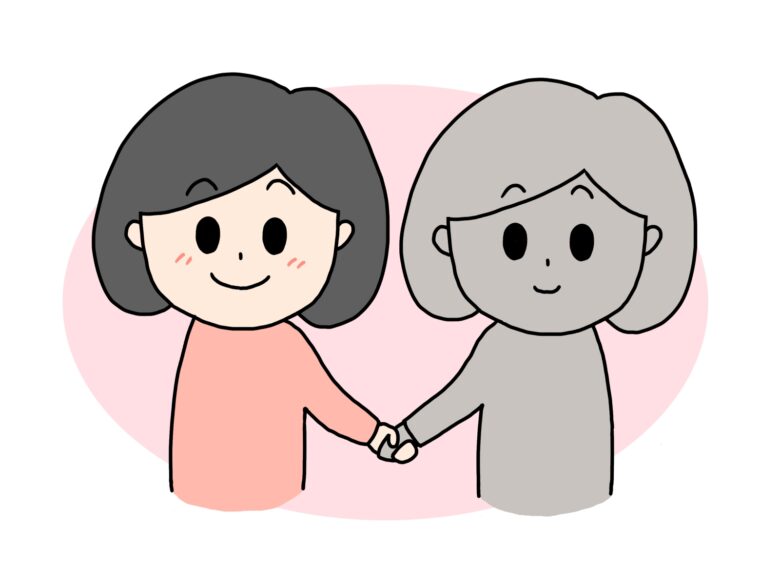
この仕事を通して、自分に優しくなれました。
私は昔は、「○○じゃないとダメだ」という考え方をしていました。
- 学校を卒業したら働かなきゃダメだ
- ○歳までに結婚しなきゃダメだ
- トップじゃなきゃダメだ
自分にも他人にも厳しい価値観で生きていました。
「0か100か」という白黒思考もありました。思い通りにならないことが多く、苦しんで生きていました。
でも、そんな生き方では楽しくありませんでした。
しかし、社会福祉士や精神保健福祉士の仕事をすると、色んな価値観や生き方の人たちに出会います。
例えば、ワケもなく「仕事すべき」とか「結婚すべき」とかは言えません。
社会福祉士や精神保健福祉士は多様性を受け入れる専門職だからです。
たくさんの人の人生をうかがいました。夢や希望、失敗や挫折、喪失や悲嘆を聴いてきました。
私が思う、優しい言葉をかけてきました。
こうして自分からかけ続けた言葉が、自分にも優しい言葉となって返ってきました。
社会福祉士・精神保健福祉士の理想像を演じるなかで、プライベートの自分自身もそれに近づいていったのです。
「人生には正解がない。生き方は自由だ。自分だってこれでいいんだ。」と思えるようになりました。
自分に優しくなれるように変わりました。昔よりも楽に生きられるようになったのです。
【最後に】私が変化できた理由
変化できた理由は2つ考えられます。
- 社会福祉士・精神保健福祉士は自己覚知を求められる専門職だから
- 様々な価値観・背景の人と向き合うから
社会福祉士や精神保健福祉士は、自分のことをよく知る必要がある専門職です。
自分の感情や考え方、価値観や生き方を見つめ直すことになります。そして、自分を知ることは、自分を変える第一歩となります。
また、社会福祉士や精神保健福祉士は、色々な人と関わる仕事です。
様々な価値観や背景の人と向き合うことで、自分の価値観や背景を見直すことができます。
利用者さんや患者さん1人の課題ではなく、家族代々の文脈で連鎖しているケースにたくさん出会います。
そうしたケースに向き合っていると、いつの間にか、私たち自身の価値観までもが変わっていく。
結果、わたしたち自身の生活や生き方が変わり、気づいた頃には人生が変わるレベルの変化へとつながっているように思います。
私は、社会福祉士・精神保健福祉士になってよかったです。興味のある方はぜひ一緒にチャレンジしていきましょう!
関連記事コーナー
社会福祉士に興味のある方は、下記の記事をごらんくださいね!どんな仕事なのか知らない人でも、カンタンにわかるようにまとめました。
精神保健福祉士にご興味のある方は下記の記事を読んでもらうと、もっと詳しくわかります!

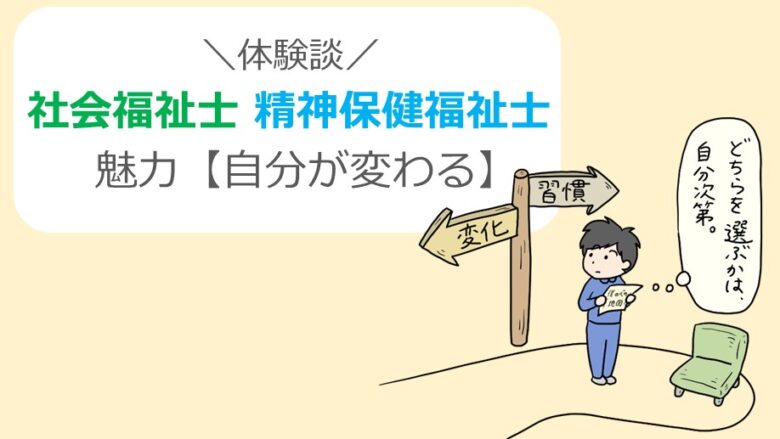


コメント