
社会福祉士の実習うけるんだけど、どんな心構えがいるのかな?
こうしたギモンのある方へ。

リアルじゃ言えないホンネの心構えをお話しますね・・・!
私は某自治体で働く社会福祉士・精神保健福祉士です。現場経験はおよそ13年です。
職場で社会福祉士実習をうけいれていたことがあり、その指導をしていたこともあります。
さてさて、あなたの学校では『社会福祉士実習の心構え』として、どんなことが言われていますか?
- 学ぼうとする態度が必要ですよ
- 指導してもらう謙虚さがいります
- 社会人としての規律を守ることです
- 学生気分で行かない!
うーん・・・確かに正しいですが、不十分です。
心構えを講義やオリエンテーションでしっかり学んだ学生さんほど、いざ実習がはじまるととても辛い目にあったりします。理不尽ですよね。
どうしてこういうことが起こるか?
それは、自分の職場に都合の悪いことは言いにくいからです。
例えば、私自身がそうです。
リアルでは「組織の人間」として働いているので、キレイなことしか話せないです。
『本音』と『建前』でいうと、『建前』しか話せなくなる。
本音を口にするのはタブーだったりします。特に外部の人(実習生含む)にはね・・・。
例えば、A大学の先生がA大学学生に向かってA大学の裏話・批判をすることって、あんまりないですよね?
その情報がどう扱われるかわからない。組織に都合の悪い話を言ってしまったら、まわりまわって自分が不利益をこうむるかもしれません。
ですが、組織に都合の悪い話こそ、実習生に役立つ心構えです。
この心構えさえあれば、実習でも「あ~なるほどね。聞いてた通りだわ。」とショックを減らせるでしょう。
このブログには組織の論理など関係ありません。私も気にせず話せます。
この記事をお読みのあなただけに、社会福祉士実習のホンネの心構えをお話しします。
ではまいりましょう!
社会福祉士の実習に役立つ心構えをホンネで語る【指導経験者の裏話】

社会福祉士実習担当者の立場・思いとは?
まず、実習担当者の思いや立場について。
実習担当者は基本的には、実習生を成長させたい、学んでもらいたいと思ってます。
ただし、実習指導というのは普段の業務のプラスアルファ。追加分なんです。
普段の業務をやっているところに、「実習指導もお願いします」って追加で仕事がやってきてる。
例えば学校でいうと、普段の講義・授業があるんだけれど、同時にテスト勉強もやらないといけないような状況です。
実習担当をする人は、そういう状態です。ひらたくいうと、実習指導はけっこう忙しいです。
だから、実習担当者があなたを指導するには熱意・気合が必要です。
実習担当者が実習生の指導にどれだけ時間・労力をついやせるかは、実習担当者の熱意・業務量・余裕にかかっています。
もし、毎日、振り返りの話をしてくれたり、実習生の感想や意見などをきいてくれる実習担当者ならラッキーです!
ギモンなども率直に伝えていくと、あなたは成長しやすいでしょう。
実習担当者以外の思い・スタンス3パターン!

次に、実習担当者以外はどんな思いで実習生を迎えるのか?
経験上、3パターンあります。それがこちら。
3パターン
- 応援派
- 無関心派
- 厳しめ派
応援派
まずは応援派の人たち。
あなたを温かい目で見守ってくれているし、「頑張れよ!」って思ってくれています。好意的です。
あなたに困ったことがないか、声をかけてきてくれるかもしれません。
実習担当者ではないけれど、育てる視点で関わってくれることもあるでしょう。
わからないことをよく聞くと良い方々です。
無関心派
次は、無関心な人たち。

無関心なんてあるの!?
誰もが実習生に関心があるかというと、そうでもないのが実際です。
社会福祉士の職場は忙しいです。「実習生のことは実習担当者に任せておいたら良いわ」と思っている人は、多いでしょうね。
「社会福祉士だから」「福祉の仕事をしているから」と言ってフレンドリーな人ばかりかというと、全然ちがいます。
淡々と自分の普段の業務をやり続ける人はいます。
自分の仕事だけで余裕がなくて、実習生に気が回らない人もいます。
とにもかくにも実習生に関心がない(もてない)ので、良くも悪くもあなたに関わってきません。
応援派も無関心派も味方みたいなもんです。特に対策はいらないし、疑問や相談を気軽にできるでしょう。
厳しめ派
最後に、厳しめ派の人たち。
どれくらいの割合でおられるのかは、現場によって違うでしょうね。
厳しい理由はさまざまです。
- 自分は厳しく育成されて、そのおかげで成長できたと思っているから
- 職場の管理上、厳しくしている
- 実習生に対して「ちゃんとやってるか?」とあら探し的にチェックしていて厳しい
他者から何をどう言われようが聞き流せるような人は、困らないでしょう。
でも、豆腐メンタルの人や、繊細な人にとっては、厳しめ派の人は、けっこうきついです。
もっと言うと、厳しめというか、厳しい人、嫌な人、いじわるな人に見えるかもしれません。
それで実習を断念するのはもったいないです。
なので、実習をやりきるには、厳しめ派への心構えがあるとGoodです。
社会福祉士実習生への厳しい目線【チェックポイント6つ】
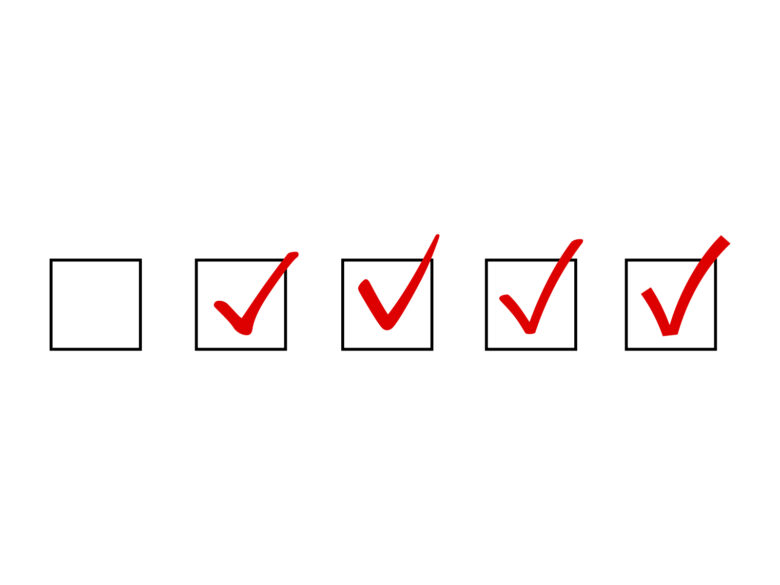
『厳しめ派』の方々がどういったポイントに目を向けているのか?
具体的にお話し、必要な対策をお伝えします!
礼儀(特にあいさつ)
一つ目が礼儀です。
礼儀のなかでも特に際立つのがあいさつ。
気をつけてください。あいさつしなかった場合の減点ポイントはけっこう大きいです。
アルバイトなどの経験のある方は知っていると思いますが、職場ではあいさつをするのがフツウです。
元気な声であいさつ、やっちゃいましょう!
職場では、実習生は目立ってます。
実習生にとっては知らない人だらけの環境です。
でも実習先としては、顔なじみばかりの職場に知らない人が入ってきているので、目に留まるのです。
そうした環境であいさつをしないのは、悪い実習態度となりやすい。そして、減点されやすいです。
職員からすると、あいさつしたのに返事が返ってこなかったら不愉快なんですね。
なので実習生のいないところで、

あの実習生、あいさつすらしないね
こんな感じで悪評がたつことになってしまうのです・・・。
あいさつは誰からすると良いかご存知でしょうか?
基本的に、目下からあいさつするのが常識です。つまり、実習生からあいさつするのが原則です。
上下関係に厳しい人は、実習生からあいさつされるのを待っていることがあります。(くだらないですが、そうやって序列を気にしている職員はいます・・・)
そうした職員にとっては、実習生からあいさつしないと「実習生からあいさつされなかったよ~」と受け取られてしまいます。
知らない間にそんな風に思われるなんて、怖いですよね。
「あいさつされたらあいさつする」という受け身ではなく、自分からあいさつするのがベターです。
ただし、職員がたくさんいる実習先(例えば大きな病院など)では職員が多すぎて、あいさつしきれませんし、かえって変なヤツになりかねません。
そうした場合は、実習担当者に聞いてみるか、職員同士があいさつしているか観察してみるのが良いです。
正解はあるようで無いです。使い古された言葉ですが、「郷に入りては郷に従え」です。実習先、職場にまずは合わせることです。
社会福祉士は組織で働くことがほぼ確定の専門職。だから、面倒くさくても挨拶には気を配りましょう。その方が世渡りしやすいし、ストレスフリーになれるはずです。
身だしなみ&メイク
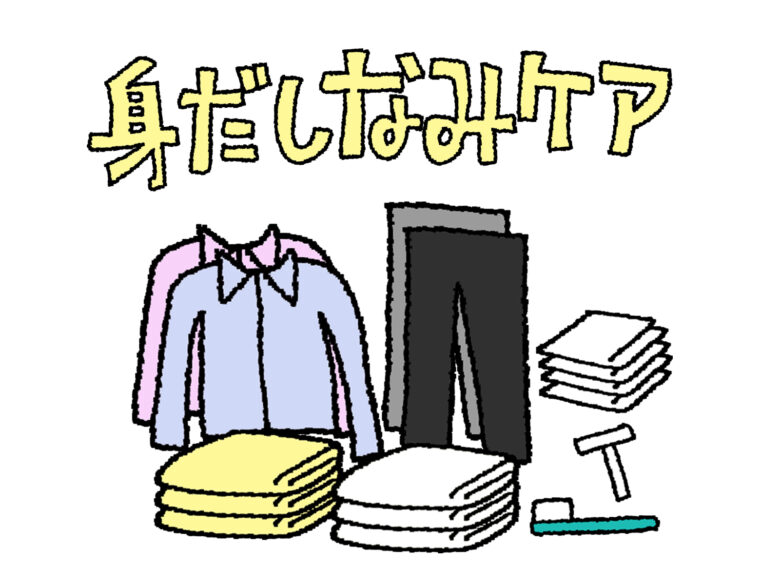
身だしなみ、メイクのOKラインは、実習先によって違います。
例えば、作業所は緩いことが多いでしょう。そうした現場で、スーツで通うのはNGです。
一方、病院であれば、白衣を着るかもしれません。白い靴を用意するように言われるかもしれません。
要は、ケースバイケースです。これも、「郷に入っては郷に従え」のポイントです。
メイク、服装、髪型、身だしなみについては、実習指導の先生に確認しておくのをオススメします。
なぜなら、学校にはあなたの実習先の情報があるはずだから。
社会福祉士の実習先は、各学校が開拓するものです。
あなたの学校は、開拓した実習先に、毎年、一定数の学生を送り出しているはずです。
そうして、実習先の情報は蓄積されていきます。
なので、あなたの実習先の情報は、あなたの先生や教授が知っているかもしれません。
身だしなみの正解ってなんでしょうか?

華美にならないように。学生らしく!
と言われても、あいまいでわかりにくいですよね。
身だしなみのひとまずの正解は「現場の職員の身だしなみ」でわかります。
福祉現場では、一般的にはスーツを着るような場面でも、ラフな格好でOKってこともよくあります。
例えば介護施設などでは、動きやすい服装が重視されるでしょう。ビジネスシューズではなく、スニーカーを履くように言われたりします。
制服貸与の現場もあるでしょう。
つまり、実習先によってOKな身だしなみは違うのです。
あなたは実習前に、実習先でオリエンテーションをうけると思います。なので、おすすめ対策は次の2つ。
- どんな身だしなみが良いか質問する
- 職員の身だしなみをチェックしておく
応用編ですが、こんな記事も書いているのでご参考に。(男性向け)
積極性

よく、受け身な実習生がいます。指示待ちで、立っているか座っている。
でも、お膳立てしてもらうのが当たり前と思ってはまずいです。
「何も言われてないから、何もしなくて良い」と考えていると、評価が落ちちゃうでしょう。
実習先ではお客様じゃないので、自ら動くことが求められます。
それに、職員は業務で忙しくて、実習生にいつも気を回せるわけじゃないんですよね。
だから、手が空いたなら「何かすることありますか?」っていう言葉を使うとGoodです。
「どう動いたらいいんだろう?」って思った時は、ぜひこの言葉を使ってみてくださいね。
そうした実習生は社会性や積極性があると思われて、好まれると思います。
実習日誌の文字量と丁寧さ

実習日誌の書き方で困る学生さんは多いですね。
実習生のなかには、文字が少なかったり、雑になってる方がいます。
これは印象が悪いし、評価が落ちる・・・。
実習日誌の文字は埋めた方が良いです。強く推奨します。
文字量はやる気のわかりやすい指標です。積極性を評価するバロメーターになってしまうんです。
「字が少ない」=「やる気あんのか?」
なので、要注意です!
例えば、文字量の少ない実習生の日誌は、裏側で回し読みされたりして、ウワサになってしまうことがあります・・・。
あと、字の丁寧さも大切です。字をみれば、丁寧に書こうとしたかどうかはわかるものです。
文字の丁寧さは、読み手である実習担当者等への配慮のバロメーターと受け取られやすいです。
読んでもらいやすいように、丁寧にかくのがマナーです。
雑に書いているのは、読み手に対して失礼なことになりますから、要注意です。
訂正をくりかえしすぎているのも、見づらいし、慎重に書いていない(丁寧さがない)と解釈されやすいので、気をつけた方が良いです。
もちろん、実習日誌に書く『内容』は大切ですし、良いにこしたことはない。
しかし、たとえ内容がイマイチだったとしても、丁寧に書いていて、文字がしっかり埋まっている実習日誌なら、やる気があるので好感をもたれやすいです。

丁寧に、たくさん書いた方が良いんだね!
ちなみに、ワンステップ上を目指すには『考察』の書き方を知ることです。
なぜなら、実習日誌で多くの人がつまずくのは『考察』だから。
考察の書き方はこちらの記事で深掘りしています。ワンステップ上を目指したい方はご参考くださいね。
利用者・患者との関わり方

厳しくチェックされているのは、利用者さんや患者さんとの関わり方です。
よくある悪例がこちら。
- 関わろうとしない(一人で黙って座っている等)
- 異性関係のような関わり・雰囲気になっている(と思われている)
よくあるのが、利用者に関わりにいかない実習生さん。
黙って座っているだけという様子だと、「あの実習生やる気あるのか?」と言われるようになります・・・。
実習で学ぶことが目的なので、利用者に声をかけにいくようにした方が良いです。
ただし、はりきって声をかけすぎるのも異様ですし、そうした関わりを望まない方もいます。
このあたり、適度なあんばいが大切です。
他には、異性の利用者さんとの距離感。
実習生の方々は20代の方が多いと思いますが、若い男性・女性が実習にきたことで、普段よりも気分が高揚したり、様子の変わる方々がいます。
仕事でクライエントと関わるときは、異性関係ではなく、支援として必要な関係をつくることになります。
なので、実習場面であっても、異性関係のような関わり・雰囲気になっていると厳しくチェックされます。
(職員側の解釈の問題でもありますが・・・)
ひらたくいえば、鼻についてしまうことがある。
利用者さんのなかには、あなたの連絡先をきいてくる人もいるかもしれません。
最近では、ゲームアカウントの情報を交換して、後日ネット上で一緒にゲームできるように・・・といったつながり方もあるようです。
こういったときの対応は、教えないが原則になっているかと思います。
事前に実習担当者から「断るように」「職員に相談するように」と言われているなら、その指導に従ってくださいね。
出身大学・若い世代への偏見

どの学校からの実習生かによって、職員の目線がかわります。
これは現場で直接いわれることはないでしょう。現場の裏話です・・・。
例えば、

〇〇大学の実習生はやる気があるけど、××〇〇大学の実習生は態度が悪い
といった感じの目線があったりします。
実習先は、毎年、あなたの大学や専門学校から実習生をうけいれていると思います。
なので、これまでの実習生の傾向から、そういった偏見ができあがっていくんですよね・・・。(先輩たちしっかりやっといてよ~!って感じですね)
良い成績をおさめている学校なら、期待が高くてプレッシャーかもしれません。
逆に、悪い成績になっている学校なら、現場サイドとしては期待よりも心配があるわけで。
良くも悪くも、たくさんの目線が向けられるかもしれません。
また、「若い世代」「今どきの世代」として、ひとくくりに捉えている職員もいます。
いつの時代も「最近の若者は・・・」とネガティブに捉える人がいるものです。実習生の立場としてはどうしようもないわけですが・・・。
実習生に求めるレベルが高すぎる!

高すぎるハードル・・・
実習生にどのレベルの動き、考えを求めるか?
このラインって、人によって違うんですよね。
例えば、厳しい実習を受けてきた人は、実習生へ厳しい目線でチェックしやすいですね。
実習生に求めるレベルは、「その職員自身が受けた実習」がスタンダードになっていると思います。
例えば、「私が実習を受けた時は、ろくに睡眠とる時間もなかったのに~。」とボヤいてたりします。
そうした職員の目には、実習生の言動が”非常識”にうつってしまうことがあるんですね。
現場で経験の長い実習指導者や職員ほど、

なんだあの実習生は!?

実習生がこんなことをしていたんだが・・・
と、眉をひそめるんですよね。
中には過大な要求をする職員も。「そんなの実習生にはまだ無理でしょ?」ってレベルを求める職員もいます。
じゃあ、周りの職員があなたを助けてくれるのか?
これが実は難しいのです・・・。残念ながら、他の職員からは手助けしにくい。
なぜなら、福祉の現場には複雑な人間関係があるから。
本音では実習生に「あの人の言うことは気にしなくて良いよ!」と声をかけたくても、
そんなことを言ったら、その職員が怒ってしまって別の波乱を呼んでしまうかもしれません。
だから、言いたくても言えなかったりするのです。
だから、あなたには心構えが必要です。
教科書のようにキレイな現場ではないのが福祉現場です。
理不尽、矛盾、たくさんあります。
適切なアドバイスや指導については、耳を傾けたら良いです。
でも、実習生のためを思った言葉ではない言い方をする人もいます。
学校の先生のように、育てる視点がある人ばかりではないんですね。
もし、ムリなことを言われているのか、真っ当な指導をされているのか判断に困ったら、実習担当者や実習巡回の先生に相談するのをオススメします。
最後に 社会福祉士実習は『やりきったもん勝ち』です!

とにもかくにも、社会福祉士実習はやりきることが最重要です。
叱られようが、いじわるされようが、落ち込もうが、やりきったもん勝ちです!
私の経験上は、実習を中断したり、よほどの大モンダイを起こさない、限り不合格になることはないです。
現場サイドは、学生に実習を無事終えさせたいと思っているものです。
あなたは「不合格になったらどうしよう!?」と心配かもしれませんが、そうそう不合格にはならないので安心して取り組んでもらうと良いです!
辛いこともあるでしょうが、必ず終わりはやってきます。
頑張ってくださいね!
関連記事
社会福祉士の実習が始まってからの辛さは、こちらにまとめてあります。知っておくと、対策になるでしょう。
実習日誌の書き方(特に考察)は、こちらでわかります。
私の社会福祉士実習の体験談はこちらでわかります。
社会福祉士実習は大変ですが、やって良かったですね。実習モチベを上げたい方のお役にたつかもしれません。







コメント