この記事でわかること
などについて、わかりやすく解説します。 では、始めましょう!- 利用者さんのできることまで手伝ってしまうと、どうして良くないのか?
- どうして手伝ってしまうのか?
- 福祉現場で「利用者さんのできることは手伝わない」方法4つ
福祉の仕事で「手伝わない」ことが大切な理由と対処法|経験者が解説
 福祉の仕事をする人は、困っている人を助けたいという気持ちが強いです。 だから、利用者さんがお願いしたら、何でもしてあげたくなりますね。私もそうです。 例えば、「自分で着替えられるけど、面倒だから手伝って」と言われたら、「わかりました。手伝いますよ」と言ってしまいたくなる。 でも、これは本当に利用者さんのためになっているでしょうか? 実は、利用者さんのできることまで手伝ってしまうと、次のような悪いことが起こります。
福祉の仕事をする人は、困っている人を助けたいという気持ちが強いです。 だから、利用者さんがお願いしたら、何でもしてあげたくなりますね。私もそうです。 例えば、「自分で着替えられるけど、面倒だから手伝って」と言われたら、「わかりました。手伝いますよ」と言ってしまいたくなる。 でも、これは本当に利用者さんのためになっているでしょうか? 実は、利用者さんのできることまで手伝ってしまうと、次のような悪いことが起こります。- 利用者さんが自分でできる力を失ってしまう
- 利用者さんが支援者に依存してしまう
- 利用者さんが自分で何もしなくなってしまう
- 利用者さんが支援者に無理を言ったり、暴力をふるってしまう
- 利用者さんが自分の人生を楽しめなくなってしまう
福祉現場で「利用者さんのできることは手伝わない」方法4つ
「利用者さんのできることは手伝わない」という原則を守るには、次の4つの方法を試してみてください。 方法4つ
- 利用者さんの能力や状況を正しく把握する
- 自分の感情や動機をチェックする
- 利用者さんに説明や相談をする
- 苦情や抵抗に対応する
利用者さんの能力や状況を正しく把握する
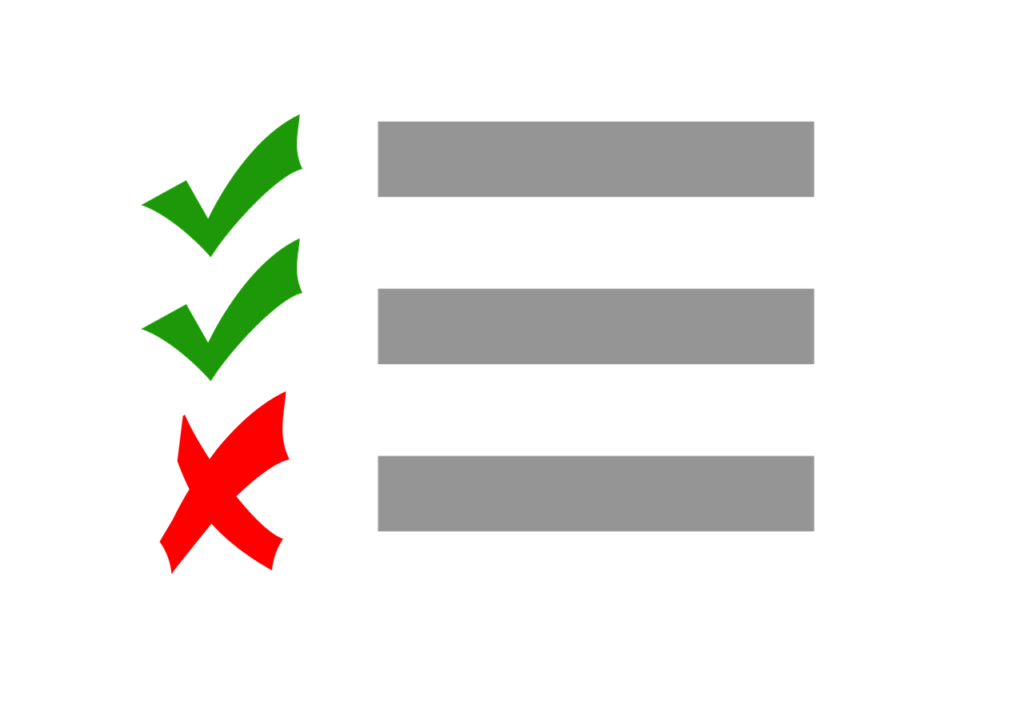 利用者さんが、何ができて何ができないかを知ることが大切です。 そのためには、利用者さんに病気や障害がある場合は、その特徴や影響を学ぶ必要があります。 また、高齢の方の場合は日常生活動作(ADL)や認知機能を評価する必要があります。 しかし、これらの知識や評価を確実にするのはカンタンではありません。だから、私たちはつい「病気や障害があるから手伝わないと」と思ってしまいます。 これだと素人的になってしまいます。 何ができて、何に困るのかは人によって違いますね。特に病気や障害は個人差や状況によって変化するものです。 だから、その利用者さんの能力や状況を正しく把握することが大切です。 そうして、利用者さんに必要な支援内容や方法を決めます。例えば、「掃き掃除」をする場合、
利用者さんが、何ができて何ができないかを知ることが大切です。 そのためには、利用者さんに病気や障害がある場合は、その特徴や影響を学ぶ必要があります。 また、高齢の方の場合は日常生活動作(ADL)や認知機能を評価する必要があります。 しかし、これらの知識や評価を確実にするのはカンタンではありません。だから、私たちはつい「病気や障害があるから手伝わないと」と思ってしまいます。 これだと素人的になってしまいます。 何ができて、何に困るのかは人によって違いますね。特に病気や障害は個人差や状況によって変化するものです。 だから、その利用者さんの能力や状況を正しく把握することが大切です。 そうして、利用者さんに必要な支援内容や方法を決めます。例えば、「掃き掃除」をする場合、- 適切な掃除用具を選ぶ
- 掃除用具を持ってくる
- 掃く(できる場所、できない場所、丁寧さはどうか)
- ごみを回収する
- 掃除用具を片付ける
自分の感情や動機をチェックする
 私たちは「人を助けたい」という気持ちが強いです。でも、その気持ちが支援に悪影響を与えていることもあります。例えば、
私たちは「人を助けたい」という気持ちが強いです。でも、その気持ちが支援に悪影響を与えていることもあります。例えば、- 自分の不安や罪悪感に耐えられなくて、手伝ってしまう
- 喜んでもらいたいから手伝ってしまう
- 早く終わらせたいから手伝ってしまう
利用者さんに説明や相談をする
私たちは「利用者さんのできることは手伝わない」という原則を守りますが、それは決して無関心や無責任ではありません。 私たちは常に利用者さんとコミュニケーションを取ります。 例えば、「掃除」をする場合、- 掃除したい理由や目的を聞く
- 掃除した後のイメージやメリットを話す
- 掃除する部屋や範囲を決める
- 掃除する頻度や時間帯を決める
苦情や抵抗に対応する
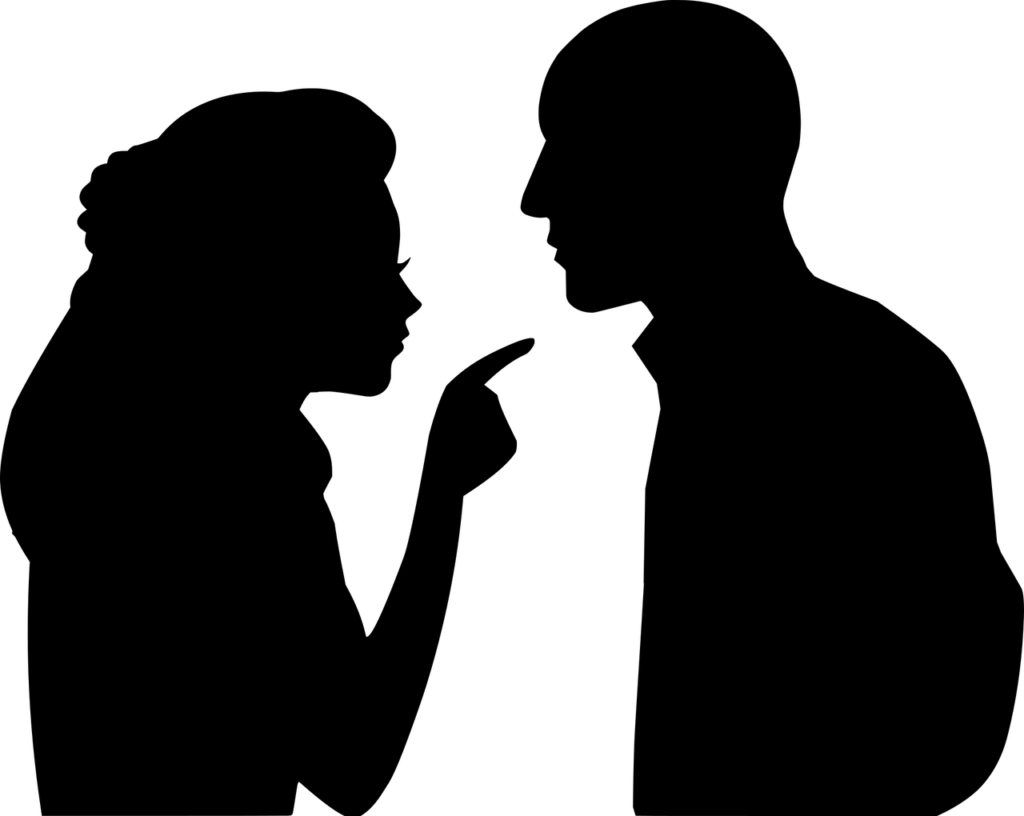 私たちは「利用者さんのできることは手伝わない」という原則を守りますが、それが必ずしもスムーズに進むとは限りません。中には、
私たちは「利用者さんのできることは手伝わない」という原則を守りますが、それが必ずしもスムーズに進むとは限りません。中には、- 前任者や他職員が手伝ってくれたから今回もそうして欲しい
- 面倒だから手伝って欲しい
- 自分では無理だから手伝って欲しい



コメント