
地域活動支援センターと地域生活支援センターって違うの?

違うよ。ただし、中には『実態は同じ』という場合があるんだ。
私は某自治体で働く社会福祉士・精神保健福祉士です。現場経験はおよそ13年。
↓の2つ、名前が似てますよね?
- 地域活動支援センター (以下:地活)
- 地域生活支援センター (以下:生活支援センター)
「同じようなもの?」と思われやすいです。
では、地域活動支援センターと地域生活支援センターは違うのか?
答えは「別物ですが、実態は同じケースもある」です。
言いかえると、「名称は地域生活支援センターだが、実際の事業は地域活動支援センター」というケースがあるのです。
なぜなら、『地域生活支援センター』という名の事業所は、実態を見てみてみないと、何をやっている事業所なのか判別できないから。
この話をよく理解するには、地域生活支援センターの歴史をたどる必要があります。
一緒にみていきましょう!
地域活動支援センターと地域生活支援センターの違い【社会福祉士解説】
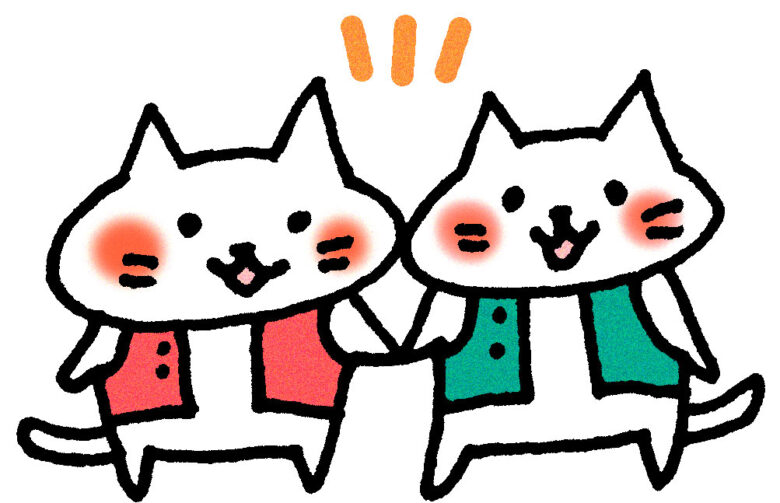
地域活動支援センターと地域生活支援センターの歴史
1996年 地域生活支援センターが制度化された
地域生活支援センターは、1996年に障害者プランによって創設されました。
地域生活支援センターの正式名称は、『精神障害者地域生活支援センター』です。
そう、対象は精神障害のある方だったのです。
そして、地域生活支援センターは、旧『精神保健福祉法』で制度化されました。
同法で、地域生活支援センターは次のように定義されていました。
地域の精神保健及び神障害者の福祉に関する各般の問題につき、精神障害者からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに、第49条第一項の規定による助言を行い、併せて保健所、福祉事務所、精神障害者社会復帰施設等との連絡調整その他厚生労働省令で定める援助を総合的に行うことを目的とする施設とする。
引用元:旧『精神保健福祉法』第50条
※現在この条文は削除されています
そうして、地域生活支援センターは、精神障害者の社会復帰施設として全国に拡大していきました。
職員配置は、次のように決められました。
地域生活支援センターの職員配置
- 施設長 専従 1名
- 精神保健福祉士 専従 1名以上
- 社会復帰指導員 3名以上(2名は非常勤可)
事業としては、どの地域生活支援センターも次の3つを共通して行っていました。
生活支援センターの主な事業
- 相談事業
- 日中活動の場の提供
- 地域交流事業
ただし、それぞれの地域生活支援センターごとに独自性もあったんですね。
2005年 障害者自立支援法成立によって移行
2005年には、障害者自立支援法が成立しました。
同法により、こんどは『地域活動支援センター』が制度化されたのです。
しかも、『地域生活支援センター』も再編されました。市町村の地域生活支援事業である、次の3つなどに移行されたのです。
地域生活支援センターは次の3つに移行
- 相談支援事業
- 生活サポート事業
- 地域活動支援センター事業 ← 注目!!

③で地域生活支援センターが地域活動支援センターに変わってる!

事業はそのままで、名称だけが変わっていることがある。だから、地活と同じような活動をしている地域生活支援センターがあるんだ。
現在の地域生活支援センター
現在も、地域生活支援センターという名称の事業所は残っています。
でも、行っているサービスや事業はさまざまです。
現在の地域生活支援センターがしていること
- 相談支援事業
- 生活サポート事業
- 地域活動支援センター事業 など
いろんな地域生活支援センターがあります。
事業内容は変わったけれど、名称は昔と同じ「地域生活支援センター」をそのまま使っているケースがあるんです。
だから、実際には何をしている事業所なのか?実態を見たり尋ねたりすることが大切です。
まとめ
地域生活支援センター(精神障害者地域生活支援センター)と地域活動支援センターは違う機関です。
まとめ
こうした歴史事情があるので、「地域生活支援センター」という名称だけでは事業内容はわかりません。
「看板は地域生活支援センターのままだが、事業は地域活動支援センター」というケースがあるのです。
ホームページを見たり、直接問い合わせたり、足を運んでのぞいてみて、ようやく実態がわかるでしょう。
ちなみに、現在の地域生活支援センター・地域活動支援センターの根拠法は、障害者総合支援法です。
法の理解なくしてプロは名乗れませんね。法律の条文を読み込める方はしっかり読んでおきたい。
私はこちらの本も参考にしています。第3版がでていて、人気の著書です。

かしこくなれた!
≫参考:精神障害者の地域生活支援の在り方について ~相談支援事業所 +ぷらすらiふの実践からの考察~ 郡山 昌明、志水 田鶴子、廣庭 裕、大坂 純

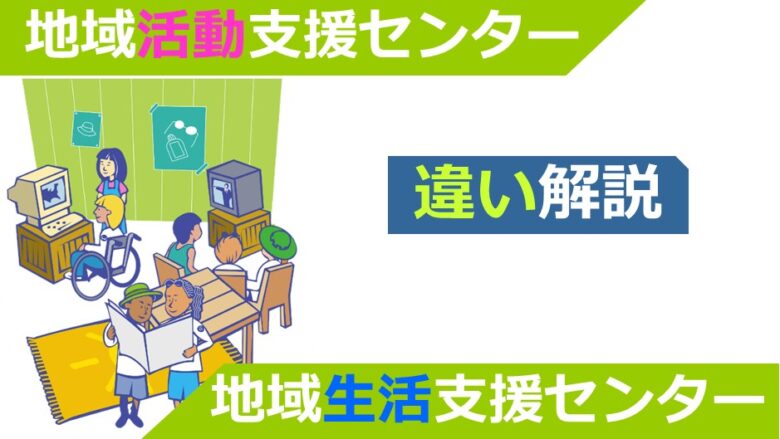



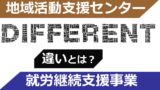


コメント