
精神保健福祉士になりたいけど、役に立つのかな?
この記事では、こんなことをお話しします。
- 資格を取っても現場で役に立たない理由は何か
- 精神保健福祉士として自分が役に立っていると感じられない理由は何か
- 役に立つ精神保健福祉士になるにはどうすればいいか

私は社会福祉士・精神保健福祉士として働いています。現場経験は10年以上です。
結論から言うと、精神保健福祉士の資格を取っても、現場で役に立つようになるまでには時間がかかります。
「精神保健福祉士として自分が役に立っている」と感じられないこともあります。
でも、それは仕方のないことで、やり方次第で変えられることです。
では、詳しく見ていきましょう!
精神保健福祉士は役に立たない?不安に感じる方へ【現役PSW解説】

精神保健福祉士の資格を取っても、現場ですぐには役に立たない理由は3つあります。
現場の役に立たない理由3つ
- 知識だけでは実践力がないから
- 現場で必要な知識はもっと深くて広いから
- 業務独占ではなくて誰でもできる仕事だから
知識だけでは実践力がないから
精神保健福祉士の資格を取るためには、国家試験を受けて合格しなければなりません。
国家試験はマークシート方式のテストです。実技試験はありません。
国家試験では、障害年金制度や精神疾患などの知識を問われます。でも、それだけでは現場で支援する力にはなりません。
知識を使えるようにするには、実際に経験してみることが必要です。それには数年かかることもあります。
例えば、「個別化」という言葉を聞いたことがありますか?
これは支援の原則のひとつです。大雑把にいうと、利用者さん一人ひとりの状況や希望に合わせて支援することです。
でも、「個別化」をするのは簡単ではありません。
利用者さんの背景や思いや障害への理解、自分自身の気持ちや考え方などを把握しなければなりません。
それには相手とコミュニケーションを取ったり、自分を振りかえってみたりすることが必要です。それには時間や努力がかかります。
自己覚知がその1つですね。
だから、資格を取ったばかりの精神保健福祉士が役に立つようになるまでには、まだまだ勉強や練習が必要なのです。
現場で必要な知識はもっと深くて広いから

精神保健福祉士の資格を取るためには、国家試験の範囲を勉強しなければなりません。
でも、現場で必要な知識は、国家試験の範囲よりも深くて広いです。
理由は、精神保健福祉士は様々な分野で働くからです。
高齢者や子どもや障害者など、対象者や施設やサービスはさまざまです。でも、実際に働くのはどこか1つの分野ということが多いです。
例えば、老人保健施設や学校や就労継続支援B型事業所など、それぞれで求められる知識やスキルは違います。
高齢者の支援をするなら、国家試験で勉強した知識だけでは足りません。もっと高齢者の心理や生活や健康に関する知識が必要です。
だから、現場に合わせて知識をさらに増やさないと、役に立つ精神保健福祉士にはなれません。
国家試験よりももっと深くて広い知識が必要なのです。これは仕事をしながら学び続けることになります。
業務独占ではなくて誰でもできる仕事だから
精神保健福祉士は、自分の名前に「精神保健福祉士」とつけることができます。
これは名称独占資格と言って、資格を持っていない人は名乗れないということです。
わたしが「精神保健福祉士のぱーぱすです」とか「精神保健福祉士です」と繰り返し名乗っているのは、このためです。
でも、「精神保健福祉士」と名乗っても、自分だけができる仕事があるわけではありません。
精神保健福祉士の仕事のほとんどは、質さえ問わなければ誰もがやって良い仕事です。
例えば、作業所で働く精神保健福祉士は、利用者さんと一緒に内職したり、食べ物を作ったり、販売したりします。相談を受けたり、面談することもあります。
でもこういったことは、精神保健福祉士以外の人でもできます。
おじさんでもおばさんでも、無資格の兄さんや姉さんでも、優しい気持ちがあれば「何とかできてる風」に見えます。
でも精神保健福祉士の支援は、ただ優しくしてあげるだけではありません。
利用者さんの生活や人生をより良くするために、専門的な視点や目標や方法を持っています。
精神保健福祉士は誰でもできる仕事をしますが、素人とは違うレベルの支援をする専門職なのです。
精神保健福祉士あるある|自分が役に立っているかわからなくなる

精神保健福祉士は自分の仕事が役に立っているかわからなくなることがあります。
精神保健福祉士は、精神疾患や精神障害があって、生活のしづらさを抱えている人を支援する仕事です。
支援するのは、生活や人生。これって、人それぞれ違いますよね。
どういう生活が良いのか、どういう人生が幸せなのかは、自分で決めることです。
精神保健福祉士の支援に正しい答えはありません。ベターはあっても、絶対的なベストはないのです。
例えば、親と一緒に住むか、一人で住むかは、自分で選ぶことですよね。精神保健福祉士は、アドバイスをすることはできますが、最終的には本人が決めることです。
それに、精神保健福祉士が支援しても、すぐに変わらないこともあります。一生懸命やっても、結果が出ないこともあります。
だから精神保健福祉士は、本当にちゃんと支援できているのか、できていないのか、自分では判断できないことが多いです。
このように「自分の仕事が役に立っているのかわからない」という気持ちが続くと、
「自分は何もできていない」「精神保健福祉士は役に立たない」と思ってしまうこともあります。
ひどくなると、いつのまにかバーンアウトしてしまいます。
役に立つ精神保健福祉士になるには?
精神保健福祉士として役に立ちたいなら、勉強を続けることが大切です。(そりゃそうだろ!って言われそうですけど
精神保健福祉士がやる仕事は、誰でもやってみれば、それなりにはできる仕事でもあります。

例えば、誰でも目玉焼きは作れますよね。でも、きれいでおいしい目玉焼きを作るのは難しいですよね。相手の好みに合わせて作るのも大変ですよね。
「支援する」というのも同じです。誰でもやってみればできますが、その内容は精神保健福祉士によって違います。
役に立つレベルの支援をするために必要なことは、たくさんあります。
例えば、次のことを考える必要があります。
- どんな病気でどんな困りごとがあるのか
- 何が得意で何が苦手なのか
- どんな生活をしたいのか
- 精神保健福祉士・所属する機関として何ができるのか
- 支援は今どの段階なのか
これらのことを確認しながら、相手の気持ちや考え方を理解しようとすることが大切です。
そのためには、研修に参加したり、本を読んだり、仲間と話したりすることが効果的ですね。
最後に
精神保健福祉士の仕事は、質さえ問わなければ誰がやっても良い仕事です。
だからこそ、精神保健福祉士ならではの支援をすることが大切ですね。
支援の質を磨いていきましょう!そのためには、資格をとってからも学習し続けることですね!
関連記事コーナー
今回はネガティブな話をしましたが、私は精神保健福祉士は魅力ある仕事だと思っています。詳しくはこちらで話しています。↓
精神保健福祉士について全体的にもっと知りたい方は、下記の記事もごらんくださいね!

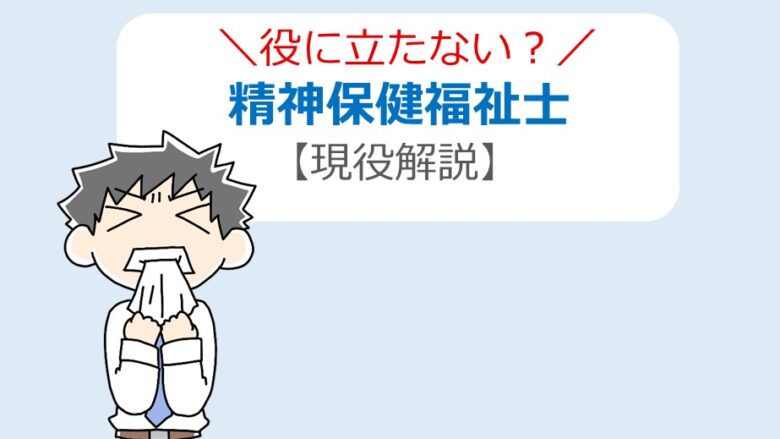

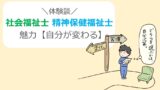

コメント