
お金とか投資って、なんか汚い気がする。福祉と関係あるの?
「福祉の仕事は“やりがい”でやるもの」
そう思っていたのは、かつての私。
ソーシャルワーカーとして働いていると、「お金より人のために」という空気がありますよね。
でも実際、福祉ほど“お金の話”と切り離せない仕事もありません。
今回は、「ソーシャルワーカーはなぜお金に疎くなりやすいのか」、そして「どう向き合うべきか」を、現場で働く私自身の経験を交えながら考えていきます。
福祉は“お金の話”ばかりでできている
福祉業界は「お金とは無縁の、清く尊い世界」と思われがちですが、現実にはほとんどがお金の話です。
- 施設の利用料
- 福祉サービスの負担上限
- 自立支援医療や障害年金
- 生活保護
これらすべて、「いくら支払えるか」「どこまで補助されるか」という経済的な話です。
「仕事がしたいけどできない」という相談も、お金の側面があります。
極端にいえば、お金さえあれば多くの福祉課題は早く解決できます。
逆に、資金が尽きた瞬間に選択肢が消えることもある。
つまり、お金の仕組みを知らないソーシャルワーカーは、自分の支援の幅を狭めてしまうんです。

給料が安くて辞めていくソーシャルワーカーたち
一方で、ソーシャルワーカーの経済状況は厳しい。
「給料が少ないから、もうやっていけない」と転職していく同僚を、私はたびたび見てきました。
確かに、社会福祉士や精神保健福祉士の給与水準は、平均か、やや下くらい。
それでも、「人のために働きたい」「やりがいを感じたい」と頑張る。
でも現実は、生活が苦しくなると「やりがい」では埋められない瞬間がやってきます。
そして、私たちの離職は利用者さんにとっても痛手です。
だからこそ私は、思うようになりました。
支援者が安定して暮らせることは、支援の安定にもつながると。
投資=お金持ちのもの?もう古い話です
「投資なんてお金持ちしかできない」
──そう思われるかもしれません。
たしかに昔はそうでした。
でも、今は違います。
金融庁が2018年に「つみたてNISA」をスタートし、2024年には制度が拡充されました。
「もう国は年金だけでは支えきれません。老後は自分で備えてください」
そう国が宣言したようなものです。
つまり、投資は“特別な人のもの”ではなく、一般市民の生活防衛手段になったのです。
NISAやiDeCoを利用しないのは、もはや「節税の機会を逃す」レベルの損。
私はそう考えています。
「うちにはそんな余裕ない」──それもリアルです
もちろん、「投資よりまず生活がギリギリ」という現実もあります。
知人は、「毎月は赤字、ボーナスでようやく黒字」と話していました。
そういう状況で「未来のために投資を」と言われても、響かないのが本音でしょう。
投資とは「今を我慢して未来に備える行動」です。
今が限界なら、投資なんてできない。
それが現実です。
ただし、少しずつでも貯金できるようになったら、100円から投資できる仕組みもあります。
私もやっている証券会社が、楽天証券やSBI証券です。
「投資=ギャンブル」だと思うなら
「投資ってギャンブルでしょ?」
──そう感じるのは自然な反応です。私の妻も最初はそうでした。
妻には何度説明してもピンとこなかったようですが、
妻自身が少額で買って実際の値動きを経験すると、
「なるほど、こういう仕組みなんだ」と実感していました。
今では妻も私も、“オルカン”(eMAXIS Slim 全世界株式)というインデックスファンドに投資しています。
もうこれは、庶民の代表的な選択肢になっています。
もちろん、投資は自己責任です。
でも、”知らないから拒否する”より、”知った上で拒否する”が賢いと思います。
私たちは「生活を支援する仕事」です。
その私たちが、お金の仕組みに疎いとしたら、少し説得力に欠けると思います。
お金の仕組みを学んで実践している支援者ほど、言葉は現実的で説得力を増す。
そのように私は思います。
ソーシャルワーカーこそ、お金に強くなったほうがいい理由
支援は、「余裕」から生まれる行為でもあります。
心に余裕がなければ、支援どころではなくなってしまう。
自分がおぼれそうな時は、無意識に人を傷つけやすくもなります。
お金も同じではないでしょうか。
私たち自身の生活がままならず、不安でいっぱいになり、「もうソーシャルワーカーを続けられない」となれば、支援は続けられません。
そして、その結果いちばん困るのは、クライエントの方々です。
自己犠牲もしすぎれば、相手を傷つけてしまうことさえあります。
だからこそ、私たち自身の生活を守る術を持ちたいと思います。
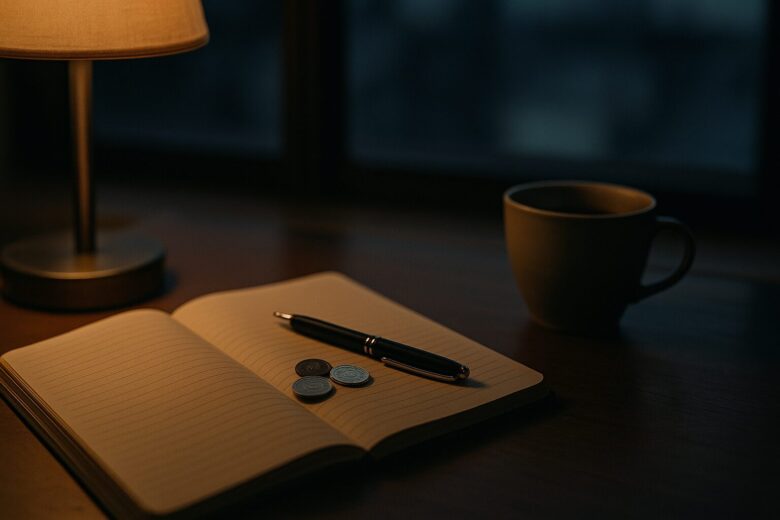
まとめ:お金の知識は、自由への第一歩
お金がなければ、お金に支配されます。
「金がない…」とそればかり考えている毎日。
これでは、自由とは言えません。
お金の悩みから自由になるには、お金の知識が必要です。
そして、ソーシャルワーカーである私たちは、そもそもお金と密接に関わる仕事をしています。
給料を根本的に上げるには、税金の配分や政策が変わる必要があります。
ソーシャルワーカーとして、社会構造の問題に声を上げていく
――それも大事なことです。
けれど、時間がかかります。
私たちの人生のタイムラインは、待ってはくれません。
一方で、個人でできる改善は“今すぐ”始められる。
貯金、支出の見直し、投資の検討。
小さくてもいい、一歩を踏み出してみること。
私がお金を学んだのは、著書:新NISA対応 超改訂版 難しいことはわかりませんが、お金の増やし方を教えてください!の旧版でした。
やってみるかどうかは、人それぞれ。
他者ができるのは知識の提供まで。行動を選ぶのは自分自身です。
ソーシャルワーカーの面白さは、自分の生活を真剣に考えることが、支援にもつながるという点にあります。
お金の勉強も、貯金も、節約も、投資も
――すべてが支援の「肥やし」になる。
それって、素敵なことだと思います。
社会福祉士や精神保健福祉士の仕事の魅力です。
関連記事のおすすめ
▼ 福祉の仕事をしながら稼ぐには?
福祉職として働きながら収入を増やすには、どんな方法があるのか。
ソーシャルワーカーでも再現できる工夫を、実体験をもとにまとめています。
▼ iDeCoやNISAを始めてみたい方へ
もし「資産運用をやってみようかな」と思ったら、まずは証券口座の開設が必要です。
私が実際に使っている楽天証券とSBI証券のおすすめ理由を紹介しています。

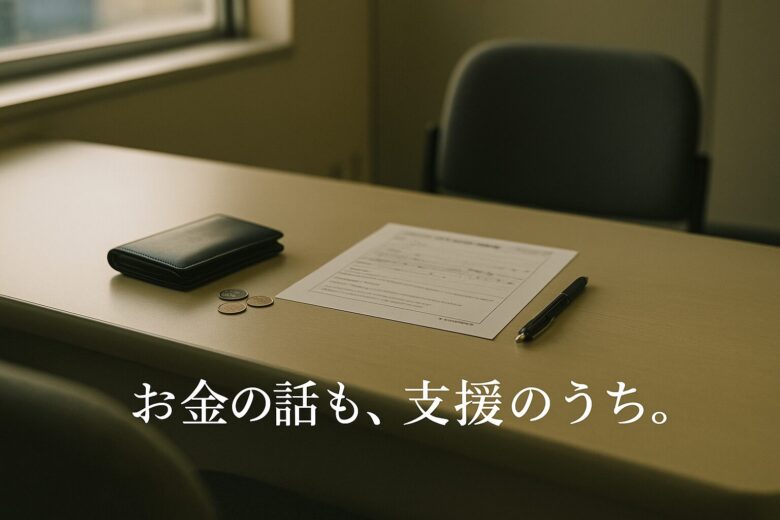



コメント