こんにちは!社会福祉士・精神保健福祉士のぱーぱすです。
実習を受けたのは10年以上前ですが、今では実習生を教えることもあります。
実習について、みなさんどう思いますか?
「面倒くさい」
「緊張する」
「不安だ」
「バイトができなくて困る」
「国家資格を取るためには必要だから」
いろんな気持ちがあると思います。
実際、実習生は知らない現場や人や制度に慣れるのに大変です。
でも、「実習は苦労ばかり」「早く終わらせたい」と思うだけではもったいないです。実習には良いこともあります。
「実習で何が得られるのか?」
これを知ることで、実習を無駄にしないようにしましょう。私が実習から得た3つのメリットをお話します。
今でも役立っていることなので、将来のあなたも同じように感じるかもしれません。
それでは始めましょう!
社会福祉士&精神保健福祉士実習は大変だが、やってよかったこと3選
就職先を選ぶときに参考になる

社会福祉士と精神保健福祉士の実習を受けることで、どんな仕事がしたいか、決めやすくなります。
「福祉の仕事がしたいけど、どんな分野がいいかわからない」という人は多いと思います。
福祉の仕事は色々あります。高齢者や障がい者、子どもや家庭など、支援する人や場所は違います。
自分に合った仕事を見つけるためには、実際に現場を見て体験することが大切です。
実習先はそのチャンスです。実習先で働くことで、「この仕事が好きだ」「この仕事は向いていない」という気づきが得られます。
自分の希望や適性に合わせて就職先を選ぶ材料になります。
私も実習経験が就職活動に役立ちました。
他機関と連携するときに役立つ
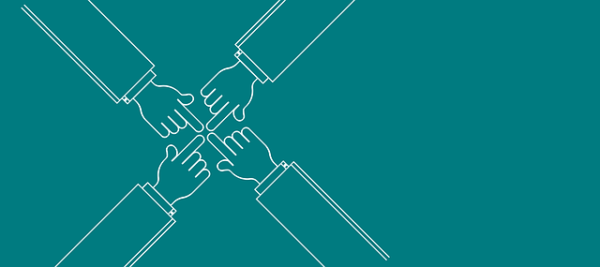
実習先で学んだことが、他の機関とのやりとりに活かせます。
例えば、病院で実習を受けた場合。病院やクリニックの考え方や仕事の流れがわかるようになるので、医療機関と連携するときにスムーズになります。
これはとても大事なことです。
実は、福祉の現場では、機関同士のトラブルがよく起こります。
「この人はあなたのところが担当でしょう?」
「この人はうちでは受け入れられません」
といった具合に、支援する人の責任を押し付け合うことがあります。(とても残念ですが・・・)
そういうときに、「相手機関の立場や考えがわかる」というのは、とても助かります。
「なぜこの人を受け入れてくれないのか?」
「相手はどういうことを言いたいのか?」
と、相手の気持ちを想像できるようになると、無駄なトラブルを避けられたり、解決策を見つけやすくなったりします。
実習先はどこでも役立ちます。病院、地域、行政、どこでも大丈夫です。
どこで実習を受けても、他の機関と協力するときに役立つ知識や経験が得られるのです。
現場を改善するヒントになる

実習先と現場を比べることで、問題点や改善点が見えてきます。
あなたが現場で働き始めてから、実習先を思い出してみましょう。
どこが違っていたか、どこが良かったか、どこが悪かったか。
不思議なことに、就職した後はその現場だけで考えたり行動したりしがちです。
だんだん発想が固まったり、新しい方法が思いつかなくなったりする人もいます。
そんなとき、実習経験が役立ちます。
例えば、うまくいかないときや困ったとき。福祉の現場では、難しいケースや問題が起こることがあります。
そうした時に、
「実習先ではどうしていたか?」
「実習先ではできていたことが、今の現場ではできていない理由は何か?」
と考えたり比べたりすることで、改善のヒントやアイデアが浮かぶことがあります。
何かできないことがあっても、「実習先ではできていたから、今の現場でもできるはずだ」と思えるようになると、希望や勇気が湧いてきます。
方法を変えれば状況も変わると信じられることは、とても大切です。
信じられないと、諦めたり、努力しなくなったりします。何をやっても無駄だと思ったら、やる気がなくなりますよね。
実習先には、良いところも悪いところもあります。でも、どちらも現場を改善するヒントにできます。
最後に
福祉の現場は、一つとして同じものはありません。同じやり方で、どこでもできるということはないです。
福祉の現場は、仕事の範囲が曖昧だったり、どんな人がやってもいい仕事が多かったりします。はっきりしないことやグレーなことが多いです。
でも、逆に言えば、自由に考えられるし、色んな答えや支援の方法があるということです。
それに、支援する人もそれぞれ違いますし、現場の人たちの考え方や働き方も違います。
つまり、100職場100色ということです。実習先もそのうちの1色です。
そんな福祉現場ですから、本を読んでいても現場はわかりません。実際に現場を見て、経験して初めてわかることがあります。経験できる実習はすごく貴重です。
実習、頑張ってくださいね!
以上、社会福祉士&精神保健福祉士実習は大変だが、やってよかったこと3選という話題でした。
関連記事コーナー
社会福祉士実習の心構えを指導経験者が本音で語る。実習担当者や職員の思い、厳しい目線、実習先と現場の比較などを解説。学校では教えてもらえない現場目線の内容です。
社会福祉士実習のつらさと対策を解説します。コミュニケーションや人間関係、実習日誌などの悩みに答えます。実習生は職員より辛いんですよね。
精神保健福祉士実習の辛いあるある話と対策を経験者として語ります。利用者・患者さんとの関わりや職員・実習担当との人間関係、実習日誌や人権・倫理的な問題についてアドバイスします。つらくても実習はやりきったら勝ちです!





コメント