
実習つらい。何話せばいいかわからないし、実習日誌にダメ出しされるし、実習担当は厳しいし…。たぶん落ちた。もうやめたい!
こういった思いのあなたへ。
- 【大前提】実習生は職員よりつらい
- 利用者・患者さんとの関わり
- 実習担当&職員との人間関係
- 実習日誌にダメ出しされる&実習日誌が返ってこない
- 人権・倫理的な問題

私は某自治体で働く精神保健福祉士・社会福祉士です。現場経験はおよそ13年です。
精神保健福祉士の実習、ほんとうにおつかれさまです。
わたしの経験上、実習生は職員よりも辛いです。
だって、実習生は
- 初めての場所
- 初めての人
- 初めての情報
こうした環境に1人だけで放り込まれるから。
職員のほうは慣れているから平気なんですね。
もしかしたらあなたは、
- あと数日で終わるけど、もう辞めてしまいたい
- もう精神保健福祉士は諦めようかな・・・
- 実習に落ちたに違いない・・・
このように思っているかもしれません。
ぶっちゃけ、実習でいちばん辛いのは人間関係だと思うんですね。
わたしが言うとブーメランになっちゃうけど、福祉現場にはクセ者がゴロゴロいます。
実習が始まるまでは「メンタルの辛さをあつかう仕事をしている人たちなのだから、優しい人が多いはず・・・」と思っていたら、
現実はぜんぜん違っていて、度肝を抜かれたかもしれません。わたしも経験しました。
そうしたあなたへ、精神保健福祉士実習のよくある話や対策をお伝えします。
一息ついていってくださいね!
精神保健福祉士実習が辛い!あるある話TOP4と対策【経験者が解説】
【大前提】実習生は職員より辛い!
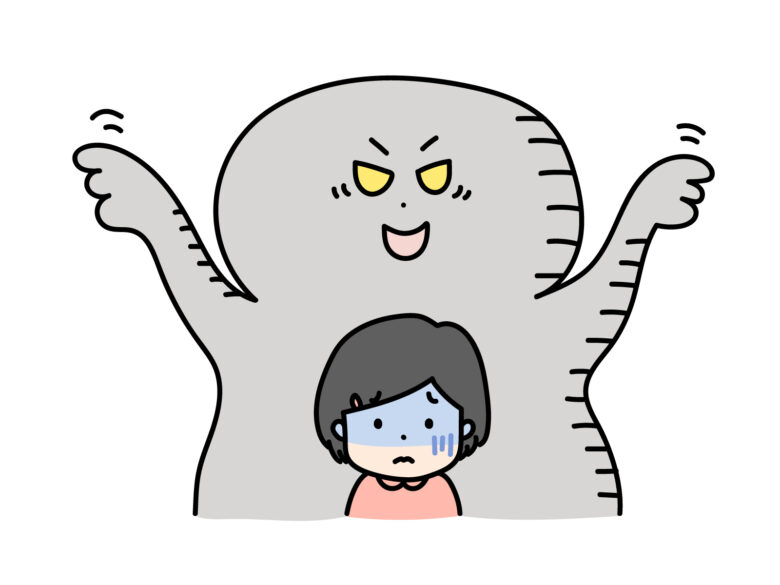
そもそも、職員より実習生のほうが辛いです。ほんとに。
だって、職員は慣れた環境・人・情報の中にいるから。
それに『職員』という役割があるので、患者・利用者さんへ『支援のため』として関わる理由があります。
つまり、話すネタがあるんです。患者・利用者さん側も、職員と話さないと困ったり、不利益になったりしかねないので、しっかり答える傾向です。
では、実習生の立場はどうでしょう?
あなたは知らない場所、知らない人間関係で、新しい知識をインプットしないといけません。
これだけでも疲れ切ってしまうのに、そのうえ実習指導者から

もっと関わるように。話さないと実習になりませんよ。
などと、だめ出しされることがあるでしょう。
実はこれ、すごく無茶なオーダーなんですよね・・・。
だって、実習生は自分の学びのために関わらないといけません。支援じゃないから、目的地もない。
誰と何をどんな意図で話すのか?何をするにも立場が中途ハンパで答えを見出しにくいんです。
自然に話すネタがないんで、相手のことを尋ねたり、自分の話をしたり、一緒に何かをしたり・・・と試行錯誤するしかないんですよね。
でも患者・利用者さんとしては、初めて会うあなたと話すのはエネルギーがいるし、「この人に話をしてもなぁ・・・」という気持ちだったりがあるわけで。消極的になりがち。
なのでどうしても、『職員↔患者・利用者さん』のような関係にはなれません。
そうした特殊環境。うまくいかなくて当たり前です。
あなたはせっかくやる気できたのに、なかなかうまくいかなかったり、職員から注意されたり、腹が立ったり、不安になったりしているかもしれません。
おまけに他にも実習生が来ていて、しかもそいつがうまく関わっているように見えたりして・・・
自分と比べて「私はできないんだ・・・」と自信をなくしているかもしれません。
でもね。気にしなくて良いんです。
実習現場では、『社交的っぽいヤツが優秀そうに見える』のがあるあるなんですけど、それは錯覚。
実は『興味本位で関わっているだけ』ということが多いです。
精神保健福祉士になるには、それじゃイマイチなんですよね。
なので、もしあなたが「コミュニケーションがうまくできない」「何を話したら良いかわからない」と悩んでいても、ぜんぜん大丈夫です!
『悩める』は精神保健福祉士に必要な素質です。答えのない人生や生き方を支援するからですね。
将来的な可能性を秘めているのは、反省したり内省したりできる人のほうです。
これは、わたしが人材育成をしてきた経験上、確信していることです。

ボクは陰キャだしコミュ障だから、精神保健福祉士に向いてないんじゃないかな・・・
もしあなたにこのような悩みがあるのなら、こちらの記事が答えになるはず。『キャリアガーデン』へ寄稿した記事です。
≫「人が苦手」「話すのが苦手」でも社会福祉士・精神保健福祉士は大丈夫?
利用者・患者さんとの関わりが辛い!

利用者さんや患者さんとの関わりが辛い。
そもそも、精神疾患や精神障害のある方は、人との関係がうまくいかない人が多いです。
そうした方々と関わるのだから、当然あなたともうまくいきにくいし、辛くなりがちです。
たとえば、次のようなことがありませんか?
- 声をかけても返事がない・・・ 怒らせてしまった?
- 笑顔がなくて関わりづらい・・・
- ハイテンションで話し続ける人がいるけど、きいていて良いのかな・・・
こうなる理由を、あなたが『できていない』とか『向いていない』と決めつけることなかれ。
そもそも相手がそういう人だったり、精神疾患が影響していたりするので。
もちろんあなたが戸惑うのはあたり前だし、それで順調です!
一言で『精神疾患』『精神障害』といっても、いろんな病気の方がいます。
- うつ病
- 躁うつ病
- 統合失調症
- パニック障害
- 不安障害 など
今の利用者・患者さんのありようが、病気などによるものなのか?
性格その他の影響なのか?
これを判別するのは、けっこう難しいです。
あるていど経験値のあるわたしでも、その利用者・患者さんの病気や障害の情報を何も知らなければ、戸惑います。
なので仕事では、事前に情報収集して人物像のイメージをつくってから会うようにしています。
でも、実習生のあなたは『出たとこ勝負』にならざるを得ないでしょう。
職員からは何も教えられず、「とりあえず関わって」「ふつうに話したら良いんだよ」と言われ、患者・利用者さんの前にほうりだされると思います。
学生当時のわたしは「普通って何!?」とたいへん戸惑いました。
今の私は、「どうなってもらうと良いか」「どうなりたいと思っている人か」から逆算して「どう関わると良いか」を考えるようにしています。
対策1:患者・利用者さんが実習先を利用している目的がヒント
「どうなってもらうと良いか」「どうなりたいと思っている人か」のヒントは、その方が実習先を利用(受診や入院)するに至った理由にあります。
おすすめは、実習担当に「昔の記録や経過を見せていただいてもよろしいですか?」とお願いしてみること。
積極性としても評価されるはず。
もし「そんなことより関わって!」と返事がかえってきたら、残念なタイプの職員・実習担当だと諦めてください(泣)
対策2:『一緒に活動』『一緒に過ごす』というコミュニケーション
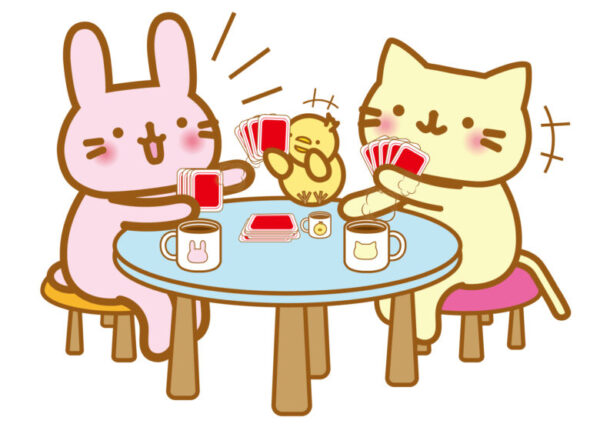
おすすめは、まずは一緒に活動したり、一緒に過ごすなかで、徐々に関係性を近づけていくのです。
相手の波長、ペースに合わせる繊細さが大切なんですね。
例えばのやり方としては
- 一緒のテーブルにすわる
- 一緒にテレビを観る
- 一緒にゲームをする
- 一緒にレクリエーションを楽しむ
- 一緒にご飯をたべる など
『一緒に』がキーワードです。
もちろん、トイレまでついていくとか、やりすぎると気持ち悪がられるので良いあんばいにしておきましょうね!
ポイントは、『言葉のやりとりで関係性を急いでつくろうとしなくても大丈夫』ということ。
『口下手』『コミュニケーションが苦手』という方でも問題ないんですね。
しかし、もしかしたらあなたは実習担当から「たくさん関わるように」と言われているかもしれません。
だからと言ってグイグイと話しかけにいくのは、おすすめしません。
精神疾患・障害のある方とは、『すぐに友達になる』『その日に仲良くなる』みたいな距離の詰め方だと、うまくいかないことが多いからです。
なのでおすすめは、まずは一緒に活動したり、一緒に過ごすなかで、徐々に関係性を近づけていくことです。
1回で距離をつめるのではなく、接触回数(出会ったり関わる機会)を増やして、徐々に近づいていけばいいんです。
ぜひ、『一緒に』を心がけてみてくださいね。
実習担当&職員との人間関係が辛い!

ぶっちゃけ、いちばん辛いのは職員との人間関係ではないでしょうか?
はじめにお伝えしたとおり、福祉現場はくせ者がたくさんいます。
- 感情のアップダウンがはげしい
- 声がバカでかい
- 話がしつこいし、くどい
そのうえ、手厳しい指摘もしてきたり。

もっと話さないといけませんよ!同じ人とばかり話してませんか?

すみません・・・
こんな感じで、注意されるのはよくある話。
実習先にどんな職員がいるのか。こればかりは運ですね・・・。
いじわるな人が多い実習先もあれば、フレンドリーな雰囲気の実習先もあるでしょう。
(実際に働きはじめてからも精神保健福祉士は人間関係によく悩みます)
対策として、こちらの記事で『職員との人間関係』に特化した話をしてあります。社会福祉士向けですが、精神保健福祉士実習でも要は同じです。
≫社会福祉士の実習に役立つ心構えをホンネで語る【指導経験者の裏話】
実習日誌にダメ出しされる&実習日誌が返ってこない!
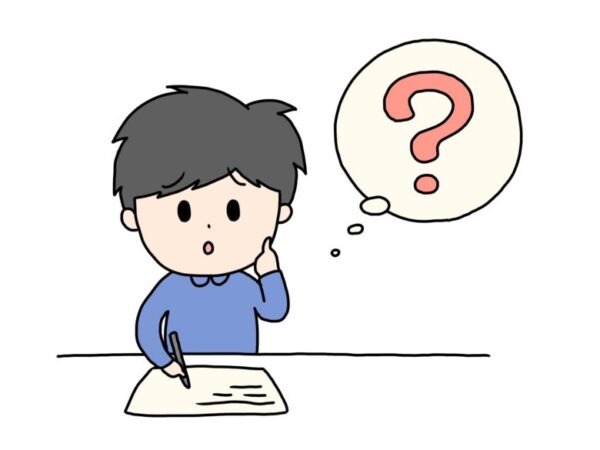

これじゃ感想文ですね・・・。
もっとよく考えて書かないとダメです。

頑張って書いたのに!うるさい!
すみません・・・!
実習日誌を書くポイントは次の2つ。
実習日誌を書くポイント
- 事実
- 事実への考察(あなたが考えたこと・感じたこと・推測など)
例えば、
これは『事実』だけ。
実習担当から「で、あなたの考えは?何が言いたいの?」とつっこまれてしまうかも。
これは『感想文』と言われてしまうでしょう。「びっくりしました」という理由を、もっと詳しく書くことが大切です。
「Aさんは『テレビやネットが自分の情報を勝手に流している。』と話していました。私には信じられませんでしたが、Aさんは深刻そうに話されるので、本当に起きていると感じておられる様子でした。しかしAさんの診断は統合失調症なので、関係妄想かもしれないと思いました。」
これなら『事実』と『考察』をしっかり書けています。
『考察』はあなたの考えや推測なので、正解である必要はありません。

考えっていわれても、思いつかないよ
慣れない作業なので、すぐにはできなくて困ってしまう人もいるでしょう。
そこで、誰もができる対策が次の2つ。
実習日誌の対策
- たくさん書く(書ける欄の90%以上を字で埋める)
- 字をできるだけキレイに書く
この2つをクリアできれば、ダメ出しがゆるむはずです。
なぜなら、やる気・積極性をしめせるから。
考察のでき具合についての評価は、実習担当や職員によって違いがあります。
でも、文字の量や字の丁寧さは「誰が見てもわかりやすい」です。評価がブレにくいのです。
なので、字がたくさん書いてあって、なおかつ丁寧なら「この人なりに頑張ってるんだろうけど、これが限界なんだな・・・」と共感してもらいやすい。
それでも何らかのダメ出しはあるかもしれません。
実習担当の側としては、「私は実習担当なんだから、何か一言は指摘しておかないと指導したことにならない!」と責任を感じていたりするんですね。
なので、どれだけ実習日誌を頑張って書いても、何か言われるのは当たり前です。それで順調なので、あまり気にせずでOKです!
なお、実習日誌の書き方を詳しく知りたい方は、こちらの記事もチェックしてみてくださいね!↓
せっかく頑張って書いた実習日誌なのに、ぜんぜん返ってこないあるある・・・。

せっかく書いたのに!見てもらえてるのかな?
実習最終日にまとめて返ってきたりしますね。ひどい所だと、実習の後日になってから返されるとか。
実習担当者側にたってみると、普段の業務が忙しくて、実習日誌のチェック&コメントにかける余裕がないのかもしれません。
だからと言ってOKという話じゃないんですけどね。
ひどいようなら、実習担当に直接いうと気まずくなるかもしれないので、できれば担当の先生に伝えましょう。
人権・倫理的な問題を感じて辛い

あなたが『精神科病院』で実習をうける時、人権や倫理的な問題を感じて辛くなるかもしれません。
精神疾患や精神障害のある方を置かれる環境や、人からの捉えられ方には、『人として扱われていない』ということがあるからです。
きっとあなたは、『呉秀三』について、講義で聴いたのではないかと思います。
下記の動画は、彼を題材にした映画予告です。精神分野における人権課題が、歴史的につづいてきたことを1分半で理解できるでしょう。
いまの日本でここまでひどい扱いはありませんが、
それでもなお、病気への治療はもう終わっているのに、さまざまな理由で退院できないことがあります。
精神科病院への入院が「刑期無き収容」と揶揄されるわけです。
現在、国を相手取った訴訟が起きています。
あなたの実習先でも、そうした当事者の方々に出会うかもしれません。
職員の方に、どうして彼らが退院できないのか聞いても
- 仕方ないんだよ
- 本人に退院する意欲がないから、自己決定です
- 家族が反対しているから退院できない。家族にも人生がある。
等と、一蹴されるかもしれません。
あなたは憤りや違和感をいだくかもしれません。
でもね、それは意味のあるな辛さです。
差別・偏見・社会的入院といった課題は、当事者の人たちをより一層くるしめています。
あなたが精神保健福祉士としてやっていくとき、解決すべき課題として心に刻めばいいのです。
最後に ほんとうに、ほんとうにお疲れさまです!

実習、ほんとうにお疲れ様です!
もしかしたらあなたは、「これくらいできてあたり前・・・」と思っているかもしれません。
それができないご自身を、責めておられるかもしれません。
情けなく感じられたり、プライドが傷ついたりしているかもしれません。
でもあなたは、初めての人たちと、初めての場所で、知らない情報に囲まれて、がんばっているのです!
くりかえしますが、職員より実習生のほうが辛いんです。
だから、職員からダメ出しされようが、実習はやりきれたらそれで良いんです。
ぶっちゃけ、成績なんてどうでも良いのです。
精神保健福祉士になってしまえば、成績の良し悪しなんてまったく関係ありません。
ましてや、仕事をするようになってからは、実習の成績のはなしなんて、一切でてきません。
(たぶん、成績なんて忘れてます)
実習はやり切れたら勝ちです!
ダサくても、ヘマしても、怒られても、とにかくやり切る。必ず終わりはやってきます。

・・・もうちょっと頑張ってみようかな

あなたの健闘を祈っています。辛いでしょうけれど、なんとかやりきってくださいね!
関連記事
あなたは実習の『心構え』は万全ですか?精神保健福祉士や社会福祉士の実習に必要な心構えを、ホンネでお伝えします。リアルじゃ言えない話です・・・。
社会福祉士の実習も受けるなら、こちらも役立つでしょう。
精神保健福祉士の国家試験対策
精神保健福祉士の実習って、国試対策や就活と時期がかぶってたりします。つらいですよね・・・。
あなたが「このままだと不安」であれば、こちらの記事も参考にしてもらえるでしょう。
【独学で勉強】
【通信web講座で勉強】

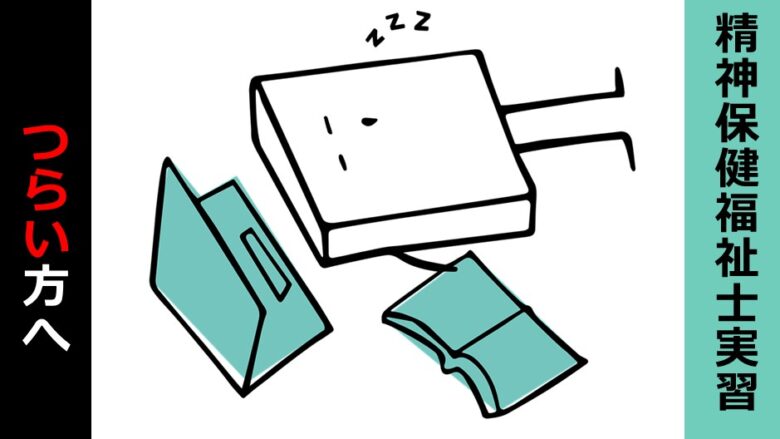






コメント