2025年10月22日、退職代行サービス「退職代行モームリ」をめぐって、警視庁が弁護士法違反の疑いで家宅捜索を行いました。
報道によれば、運営会社アルバトロスは、顧客を弁護士に紹介し、そこからマージンを受け取っていたとされます。
弁護士法72条は、弁護士資格を持たない者が報酬を得て法律事務を行うことを禁じています。
(参考:東洋経済オンライン)
モームリは公式サイトで”当社は(退職意思の)『通知』に徹しているため、違法性は一切ございません”と主張していましたが、警視庁は“違法なあっせん”の疑いがあると判断したようです。
退職代行とは何か──“辞める”を代わりに伝えるサービス
そもそも退職代行とは、「職場に直接言えない退職意思を、代わりに伝えてくれる」サービスです。
雇用契約上は「1ヵ月前の退職申し出」が一般的ですが、実際は口頭でも成立します。
私自身、1回目の転職のときは上司に「辞めます」と口頭で伝えただけでした。
退職届も書かず、口頭で意思表示しただけで手続きが進みました。
ただ、すべての職場がそうスムーズにいくわけではありません。
たとえば、引き止めにあって辞めづらいとか、
そもそも上司と顔を合わせたくないとか。
そういう状況で生まれたのが、この「退職代行サービス」です。
法律的にはグレー、それでも広がる理由
退職代行には、法律上の明確な根拠がありません。
「退職を伝えるだけ」なら誰でもできますが、交渉に踏み込めば弁護士法違反になる可能性があります。
その“あいだ”のグレーゾーンをくぐって成り立ってきたのが、この業界です。
実際、私が以前関わっていた入所施設の職員さんの中にも、
「退職代行を使って辞めた人」がいました。
「福祉業界にも広まってきたのか」と、正直驚きました。
現場で、そうした利用例が広がってきているのを感じます。
利用する価値はあるのか
では、退職代行は「使っていい」ものなのでしょうか。
私の結論は、“状況によっては、十分あり”です。
確かに、法的な裏づけが弱いサービスもあります。
ただし、実際に利用して有給休暇を取得できたり、給与をきちんと受け取れた例もあります。
私自身も、これまでの転職で「有給を残したまま辞めてしまった」ことがありました。
当時は、上司に切り出すのが申し訳なくて言えませんでした。
だからこそ、言いづらさを代わりに引き受けてくれる存在には、一定の価値があると感じます。
「違法」報道=サービスの終わりではない
あくまで現時点の報道内容による推測ですが
今回のモームリの件は、利用者を直接的に害したものではありません。
問題とされたのは運営上の構造(弁護士への紹介・マージン)であって、
サービスの本質部分、つまり「退職意思を伝える」行為自体ではないのです。
したがって、退職代行サービスの価値が一気に失われるわけではありません。
むしろ、こうした事件をきっかけに、業界の透明性が高まり、
利用者にとってより安心できる方向へ進むことも考えられます。
ソーシャルワーカーとして考える、“辞める”ことの支援
「辞めること」も、支援の一つの形になりうると私は思います。
退職は、現在の職場のあり方に問題があることを静かに突きつける、究極の意思表示でもあります。
誰かが辞めなければ、その問題性は見えないまま、組織に埋もれてしまうかもしれません。
だからこそ、誰かが過労や人間関係で心身を壊す前に、私自身が立ち止まることも選択肢。
「私が辞めたら、この人たちが困るから」
――まるで人質を取られているかのように働き続けてしまう。
そんなときこそ、退職代行という手段が“自分を守る選択肢の一つ”としてあることを、知っておいて損はありません。
ただしもし使うなら、今回の報道をふまえ、弁護士が運営しているサービスを選ぶのが安全だと思います。(割高になりますが)
まとめ:グレーでも、“逃げ道”があることは大事
退職代行は、法的にグレーな側面を持ちつつも、
「声を上げにくい人が、自分を守るために使う」現代的なツールです。
今回のニュースを通じて、私たちソーシャルワーカー自身が“辞め方”をどう支えるかを考えるきっかけにもなります。
クライエントが退職を検討している、悩んでいる
――そんな場面に出会うことだってあるのが、ソーシャルワーカーです。
「辞める」という行為は、誰かが”幸せなりたい”と願って進む一歩。
逃げることと決めつけず、次に進むための選択でもあると知っておきたいです。

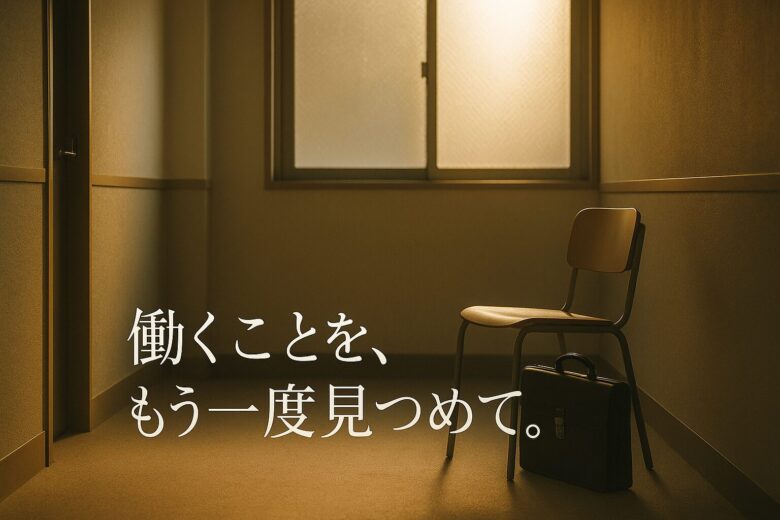


コメント