
偽ベテランってなに?

経験年数はベテランだけど、エラそうにしてるだけで実力ないひと。
福祉の現場って、10年・20年で「ベテラン」って呼ばれる人がいますよね。
常識的には「ベテラン=すごい」「きっと良い支援できる」って思うはず。
でも現実は、年数だけ長くて「オレ流」「ワタシはこれで○○年やってきた!」って言う偽ベテランがうじゃうじゃおられるわけです。しかもタチ悪いことが多い…。
「へえそうなんだ」で流してると危険です!
実際、偽ベテランと同じ職場で働く可能性はけっこう高いと思います。
そう、“福祉現場あるある”なのです。
この記事では偽ベテランの正体と、自分が偽ベテランにならないためのコツを書いておきます。
まずは現場の「年数=実力じゃない」から確認していきます。
この記事が役立つ方
- 福祉現場の経験が浅い方
- 本物のベテランになりたい方(社会福祉士・精神保健福祉士のキャリアを伸ばしたい方)
では、まいりましょう!
年数=実力じゃない、という話【こんな人が偽ベテラン】

福祉の現場では、年数が長い=すごい支援者ではない。ベテランでもない。
私はそう考えます。
むしろ、経験年数が高まるにつれて、油断しているとプライドが高く、意見が強くて厄介になりがち。
独自の経験則で指示したり、「私が一番知ってるのよ!」とマウンティングしたりする。
この記事では、こうした振る舞いをする年数頼みの支援者を「偽ベテラン」と呼んでいます。

年功序列の現場だと、偽ベテランでも役職がついてることが多くて、誰も意見できない空気ある…。
このブログは利害関係ないのでハッキリ言わせてもらいます。
年数だけの偽ベテランは、支援者というより“加害者性”が強い。
利用者・患者さんや周りのスタッフに不利益が出やすいです。
偽ベテランの見分けポイントは、次の3つです。
偽ベテランの見分けポイントはこの3つ
- 専門的な知識があるか?(アップデートしてるか?)
- 実行力があるか?(言うだけじゃなく現場で動けてるか?)
- めざす価値がクライエント本位か?
偽ベテランのパターン①:経験だけ積んで「オレ流」一直線
たとえば、こんな感じ。
- 「オレは長年この方法でやってきたんだ!お前に何がわかる?」
- 「専門書とか理論なんか、現場では使い物にならんぞ!」
知識や技術のアップデートを放棄してて、自己本位に流れがち。
我流が通じない利用者・患者には、すぐサジを投げる。
例えば、「もう頭がおかしいから、入院したほうが本人のためになる」とか言う。極端にいうと、そういう考えになる。
ほんとは自分の支援を振り返るのが怖いんですよね。だって、「今までの何十年を反省する」みたいに感じてしまうから。直視しきれない。
で、自分を守るために、利用者・患者・同僚のせいにする。これが“加害者性が強い”と言う理由です。
偽ベテランのパターン②:知識はあるのに動けない、口だけ“評論家”

知識だけじゃだめ?
知識だけでは現場に落とし込めず、実行できないです。
例えば、会議でたくさん正論は言うんだけど、実際にはできていない人がいませんか?自分ができていないことを棚に上げてしまっている人も、いるかもしれません。
周りからは「言ってることは正しいんだけど、行動が伴ってない人」に見えます。
これは、客観的な振り返り(事実→解釈→次の一手)が回ってないパターンが多いです。
新人に「絶対的に足りない」のは経験。でも武器はある
就職したての新人は、どうしても知識にかたよりがち。でも、落ち込む必要はありません。
新人にはちゃんと武器があります。ここを押さえれば、いわゆる“偽ベテラン”にはなりません。
新人の強み2つ
- 知識の鮮度が高い
学びたての内容は、頭に残っていてすぐ取り出しやすい。国家試験で培った基礎も、現場での仮説づくりに直結します。 - 価値がまだ廃れていない(感覚が鈍っていない)
現場の「慣れ」に染まりきっていないから、おかしいことをおかしいと言える。ここは新人の大きな強みです。
「経験不足で先輩にかなわない…」と気落ちする必要はなし。鮮度×感度は立派な武器です。
具体例:その“違和感”は大事なセンサー
- 精神科病院の閉鎖病棟で、保護室にいる患者さんを見て抱く違和感。その感覚は、人権の視点につながる大切なスタートです。
- 介護現場で「家に帰りたい」と訴える利用者さん。慣れている職員は流してしまうこともありますが、新人なら一大事として耳を傾ける――その姿勢が支援を前に進めることがあります。
- 利用者からの暴力・暴言に耐えるスタッフを見たとき、「それはおかしくないか?」と感じられる普通の感覚。現場慣れしていないからこそ、当たり前にしないで立ち止まれる。
“普通の感覚”は新人の資産。 現場の前提を疑い、言葉にすることで、チームに新しい視点を持ち込めるんですね。(これって、新人に限らず、実習生の強みでもあります)
鮮度の高い知識 × 謙虚さで、吸収率はぐっと上がる
しかし、知識の鮮度だけでは独りよがり、経験だけでも硬直します。
そこで効くのが、謙虚さ。
「すみません、わからないので教えてもらえませんか」――この一言が、学びの速度を一気に上げます。
ここで相手が「そんなことも知らないのか」とバカにしたり、「自分で調べなさい」と断ずるだけの人であれば、偽ベテランの可能性ありです。
残念ながら、その人はあてにしなくて良いでしょう。他の人に聞いてみましょう。
経験は「量 × 質 × 振り返り」で積み上がる
経験は、困り感・悩み・不安・失敗・成功・喜び・楽しさ――ぜんぶ込みです。
学生時代のボランティアやバイトは貴重ですが、社会人の経験とは別物(立場・責任・役割が違う)。
だからこそ、新人のうちは過去の経験を過度に持ち出さないほうが得策。
強く主張すると、ごうまん・根拠ない自信に見えがちです。
むしろ、量(場数)を踏み、質(関わりの深さ)を意識し、振り返り(自己覚知)で回収する――この掛け算が効きます。
だって、「完璧な新人」=伸びしろがない ってこと。
それはもったいない。未完成だからこそ、伸びるんですね。
偽ベテランをしのぐキャリアの積み方

まずは謙虚に経験を積むこと。
「まだまだ経験が足りない」
「まだまだ知らない」
「すみませんが教えてください」
という姿勢を手放さない人は、経験が“質”に変わるスピードが速いです。
逆に、謙遜を失った人の末路が、だいたい“偽ベテラン”。
知識のアップデートが止まり、他者から学ばなくなった瞬間に、感覚は鈍り、支援は独りよがりになります。
ですから、次が偽ベテランにならずに成長するキャリアの積み方と考えます。
偽ベテランにならずに成長するキャリアの積み方
- 鮮度の高い知識 を遠慮なく使う
- 普通の感覚(価値)を大事にし、違和感を言葉にする
- 謙虚さ で学びの回収率を上げる
- 量×質×振り返り で経験をまっとうに積み上げる
何より大事なもの:めざす「価値」
そして、経験・知識・実行力を正しい方向(クライエントの利益のため)へ導くのが、価値(羅針盤)です。
中でも価値は、知識と技術をどの方向に使うかの道しるべです。最重要といっても過言ではない。
だから、次のことをチェックしながら支援することが大切です。
チェックポイント
- 自分のために悪用してないか?
- クライエントの利益になってるか?
- 組織のためだけになってないか?
- 興味本位で関わっていないか?
私たちは知識や技術が上がるほど、人に与える影響も大きくなる。実際、ある程度は人をあやつったり、コントロールすることもできてしまいます。
だから、価値をもたない(間違っている)支援者は、加害者性が強い存在になりえます。
価値をもたない=偽ベテランの代表、これ忘れないでください。
まとめ:本物のベテランになるために
最初はみんな、夢や希望を持って社会福祉士や精神保健福祉士の仕事を選んだはず。
でも、働きだすと本物ベテランと偽ベテランの分かれ道が始まる。
偽ベテランに堕ちるプロセスは地味です。
偽ベテランに堕ちるプロセス
- 知識のアップデート…面倒
- 他にしたいことがあって後回し
- 実行するのが怖い・面倒
- 目標や理想をあきらめた
- デキてない自分を直視するのが怖い(他責化)
「オレはできてる」「私はできてる」にしがみついて、うまくいかない理由を利用者・家族・同僚・職場のせいにし続ける…。なれの果てが偽ベテランです。
では、本物のベテランになるにはどうしたら良いか?大切なことはシンプルです。
「まだまだ経験が足りない」「まだまだ知らない」「すみませんが教えてください」という姿勢を手放さない人は、経験が“質”に変わるスピードが速いです。
謙虚に経験を積むスタンスこそ、偽ベテランをしのぐキャリアの積み方でしょう。
めざす価値を失わず、研ぎ澄ましながら、経験・知識・実行力を謙虚に積み上げた先に、本物のベテランがある。
私はそう考えます。
もちろん、はりきりすぎず、のんびりコツコツでOK。社会福祉士・精神保健福祉士、福祉職の仕事は精神労働。余裕は極限まで食いつぶされます。
だから、中断があっても、ひと休みがあっても大丈夫。しかし継続すること。私もそんな感じです。
ずいぶんと偉そうに申し上げてきましたが、私もベテランに向けて修行中なのです。私こそ「評論家」にならないように、いっそう気を付けていきます。
一緒にやっていきましょう。それではまた!
関連記事
新人の方や学生の方に向けた私からの5つの指南書です。リアルを盛り込んだ、現実的な話です。知っておいて損はないです。
偽ベテランにならないために絶対に必要なのが、自己覚知です。この記事では、教科書的にならず、私のような現場の人間目線で重要性ややり方を書いてあります。

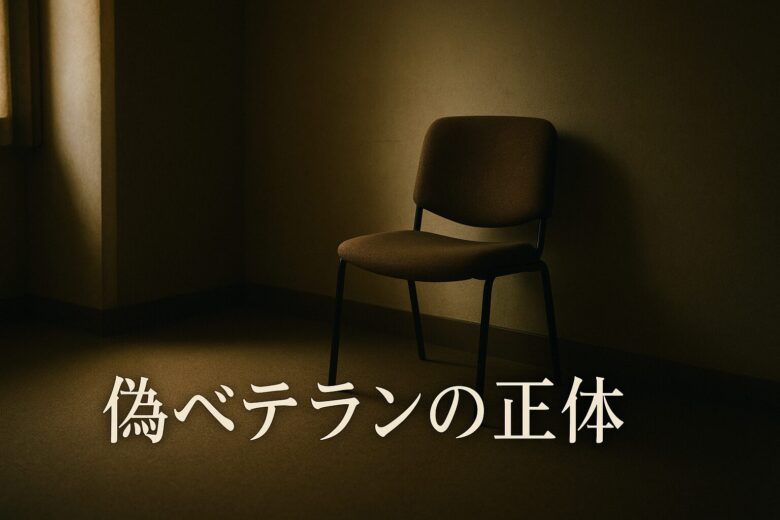
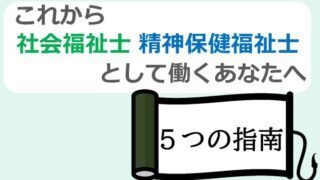

コメント