
児童福祉司が学校と連携するときに知っておいたほうがいいことって何?
こうした疑問のある方へ。

わたしは社会福祉士・精神保健福祉士で、現場経験は10年以上です。児童相談所で児童福祉司をしていた経験があります。
児童相談所で児童福祉司として働いていると、いろいろな人から通告を受けることがあります。
通告者は緊張していたり切迫していることが多いです。すると私たちも、焦ったり混乱したりしがちです。
そうなるとケアミスが起きたり、相手の人に不満や不安を感じさせてしまったりすることがあります。
それを防ぐためには、通告を受ける前に「相手の人はどんなルールに従って通告しているのか(しなければならないのか)」を知っておくといいです。
そうすれば、冷静に対応できますし、余計な衝突も減らせます。
よく通告してくる人の中には、学校や教育委員会の人がいます。教育サイドでは、児童虐待にどう向き合っているのでしょうか?
それを知る方法の一つが『学校・教育委員会等向け虐待対応の手引き』を読むことです。
児童福祉司は必見!学校・教育委員会との連携をスムーズにする手引き

児童福祉司にとって『学校・教育委員会等向け虐待対応の手引き』は必見です。
この手引きは、文部科学省が学校や教育委員会などに出した虐待対応の説明書みたいなものです。
しっかりした学校(特に校長先生や教頭先生)や教育委員会は、この手引きに沿って対応しています。
『学校・教育委員会等向け虐待対応の手引き』は3種類ある
『学校・教育委員会等向け虐待対応の手引き』は3種類あります。
内容は同じですが、長さが違います。
「忙しくて読んでられない!」という人は概要版だけでも読んでおいてください!1ページだけですから。
児童福祉司として『学校・教育委員会等向け虐待対応の手引き』を使う方法
学校からの通告は、通告と言わずに”相談”と言って話してくることが多いですね。
「通告すると親にバレてしまうかもしれません」「通告するほどではないと思います」と言ってためらう方もいます。
でも、手引きでは虐待されているかもしれない子どもについて、市町村(虐待対応担当課)や児童相談所などに通告することは義務だと書いてあります。
そして、通告するときの注意点では「親との関係よりも子どもの安全を優先すること」と書いてありますから、
ためらう先生がいたら、「勇気を出して対応して下さい」と強く助言することができます。
また、親と向き合う覚悟を持って通告したのに、「本当に正しかったのかな?」と不安になる学校の先生もいます。
そうした先生には、「子どものために正しいことをしてくださった」と声をかけるのも児童福祉司の務めですね。
ちなみに、学校や教育委員会が児童相談所に直接通告するのは次の4つの場合です。
児童相談所に直接通告する場合
- 明らかな外傷(打撲傷、あざ(内出血)、骨折、刺傷、やけどなど)があり、身体的虐待が疑われる場合
- 生命、身体の安全に関わるネグレクトがあると疑われる場合
- 性的虐待が疑われる場合
- 子供が帰りたくないと言った場合(子供自身が保護・救済を求めている場合)
身体的虐待やネグレクトについては、どれくらいひどいかで児童相談所へ通告するか決めますが、
性的虐待については、疑いだけでも児童相談所へ直接通告することになっています。
あと、学校からの通告でよく聞くのは「子どもが家に帰りたくないと言っています」ということですが、これも児相へ直接通告する場合の一つとなっています。
最後に
児童相談所で働く児童福祉司のあるある話ですが、
他の人や機関と話すときに「なんでそうしてくれないんだ!?」「どうしてこんなことを言ってくるんだ!」とイライラすることがあります。
ひどくなると対立してしまって、支援がうまくできなくなることもあります。これは避けたいですよね。
子どもを救いたい気持ちは同じなのに、仲が悪くなるなんて、残念です。
それを防ぐためには、例えば他の人や機関の役割や義務・指針などを知ることです。
私たちが他の人や機関の対応に不満を持つ時は、相手の立場やルールをよく知らないことが多いです。(これは児童相談所だけでなく、福祉現場全体で言えることです。)
相手の人や機関の義務や役割を知れば、余計なトラブルを減らせます。
今回は一つの例として、『学校・教育委員委員会等向け虐待対応の手引き』を紹介しました。
手引きを読めば、学校や教育委員会の考え方がわかるようになって、スムーズに協力できるし、落ち着いた対応がしやすくなると思います。
児童福祉司は大変な仕事で忙しいです。
やらなければならないことはたくさんありますが、できることから少しずつやっていきましょう!
以上、児童福祉司は必見!学校・教育委員会との連携をスムーズにする手引きという話でした!
関連記事コーナー
以下の記事は、児童福祉司1年目の方が自分で支援を組み立てられない悩みに対して、私がアドバイスした内容です。
例えば、支援の選択肢や方向性は、知識や経験から生まれるもので、思い付きやセンスではないこと。知識や経験を増やすには、本を読んだり、先輩のやり方を真似たりすることが有効という話をしています。
以下の記事は、児童福祉司になったものの不安に感じている読者さんに、私が自分の経験やアドバイスをした内容です。要約すると以下のようになります。
- メンタルを保つためには、運動や睡眠、趣味などの習慣が大切
- 仕事上のモチベーションを高めるためには、手引きやガイドライン、研修などの資料や法律知識を活用することが有効
- どうしても続けられない時は、休職や転職も選択肢の一つと考えても良い
詳しくは記事に書いてあります↓

今回はここまでです!読んでいただきありがとうございました!またね。

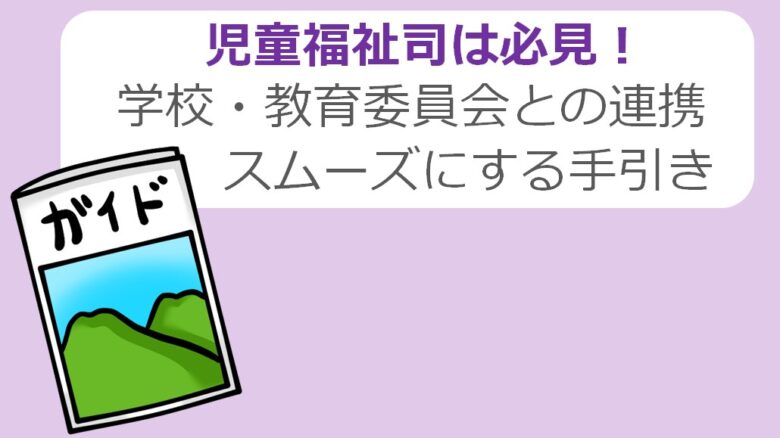


コメント