今の私の感覚とは少し違いますが、人の気持ちは移り変わるものです。
当時の私の考えや感情のほうが、誰かに届くかもしれないと思い、校正して公開しました。
「自分は社会福祉士に向いていないんじゃないか」
「精神保健福祉士を続ける資格がないのでは」
現場で働くうちに、そう感じたことがある人は多いと思います。
私自身、何度も何度もこの思いに飲み込まれた一人です。
社会福祉士・精神保健福祉士に”向いていない”と感じた原点
福祉の仕事を私が始めたのは、大学を卒業してから。
勉強は得意な方でした。
社会福祉士・精神保健福祉士をダブル受験し、一発合格できました。
しかし、現場では通用しませんでした。
「勉強ができる」と「支援ができる」は、別の力。
頭で理解していても、実際に人と関わるとうまくいかなかったのです。
現場では、人の柔らかさ・タイミングの感覚・郷に入りては郷に従え――
そうした“人間的な力”のほうがよほど求められた。
それを思い知らされてから、自信は一気に崩れました。
失敗の連続と、「向いていない」という自己否定
仕事では失敗が続きました。
ある時、上司(医師)からこう言われたことがあります。
「お前が担当になってから、あの患者の病状が悪くなった」
別のケースでは、私が外れた途端に患者さんが落ち着いた。
その事実が頭から離れませんでした。
「自分が関わるとかえって悪化させてしまうのでは…」
そう考え始めると、“自分の存在そのものが迷惑”に思えてくる。
これが「向いていない」という悩みの正体でした。
それでも辞めなかった理由

それでも私は、この仕事を辞めませんでした。
理由は単純で、他にやりたいことがなかったからです。すごく後ろ向きですよね。
もう一つは、音楽の道を諦めてまで選んだこの仕事を、
「また途中で投げ出したくない」という意地がありました。
正直、仕事が“楽しい”と思ったことはほとんどありません。
でも、人を支援する中で自分が助けられる瞬間が、確かにありました。
面白みはあっても、楽しさではない。
それでも、「続けよう」と思える瞬間があったのです。
支えになったのは“人”だった
私を支えてくれたのは、人でした。
職場の同僚、先輩、後輩、大学の先生――
特定の誰かではない。
みんなが、少しずつ私を支えてくれた。
支援職は、人とのつながりでしか立ち上がれない仕事だと感じます。
優れた実践者も、孤立して成果を出しているわけではない。
いつも、志を共有する仲間がいる。
そう考えると、
「向いていない」という気持ちを氷解するのに必要なのは、
完璧さではなく、つながりと志なんだと思います。
「向いていない」という問い自体が、苦しみを深める
そもそも私は、
「向いている・向いていない」という問いがあまり好きではありません。
(それなのに、よく考えてしまうのだけど)
なぜなら、それは
“自分にはできない”と決めつける言葉だからです。
「向いていない」と言った瞬間、
努力する理由を自分から奪ってしまいます。
「どうせ無理だから」と、工夫も挑戦もしなくなる。
でも、本当に“努力も工夫もして、それでもダメ”だったか。
何かを続けるには、根性だけでは足りないけれど、根性が必要です。
工夫と支えと、少しの希望。
それさえあれば、仕事はもう少しだけ続けられそうです。
おわりに ― それでも続けてきたあなたへ
向いていないと感じるのは、
きっと、あなたが本気でこの仕事に向き合っている証拠です。
悩みながらも現場に立ち続けているなら、
それだけで十分、福祉の実践者だと私は思います。
私の悩みが、あなたと通ずるものであれば。
役立つものがあったなら。
私が悩んできたことに、意味が与えられます。
ここまで読んでくださって、ありがとうございました。
関連記事
「向いていない」「向いている」
当サイトでは、こうした思いに悩む方へ向けて、他にも記事を書いてあります。
こちらに載せておきます。
こちらは、キャリアガーデンへ寄稿した記事です。

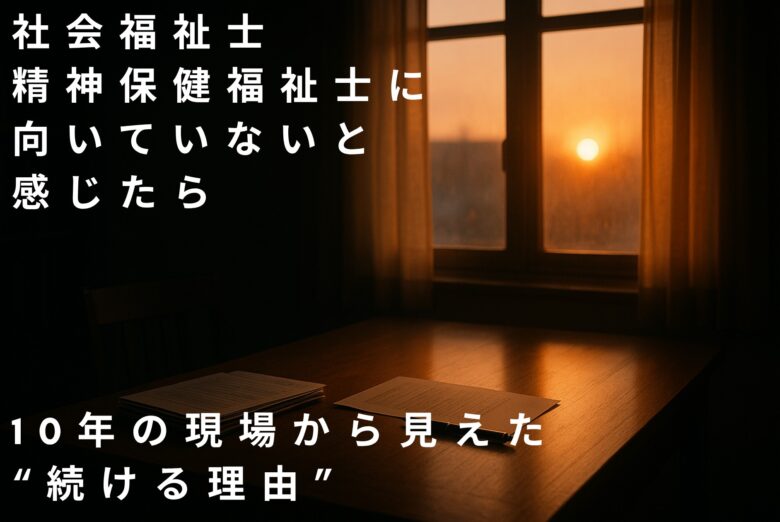






コメント