
AIで社会福祉士や精神保健福祉士の仕事は奪われる?これからどうしたらいいんだろう?
この記事の内容
- 関係性を築くには「記憶」が不可欠
- ChatGPTなどのAIは記憶機能を通じて関係性を錯覚させる
- 福祉の現場でも、AIはすでに影響を与え始めている
- AIは脅威ではなく補助ツールであり、理解し活用する姿勢が必要
近年、ChatGPTをはじめとする生成AIの進化が注目を集めています。
では、社会福祉士や精神保健福祉士といった相談支援の専門職にとって、AIはどのような存在となるでしょうか?
特に相談支援に欠かせない「記憶」と「関係性」という視点から考えてみます。
社会福祉士・精神保健福祉士の相談支援における「記憶」と「関係性」
相談支援において「関係性を作ることが大事」とよく言われます。実際、それは間違いなく大切です。
では、この「関係性」は一体何で成り立っていて、どうやって築かれていくのでしょうか。
私も全容を語れるほどの知識を持っているわけではありませんが、ひとつ確信しているのは 「記憶」こそが関係性の土台になる ということです。
人はお互いを覚えているからこそ、関係が積み重なります。
良い関係も悪い関係も、過去の出来事を記憶しているから成立するのです。
例えば、認知症が進行して記憶が失われてしまうと、関係性そのものが途切れてしまうことがあります。
「あんた誰?」――忘れられた側が強いショックを受けるのは、まさに関係性が失われた瞬間だからでしょう。これは近い関係にあった家族ほど、大きくなります。
ChatGPTとAIがもつ「記憶機能」

では近年急速に進化している生成AI、たとえばChatGPTはどうでしょうか。
ChatGPTは会話の形式で話した内容を「記憶」し、それを踏まえて返答することができます。
たとえば私が健康診断の数値を伝え、改善策を相談したとします。
後日、サプリメントについて質問すると、「あなたは以前この数値が高かったので服用には注意が必要です」と返ってくる。これはまさに記憶の働きです。
その瞬間、私は「覚えていてくれた」と感じ、そこに“人格めいたもの”や“関係性”を錯覚しました。
AIが記憶をもとに返答することで、人間に似た関わりが生まれるのです。
ソーシャルワーカーと「記憶」
私たちソーシャルワーカーも、クライエントの個別性を大切にし、記憶を重ねていきます。
面接や電話で聞いたことを覚えているからこそ、誠実な対応ができるし、相手も一から説明する手間を省けます。
逆に「覚えてもらえていない」と感じさせてしまえば、
- この人は関心をもってくれていない
- 相談しても意味がない
- 疲れるから他の人がいい
と受け止められてしまうでしょう。
つまり、記憶は支援の信頼をつくる基盤なのです。
AIは社会福祉士・精神保健福祉士を代替できるのか?
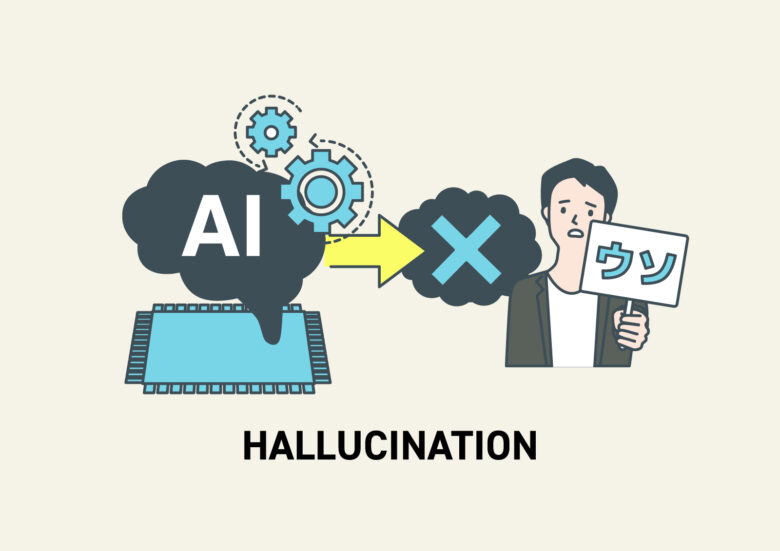
もちろん現状のChatGPTは完璧ではありません。
エラーや誤答も多くあります。しかも、自信満々に誤った回答をされるので、こちらに知識がないと嘘は見抜けない。
まだまだ支援現場でそのまま使えるレベルには達していません。
しかし、記憶の精度が上がり、情報を適切に出し入れできるようになれば、人はAIに“関係性”を錯覚するようになるかもしれません。
そうなれば、「AI相談支援サービス」や「AI相談ロボット」が登場するのは自然な流れでしょう。実際、次のようなニュースもあります。
「死にたい」「消えたい」気持ちが抑えられなくなったときの子どもの相談先で、最も多いのは生成AI――。子どもの自殺対策などに取り組むNPO法人「自殺対策支援センターライフリンク」が8月27日に公表した、「しんどい」気持ちを抱える18歳以下の子どもを対象としたアンケート調査の結果から、このような姿が浮かび上がった。
出典:教育新聞 2025-08-27
これは衝撃的な事実であり、すでにAIが“相談相手”として利用されている現実を示しています。
社会福祉士・精神保健福祉士に求められる役割は
生成AIは、まだ十分に社会に浸透しているとは言えません。しかし確実に、社会福祉士や精神保健福祉士を含む福祉の仕事に影響を与え始めています。
大切なのは「AIに置き換わるかどうか」ではなく、「どのような影響を受け、どう活用していくか」を理解することです。
そのためには、まず自分自身がAIを触り、試し、活用してみることが第一歩となります。
近い将来、クライエントから「相談はAIにしましたから、あなたには実際のサービス提供だけお願いします」と言われる日が来るかもしれません。
だからこそ、AIにはできないことを見極め、人間にしかできない関わり方を磨いていく必要があるのです。
同時に、私たちが守るべきは自分たちの立場や既得権益ではなく、あくまでクライエントの利益です。
場合によっては、ソーシャルワーカーの役割が縮小したり、退いていく未来も考えなければなりません。
医療の究極の目標が「病気をなくすこと=医療が不要になること」であるように、私たち福祉職の究極の目標も「支援が必要ない社会をつくること」にあると言えるでしょう。
もっとも、現実にはまだその時代は遠いようです。
例えば、文部科学省の速報値によると、通信制高校に通う生徒数は2025年度に初めて30万人を超え、過去最多を更新しました。 高校生全体に占める割合は9.6%、約10人に1人に上ります。
その背景を受け、文科省はスクールソーシャルワーカーの配置を充実させる等の方針を示しています。
≫出典:福祉新聞WEB 通信制高校生30万人 不登校の広がり背景に急増〈文科省〉
スクールソーシャルワーカーになる筆頭の資格職は、社会福祉士や精神保健福祉士であり、我々への期待は高まっています。
また、2020年には精神保健福祉士の略称がPSWからMHSWへと改められました。これも社会の変化や役割の拡大を踏まえたものです。
≫過去記事:精神保健福祉士の略称がPSWからMHSWに変わった理由|現役解説
急速に発展するテクノロジーのなかで、社会は大きく変化しています。
その流れの中で、社会福祉士や精神保健福祉士に求められる役割やスキルも変わり続けていくのは間違いありません。
まとめ
この記事のまとめ
- 関係性を築くには「記憶」が不可欠
- ChatGPTなどのAIは記憶機能を通じて関係性を錯覚させる
- 福祉の現場でも、AIはすでに影響を与え始めている
- AIは脅威ではなく補助ツールであり、理解し活用する姿勢が必要
社会福祉士や精神保健福祉士、ソーシャルワーカーにとって、AIは避けて通れない存在です。
だからこそ、まずは自ら触れ、学び、活用することが出発点になるのではないでしょうか。



コメント