
社会福祉士はどうやって仕事を探しているの?コネがないと無理かな?
- 社会福祉士の仕事はどうやって探したいい?
- いい職場に就職したいけど、見つけ方がわからない。
- 就職・転職活動で失敗したくない。
- 給料が低すぎる。いい求人はどこにある?

私は某自治体で働く社会福祉士・精神保健福祉士です。転職を2回した経験があります。
社会福祉士は、働く職場によって、日々の苦労も、給料も、人間関係も変わります。
それは、長期的にはメンタルヘルスやキャリアにも影響します。
就職・転職活動は、あなたの人生を決定する分岐点と言えるでしょう。
では、どうやって仕事を探したらいいのでしょうか?
正解はありませんが、社会福祉士が仕事を見つけた方法を調べた統計調査があります。
その結果によると、社会福祉士の就職・転職方法は多種多様。
「みんな、この方法で探しているよ」という方法はありませんでした。一番メジャーな方法でも、わずか20%程度です。
この記事は、公益財団法人社会福祉振興・試験センターが行った調査結果を、ランキングにしたものです。調査回答者の数は、全社会福祉士の約40%(約10万人)で信頼度が高いです。
≫参考:令和2年度 社会福祉士就労状況調査結果報告書)
先輩達の足跡は、あなたの就職・転職活動の道しるべとなるはず。あなたに合った道を選びましょう!
社会福祉士の仕事の探し方・就職&転職方法ランキングTOP10【統計調査より】

ではまず、ランキング結果です。
| 順位 | 方法 | 割合 |
| 1位 | 友人・知人からの紹介 | 21.6% |
| 2位 | ハローワークの無料職業紹介 | 18.7% |
| 3位 | その他 | 16.7% |
| 4位 | 民間の職業紹介、就職情報誌、求人チラシ、求人情報サイト等 ≫経験者が選ぶ!社会福祉士おすすめ転職サイト・転職エージェント3つ | 13.4% |
| 5位 | 学校・養成施設等での進路指導 | 10.9% |
| 6位 | 法人・会社の求人(就職説明会等) | 9.3% |
| 7位 | 行政広報誌(区報・市報等) | 7.6% |
| 8位 | 実習・施設見学・ボランティア | 5.5% |
| 9位 | 福祉人材センターの無料職業紹介 | 4.9% |
| 10位 | 前の職場からの紹介 | 3.2% |
以下、それぞれ解説していきます。
10位 前の職場からの紹介 3.2%

前の職場から紹介してもらって転職したということですね。
どうして前の職場が紹介してくれたのか?いろんな理由があると思います。
たとえば、職場がなくなったり、期間が終わったり、定年になったりしたときに、別のところに行けるようにしてくれたとか。
前の職場とつながりのあるところだったとかも考えられますね。
9位 福祉人材センターの無料職業紹介 4.9%
福祉人材センターは、福祉の仕事を探す人のためのハローワークみたいなところで、社会福祉協議会がやっています。
「社会福祉協議会なら営利目的じゃないから安心」と感じる人もいるでしょう。
福祉人材センターでは、仕事や事業所を探したり、相談したりできます。一度見てみると、いいところが見つかるかもしれません。
ちなみに、社会福祉協議会は社会福祉士に人気の職場です。公務員ではないですが、待遇や給料は公務員レベルです。詳しくはこちらの記事で説明しています。
8位 実習・施設見学・ボランティア 5.5%
実習先、見学先、ボランティア先に行ったときに「うちで働いてみない?」と声をかけられることは、けっこう聞く話です。
私としては、実習やボランティアからの就職はおすすめです。
一回の面接試験だけでは、相手のことを表面的にしかわかれません。お互いに良いところの見せあいっこです。
だから、あえて心理的に負荷をかけて本性を暴こうとする(?)圧迫面接なるものが横行するのです。それでも、よく理解するのは難しいです。
でも、実習やボランティアでしばらく一緒にいると、お互いに普段どんな感じかがわかります。
例えば人間関係や仕事内容の本当のところがわかりますし、職場の「隠したい部分」まで知ることができます。
すると、「ここなら働いても大丈夫だな」「ここでは働きたくない!」って決めやすいですね。
職場側も「この人と一緒に働きたいな」「この人ならうちで頑張れそう」と思ってくれます。逆に「この人は合わないだろうな・・・」って判断することもあるでしょう。
ぶっちゃけ、福祉の現場では、賢さより人柄が大事です。ポイントは以下の2つです。
- 職場の人間関係
- クライエント(利用者)との支援関係
社会福祉士は人と関わる仕事ですから、関係がうまくいかないと仕事になりません。
言い方は悪いですが「バカでもいいから、いい人に来てほしい」という現場は多いでしょう。
・・・と言われて「私は人が苦手だから無理だ・・・」と思った人へ向けて、「人が苦手」「話すのが苦手」でも社会福祉士・精神保健福祉士は大丈夫?をキャリアガーデンさんへ寄稿しています。
7位 行政広報誌(区報・市報等) 7.6%

区や市が出している広報誌には、地域の福祉施設や団体の求人情報が載っています。
地元で働きたい人や、小規模な職場を探している人にはおすすめです。
ただし、広報誌に載っている求人は、あまり多くないかもしれません。
また、応募するときには、電話や郵送などの方法が必要になることもあります。インターネットで応募できる求人サイトと比べると、少し手間がかかるかもしれません。

ぼくの家には届いてないかも

大丈夫。インターネットで探せるよ!
あなたの地域の行政広報誌は『全国自治体マイ広報紙リスト』から検索できます。
リンク先から地域名を入力して検索すれば、広報誌が出てくると思います。
掘り出し物の求人募集があるかもしれません。一度チェックしてみてくださいね。
6位 法人・会社の求人(就職説明会等) 9.3%
法人や会社が募集しているところに応募する方法です。
例えば説明会や面接などを通して、採用されることですね。福祉業界で就職説明会といえば、福祉の就職総合フェアが有名です。
「福祉の就職総合フェア」とは、
・福祉や介護にかかわる仕事に就職を希望する方を対象とした合同面接会
・福祉や介護の職場
・仕事内容の説明等を行うセミナー、相談会等のイベント です。
各都道府県の福祉人材センター・バンクが主催、あるいはハローワーク等と共催で開催しています。
引用元:福祉のお仕事HP
この方法のメリットは、自分で職場を選べることです。
自分の希望や条件に合った職場を探すことができます。また、大きな法人や会社であれば、待遇や給料も良い場合があります。
デメリットは、競争率が高いことです。
多くの人が応募する職場もあるでしょう。また、応募するためには、履歴書や職務経歴書などの書類作成や面接対策などの準備が必要です。時間や労力がかかることもあります。
なお、福祉の就職総合フェアのイベント情報は福祉のお仕事で検索できます。
5位 学校・養成施設等での進路指導 10.9%

学校や養成所などで進路の先生に教えてもらう方法です。先生たちが知っている求人情報や紹介先を教えてもらうイメージですね。
この方法のメリットは、信頼できる情報を得られることです。
先生は福祉の現場に詳しいですし、あなたのこともよく知っています。あなたに合った職場を紹介してくれるかもしれません。
デメリットは、選択肢が限られることです。
先生が知っている求人情報や紹介先だけしか選べません。自分で探したり比較したりすることができません。
それと、先生の紹介だと、断りにくいこともあります。自分の意思と違う職場に行くことになるかもしれません。
時には『NO』といえるハートが必要です。
4位 民間の職業紹介、就職情報誌、求人チラシ、求人情報サイト等 13.4%
民間の紹介会社や求人雑誌やチラシやサイトなどを利用する方法です。インターネットで検索したり、電話したり、メールしたりして応募します。
この方法のメリットは、選択肢が多いことです。
たくさんの求人情報がありますし、自分の希望や条件に合わせて絞り込むことができます。また、応募するための手続きも簡単です。インターネットでできることも多いです。
また、誰にでもチャンスがある探し方なので、他の方法が見つからなくても使えます。
デメリットは、たくさんの転職サイトがあって、どのサイトが良いかわからないことです。
そこで、私が調べておすすめをまとめたのがこちらの記事です。
3位 その他 16.7%
その他の方法です。具体的には、以下のような方法が考えられます。
- 新聞や雑誌の求人広告
- ラジオやテレビの求人情報
- SNSやブログなどの口コミ
- セミナーやイベントなどで知った
- 自分から直接問い合わせた
これらの方法は、一般的ではないかもしれませんが、自分に合った職場を見つけるチャンスがあるかもしれません。積極的に情報収集をしてみましょう。
2位 ハローワークの無料職業紹介 18.7%
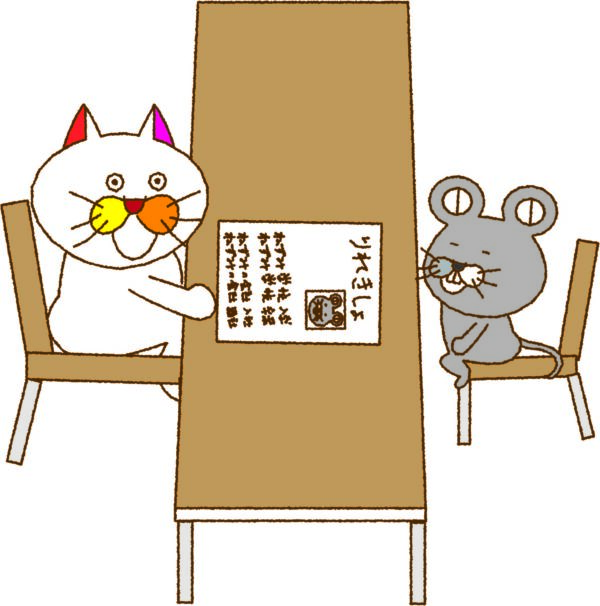
ハローワークは、国が運営する公共の職業紹介所です。インターネットや電話で予約をして、相談員に希望や条件を伝えます。相談員があなたに(たぶん)合った求人情報を探してくれます。
最近はスマホから、ハローワークインターネットサービスで仕事を探せるようになりました。便利ですね。
この方法のメリットは、強引に転職を勧められることが少なく、自分の意思を尊重してくれやすいことでしょう。
また、求人情報がたくさんあります。
デメリットは、職場の質にばらつきがあり、ブラック企業に当たる可能性があることです。
また、応募するためには、履歴書や職務経歴書などの書類作成や面接対策などの準備が必要です。時間や労力がかかることもあります。
1位 友人・知人からの紹介 21.6%
友人や知り合いから紹介してもらう方法ですね。これが1位です。
友人や知り合いが働いている職場や、知っている職場を教えてもらえたのでしょう。
この方法のメリットは、安心感があることです。友だちや知り合いが紹介してくれる職場は、信頼できるところだと思います。
また、職場の雰囲気や仕事内容などを事前に聞くことができます。入ってからの不安が少ないでしょう。
デメリットは、誰でもできる探し方じゃないこと。友だちや知り合いに紹介してもらうには、まずそういう人がいなければなりません。
また、紹介してもらったからといって、必ず採用されるわけではありません。面接などの選考は自分で受けなければなりません。
さらに、必ず安心な職場とは言い切れません。わたしは紹介から働くようになった職場でパワハラ(上司から叩かれるとか)を受けました。
ただし福祉の仕事は人柄重視で採用しますから、コネや縁故は強力です。
採用側にしてみると「この人がおすすめするんだから、きっと良い人だろう」と考えやすいんですね。
例えば、私の知り合いにこんな例があります。
AさんとBさんは大学の同級生で、卒業後はそれぞれが福祉の仕事につきました。
それからも定期的に会っていましたが、Bさんは結婚して退社。
さらに数年経ち、Bさんは子どもが大きくなってきたので、仕事を再開しようと思いました。
BさんはAさんに「仕事をまた始めようと思うんだけど」話したところ、Aさんは自分の職場をオススメしました。
Bさんは「Aさんが長く働いてるんだから良い職場なんだな」と、信頼し、採用試験を受けることにしました。
Aさんは、職場でキャリアを重ねていたので、職場からは厚い信頼を受けていました。
AさんがBさんを職場に推薦したので、Aさんの職場は

Aさんがすすめるんだから、間違いないだろう。
と評価。Bさんは採用試験をスルリと通って合格しました。

やっぱりコネが良いんだ・・・。ボクにはそんな知り合いいないよ。どうしたらいいの?

コネなら良い職場につけるとは限らないよ!ほかの方法で探したら問題ナシ!
私は大学教授からの紹介にもかかわらず、ブラック職場に入職しました。ここからお伝えできる教訓は、「コネなら安心とは限らない」です。
だから、仕事を紹介してくれる人がいないからといって、気落ちすることなかれ。
ハローワークや転職サイトなど、社会福祉士が仕事を探す方法は充実しています。
ランキングを参考に、他の方法を検討してみてくださいね!
まとめ
社会福祉士が仕事を探した方法ランキングをもう一度みてみましょう。
| 順位 | 方法 | 割合 |
| 1位 | 友人・知人からの紹介 | 21.6% |
| 2位 | ハローワークの無料職業紹介 | 18.7% |
| 3位 | その他 | 16.7% |
| 4位 | 民間の職業紹介、就職情報誌、求人チラシ、求人情報サイト等 ≫経験者が選ぶ!社会福祉士おすすめ転職サイト・転職エージェント3つ | 13.4% |
| 5位 | 学校・養成施設等での進路指導 | 10.9% |
| 6位 | 法人・会社の求人(就職説明会等) | 9.3% |
| 7位 | 行政広報誌(区報・市報等) | 7.6% |
| 8位 | 実習・施設見学・ボランティア | 5.5% |
| 9位 | 福祉人材センターの無料職業紹介 | 4.9% |
| 10位 | 前の職場からの紹介 | 3.2% |
仕事を探すときや、仕事を変えるときは、運もあります。入ってみないとわからないこともあります。
どんなに気をつけても、ブラック職場に行ってしまうこともあるかもしれません。
でも、社会福祉士の仕事は年をとってもできます。仕事を変えたいと思ったら、たくさんの選択肢があります。引く手あまたなんですよね。
そして、今までの仕事で得たノウハウは、あなたの財産です。
仕事を変えても、その知識や技術は役立ちます。だから、社会福祉士は転職に強いのです。
自信をもって、仕事をさがしていきましょう!
関連記事コーナー
社会福祉士のみんなは、どんな理由で転職&退職しているのでしょうか?こちらの記事でその答えがわかります。(ぶっちゃけ、人間関係が一番おおきいですけど)
社会福祉士におすすめできる転職サイトや転職エージェントは、こちらの記事で解説しています。
社会福祉士の世界は広いようで狭い。転職後も元の職場の人と出会ったり、関わることがあったりします。なので、円満に退職するのがベター。その方法はこちらでわかります。









コメント