
「病院とかクリニックって安定してそうだし、就職したいなあ〜」
そんなイメージ、ありますよね。
確かに、安定して見えます。
でも、実際はぜんぜん楽じゃない。
医療ソーシャルワーカーとして働くと、想像以上に“きつい現実”があります。
この記事では、医療ソーシャルワーカーがきつい3つの理由を、私の体験をまじえてお話しします。
医療ソーシャルワーカーがきつい3つの理由
- 医師の指示に従わなければならない場合が多い
- 医療の価値観とぶつかって葛藤する
- 給料・年収・昇給はイメージほど高くない
ではまいりましょう。
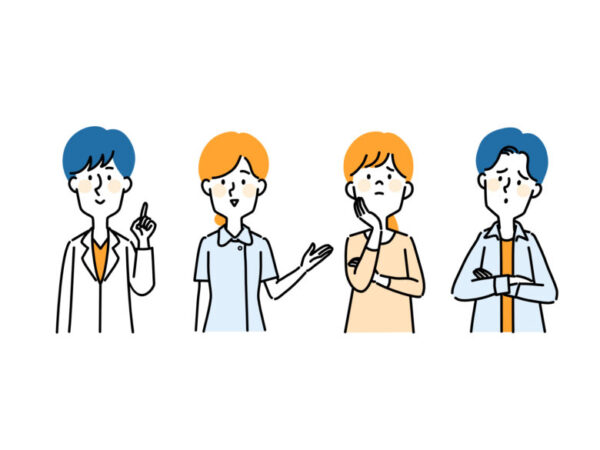
医師の指示に従わなければならない場合が多い
医療の世界では、医師の権力が絶対です。
良くも悪くも、医療機関は「医師を中心に回る」構造になっています。
私は最初、医療ソーシャルワーカーも“チームの一員”として対等に意見を言えると思っていました。
でも、実際は違いました。
医師の「ひと言」で全部が変わる
私が働いていた精神科クリニックでは、医師が出すオーダーがすべて。
「○○さんは今日来なくていい」「あの支援はやめよう」——そう言われたら、それで終わりです。
カルテも誰にも読めないような字で書かれ、スタッフが「先生の字は象形文字ですね」と冗談を言うしかないような現場でした。
指摘しても改善されない。結局、読む努力をするのは私たち。
医師は重い責任を背負っています。そのプレッシャーのなかで必死に判断されているのも分かります。
でも同時に、「自分だけが正しい」という態度に疲れることもあります。
“指導”じゃなくて“指示”に近い関係
医師と医療ソーシャルワーカーの関係は「指示」ではなく「指導」です。ただし実態は「指示」のような圧力があります。それくらい、医師の立場は絶対的です。
医師がワンマンだと、医療ソーシャルワーカーはただの下請けになります。
もちろん、尊敬できる医師もいました。スタッフの意見に耳を傾け、チーム全体で患者さんを支える姿勢を持つ方。
そういう方と働けたときは本当にやりがいを感じました。
でも、そんな医師ばかりではないのも現実です。
結局、強い上下関係のなかでどう立ち回るかが求められる現場だったのです。
医療の価値観とぶつかって葛藤する
社会福祉士や精神保健福祉士は、生活モデルで支援します。
でも、医療は医学モデルで動く世界です。
この違いが、思っている以上に大きい。
「本人を信じたい」と「症状を管理したい」の衝突
私は「本人の希望に寄り添いたい」と思っていました。
でも、医療現場では“本人を信じる”よりも“リスクを管理する”ことが重視されがちです。
ある患者さんに「外出したい」という希望があっても、「転倒したら危ないから」と止められる。
「今日は休みたい」という希望があっても、「服薬が守れないかもしれないからクリニックに来なさい」と促される。
「本人の意思や可能性を信じる支援」よりも「安全を守る支援」が優先されます。
それが悪いとは言い切れません。確かに、安全や命は守られる例はあります。
けれど、“本人の意思を尊重したい”という思いが押しつぶされそうになる瞬間は、何度もありました。私はそれが苦痛でならなかった。
いったい、誰のための支援なのでしょう?
それを突きつめれば、患者さんのためではない。自分たちのため。
「自分たちが責められたくない」「患者さんに何かあれば、自分たちの責任だ」というリスク管理があったと思います。
医療ソーシャルワーカーの存在意義とは
医療の現場では、医師や看護師の意見が強く通ります。
だからこそ、異なる視点を持つ人間がチームにいることに意味がある。
「本人の生活を支える」という社会福祉士や精神保健福祉士の視点がなければ、
医療はどうしても“病気だけを見る支援”になってしまいます。
従うだけの存在になると、医療ソーシャルワーカーは“看護師より安い職種”として扱われてしまう。
私は繰り返し意見を主張しました。若さも相まって繰り返し衝突もしましたが、それでも言わずにはいられなかったのです。
給料・年収・昇給はイメージほど高くない
医療機関は安定している。だから給料も高い——そう思っている方、多いと思います。
でも、私の経験上、それは幻想に近いです。
私のケース(精神科クリニック勤務)
- 手取り:約20万円
- 賞与:年2か月
- 年収:約300万円
- 昇給:年1回 0〜2000円
仮に10年働いても最大で2万円の昇給。
医療機関=好待遇という図式は成り立ちません。
その後、地域の事業所に転職したところ、年収は約50万円アップ。
安定感は減りましたが、「生活できる」という実感は増えました。
統計でも“夢は見すぎない方がいい”
全国的に見ても、医療ソーシャルワーカーの平均年収は社会福祉士・精神保健福祉士とほぼ同じ。
イメージほど恵まれてはいません。
最後に:それでも医療ソーシャルワーカーを目指すなら

ここまで「きつい話」をしてきました。
でも、医療ソーシャルワーカーという仕事が嫌いになったわけではありません。
むしろ、あの現場でしか得られないものがあったと思っています。
相談支援をしている限り、福祉の仕事をしている限り、医療ソーシャルワーカーと関わることはあります。
医療ソーシャルワーカーの現場を知っているから、相手の状況がわかるのです。
そして、どんな情報を必要としていて、どんな情報があれば医療ソーシャルワーカーは動きやすいのか、想像できる。
ただし、医療ソーシャルワーカーとして働く前には、ぜひ考えてみてください。
- なぜ医療ソーシャルワーカーになりたいのか
- どんな支援をしたいのか
- どんな働き方を望むのか
自分の「軸」がないと、現場の波に飲み込まれます。
目的をはっきりさせておくことで、きつい現実の中でも折れずに働けると思います。
2️⃣ 医療の価値観とぶつかって葛藤する
3️⃣ 給料・年収・昇給はイメージほど高くない
それでも、患者さんや家族の人生に関われる医療ソーシャルワーカーは、誇りにできる仕事です。厳しさを知った上で、ご自身らしく働ける道を選んでいただきたいと思います。
あなたが「合わない」と感じたら、それは悪いことじゃない
医療ソーシャルワーカーとして働くなかで、「この現場は合わないかも」と感じることもあると思います。
それは、あなたが弱いからではなく、環境との相性です。どんなに志があっても、合わない職場では力を発揮できません。私は転職しましたし、後悔はありません。
もし今の職場に違和感を感じているなら、ほかの現場を知ること自体が、キャリアの第一歩になるはずです。
最近では、社会福祉士・精神保健福祉士の求人を専門に扱う転職サイトやエージェントも増えています。
登録するだけで「どんな求人があるのか」「今の相場はどれくらいか」などの情報を得られるので、実際に転職するかどうかは別としても、知っておいて損はありません。

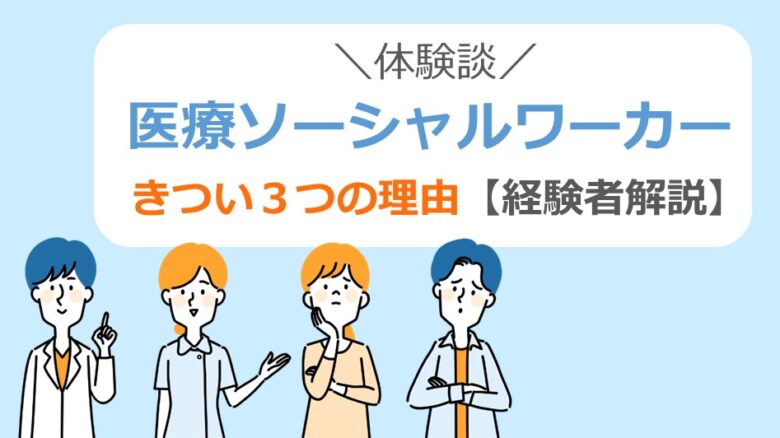



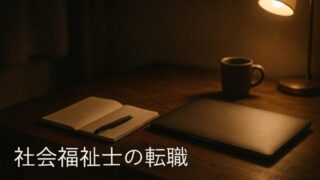
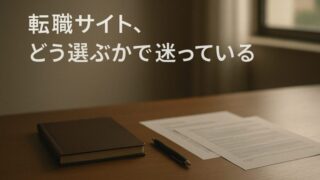
コメント