支援で困ったとき。
人生で困ったとき。
どうにもこうにもならないとき。
そんなとき、私は本を開きます。
答えは、本の中にある。
私たちの悩みは、人類で初めてのものではない。
先人たちが、先に悩み、考え、書き残してくれた。
だから私は、本を信じています。
それくらい、本に助けられてきました。
この記事のラインナップは、そんな私が現場で“本当に効いた”本をまとめたものです。
福祉の専門書というより、自分を最適化して、持っている力を最大限に活かすための本。
読むことで、支援にも、自分にも、余白とエネルギーが戻ってくる。
知識を詰め込むためではなく、
「どう動くか」「どう整えるか」──
そのヒントをくれた本たちです。
- 気分の安定と支援力をくれた本 『嫌われる勇気――自己啓発の源流「アドラー」の教え』(岸見一郎・古賀史健 )
- 自己覚知力と支援力をくれた本 『愛着障害~子ども時代を引きずる人々~』(岡田尊司)
- 自己覚知力と支援力をくれた本 『発達障害と呼ばないで』(岡田尊司)
- 自分の生い立ちを気づかせてくれた本 『消えたい──虐待された人の生き方から知る心の幸せ』(高橋和巳)
- 世の中を冷静に見る力をくれた本 『FACTFULNESS(ファクトフルネス)』(ロンスリング)
- 世の中を冷静に見る力をくれた本 『影響力の武器[第三版] なぜ、人は動かされるのか』(ロバート・B・チャルディーニ)
- お金が増えることを初めて教えてくれた本 『新NISA対応 超改訂版 難しいことはわかりませんが、お金の増やし方を教えてください!』(山崎元・大橋弘祐)
- お金の使い方を教えてくれた本 『DIE WITH ZERO 人生が豊かになりすぎる究極のルール』(ビル・パーキンス)
- ブログを始めるきっかけをくれた本 『学び効率が最大化する インプット大全』『学びを結果に変える アウトプット大全』(樺沢紫苑)
- 読みっぱなしにならない読書法を教えてくれた本 『すべての知識を「20字」でまとめる 紙1枚!独学法』(浅田すぐる)
- 仕事と私生活のパフォーマンスを上げてくれた本 『自分を操る超集中力』(メンタリストDaiGo)
- 運動する習慣をくれた本 『脳を鍛えるには運動しかない!』(ジョン J.レイティ)/『運動脳』(アンデシュ・ハンセン)
- 仕事パフォーマンスを上げてくれた本 『SINGLE TASK 一点集中術』(デボラ・ザック)
- 仕事パフォーマンスを上げてくれた本 『いちばん大切なのに誰も教えてくれない 段取りの教科書』(水野学)
- 嫌だった飲み会を面白くさせてくれた本 『「飲み会」仕事術』(藍原節文)
- 仕事のピンチを助けてくれた本 『超呼吸法』(根来秀行)
- 仕事を辞めたくなったとき、冷静にしてくれた本 『科学的な適職』(鈴木祐)
- 良眠をくれた本 『人はなぜ眠れないのか』(岡田尊司)/『スタンフォード式 最高の睡眠』(西野精治)
- メンタルを底上げしてくれた本 『しつこい不安感が必ず消える セロトニン復活ストレス解消法【対話版】』(Jeg)
- 人生を取り戻させてくれた本 『脱スマホ脳かんたんマニュアル』(アンデシュ・ハンセン)
- おわりに
気分の安定と支援力をくれた本 『嫌われる勇気――自己啓発の源流「アドラー」の教え』(岸見一郎・古賀史健 )
『嫌われる勇気』の中で、いちばん支援に役立ったと思うのは、「人の課題と自分の課題を分ける」という考え方です。
福祉の支援をしていると、つい相手の課題を自分のことのように背負ってしまうことがあります。
これがほんとに難しい。成人の分野なら「自己決定」という言葉も出てきますが、頭でわかっていても、実際はなかなか線を引きにくい。
たとえば、相談支援事業所で働いていたとき。
ある相談者さんが「作業所に通うか、デイケアに通うか」で迷っていたんです。
こちらがやるのは、情報を整理して、本人がわかりやすいように伝えたり、一緒に見学に行ったり、そのあと一緒に振り返ったり。
必要なら別の選択肢も考える。
でも、最終的に選ぶのは本人の課題なんですよね。
それなのに、「こうなってほしい」と期待を持ちすぎると、知らず知らずのうちに指示的になったり、期待どおりにいかないと自分を責めたりしてしまう。
逆に、自分を守ろうとして相手や他機関のせいにしたり。
そういう発想って、一見“真剣”に見えるけど、じつは危ういんですよね。
たとえば、クライエントがリスクのあるチャレンジをしたいと言うとき。
起業したい、転職したい、結婚したい、子どもを持ちたい――どれも人生の大きな選択です。
支援者がそれを、自分の責任のように抱えすぎると、「失敗されたら困る」という気持ちになって、他の機関に責任を回そうとする。
「病院のせいだ」「親が悪い」といった思考です。
児童相談所でもよくあります。
たとえば子どもがリストカットをしたとか、ODしたとか。
そうなると、学校の先生は一気に防衛モードに入ることがありますね。
「いじめと言われたらどうしよう」「責められたら困る」って。
そして、「児相がなんとかして」と丸投げしてしまう。
でも、私たちも100%の責任を背負うことはできない。
その人の人生を肩代わりしちゃいけないんです。
相手の課題と自分の課題を分ける。どこまでが自分の仕事か、どこから先は本人の人生か。
そこを見極めることが大事だなと思います。
責任を回避するための方便ではなく、心の持ちようであり、バランスの大切なところです。
『嫌われる勇気』は、それを繰り返し思い出させてくれる。
相手に嫌われるかどうかは、相手の課題。
それを私がコントロールしようとすると、支援の方向がズレていく。
嫌われてもいいから、やるべきことをやる。
その潔さを教えてくれた一冊でした。
自己覚知力と支援力をくれた本 『愛着障害~子ども時代を引きずる人々~』(岡田尊司)
岡田尊司先生の本はたくさん読んできましたが、とくに「愛着障害」はソーシャルワーカーなら必読だと思います。
大学の授業ではあまり深掘りされないけれど、現場では確実に必要な知識なんですよね。
人間関係のつくり方って、結局のところ幼少期の養育者との関係がベースになっている。
だから、愛着のパターンを理解していないと、クライエントとの関係も読み間違えることがあります。
しかもこれは、支援者自身の愛着のクセにも関わってくる。
支援していて、休日になっても心が重いとか、相手の言葉がずっと頭から離れないとか。
周りから「入り込みすぎ」って言われる背景には、相手の愛着の傷と自分の傷が響き合っていることもあります。
誰にでも少なからず愛着の傷はあります。
0か100かじゃなくて、10%、20%、30%というグラデーション。
そこを自分で知っておくことが、支援の安定につながるんですよね。
愛着障害の理解があると、「なぜこの関係で疲れるのか」が見えてきます。
クライエントの反応だけでなく、自分がどう反応しているかにも目が向く。
だから、自己覚知の本としてもすごくおすすめです。
自己覚知力と支援力をくれた本 『発達障害と呼ばないで』(岡田尊司)
「発達障害と呼ばないで」は、「愛着障害」とセットで読むとすごくわかりやすい。
発達障害と愛着障害って、症状が似ていることが多いんですよね。
だからこそ、見立てを間違えるリスクがある。
発達障害は先天的なもの。
愛着障害は後天的、つまり環境の影響で起きる。例えば不適切な養育や虐待だ。
でも現場では、その違いがぼやける。
だから、児童相談所では成育歴や検診、受診歴、虐待の有無まで調べる。
できるだけ資料を集めて育ちをたどるようにしています。
それでも、はっきりしないこともあるんですよね。
だから、医師も誤診をします。
大切なのは、親にとって発達障害という言葉が“免罪符”になることがあるということ。
「子どもの問題は私の育て方のせいじゃない」と思いたくて、診断をもらいたがる。
診断をくれない医師を「悪い医者」扱いしてしまうケースもあります。
でも私たちは、診断だけで人を見ないことを知っておく必要があります。
ラベルにとらわれず、その人がどう生きてきたかを見ること。
「発達障害と呼ばないで」は、それを考えさせてくれる本です。
自分の生い立ちを気づかせてくれた本 『消えたい──虐待された人の生き方から知る心の幸せ』(高橋和巳)
「消えたい」「死にたい」と言う人にどう関わるか。
気になって、この本を手に取りました。
読んでいくうちに、彼らの世界観が自分と重なるところが多くてびっくりしたんですよね。
「消えたい」と思う人の世界の見え方が、とてもリアルに書かれていた。
読んでいるうちに、自分の感じ方の理由が腑に落ちていきました。
私は今は「消えたい」と思うことはないけど、当時の自分には本当に刺さった。
「消えたい──虐待された人の生き方から知る心の幸せ」は、クライエントの世界観を理解する助けにもなるし、自分の世界観を見つめ直すきっかけにもなる。
支援でも、自分でも、「なぜ苦しいのか」「なぜ生きづらいのか」がわかると、前に進める。
そんな本でした。
世の中を冷静に見る力をくれた本 『FACTFULNESS(ファクトフルネス)』(ロンスリング)
すごく有名な本ですが、支援にも直結する内容です。
人間には、「分断本能」「ネガティブ本能」「犯人探し本能」など、思い込みのクセがある。
それが事実の判断をゆがめるんですよね。
私はプロフィールにも書いていますが、支援では事実を重んじたいと思っています。
人は感情に巻き込まれると、事実を脚色したり、誇張したり、違う文脈で語ったりする。
だから、冷静に事実を見つめ直す力が必要なんです。
たとえば「子どもの命が危ない」という情報が入ってきたとき。
みんな動転します。
でも、その情報が一次情報なのか、憶測なのかを整理しないまま動くと、間違った支援や権利侵害につながることがある。
だから、落ち着いて「事実」を確認することが大事なんですよね。
「FACTFULNESS」を読んでから、感情に引っ張られないように意識するようになりました。
「冷静さ」は支援力だと思います。
世の中を冷静に見る力をくれた本 『影響力の武器[第三版] なぜ、人は動かされるのか』(ロバート・B・チャルディーニ)
「影響力の武器[第三版]: なぜ、人は動かされるのか」は、人がどう動くかの「仕組み」がわかる一冊です。
返報性とか、一貫性とか、社会的証明とか。
聞いたことはあるけれど、実際の人間行動をここまで具体的に解説してくれる本は少ないと思います。
もちろん、使い方を間違えると危ない知識でもあります。
だからこそ、倫理観がセットで必要なんですよね。
でも、どう伝えたら人が動きやすいか、どう言えば誤解されにくいか、
そういう「伝え方の技術」を知っておくのは、支援でもすごく大切です。
言葉の順番や伝え方ひとつで反応が変わる。
「変えられるのは自分だけ」とは言うけど、自分の伝え方を変えたら、相手の反応も変わる。
それを実感できる本です。
お金が増えることを初めて教えてくれた本 『新NISA対応 超改訂版 難しいことはわかりませんが、お金の増やし方を教えてください!』(山崎元・大橋弘祐)
私が買ったのはこちらの旧版。
お金の話って、福祉職だとちょっと避けがちですよね。
でも実際、この仕事を続けるうえで“お金の安定”は欠かせないと思っています。
ボランティアではやっていけないし、生活が不安定だと支援どころじゃなくなる。
私はお金の専門家じゃないけど、この本に出会ってから、お金の使い方や増やし方に対する考え方が大きく変わりました。
本の内容を実践してみた結果、実際に資産が増えたんです。
10年弱で、車が数台買えるほどお金が増えました。
それだけこの本の影響は大きかった。
大変惜しいのですが、著者の山崎元さんは、2024年に亡くなられました。
私はほんとに感謝しています。
もし直接お礼が言えるなら、「あなたの本のおかげで、福祉の仕事を続けやすくなりました」と伝えたい。
お金の不安が減ると、日々の支援にも心の余裕が生まれる。
そう実感しています。
お金の使い方を教えてくれた本 『DIE WITH ZERO 人生が豊かになりすぎる究極のルール』(ビル・パーキンス)
お金を増やすのは大事。
でも、それをどう使うかはもっと大事なんですよね。
この本は、それを気づかせてくれました。
たとえば、30歳の自分が持つ100万円と、100歳の自分が持つ100万円。
どちらの価値が高いかといえば、やっぱり30歳のときの100万円です。
そのお金で経験できることが多いし、一緒に楽しめる仲間や体力もある。
同じ金額でも、使う「時期」によって価値が全然違うということ。
「貯金=安心」って思いがちだけど、安心料が高すぎると、
やりたいことを逃す“機会損失”になってしまう。
「DIE WITH ZERO 人生が豊かになりすぎる究極のルール」を読んでから、お金の使い方を意識するようになりました。
お金は守るだけじゃなく、人生を豊かにするために使う。
特に、体験に使うこと。
そんな視点をもらえた本です。
ブログを始めるきっかけをくれた本 『学び効率が最大化する インプット大全』『学びを結果に変える アウトプット大全』(樺沢紫苑)
この2冊を読んだとき、「ああ、自分はまだまだ“学びっぱなし”だったな」と気づきました。
どれだけ本を読んでも、行動しなければ身にならない。
それなら、アウトプット前提でインプットしようと。
そこで始めたのが、ブログ「しゃふくさん」でした。
樺沢先生の本は、とにかくToDoが具体的で、すぐ試せるのがいい。
「どうすれば改善につながるか」を教えてくれるので、読書が行動に変わりやすいです。
「成長したい」「自分を整えたい」と思っている人に、特に役立つ本です。
読みっぱなしにならない読書法を教えてくれた本 『すべての知識を「20字」でまとめる 紙1枚!独学法』(浅田すぐる)
本を読んでも、なかなか身についた気がしない。
そんな悩みが続いていました。
樺沢先生のインプット大全・アウトプット大全を読んでの影響もありますが、
この本を読んでから、読書のやり方そのものが変わりました。
読んだあとに、一言で書きまとめる。
加えて、本を読みながら「実際に何をやるか」を3つ書く。
これを決めたことで、本の内容が自分の中に定着していく感覚がありました。
実際、3つじゃ足りない本もあって、10個くらい書くこともあります。
もちろん、全部の本でToDoが出るわけじゃないです。
「愛着障害」とか「発達障害」みたいな教養系の本は、直接の行動には結びつきにくい。
でも、「次にこのケースで試してみよう」と1つでも書き出すだけで、
読書が実践に変わるんですよね。
「読んで満足」で終わらせない。
「すべての知識を「20字」でまとめる 紙1枚!独学法」のおかげで、「読む→書く→試す」という流れが身につきました。
仕事と私生活のパフォーマンスを上げてくれた本 『自分を操る超集中力』(メンタリストDaiGo)
DaiGoさんの発言は、人によって感じ方が分かれると思います。
福祉の立場から見ると、ちょっとドライすぎたり、倫理的にどうなの?って思うときもある。
でも、科学的な根拠に基づいて行動を設計しているところが、すごく参考になるんです。
「集中力」は、感情の波や周囲のノイズに左右されやすいもの。
DaiGoさんの本を読んでからは、環境を整えることを意識するようになりました。
スマホの通知を切る、机の上を整える、体調を整える。
気合とか根性で集中するんじゃない。
システムを変えることで、パフォーマンスは驚くほど変わる。
大事なのは、知識の使い方。
包丁と一緒で、どう使うかで善にも悪にもなる。
この本を読むと、そんな“使い方の責任”も考えさせられます。
運動する習慣をくれた本 『脳を鍛えるには運動しかない!』(ジョン J.レイティ)/『運動脳』(アンデシュ・ハンセン)
運動は、もう万能薬です。
「脳を鍛えるには運動しかない! 」を読んでから、
「なんで運動がいいのか」という理屈が腑に落ちました。
運動をすると、脳の神経伝達物質が整う。
気分が上がるだけでなく、集中力・睡眠・記憶力・ストレス耐性までよくなる。
科学的に説明されると、「やらなきゃな」という気持ちが腹に落ちました。
最近も「運動脳」も読んで、運動するモチベーションを上げました。
私も運動を習慣にしています。
妻と散歩をしたり、山に登ることもあります。
無理のない範囲で続けることがいちばん大事なんですよね。
「動くことで心が整う」――それを実感できる本です。
仕事パフォーマンスを上げてくれた本 『SINGLE TASK 一点集中術』(デボラ・ザック)
「SINGLE TASK 一点集中術」を読んで、「マルチタスクは幻想だ」と知りました。
人は同時にいくつものことをしているように見えて、
実際は注意を高速で切り替えているだけなんですね。
そのたびにエネルギーを消耗して、結果的にパフォーマンスが下がる。
福祉の現場でも、電話しながら記録を書いて、同時に別の書類を書いたり。
でも、そういうやり方って、結局どれも中途半端になりがちなんです。
「今やっていることに集中する」。
それだけで、気持ちも落ち着くし、仕事の質も上がる。
”ながら作業”ではない。
相手に誠実に向き合うことにもつながります。
仕事パフォーマンスを上げてくれた本 『いちばん大切なのに誰も教えてくれない 段取りの教科書』(水野学)
仕事って、段取りの連続ですよね。
でも、意外と誰も教えてくれない。
「いちばん大切なのに誰も教えてくれない段取りの教科書」を読んで、「段取りを“細かく分ける”と仕事が変わる」と気づきました。
たとえば「東京ディズニーランドに行く」という予定を立てるとします。
それだけだと漠然としてるけど、実際には、
- チケットを調べる
- 日程を合わせる
- 宿を取る
- 予算を決める――
たくさんの小さなタスクがあります。
それを整理して書き出すだけで、見通しが立つ。
支援の仕事も同じで、家庭訪問や面接を分解して考える。
「準備」「実施」「記録」「共有」などに分けて、
どの段階で何が必要かを見える化すると、焦りが減ります。
ガントチャートを使うのもおすすめ。
不安の正体って、「段取りが見えてないこと」なんですよね。
嫌だった飲み会を面白くさせてくれた本 『「飲み会」仕事術』(藍原節文)
▶ 「飲み会」仕事術
私は昔から飲み会が苦手でした。
お酒も飲めないし、あの空気がちょっとしんどくて。
でも福祉の現場って、意外と飲み会でのコミュニケーションが多い。
「顔の見える関係を作ろう」という文化もあります。
「「飲み会」仕事術」を読んで、「あ、飲み会にもコツがあるんだ」とわかりました。
どんなふうに話すと相手が話しやすいか、
どんな立ち回りをすると場がなごむか。
ちょっとした工夫で、空気が全然変わるんですよね。
それでも、私は今でもそんなに好きにはなれないけれど(笑)
「苦手でも、それなりに楽しめる方法」はある。
そう思えたのが大きかったです。
こちらの記事でもご紹介しています。
仕事のピンチを助けてくれた本 『超呼吸法』(根来秀行)
仕事をしていると、どうしても焦ったり、不安になったりしますよね。
相談が立て続けに入るとか、目の前でトラブルが起きるとか。
ソーシャルワーカーの現場だと、そんな場面も少なくない。
そんなときに、呼吸を使って自分を落ち着かせる方法を知れたのがこの本でした。
「意識的に交感神経と副交感神経をコントロールできるのは、呼吸だけ」という考え方。
たしかに、浅い呼吸のままだと、ずっと戦闘モードのままなんですよね。
吸うよりも、長くゆっくり吐く。
それだけで体が整っていく。
いろんな宗教やマインドフルネス、瞑想でも、呼吸が大事にされているのは理にかなってるんだなと思いました。
いまでも、緊張しそうなときやダメージが大きいときは、
数分でも時間をとって、深く呼吸するようにしています。
仕事を辞めたくなったとき、冷静にしてくれた本 『科学的な適職』(鈴木祐)
ソーシャルワーカーをしていると、「自分、向いてないかも…」って思うこと、ありませんか。
私も何度もありました。
児童福祉司をしているときも、「もう限界だ」と思った時期が繰り返しありました。
そんなときに読んだのが「科学的な適職」。
「適職って、最初から決まってるわけじゃない」
「やっていくうちに天職になることもある」
という考え方に救われました。
「何が自分に合っているか」を考えるとき、
「好きか嫌いか」よりも、「自分の裁量権がどれくらいあるか」「成長を感じられるか」
そういう視点の方が大事だったりする。
読んでいて、感情的になっていた自分を一歩引いて見られた気がします。
「科学的な適職」がなければ、私はソーシャルワーカーを辞めていたかもしれません。
良眠をくれた本 『人はなぜ眠れないのか』(岡田尊司)/『スタンフォード式 最高の睡眠』(西野精治)
もともと、睡眠には悩みを持っていました。
支援のことを考えすぎて寝つけない夜があったり、明け方まで頭が冴えてしまったり。
「自分の性格の問題なのかな」と思っていたんですが、それだけじゃなかった。
まず読んだのが、岡田尊司の『人はなぜ眠れないのか』でした。
発見だったのが、「現代人が睡眠に悩むようになったのは、エジソンが電球を作ってから」という話。
夜が明るくなり、昼夜の境目がなくなった――
それが、私たちの体内時計を狂わせたんですね。
このくだりがとても印象的で、「ああ、自分だけの問題じゃないんだ」と納得しました。
現代の仕組みが、不眠を生んでいるんだと。
そして次に読んだのが、『スタンフォード式 最高の睡眠』。
どう整えるかを科学的に教えてくれる本でした。
睡眠の「質」を上げるにはどうしたらいいのか、
光・温度・時間・ルーティンの組み立て方まで、実践的な内容が多くてとても助けになりました。
今では、寝る前のルーティンを決めて、部屋の光も落としています。
おかげで、夜の思考が落ち着くようになりました。
睡眠が整うと、心が静まる。
その静けさは、支援にも直結すると感じています。
メンタルを底上げしてくれた本 『しつこい不安感が必ず消える セロトニン復活ストレス解消法【対話版】』(Jeg)
▶ しつこい不安感が必ず消える セロトニン復活ストレス解消法【対話版】: 脳と腸の仕組みから紐解く最短最善のメンタル改善手順とオキシトシン分泌法
タイトルのとおり、すごくわかりやすい本でした。
「難しい理屈はいらない、まずこれをやってみて」という感じの本です。
結論は表紙に書かれている通り。
整腸剤を飲んで、朝にバナナを食べて、抱き枕を抱いて寝る。
たったこれだけ。
最初は「ほんとに?」と思ったけど、実際にやってみたらびっくりするくらい調子がいい。
私は今でも、朝バナナを食べて、整腸剤を飲んで、抱き枕を抱いて寝てます(笑)
妻には「なにしてるの?」って笑われますけど、
効果があるからやめられないんですよね。
腸は「第二の脳」とも言われているし、体から整えるっていうのは理にかなってる。
精神論じゃなく、行動で整えるっていう考え方が好きです。
ちなみに、私が飲んでいる整腸剤はこちらです。
人生を取り戻させてくれた本 『脱スマホ脳かんたんマニュアル』(アンデシュ・ハンセン)
スマホとの距離感、ここが崩れると可処分の注意力がごっそり持っていかれるんですよね。
私も一時期はスクリーンタイム5〜6時間あって、「これはまずいな」と。
「脱スマホ脳かんたんマニュアル」でまずやったのは、現状を見える化すること。
それから通知を切る/YouTubeを消す/代わりの行動を決めておく(散歩・本の数ページ・軽い片づけ)をセットで入れました。
最初は手持ちぶさたで落ち着かなかったけど、数日で慣れました。
で、面白いのは、“人生の主導感”が戻ってくること。
「自分で自分の一日を運転してる」感覚が、少しずつ戻るんですよね。
スマホが悪いわけじゃなくて、環境の設計の問題。
「脱スマホ脳かんたんマニュアル」は、その設計のコツをくれました。
おわりに
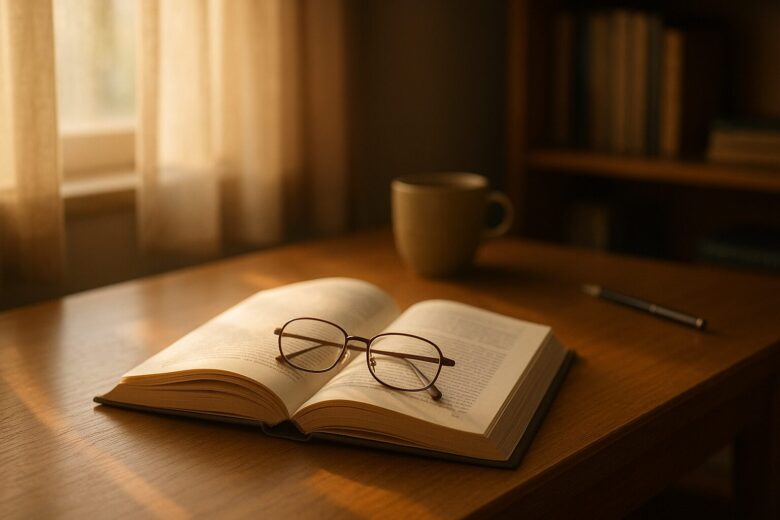
本を読むたびに思います。
「自分には、まだ使えていない力があるんだな」と。
誰にでも、本来の力があります。
でも、引き出し方を知らないばっかりに、力を出しきれずにいる。
本は、その力を“使えるようにしてくれる”存在だと思うんです。
支援が難しい日も、うまくいかない夜も、
ページをめくるたびに、
心と体が少しずつ整っていくのを感じます。
今回のリストは、現場で働くソーシャルワーカーのための読書の道しるべです。
新人でも、ベテランでも、
支援と人生の両方に立ちつくしてしまったとき、
どれか一冊でも、手に取ってもらえたらと思います。
本は、静かに待っています。
手に取る者だけが、先人たちの人生に触れられる。
ページの向こうにあるのは、誰かの経験であり、あなたの明日でもあります。
本を読まない時期もありました。
それでもまたページを開くのは、
やっぱり「答えは本の中にある」と感じているからです。
本は偉大です。
読むたびに、その確信が少しずつ深まっていく。
そんなふうに、本と生きてきました。

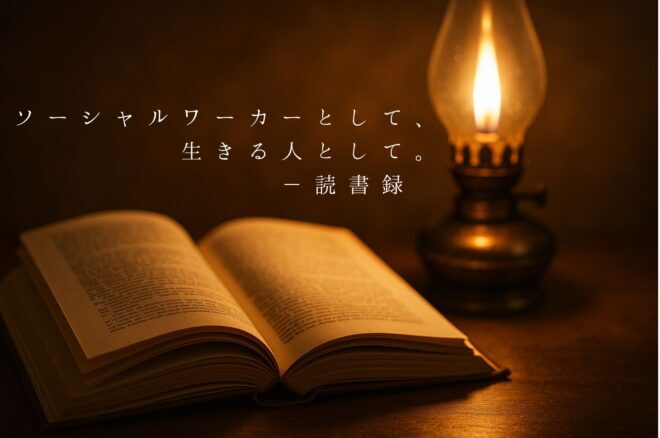






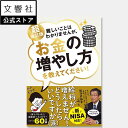
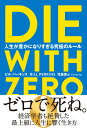



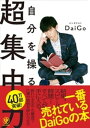












コメント