
地域活動支援センターと就労継続支援事業所の違いはなに?
やってること同じ?
こういったギモンのある方へ。
- 就労継続支援A型とB型の違い
- 就労継続支援A型の特徴
- 就労継続支援B型の特徴
- 就労継続支援と同じに見えるのは地域活動支援センターの『Ⅲ型』

わたしは社会福祉士・精神保健福祉士で、現場経験は10年以上です。
結論は、就労継続支援と地域活動支援センター(Ⅲ型)は似ているということです。
ポイントごとに比べながら解説していきますね!
地域活動支援センターと就労継続支援の違いとは?【社会福祉士解説】
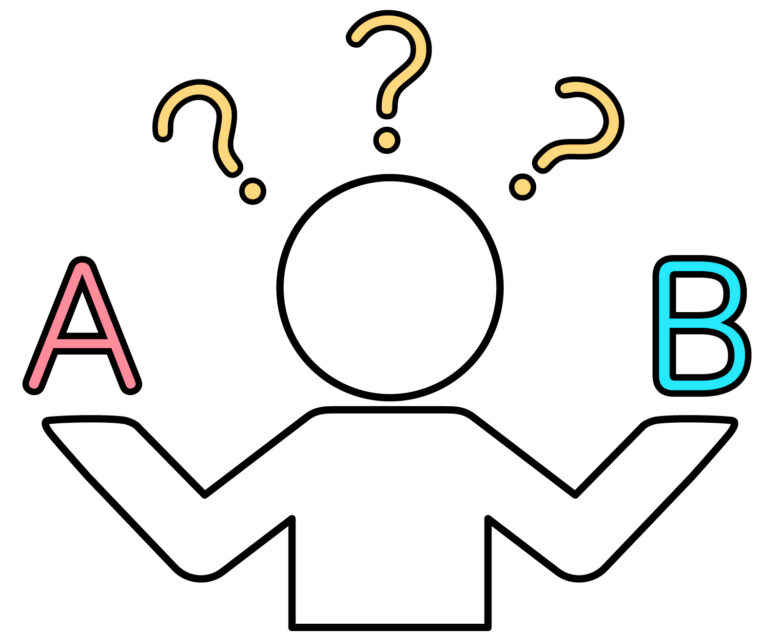
就労継続支援(作業所)は『働く場』
就労継続支援事業所は、障がいや難病のある方などが働く場というのがメインです。
会話では「作業所」とよく呼ばれますね。
就労継続支援A型とB型の違い
A型とB型の2パターンに分かれていて、一番の違いは雇用契約を結ぶかどうかです。
A型は雇用契約を結び、B型には雇用契約がありません。
A型
- 雇用契約あり
☞最低賃金保障あり
B型
- 雇用契約なし
☞最低賃金保障なし
雇用契約を結ぶかどうかは、工賃(賃金)の違いとなります。
就労継続支援A型の特徴
要点は次のとおりです。
- 最低賃金(最賃)が保障される
- B型より賃金が高い
- 負荷は高くなる ex.週5日通わないといけない など
ちなみに全国の最低賃金は、厚生労働省が公表していますね。
就労継続支援B型の特徴
要点は次のとおりです。
- もらえるお金は最低賃金未満
- マイペースにつかいやすい ex.週1回だけ通う など
B型の工賃は、1時間あたり数十円のところもあれば、300円程のところもあります。
一か月かよって、1万円~2万円かせげたら良い方でしょう。
B型のメリットは、週1日だけ通えたりする等、自分のペースで通いやすいことです。
それと働くだけでなく、サロンのようにゆっくり過ごせたりもします。
A型・B型、いずれの就労継続支援も、『働く場』というのがメイン機能です。
ちなみに作業所の工賃については、こちらの記事で深掘りしてあります。
≫【最新】A型・B型作業所の平均工賃・給料【生活できない対処3つ】
地域活動支援センターの活動内容【型による違いを比較】
地域活動支援センターは3つの型にわかれています。
型によって、活動内容が違います。
| 地域活動 支援センター | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 |
| 職員配置 | ・3名以上 (2名以上が常勤) ・専門職員 (精神保健福祉士等)を配置 | 3名以上 (1名以上が常勤) | 2名以上 (1名は専任者) |
| 基礎的事業 | ・創作的活動 ・生産活動 ・地域にあわせた支援を行うこと | ・創作的活動 ・生産活動 ・地域にあわせた支援を行うこと | ・創作的活動 ・生産活動 ・地域にあわせた支援を行うこと |
| 機能強化事業 | ・相談支援事業 ・地域住民の ボランティア育成 ・障がいについての 普及啓発など | ・機能訓練 ・社会適応訓練 ・入浴等のサービス | 援護事業(小規模作業所)の実績が概ね5年以上あり、安定的に運営できていること。 |
| 実利用者数 の想定 | 概ね20名以上/1日 | 概ね15名以上/1日 | 概ね10名以上/1日 |
機能強化事業を比べると、活動に違いがあるとわかりますね。
就労継続支援と同じに見えるのは地域活動支援センターの『Ⅲ型』
就労継続支援と同じように見えるのは、『Ⅲ型』の地域活動支援センターでしょう。
なぜなら、Ⅲ型はもともと作業所だったからです。
障害者自立支援法ができる前は、小規模作業所(別名:無認可作業所、共同作業所、福祉作業所)とよばれていた事業所だったのです。
障害者自立支援法ができてからは、小規模作業所の多くが事業内容にあわせて、以下の事業へと移行していきました。
- 生活介護
- 自立訓練
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型・B型
- 地域活動支援センター など
つまり、地域活動支援センターのⅢ型は、もともと作業所なので、パッと見ると就労継続支援とやっていることが同じなのです。
現行の障害者総合支援法をよく理解すると、地域活動支援センターや就労継続支援事業所、福祉制度やサービスなどがわかるようになります。
わたしが使っているのはこちらの本で、図解があってわかりやすいです。





コメント