あなたは福祉の仕事ってどんなイメージがありますか?
私は友だちや親戚に「福祉の仕事をしてるんだ」と言うと、「えらいね」「すごいね」と言われることがよくあります。
みんな、福祉の仕事は社会の役に立っていると思ってくれているみたいです。
一方で、「体力的にきつそう」「離職率が高そう」とも言われます。
でも、本当にそうでしょうか?

わたしは社会福祉士・精神保健福祉士で、現場経験は10年以上です。
この記事では、福祉・介護業界に世間が抱くイメージに対し、私の現場経験をもとに現実を話していきます。
福祉・介護業界のイメージに対し、現役社会福祉士が現実を語ります!
(株)リクルートキャリアHELPMAN JAPANグループが、福祉・介護の職業イメージを調べました。
私は、上記の調査結果を見て、福祉業界のイメージが少しわかった気がしました。
この調査では、福祉・介護の仕事について、どんなイメージがあるかを聞いています。それぞれみてみましょう。
まずはネガティブなイメージからです。
福祉・介護業界のネガティブイメージ|TOP10
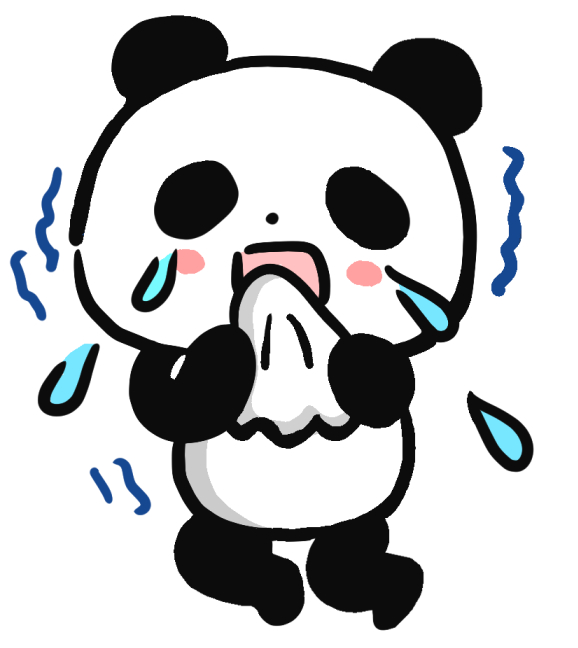
| 順位 | 介護サービス業のネガティブイメージ | 割合 |
|---|---|---|
| 1位 | 体力的にきつい仕事の多い業界だと思う | 61.0% |
| 2位 | 精神的にきつい仕事の多い業界だと思う | 53.8% |
| 3位 | 給与水準が低めの業界だと思う | 48.0% |
| 4位 | 他人の人生に関わるのが大変そう | 46.1% |
| 5位 | 離職率が高い業界だと思う | 44.6% |
| 6位 | 個人の向き・不向きのはっきりする業界だと思う | 43.4% |
| 7位 | 補助金頼みの会社や施設等が多い業界だと思う | 37.4% |
| 8位 | 社会的地位・評判があまり高くない業界だと思う | 29.6% |
| 9位 | 知名度や規模の小さい会社が多い業界だと思う | 29.8% |
| 10位 | 福利厚生があまり充実していない業界だと思う | 27.0% |
1位:『体力的にきつい仕事の多い業界だと思う』というイメージは本当?
これは、介護分野だと正解でしょう。
ロボットやAIの技術が進歩して普及すれば、介護負担は減ると思いますけど、まだまだ力仕事が多いのは現実です。
いっぽうで、社会福祉士や精神保健福祉士の仕事のメインは、相談支援などの精神労働であると考えると、体力的にきついかどうかは各現場次第でしょう。
実際わたし自身の経験でも、作業所などは体を比較的つかいました。
動くことが多かったです。 いっぽうで、相談支援事業所のようにデスクワークばかりの現場についたときは、体重が増えてしまった時期もありました・・・。
近頃はウェアラブル端末とか、スマホで万歩計アプリがあったりするので使ってみるとリアルにわかります。
一日の歩数は、デスクワーク現場は少ないですが、直接支援する現場だと1万歩は普通に超えるのではないかと思います。
2位:『精神的にきつい仕事の多い業界だと思う』というイメージは本当?
人によって違いますが・・・
私たちの仕事は、人の気持ちに合わせて話したり聞いたりすることが多いです。こうした仕事を感情労働と言います。
だから、精神的にきつい仕事が多いというイメージは、あながち間違ってないです。
実際に、私は色々なところで働いたことがありますが、どこでも精神的にきついことはありました。
私たちの仕事は、生活などで困っている人を支援することです。そうすると、自分も一緒に悩んだり、悲しくなったり、辛くなったりすることがあります。
毎日、ニコニコしながら支援する・・・というわけにはいきませんね。
でも、介護や社会福祉士、精神保健福祉士の仕事だけがそうなのではありません。
他の仕事でも精神的にきついことはあります。今の時代はどんな仕事でも楽なものは少ないですからね。
だから、私は毎日、心も体も元気になるように頑張っています(笑)
社会福祉士や精神保健福祉士になってからは、前よりも元気になれた気がします。
それは、仕事をする日々で「もう無理だ!」と思った時期があって、色々な本を読んで生活を変えたからです。
その時に学んだコツはこちらの記事に書きました。今も続けているものだけ厳選して紹介しています。
3位:『給与水準が低めの業界だと思う』というイメージは本当?
給与が低めというイメージは確かに当たっています。
社会福祉士の平均年収は403万円です。
精神保健福祉士の平均年収は404万円です。
介護福祉士の平均年収は394万円です。
これらに比べて、世の平均年収は436万円です。
≫参考:国税庁民間給与実態統計調査(2019年)
なので、給与水準が低めの業界というイメージは正解です。
じゃあ、どうやってお金を増やしたらいいのでしょうか?その方法はこちらの記事に書きました。↓
4位:『他人の人生に関わるのが大変そう』というイメージは本当?
これも本当です。人の人生に関わることばかりで、大変なことはあります。
相談支援事業所で働くとしたら、自分が決めたことで通所先や入所先、就職先、ヘルパーの会社やサービス内容、利用量などが変わります。
これって、人生そのものじゃないですか。だから、大変だし、責任も重いです。
でも、だからこそ楽しいこともあるんです。
人の人生に関わるから、嬉しいことや感動することも多いです。人の人生に関わる大変さを乗り越えて、楽しさややりがいを得ているとも言えます。
だから、大変そうというイメージは当たっていますけど、大変な分だけ良いこともあるというのが私の感想です。
5位:『離職率が高い業界だと思う』というイメージは本当?
これはよく言われることです。
確かに、辞めていく人はいますし、私自身も転職したことがあります。
でも、調べてみると、介護・福祉業界の離職率はさほど高いわけでもありません。詳しくはこちらの記事に書いています。(離職率の低い職場の傾向も書いています)
離職率は、介護・福祉の業界全体で多いのではなく、低い職場もあれば、高い職場もあります。
例えば、私が最初に働いた医療機関の退職率は、『3年で3割退職』どころじゃなかったです。
ほとんどの人が辞めていくので、3年働けばベテランと言われて役職がつくくらいでした。
だから、医療・福祉業界全体が辞める人が多いというより、離職率は職場によると思った方が現実に近いのではないでしょうか。
働きたい職場がどんなところなのか、よく見ておいた方が良いですね。
福祉・介護業界のポジティブイメージ|TOP10

次に、ポジティブなイメージを見ていきましょう。
| 順位 | 介護サービス業のポジティブイメージ | 割合 |
|---|---|---|
| 1位 | 社会的に意義の大きい仕事だと思う | 38.8% |
| 2位 | 今後成長していく業界だと思う | 30.9% |
| 3位 | 資格や専門知識を活かすことができる業界だと思う | 29.8% |
| 4位 | 人との交流がやりがいにつながる業界だと思う | 28.9% |
| 5位 | 仕事にやりがいがある業界だと思う | 22.9% |
| 6位 | 専門知識や技術面でスキルアップしていける業界だと思う | 15.9% |
| 7位 | 雇用不安の少ない業界だと思う | 15.4% |
| 8位 | 様々な働き方が可能で長く働くことができる業界だと思う | 8.5% |
| 9位 | 誰でもできる仕事が多い業界だと思う | 8.4% |
| 10位 | ワークライフバランスを取って働ける業界だと思う | 6.7% |
一番多かった回答は「社会的に意義の大きい仕事だと思う」というものでした。約4割の人がそう答えています。
でも、実際はどうでしょうか?
1位:『社会的に意義の大きい仕事』というイメージは本当?
確かに社会的な意義はあると思います。
私も、頭では、そう理解できます。
しかし、実際に福祉業界で働いている人たちは、あまり実感がないかもしれません。なぜでしょうか?
理由は、「社会」ではなく「個人」に向き合って仕事をしている感覚が強いからです。
福祉や介護の仕事で日々かかわるのは、一人ひとりのクライエントです。
例えば高齢者、子ども、病気や障害のある方、生活に困っている方などです。
目の前の人たちの生活を少しでも良くしたいと思って仕事をしているんですね。
その人たちが笑顔になれば嬉しいし、困りごとがあれば一緒に悩んだりします。
もちろん、個人を支援することは社会全体にも影響することだと思います。
でも、現場ではあまり実感できません。毎日忙しくて、自分の仕事がどんな意味を持っているか、ゆっくり考える余裕がなかったりしますね。
「社会の明日よりも、目の前のAさんの明日が気になる」というのがリアルです。
だから、現場では「社会的に意義の大きな仕事をしてるんだ」と胸を張れない人が多いと思います。(胸を張って良いはずなんですけどね!)
2位:『今後成長していく業界』というイメージは本当?
私は、福祉・介護業界は伸びていく(高需要が続く)と思いますが、人間がやる仕事は変わっていくと思います。
日本では高齢者が増え続けています。そうすると福祉業界も伸びるんじゃないかと思いますよね。
政府のホームページを見ると、これから何十年後までお年寄りや働く人の割合がどう変わるかが書いてあります。
今年生まれた赤ちゃんが大人になるまで20年くらいかかりますよね。だから高齢者の割合が高くなるのは止められません。
介護の仕事や高齢者の相談支援は、これからますます必要になるでしょう。
介護以外にも、子どもが虐待されたり、発達障害があったりする子どもも増えています。
福祉の仕事をする人はこれからも必要です。
でも、福祉の仕事はAI(人工知能)にできないって本当でしょうか?
例えば、高齢者や障害のある方の介護では、ロボットを使うことができるかもしれません。
もし自分がトイレに行けなくなったら、誰に手伝ってほしいですか?人間ですか?ロボットですか?
私は人間にしてもらうのは申し訳なくて恥ずかしいと思います。ロボットだったら気軽にお願いできます。
だから、AIロボットは介護と相性が良いと思うんですね。
相談支援業務みたいに、時代や状況、個人によって選択が変わる難しい仕事はAIにできないでしょうけど、力仕事みたいなのはAIに任せられる時が来ると思います。
だから、福祉・介護業界は伸びていくと思いますが、人間がやる仕事は変わっていくと思います。福祉・介護業界だけじゃなくて、どんな産業も同じですけどね。
3位:『資格や専門知識を活かすことができる業界』というイメージは本当?
これは本当です。
資格の勉強をとおして、専門知識を増やせます。専門知識があれば、より良い支援につなげられます。
そして、資格があれば、条件の良い職場に就職・転職しやすいです。
例えば介護は、育児と同じように『誰でもできる』というイメージをもたれがちです。
実際、日本では、『介護は、まずは家族や親族がやるべきで、できない場合に公のサービスを使うもの』という考え方があります。
専門的なノウハウのない素人でも、介護はできると思われているのです。
確かに、福祉・介護業界では、資格や専門知識がなくてもできる仕事はたくさんあります。
でも、介護や支援の質(クオリティ)はどうでしょうか?
例えば、認知症の方に対して、どう接すれば良いでしょうか?
認知症の方は、現実と過去の記憶が混同したり、自分の意思が伝えられなかったりすることがあります。
そんなときに、どうやって話しかけたり、気持ちを汲んだり、安心してもらえるでしょうか?
それは、認知症について勉強したことがある人じゃないと、できません。
また、介護や支援にはリスクもあります。
例えば、介護の必要な方を移動させるときに、どうやって体を持ち上げたり、寝かせたりすれば良いでしょうか?
間違った方法でやると、怪我をさせてしまったり、自分自身に負担をかけたりすることがあります。(ぎっくり腰になったり)
どうやって安全に移動させるかは、介護技術について勉強・実習したことがある人ならできることです。
このように、介護や支援の質は、専門知識があるかないかで大きく変わります。
そして、専門知識や資格があれば、クライエントやご家族からの信頼も得られやすくなります。
信頼されると、仕事にやりがいを感じたり、評価されたりすることも増えますね。
だから、福祉・介護業界は、資格や専門知識を活かすことができる業界だと言えます。
4位&5位:『人との交流がやりがいにつながる』『仕事にやりがいがある業界』というイメージは本当?
人それぞれですけど、福祉の仕事は、やりがいのある仕事だと思いますね!
やりがいがなければ、収入が多くはない福祉・介護の仕事は選べませんね。
でも、社会福祉士や精神保健福祉士、福祉の現場の人にとって、「やりがいはおまけとしてもらえるもの」というのが私の考えです。
その理由は別の記事で書いていますので、興味があったら見てみてくださいね。↓
最後に
今回は、福祉の仕事の良いイメージに対して、わたしの経験をもとに現実を話しました。
もっとリアルを知りたい方に向けて、このサイトでは社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士について情報発信しています。
以下の記事から調べてみてくださいね!

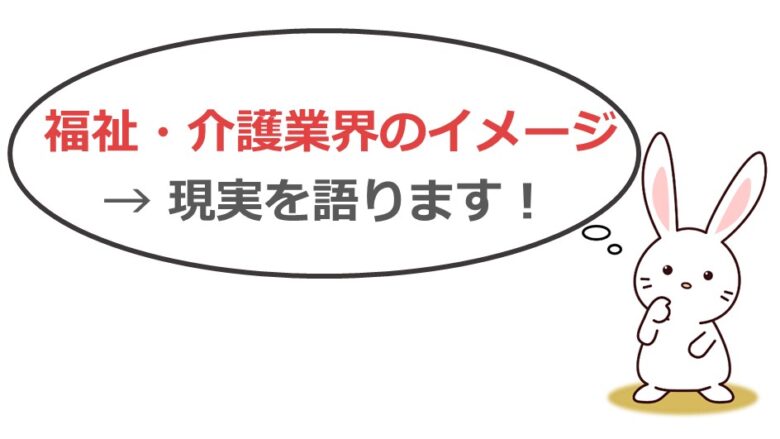











コメント